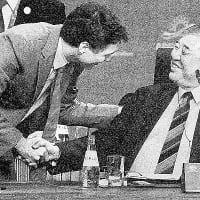カラマツは、トドマツやアカエゾマツと比べて生育がはるかに早く、条件がよければ三十年で製材用原木として利用できるため、戦後、大量に植林された。ところが、材質に油分が多いこと、乾燥の途中で捻れが生じる、という欠点があり、建築材としての利用価値はほとんどなかった。道内の炭砿が健在な頃は、もっぱら坑木として需要があったが、石炭産業の衰退・壊滅とともに、原木生産は大きな打撃を受けた。
私の父は、二十一町歩のカラマツ人工林を所有していたが、昭和四十年代前半、坑木としての需要がまだ盛んな頃に、植林後二十五年で処分し、利を得ることができた。しかも、日本経済が高度成長期にあって、農地改良が積極的に行われていて、土地を高価で手放すことができたのは、幸いだったというべきだろう。 上左の切り株は、樹齢四十年・切り口一尺一寸、上右は、樹齢三十年・切り口七寸三分。右横の切り株は、樹齢四十年・切り口一尺五分。四十年でおおよそ直径一尺まで生育することが分かる。
上左の切り株は、樹齢四十年・切り口一尺一寸、上右は、樹齢三十年・切り口七寸三分。右横の切り株は、樹齢四十年・切り口一尺五分。四十年でおおよそ直径一尺まで生育することが分かる。
長らく低迷していた道産カラマツの需要が、このところ高まっているという。10月3日付『北海道新聞』第12面〈経済〉の<データでわかる!北海道経済>欄では、需要急増の原因と今後の道内林業の見通しを詳しく解説している。伐採適期を迎えた大量のカラマツ材の需要増は、道内経済活性化にとって喜ばしい要因である。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事