
キハ37と言って、わかる方は少数かもしれないので、実車紹介をします。
昭和58年にそれまでの本線向けのキハ40系に対し、老朽化の進んだ地方交通線の
車両の体質改善用に新規設計された形式です。
その為、当時の国鉄の財政状況を鑑みたコストダウンが図られています。
エンジンはなんと一世を風靡したDMH17Cを船舶向けに、8から6気筒化しな
がらも直噴化により出力アップ(180→210ps)されたDMF13Sを使用するこ
とで軽量化と燃費改善(このエンジン自体は船舶用)
主要機器に廃車発生品を採用することで徹底したコストダウン
運転台機器はキハ20系とほど同等
という仕様となっています。
車体は2ドアながらもロングシートですが、両運クロス化も考慮された
設計となっています。
便所付がオリジナルの0番代、なしが1000番代の2車種に区分され、
西(加古川:加古川線)に1と1001の2両が
東(木更津:久留里線)に2と1002,1003の3両の
計5両が量産試作的な要素も掛け持ったまま配置されましたが、結局この5両
のみとなり、JR化によりそのまま継承され、後にJR東配置は屋根上形で、
JR西配置は床下形で冷房化されました。さらに東の車のエンジンはカミンズ
製のDMF14HSに換装されています。
加古川配置の2両はキハ40系の集中配置により米子に転属となり、境線および
山陰線米子近郊での運用となっています。
塗装は登場時は首都圏色ではなく、急行気動車色の赤11号による1色塗りでし
たが、JR化後、木更津配置に車は久留里線色となり、今は2代目です。
加古川配置に車は同じく加古川線色となりましたが、米子転属後、首都圏色の
朱色5号に塗り替えられ、今に至っています。
以上、簡単に実車の歴史をざっとおさらいしてみました。
画像は今の久留里線色のキハ37です。
昭和58年にそれまでの本線向けのキハ40系に対し、老朽化の進んだ地方交通線の
車両の体質改善用に新規設計された形式です。
その為、当時の国鉄の財政状況を鑑みたコストダウンが図られています。
エンジンはなんと一世を風靡したDMH17Cを船舶向けに、8から6気筒化しな
がらも直噴化により出力アップ(180→210ps)されたDMF13Sを使用するこ
とで軽量化と燃費改善(このエンジン自体は船舶用)
主要機器に廃車発生品を採用することで徹底したコストダウン
運転台機器はキハ20系とほど同等
という仕様となっています。
車体は2ドアながらもロングシートですが、両運クロス化も考慮された
設計となっています。
便所付がオリジナルの0番代、なしが1000番代の2車種に区分され、
西(加古川:加古川線)に1と1001の2両が
東(木更津:久留里線)に2と1002,1003の3両の
計5両が量産試作的な要素も掛け持ったまま配置されましたが、結局この5両
のみとなり、JR化によりそのまま継承され、後にJR東配置は屋根上形で、
JR西配置は床下形で冷房化されました。さらに東の車のエンジンはカミンズ
製のDMF14HSに換装されています。
加古川配置の2両はキハ40系の集中配置により米子に転属となり、境線および
山陰線米子近郊での運用となっています。
塗装は登場時は首都圏色ではなく、急行気動車色の赤11号による1色塗りでし
たが、JR化後、木更津配置に車は久留里線色となり、今は2代目です。
加古川配置に車は同じく加古川線色となりましたが、米子転属後、首都圏色の
朱色5号に塗り替えられ、今に至っています。
以上、簡単に実車の歴史をざっとおさらいしてみました。
画像は今の久留里線色のキハ37です。










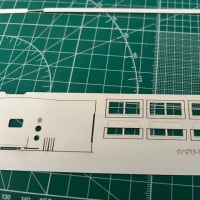


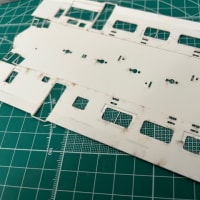






最近は、気動車に嵌られているようですね。
BOLGだと抵抗感なく、記事がアップできますから、忙しい「てつ」さんにピッタリかも。
当方のBOOKMARKに登録させていただきます。