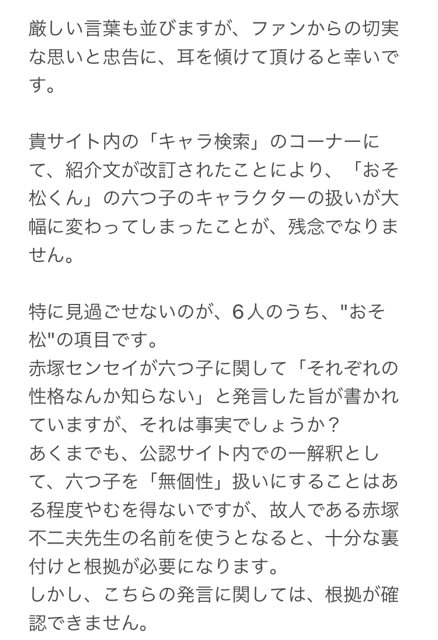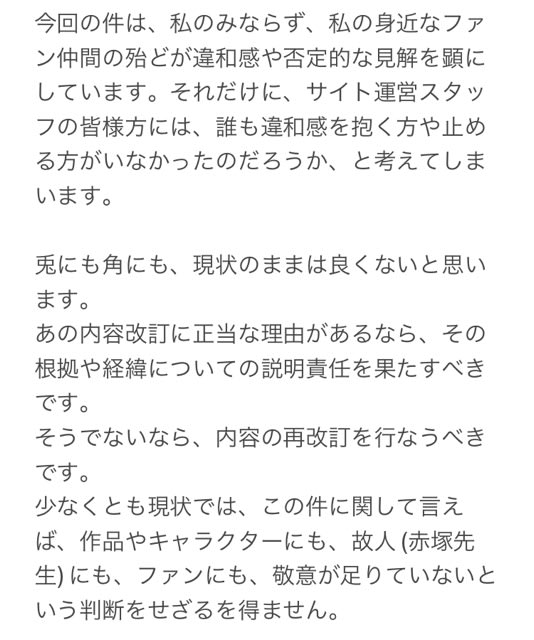当ブログでも過去に取り上げた(1回目、2回目)、赤塚不二夫公認サイトでの問題が発生してから、そろそろ1年が経ちます。
今一度、この件について語ってみたいと思い、このブログを書きました。
新情報・新展開などはなく、あらためてこの問題について見つめ直し今現在の私の感情を書き綴るのみになります。そして今回はかなりナーバスというか感傷的になってしまっている可能性があります。まずその点、ご注意ください。
また、「ここは違うんじゃない?」「ここは良くないんじゃない?」というようなことがあれば全然言ってもらって構いません。
以上、よろしくお願いします。
問題及び、現在の感情について
この問題は、未だ解決はしていない。
既に私は2度、形を変えてサイト宛に意見を送っているにもかかわらず、である。
件の紹介文を読むのは心が痛むので、できることなら読みたくないのだが、「対応してくれたのに、いつまでも問題提起を続ける」というのは良くないというか意味のないことなので、変化がないか時々サイトに確認しに行ってはいる。
そして結局のところ依然として状況は変わっておらず、件の紹介文を読んでしまって心を痛める…そんなことが続いている。
詳細をご存知ない方には上記リンクの過去記事を参照してもらうことにして、
改めて、この件は何が問題なのか、
かいつまんでまとめてみよう。
「赤塚不二夫公認サイト これでいいのだ‼︎」にて、六つ子(おそ松、一松、カラ松、チョロ松、十四松、トド松)の紹介文が改訂された。
①その改訂後の内容は、設定や作中描写と照らし合わせても的確なものとは言えない。原作者の意向にも反することである。
②その内容にキャラクターへの愛が感じられず、心が痛む。
③そしてその内容を、「赤塚不二夫がそう言った」ということにしている。赤塚不二夫の存在を盾にしながら、赤塚不二夫に対する背信行為をしている。
「赤塚不二夫の言ったことを守ってます!」と言いながら、その実、赤塚不二夫の言ったことに背いている。
…といったところだ。
ぶっちゃけ言うと、①と②だけであれば、私もここまでこの問題に拘っていない。これだけでも問題提起自体はしただろうし残念だとも感じただろうが、「あってはいけないこと」「許せないこと」とまでは捉えていなかったんじゃないかと思う。
ここまで問題視しているのは、やはり③があるからだ。
「六つ子に違いなどない」というのは、厳密に言えば正しい情報とは言えないものの、作中描写においても赤塚先生の発言においても、常に明確にされてきたわけでもない。だからあくまでも一解釈としてであれば、①のような内容も全く許容できないわけではない。事実、「六つ子には性格的な違いが見られない」とする公式的な解説自体は、今回が初めてではない。
②についても、「感じ方は人それぞれ」と言ってしまえばそれまでだろうと思う。
しかし、③のように「赤塚不二夫がそう言った」という体で語られるなら「それは違うだろう」となって当然だろう。
赤塚先生が過去に似たようなことは言っていて、その要約と受け取れる内容がサイト上に載せられているのならまだしも、実際には赤塚先生はそれと真逆の発言をしているのだ。
「一解釈」として許容できたことも「間違った内容」になるし、「感じ方は人それぞれ」と考えることができたものも「タチの悪い内容」となるのだ。
きちんとした根拠に基づくのなら、「六つ子に違いなどない」というのは誤解、悪く言えば思い込みのようなものだ。
思い込みの内容を"公認サイト"上に記載すること自体問題だし、そんな投げやりとも言える文章の中で
「六つ子に特徴なんてないから書くこともないし、赤塚不二夫がそう言ってた、ってことにしよう」
くらいの意識で"赤塚センセイ"の名前を出しているのなら大問題なのだ。
原作者・故人軽視も甚だしいし、実際の赤塚先生の発言と相反するのだから、それは背信行為と言って差し支えない。
些細なものであったとしても、根拠は根拠である。無視するべきではない。
そうでなくても、故人の存在を利用し事実を捏造すること自体、褒められるようなことではない。
これは何も、この件に限った話ではない。
今回はたまたま、六つ子のキャラクター設定に関しての話題でこういったことが起こっているが、場所や場合を問わず、こんなことは起きるべきではない。
改訂そのものについてだが、元々あった紹介文も、作中では読み取れないような情報が含まれていたりもしたので、その意図が100%汲み取れないわけでもない。しかし、それらの情報を「誤情報」として削除しても、それを補うために別の「誤情報」を記載してしまえば、それは本末転倒ではないか。
というか、赤塚先生は実際には設定をきちんと考えていたのに、「いい加減に考えていた"ことにする"」というその精神自体が、赤塚先生に対して失礼にあたらないだろうか。
とはいえやはり、「あの内容への改訂には正当な根拠がない」と言い切ってしまうことができないのはわかっている。
要するに、サイトに書いてある通りのことを赤塚不二夫がどこかで実際に言ったという可能性を完全には否定できない、ということだ(悪魔の証明)。
だから私は、サイト宛に意見を送る中で、「正当な根拠があるならそれを示してほしい」ということも併記した。
しかしそれさえも全く反応がないので、こちら側としては「根拠を出さないということは、出せない、それが無いということですね」という風に判断するしかない。
状況から言っても、可能性は低いと言うしかない。
そして、仮に赤塚不二夫がサイトに記載された通りのことを実際に言っていたのだとしても、それとは真逆のことを言ったこともまた紛れもない事実として確認しているので、私の主張が完全に的外れになることはないと考えている。
結局のところ、「赤塚不二夫公認サイトでは故人の遺志に反する形での内容改訂が行われ、かつその責任が故人に転嫁されている。説明責任を求められても、だんまりを決め込んでいる」というのが、現在こちらから観測できるありのままの状況なのである。
また、本質的な問題はそこにはなく憶測の域を出ないとも言えるため先程は挙げなかったものの、「無個性」「順番不明」をやたらと強調した文章が、
六つ子に明確な個性がつき順番も設定として固定された「おそ松さん」(以下「さん」)を意識してのものとしか思えないのも大きな問題として捉えている。
「さん」に対してはこれまで否定的な感情を抱くことも多かったが、今にして思えば、それらは概ね「不満」(あくまでも個人的な感情)止まりなものが殆どだったように思う。
しかしこの件では、「さん」が原作サイドに与えた影響が、実害レベルに及んでしまっているように感じる。そこも辛い。
「さん」は「さん」で自由にやるだけにとどまらず、「さん」によって「おそ松くん」そのものの歴史や設定が歪められつつあるのだ。
本格的に、「おそ松くん」という作品の尊厳に関わる事態になってはいないだろうか。
尤も、この場合おそ松さんが悪いというより、やはりおそ松さん側に合わせてしまうサイト側に問題があるのだが…。
実際にあの内容改訂そのものが与える影響というのはそう大きくはないかもしれない。私の知る限り、ファンの多くはあの内容に対してちゃんと違和感や否定的な感情を抱いているし、今からあの内容を参考にして鵜呑みにする人が一体どれほどいるか、という話だ。
しかし、それはそうとしてこの件は、サイト運営者(=フジオプロスタッフ)が、こういうことをしてしまうような人たちなのだということが露呈してしまったのが辛い。
(作品についてきちんと理解していない、キャラクターへの愛も感じられない、第三者による派生作品の設定に合わせてしまう、故人の存在をも利用してしまう、ファンからの問い合わせにも応じない…)
私自身、ファンとして、赤塚作品に対して「あれのリメイクアニメが観たい」「あれとコラボしてほしい」というように様々な希望や展望がある。しかし、今となってはそうしたものについても、「この人たちに任せていて大丈夫だろうか」という感情が拭えず、期待が消えたわけではないが不安がかなり大きくなってしまっている。現に「おそ松くん」がこんなことになってしまっているんだから。
これまでも赤塚作品絡みであまり良いとは言えないことは度々あったが、概ねはあまり重視せず見逃してきていた。しかし、そんなアレやコレやについても「フジオプロがこんな体制だから起こってしまったことなのでは」と感じ、一気に気になるようになってしまった。
実を言うと、この件がわかって以降、それ以前と比べて赤塚作品を気兼ねなく楽しむということができなくなってしまっている(あくまで"それ以前と比べて"ではあるが)。
作品や赤塚先生本人には何の罪もないのに…。
赤塚作品を見ていると、どうしてもこの件のことが頭をよぎってしまうし、「今」赤塚作品を推すということは必然的に「今」のフジオプロを支援することにも繋がる、と考えてしまう。
他の往年の人気作品と比較しても、「どうして赤塚作品だけ、こんなことになってしまったんだろう…」という風に感じることが増えた。
あえてこういう言い方をするが、「好きなのに、好きだからこそ、好きなように好きでいられない」というような、矛盾した状況が今ある。
赤塚ファンになってからもう15年以上経つが、ここまでのことは初めてだ。
私だって、「赤塚作品なんか好きになるんじゃなかった」とだけは絶対に思いたくない。
長くなったが、これが問題についてと、今のありのままの感情だ。
私はそれほど、重く、辛くこの件を受け止めているのだ。
フジオプロさん。
ここに書いてあることが違うのなら、何か言ってくださいよ。
結局のところ…
ここまでざっと書き綴ってきたが、やはりどんな言葉を使うのが正解かわかっているわけではないので、問題についても感情についても、ちゃんと適切に的確に閲覧者の皆さんに伝わっているかどうか、正直言うと自信がない。ちゃんと伝わっているだろうか。
私はこれまで、この件について、ずっと思い悩んできた。状況が変わらないから、ずっとそのままなのだ。
そんな風に、変わらない状況の中で、変わらない状況の中だからこそ、考えることがある。
結局のところ、こんなに重大視しているのは、自分だけなのではないか、と。
この件に対して否定的な見解を持っている方が自分以外にも大勢いること自体は存じ上げている。サイト側が動いてくれない状況の中で、それは私にとっては心の支えでもある。しかし、ここまでこの件にこだわり、大きく問題視しているのは自分だけなのではないかと、思ってしまうことがある。
私は一応、サイト宛に二度意見を送った。かつ、当ブログ内やTwitterでは、「この件を良くないと思った方は、サイト宛に意見を送ってほしい」という旨の呼びかけも行った。
結局、自分以外に意見を送った方というのは、いらっしゃったのだろうか。
そういった話を聞かないので、おそらくいないのではと思う。
そりゃ、問い合わせの数が多くなれば変化が表れるという保証もないし、人によって事情などもあるだろう。私も、無理強いをしたいわけではない。
しかし、本当に意見を送ったのが私だけであれば、その事実はどうあっても残る。
私は一人で騒いでいるだけだったのだろうか。
そうなると、サイト側からしても、あくまでも一ファンの意見、極端な言い方をすれば"わがまま"のようなものとしてしか見られていなかったのだろうか。
まぁ、一人の発言や行動にいちいち一喜一憂するのも"公式"にあたるポジションとしては問題ありなのかもしれないし、ファンからの意見や問い合わせには全て応えろというのも傲慢なのかもしれない。
それでも、やっぱり、数は別として、内容としてこれは「ファン一人のわがまま」として片付けて然るべきことなのだろうか?という疑念は残る。
もう率直に言おう。
皆さん、
私の言っていることと、
フジオプロのやっていること
正しいのはどちらだと思いますか?
いや、ほんとに。
私がもし何か間違ったことを言っているのなら、教えていただきたいのだ。
…ふりだしに戻るようなことを言うようだが、
この件の何が良くないか最も根本的なことを言えば、
「公認サイト上の六つ子の紹介文が書き換えられた」ということしか、事実として確実なものがないということだろう。
どのような意図・経緯・根拠のもとああいった改訂が行われたのか。
誰の意思が主導となって行われたことなのか。
全くわからない。
公認サイト内やフジオプロの運営する別サイト等各所を見るに、六つ子各人を均一なものとして区別しない扱いが徹底されているわけではないので、余計にどういうつもりなのかがわからない。
(単に放置されているだけなのかもしれないが…)
ファンの声を求めるようなフリースペースを設けておきながら、その内容には無反応なので、ファンの声に耳を傾ける気があるんだかないんだかも、さっぱりわからない。
フジオプロが何を考えているのかが、私にはさっぱりわからない。
わからないから、ひたすら思いを巡らせては空回りするだけ。
"公認"ってなんだ。
"公式"ってなんだ。
何が正しいんだ。
誰が赤塚作品を守るんだ。
俺はどうすればいいんだ。
俺にはわからない。
(参考:サイト宛に送った意見全文)