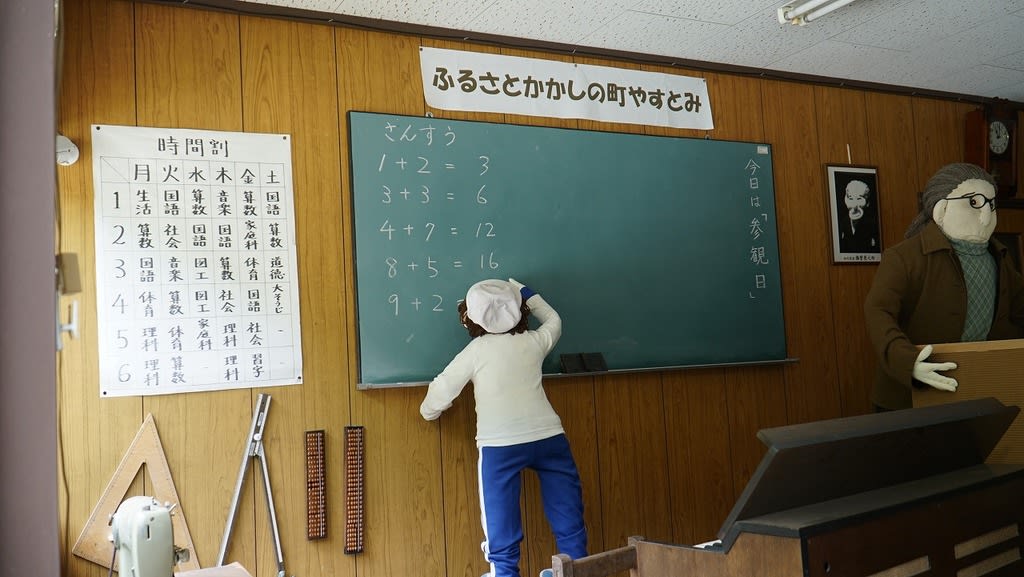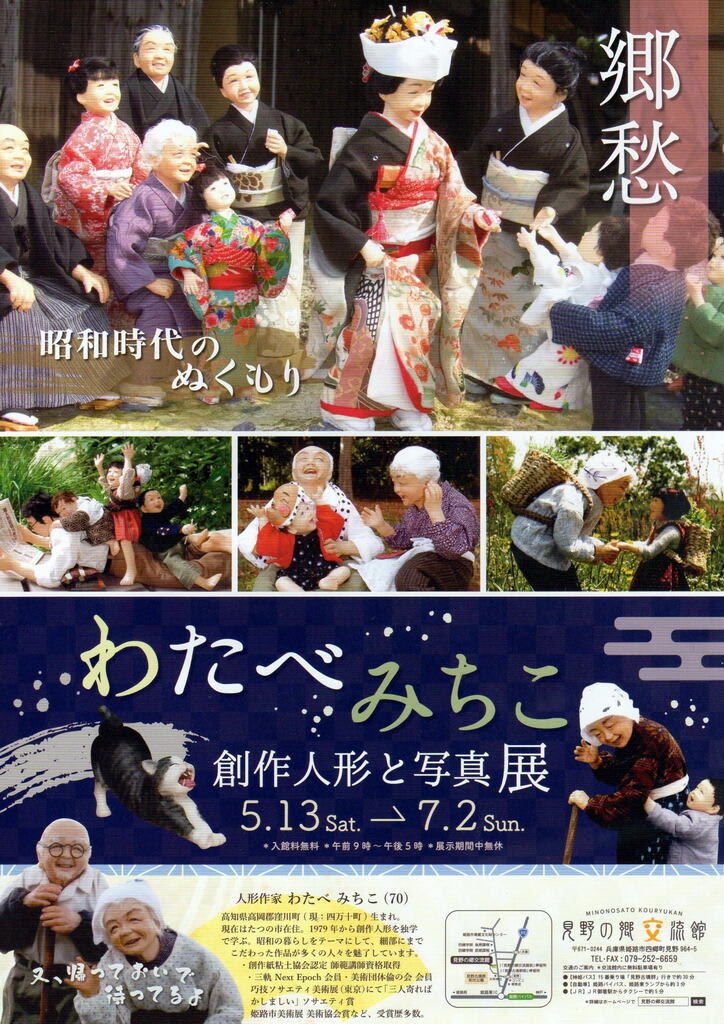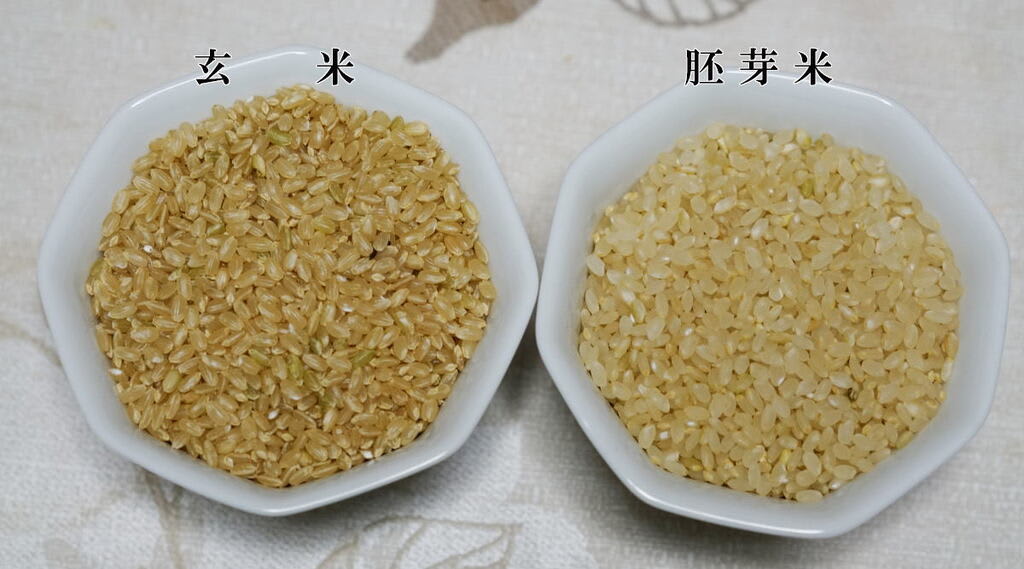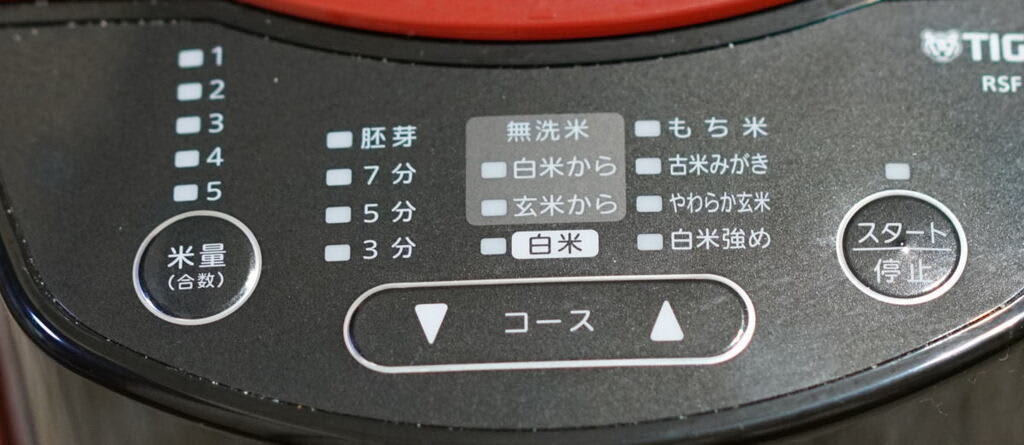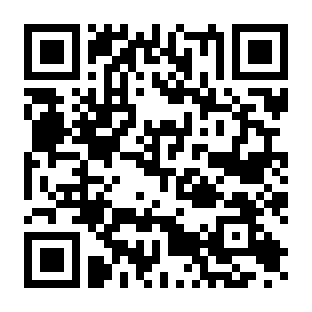キンモクセイとクマゼミ
近年ニイニイゼミやアブラゼミを見かけることが少なくなりました。子どもの頃クマゼミは珍しくて、見つけても木の高い位置に居るため、捕まえることが難しくその分捕まえたときはわくわくしたことを覚えています。時代は移り、数十年前に庭に植えたキンモクセイが大きくなり、いつしかクマゼミがこの木と庭を居場所として夏が来れば朝早くからシャーシャーシャーと賑やかな合唱を聞かされるのが我が家の「夏の風物詩」でした。
このキンモクセイは、秋にいい香りを漂わせてくれていたものの、大きく茂り過ぎたため、落ち葉がトユを詰まらたり、庭を掃いても掃いてもきりがなくなりました。昨年5月思い切って幹の一部を残してほとんど切ってしまいました。そのため、昨年の夏は、セミの居場所がなくなり静かでした。それが今年になって細い枝が多く出たせいもあって、ここ数日クマゼミが鳴くようになりました。
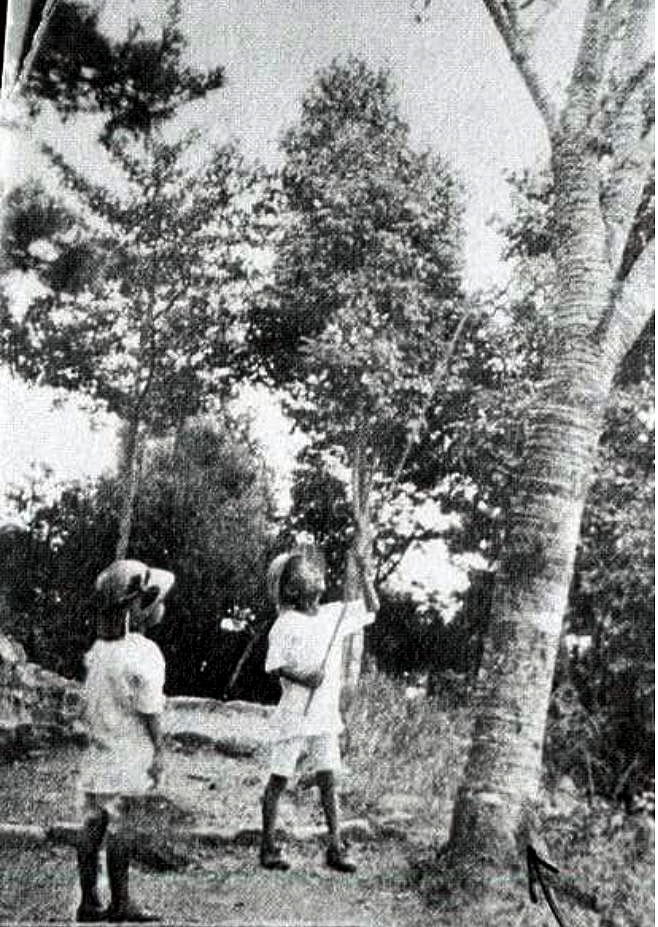
▲古写真 セミ捕り(最上山)

▲庭のキンモクセイ 小枝が多く出てきました。

▲昨年切り落としたものの一部

▲クマゼミ
クマゼミの一生と寿命を考えてみた
セミは、何年(数年~7年)もの間、地中生活を経て、地表に出て、わずか1週間程の命という。地表ではオスは早朝より鳴き続け、メスに居場所を知らせる。大切な種を残すための貴重な日々だ。その日の為に地表に小さな穴を空け、木に登り脱皮する。それは長年地下生活で身を守ってきた防御服を脱ぎ捨て、新たな生活に羽根を身に着けることだ。卵から幼虫、そして脱皮(羽化)を成功させたものだけが、種を繋ぐことができる。7年ともいう長い地中生活の期間は詳しくわかってはいません。セミの種類、個体によって違いもあるのだろうし、居座った木の根っこの栄養分の違いもあるのでしょう。ちなみに、キンモクセイはセミの好きな木であるようです。
そこで、セミの地上生活の1週間は、寿命全体のどれくらいの割合になるのか、計算してみました。すると寿命の1%にも及ばない0.27%ことがわかりました。
(計算式)
地上の生活日数(推定1週間)÷ セミの寿命(推定7年とする)
7(日)÷(7年×365日+7日)×100=0. 27%
この0.27%の数字を人間の寿命に例えると、どうなるのでしょうか。
計算では84日(3か月弱)の短い期間になります。
卑近な例ですが、核シェルターに入った生活を余儀なくされたとして、一生で3か月しかお日様を拝めないことになります。分割しても1年に1日しか出られない計算です。
セミの生活が暗い地下生活でかわいそうだとか、何をしてるんだとか、何を食っているんだとか、そんなことは勝手な人間の思いであるわけで、セミに聞いたらほっといてくれと返事が返るかも知れない。これがセミの生きるサイクルなのだから。 でも、長すぎじゃない……
(計算式)人間の寿命を仮に85歳とすると
85年×365日×0.0027=84日 3か月弱
クマゼミの地下生活期間の実証実験を思いつく
この木には、卵を生みつけるスペースはほとんどなくなったので、7年前に産みつけられた卵(幼虫)があと5年間は毎年庭から出てくると考えられます。はたして6年後にはにはセミは出てこなくなるのかどうか、クマゼミの地下生活の期間を推定する実証実験を続けてみようかと思っています。
このブログを最後まで興味深く見ていただいた方には、是非ともフォロワー になってください。そうすれば、実験結果を知るチャンスがありますよ。_(._.)_(笑)

▲枝に残されたクマゼミの抜け殻

▲▼こんなところ(干していた風呂のマットや井戸縁)に這い上がっていました


◆城郭一覧アドレス