「
其の壱(第二章~第五章)」はこちら。
「第六章 京のかたなの再興(室町時代後期 - 桃山時代)
戦国時代の終焉とそれに伴う上方の発展により、再び活気を取り戻す京都の鍛冶。新刀の登場です。
新刀の祖・埋忠明寿、三品派・伊賀守金道、堀川派・堀川国広の作が展示されています。
ちなみに堀川国広は、私の最も気に入っている刀工だったりします。
「No.119 重美 刀 切付銘 備州住長船兼光 大町仁右門尉磨上之/嘉吉二年八月日 中心有之」は、磨上加工の最初期の作例。
そして「No.120 重文 刀 本作長義天正十八年庚寅五月三日二九州日向住国広銘打/天正十四年七月廿一日小田原参府之時従屋形様被下置也長尾新五郎平朝臣顕長所持」(長い

)。
いわゆる「本歌 山姥切」です。堀川国広が磨上げ、銘を刻んだのがこの刀。
この作業に先立ち打たれた刀が、写しである「山姥切国広」、これを高く評価されて磨上げを命じられたのだそう。
本歌と写しという概念を捨てて観るべき二振であることは明らか。
この本歌、基本は一定リズムの乱れ刃文。身幅は広く重ねは厚め。備前長義の手による刀。
「No.122 短刀 朱銘元和二 正宗/光徳(花押)(名物 朱判正宗)」、相州鍛冶の特徴が随所に見られるとのこと。
「No.123 重文 刀 金象嵌銘 本多美濃守所持/義弘本阿(花押)(名物 桑名江)」は全てが無銘の極め。相州風と大和風が一体となった作風。
「No.128 重文 刀 銘山城国西陣住人埋忠明寿(花押)/慶長三年八月日他江不可渡之」は、初めから磨り上げたような形に作られていて、慶長新刀の初代にして最高作とされる一振。
「No.135 重美 短刀 銘 藤原国広造/沢田道円所持」は、短刀の中では最大級の身幅を誇る。
「No.141 剣 銘 肥後住人越前守藤原国次/貞享四丁卯歳十月吉日」は、永世文庫の蔵から発見された新出の剣。密教系寺院への奉納用と見られる。
この章で最も混雑していたのは「No.151 刀 銘 吉行」、陸奥守吉行。
そして「No.140 刀 銘 濃州関住兼定作(号 歌仙兼定)、でした。
個人的には「No.143 短刀 銘 濃州岐阜住大道/信濃守国広」が超おススメ! 単眼鏡で、かつ離れて観るととても綺麗。
なお、ここでは章の冒頭にて「重文 阿国歌舞伎図屏風」も展示。刀だけじゃないのだよ。
「第七章 京のかたなの展開(桃山時代 - 江戸時代前期)
京都の鍛冶の元で学んだ門人たちが全国へ展開、各地で新たな新刀文化が芽吹く。
ここでは新刀文化の完成形・大阪新刀が観られます。
「No.160 重文 銘 粟田口一竿子忠綱 彫同作/宝永六年八月吉日」は、自らを粟田口の末裔と名乗る刀工の作。足長丁子と呼ばれる刃文が特徴で、その刃渡りは実に90cm以上。
大阪新刀は評価が低く、現在その見直しと再評価が叫ばれているのだそう。
「第八章 京のかたなと人びと(江戸時代中期 - 現代)」
京都の人々にとって「刀剣」とは何か。
古社寺に奉納された宝剣や御神刀、そして祇園祭。
そして現代。立命館大学と京都大学にて作られた刀と、そこから巣立った最後の最後の山城鍛冶にて人間国宝・隅谷正峯の作品を。
ここでは「名物 膝丸(薄緑)」「名物 義元左文字」が展示。「圧切長谷部」と同様、後ろ側も観られる展示。
「膝丸(薄緑)」は以前同じ名前の一振りを箱根神社の宝物殿で見ているのですが、かなり違います。こっちのが全然すごい。
「義元(宗三)左文字」は今回は後ろ側が観れて感激。
祇園祭にちなんだ屏風や人形、そして若冲の「伏見人形図」等を経て、流れは現代へ。
大正・明治・昭和に立命館大学と京都大学で打たれた刀。
人間国宝・隅谷正峯の手による「No.200 太刀 銘 備前国包平作/傘笠正峯作之 平成八年十二月日(大包平写)」が展示のフィナーレとなります。
とんでもない再現度です。実物を見た記憶がまだ新しいだけに、本気でその技術に圧倒されました。
この完成の二年後、氏の逝去をもって山城鍛冶の歴史も終焉を迎えたのだそうです。
で、ここで私は3階へ戻ります(混み過ぎで流し見しただけだったので)。
「第一章 京のかたなの誕生(平安時代後期)」
合戦絵巻と文書による、刀剣誕生の背景。そして山城鍛冶の祖である三条派・宗近と、派生した五条派など、山城鍛冶の源流を。
ここに展示されているのは「No.7 国宝 銘 三条(名物 三日月宗近)」。ケース四方を巡る形で鑑賞できます。
東博で展示の際に見られるのはやはり一方だけなので、これはなかなか有難い展示です。
地鉄が摩耗し、刀がうるみ、打ち除けが生じているのだそう。
3階に展示されている刀は全てが平安刀で、状態の良いものが揃えてあります。
鉄としては当たり前に、とうに寿命のはずなんですけどもね・・・。
個人的には「No.14 重文 太刀 銘 兼長」がおススメです。
鋒が小さく細身、華奢な刀。地鉄が白銀みたいでした。
「No.16 太刀 銘 国永」、この銘で最も有名なのは「皇室御物」鶴丸、ですね。
ここで全てを鑑賞終了。時間は16時を回っていました。
それにしてもとんでもない展示数・とんでもない振数・とんでもない情報量です。
メモに鉛筆持参で書きながら進んだのですが、最後には芯がすり減り字を書くことができませんでした。
それでも何とか記した言葉は「すごい」「きれい」「好き」・・・語彙力どっか行きました。
2日目(10/11)は同じく11時半に入館、前日のデータ補完をメインにぐるぐる鑑賞しました。
出たのは15時過ぎ。
2日間で館内滞在時間は合計8時間(4.5+3.5)!
その間一度も座らず喫茶等も挟んでいないので、単純に鑑賞だけで捉えると7時間半は観てたことになります。
これ、足痛くて当たり前だし、普段めったに出ない腰痛も出るわけです(苦笑)。
それでも、観に行けて本当に、本当に、心の底から良かったです。
これを魅せて下さった全ての方々に謹んで御礼申し上げます。ありがとうございました。
本音を言えば後期展示も行きたい、のですが、ガマン、我慢・・・・・・。















 本堂。
本堂。
 拝殿と、奥に信長公墓。
拝殿と、奥に信長公墓。
 森蘭丸と、その弟・力丸の名も。
森蘭丸と、その弟・力丸の名も。
 着いた♪
着いた♪ 

 平成知新館内から庭園を。
平成知新館内から庭園を。
 車窓に富士。
車窓に富士。 墨染駅下車・
墨染駅下車・


 続いて
続いて 11時半入館。
11時半入館。 雨上がりの「考える人」。
雨上がりの「考える人」。


 夜の
夜の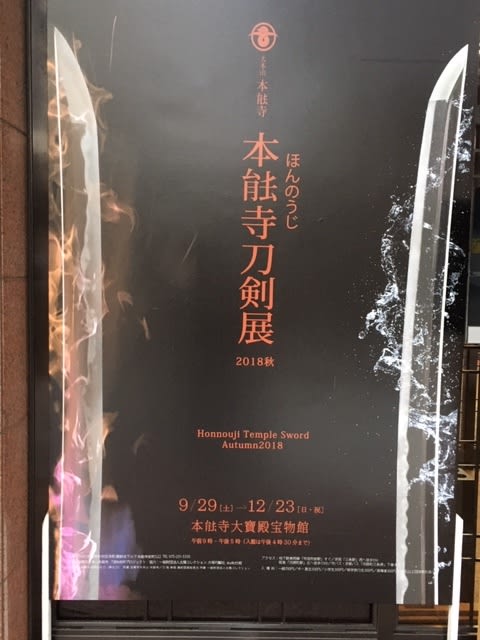
 さて、三階へ移動。こちらは撮影OK。
さて、三階へ移動。こちらは撮影OK。


 )。
)。


 じゃーん!
じゃーん!
