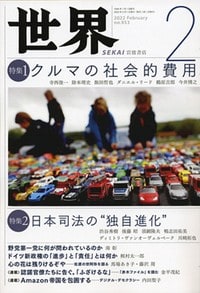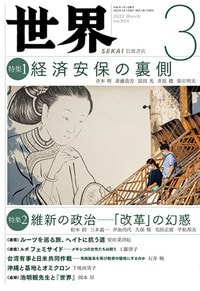富岡の『世界』を読む会・2月例会の報告
(郡山さんから)
富岡『世界』を読む会・2月例会は、2月16日、6人が参加して開催された。
テーマは、『世界』2月号の
「特集1.クルマの社会的費用」から、
ダニエル・リード『Fun to Drive?―トヨタと気候変動』、
飯田哲也『テスラ・ショック-モビリティ大変革と持続可能性』および
鶴原吉郎『電動化が引き起こす自動車産業の「解体」と「再構築」』の三つの論考、そして
「特集2.日本司法の"独自進化"」から
須網隆夫『取り残される日本の司法』と
ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーク『日本の法曹養成制度は社会の変化に対応できているか』
の二つの論考、合計5論考を取り上げ、話し合った。
二つの特集ともに専門性が高く、テクニカル・タームを丁寧に読み解きながらの読書となった。
特集1.クルマの社会的費用について。
まず事実の確認。地球上のCO²排出量の24%が輸送機関が占め、その45%が乗用車である。その自動車が現在14億台稼働し、毎年1億台の新車が販売されている。これは、人類と地球の未來にとって「危険な光景」(リード)との指摘に納得。Hさんは、「このことは50年前に、宇沢弘文が先取り的に警告していたことだ」と紹介した。
テレビコマーシャルでは、トヨタ自動車の脱炭素化・全方位戦略が喧伝されているが、トヨタが気候対策ランキングで最下位にあることをリード論文で知る。中・米・欧の自動車メーカーと新規参入企業が、極めて積極的にEV戦略を展開しているのに対して、世界トップメーカーであるトヨタ自動車の慎重さや曖昧さが際立っている。特集2の日本司法の"独自進化"という言葉を援用すれば、トヨタの全方位戦略はまた、日本自動車の"独自進化"といえるかもしれない。この独自進化こそが、飯田哲也のいう「半導体・家電・液晶・太陽光と次々に敗れ去った日本の、最大かつ最後の基幹産業である自動車産業の危機という"日本沈没"リスク」なのだろう。
では、日本のEV化の課題は何なのか。Sさんは、EV化必至とする各論考に対し、疑問を提起した。まず、日本の再生可能エネルギー発電の進捗の遅れから、ただ自動車のEV化だけが先行しても、脱炭素化にとっては意味がないのではないか。また、EV化に対応した充電設備等のインフラ整備が遅々として進まず、しかもEV自動車が超高価格であることから、2030年目標到達は極めて困難だ、と発言した。EV化に積極的な中・欧・米各国政府および多国籍ファンドの最大の関心事は、気候変動対策も然(さ)る事ながら、産業・経済政策の面がより強いのではないか、との指摘もあった。また、南北格差や貧困問題をそのままにしてEV化を論じても、「先進国の富裕層のみのEV」となるのではないかとの懸念が示された。
そこで問題は、EV化の必要性・重要性を肯定しつつも、本当にそれだけで脱炭素社会へ到達できるのか、ということだ。リードは「クルマの数そのものの減少が必要」だとし、究極的には「移動自体を減らすことが必要」と主張している。飯田もまた、「そもそも私たちは何のために移動するのか」という根源的な問いかけをした。コロナ禍のもと、私たちは移動・外出・旅行・海外渡航などの制限や自粛を求められた。メルケルが苦渋の選択として国民に訴えかけたように、移動制限は基本的人権としての自由権を侵すものであることは、自明のことである。では、「移動自体を減らす」ということをどのようにイメージすればいいの? 通勤・通学距離の縮小、買い物・遊興距離の縮小、エネルギー・食糧・貨荷物郵送距離の縮小などが、移動減少に寄与する。それらを実現するための社会経済政策コンセプトは、巨大都市・一極集中から地方中小都市・多極分散、店舗や遊興施設の広域大型から狭域小型、エネルギー・食糧・介護の自給自足などとなるのではないか。つまり脱成長=循環型社会・経済を構築していくことが、いま厳しく問われている。
特集2.日本司法の"独自進化"について
日本の弁護士数は、人口当たりでみると1/2986(2020)で、欧州の1/6~1/3程度である。つまり弁護士は少ない。だから、参加者の身近に弁護士は少なく、その姿は漠然として定まらない。マイノリティの味方になって法に基づき正義を実現してくれる存在、という認識もあれば、米国TVのリーガルドラマの描く大企業をクライアントに「正義よりも利益」を追求する有名弁護士像まで、さまざまだ。ただ、日本社会が今よりも多くの弁護士を必要としていることについては、その善悪を超えて、そうなんだと納得してる、との発言があった。
須網論文『取り残される日本の司法』は、法曹界の国際交流について多くの事を教えてくれた。異なる裁判所が判例情報を交換する「裁判官対話」や欧州の憲法裁判所を中心に62か国の現職裁判官が作っている「ヴェニス委員会」と118か国参加の「憲法裁判世界会議」、そして韓国憲法裁主導による「アジア憲法裁判所協会」などである。これらの国際交流に、米・欧・韓の法曹界が積極的にコミットしているのに対し、日本の法曹は参加せず、消極的である。とりわけ、アジアの隣国、韓国法曹界の国際性には目を見張るものがある。このことは、韓国の慰安婦裁判や徴用工裁判で、国際人権条約が重視されていることと無関係ではない、との発言があった。
ディミトリ・ヴァンオーヴェルべーク論文『日本の法曹養成制度は社会の変化に対応できているか―ベルギーから見て』は、ベルギーの法曹養成制度-大学教育5年・実務研修3年・資格取得後の継続学習-においては、「非法律系学習を弁護士業務に不可欠として重視し、多文化・異文化理解能力の向上を必須としている」と指摘した。国際化を「知的財産権」問題に集約する日本の法曹界との認識差を強く感じる。
ガラパゴス化とはweblio辞書によれば、「 市場が外界から隔絶された環境下で独自の発展を遂げ、その結果として世界標準の流れからかけ離れていく状態を揶揄する表現」と定義されているが、日本のEV化を含めた気候変動対策も、日本の司法の在り様も、まさにガラパゴス化していると言わざるを得ない。『世界』2月号の二つの特集から、このことを痛烈に感じさせられた。