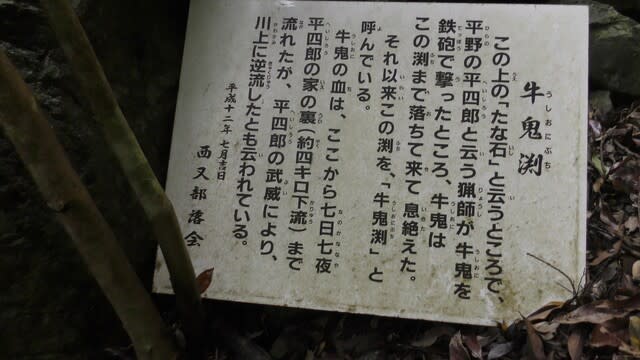このシリーズを書く上で、大雨のせいにはして行けない!
確かに、大雨が降り、今の東祖谷の実情を知ってほしいと言う思いからも
8月は雨に関しての話題が多くなっていていましたが、大きな被害も無く
安堵した8月の長雨・・・8月も下旬ころから9月にかけて天候も安定し始め
落ち着いた状況と言う事もあり、途中で終わらせたら、一体何だったのか・・・
と言う事になりかねないので、続きを書いて見たいと思います。
あたしゃ~の、ごたくは、いいから早く進めろ! 失礼いたしました。

今回の目的は!やれやれ峠とは、何ぞや!と言う所にありました。地名の由来からして
どのような場所なのか?興味が湧いたのは言うまでもありませんでした。
そこで、数回にわたり県南・牟岐へ!と言う事でシリーズを書いていますが、
やっとヤレヤレ峠へ!歩いて20分程度の行程との事でしたが、道は荒れていたり
新道があったりと、迷う場面もあったり!
波瀾万丈な行程となった峠歩き・・・少しずつ書いて行きたいと思います。

やれやれ峠への道・・・最終的には道跡などの痕跡を見つけながら峠への
道を見つけ出しました。入道山・登山への道の一つとされて
色々な方が本やネット情報などで書かれていますが、今回、参考にしたのが鳴門岳友会の
徳島250山と阿波の峠を歩く会の2冊の本の資料と山マップにあった資料を参考に
歩いてみました。実際には手ごわい! GPS受信機を持っていたから
何とかなったものの20分処か!倍の時間をかけての峠にある地蔵尊へ到着!
困難極めた峠歩きとなりました。
廃道となりつつある峠道・・・地図読みや道跡などをイメージが出来る人・・・
向きの場所でもあると書いておきます。
あまり、山に関わった事が無い方、山登り初心者の方、方向感覚つかみ難い方などが
興味本位で行くと思わぬ事故などに繋がりかねないと言う事だけ書いておきます。

今回は知人でもある大学の名誉教授も同行したいとの事だったので一緒に登る事に・・・
登山口から登ると歩きやすい歩道が見えて来るのですが・・・これが
最初の落とし穴でした!
この道は歩きやすかった事も有りますが、林業を行うための作業道のようでした。
奥谷トンネル方向に伸びている歩道は地図上の、やれやれ峠へ峠への
方向に向かっているのですが、実際のやれやれ峠には地蔵尊がある場所・・・
GPS受信機を見直し進む方向を定め直した時でもありました。
歩いて来た道を引き返しGPSを見直し進む方向の選択を測り進む事に・・・

GPSを確認する中、どこが道なのか?四苦八苦する事となりました。
道らしきものが数本・・・どの方向に進めば・・・?
とにかく、あらかじめ、GPSには進行方向のデータと前任者の方が踏破したデータを
入力していたので、データを頼りに進む事に・・・・
確かに、本にも書かれてありましたが、道跡が、わかり難い場所があるとは書かれてありましたが
ここまで来ると本当に解かり難い・・・慎重に道跡らしきものを見極めながら
進行方向を進む事に・・・

頼りになったのが、これ!持っているのが良いのか?持っていないのが良いのか?
持っていても、使い方が解らなければ、ただの箱・・・・
最近ではスマホ・アプリでもGPS機能が充実したものがありますが、持っているからと
いきなり、山に入っても使い物にはならないので、使い方を熟知した上で
山と向き合いましょう!
私の場合は自宅周辺を持って歩き、データを収集し、パソコンに収集データを
表示させたり、GPS上に表示される地図データ(等高線)を見ながら
進むべき目的の方向・進んでいる場所に何があるのか?
(等高線の間隔を見て急斜面や崖・谷川などが無いかなど・・・)
基本的な地図読みが出来て初めて地図読みの面白さや危険個所の回避などにつながる
のでは無いかと思われます。
この事からも、GPS受信機などを持っているから安心と言うのではなく
サポートをしてくれる道具の一つでもあるものだと言う認識の上
使い方を間違えるとGPS受信機・スマホ・アプリを使っていても
道迷いは起こります・・・私、自身もこれまでにも受信機を持っていても
何度か道を間違った事もあり50m前後の場所で間違いに気づき
引き返した後に進行方向を補正し進むべき方向に進み難を脱した事も多々あり・・・
経験上の事も書いておきます。
この事からもGPS受信機などの取り扱いについては、身近な場所で扱い方を
学んだ上、経験を重ねて行きながら安全な登山をサポートしてくれる
これらの機器の取り扱いを行って頂けたらと思います。
話が脱線いたしましたが・・・次回!ヤレヤレ峠にたどり着いたのか・・・?
そこにあった物は・・・など???これは別のお話に・・・!