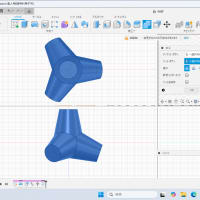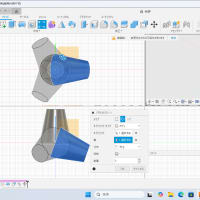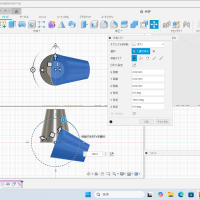ジョンズ・ホプキンス大学キャリー経営大学院のクリストファー・G・マイヤーズ氏らは、「失敗したときに、その責任を自分で負う人は、そうでない人に比べて失敗から学ぶ確率が高い」とする研究報告をまとめました。
一方で、「失敗したのはあの人のせいだ、状況が悪かったからだ」など他責にする人は失敗から学べず、次なる挑戦において成功確率を上げられないとのこと。
失敗から背を向けるのではなく、自分の責任ととらえて今後の改善策を立て、実行する。このサイクルを回せる人が、成長できる人なのですね。
過度に自分を責める必要はありません。「失敗は成功のもと」という言葉があるとおり、「何が問題だったのか」「今後どうしたら防げるのか」を冷静に考え、そこから “学ぶ” 意識をもつことを心がけましょう。
3. 頭のいい人は「知性の落とし穴」に気づけていない
頭の回転が速いと言われる。専門知識の豊富さには自信がある——このように、頭のいい人のなかには、自分の知性を誇りに思う人もいるでしょう。ところが、そこにも落とし穴が。ジェームズマディソン大学とトロント大学の共同研究では、賢い人ほど、間違った答えに確信をもってしまうことが示されています。
たとえばあなたは、以下の問いにどう答えますか?
「合計1ドル10セントのバットとボールがある。バットはボールより1ドル高い。では、ボールの値段はいくらか?」
答えは10セント?——いいえ、正解は5セントです。
(※バットとボールの差額は1ドル。残り10セントをバットとボールで均等に分け、バットは1ドル5セント。ボールは5セント)
このような単純な引っかけ問題に、認知能力の高い人ほど、自信をもって間違えた回答をしてしまうのだとか。頭のいい人は、自分の論理的思考力や推論能力を過信する傾向にあります。つまり、すばやく答えを出すことに慣れているため、単純なミスを犯すのです。
この傾向は、チームワークにおいても問題となりえます。自分の主張がじつは合理的ではないのに、知性を用いて自分を正当化しようとするため、違う立場の意見を素直に聞き入れられないことも。
自分の頭の良さに自信があっても、誰かと意見が食い違ったときは、自らの主張を一度見直してみましょう。根拠は正しいのか、先入観で言っていないか、誤った確信をしていないか。冷静に考える癖をつけることが大切ですよ。
4. 頭のいい人は「成功が幸福とは限らない」と気づけていない
優秀な人ほど、成功のためにスキルを磨き、よいキャリアを築くことに注力するものでしょう。ですが、頭がよければ成功でき、成功できれば幸福になれる “とは限らない”、と留意しておいてください。
前出のアリス・ボーイズ氏によると、知能が非常に優れている人は知能以外のスキルを重要視しない傾向があり、高い知能さえあれば成功できると思い込んでいるそうです。
たとえば、「専門性の高い業務をミスなく遂行するには、知能があれば十分。面倒な対人関係を構築する必要はない」と考えるといったようなこと。ですが本来、仕事はチームワークをともなうものですから、人間性を高めることも必要ですよね。
また、成功によって幸福になるとは限らないことも明らかになっています。「幸福学」の第一人者・慶應義塾大学大学院教授の前野隆司氏は、「年収が上がって満たされるのは満足度だけで、幸福そのものではない」と説きます。
出典:https://studyhacker.net/smart-people-mistakes
⇨この記事における「頭が良い人」とされている基準は学力偏差値であって 正確に言い換えれば「頭の回転が速く 知識の量が豊富な人」である
「頭の回転が速い」というのは 思考が短絡的であるということでもあります
既に知っている思考のパターンに則った思考であるからこそ高速化が可能であって 深層学習型ニューラルネットワークAIで例えれば「蒸留(高度に学習された状態)」のことだと言えます
「学力=知能」という短絡的解釈には認知科学的根拠がないにも関わらず 「皆がそう言っているから」という「多数」こそが「正常」だという「常識(正解データ)」として「学習」されてしまっているために とても速い判断ができるようになるわけです
ヒトの脳はコンピューターのようにクロックパルスが高くできるわけではなく 神経回路の伝達速度そのものはヒト同士どころかサルでもさしたる違いはありません
思考の速度が「学習」によって速くなるのは 思考を単純化させているからであって 単純化された思考回路は専門性が高くなる一方で応用性が失われることになります
普段 私達が日常生活を送る上において 物事のいちいちを全部論理的に検証して判断することはほとんどありません
財布の中のお金が偽物かどうかをいちいち確認したりはしないものです
ヒトはそうやって お店で渡されたお釣りに偽札は混ざってなどいないという前提で生活しているものであり これは思考判断を単純化させているからです
アイヒマン実験において ヒトの6割以上が権威の命令に唯々諾々と服従し他人に危害を加えてしまうのも 普段の生活の中で権威を疑う必要性がないため 思考が単純化され 権威から命じられた内容に疑いを持つ応用性を失っているためです
普通の一般の人達は「東京大学名誉教授の言っている内容が本当に正しいことを言っているのかどうか」をいちいち考えたりはしないものなのです
○「失敗したのはあの人のせいだ、状況が悪かったからだ」など他責にする人は失敗から学ぶことができない
しかし「自責の念に駆られて」も失敗からは学べません
過度に自分を責める必要はありません。「失敗は成功のもと」という言葉があるとおり、「何が問題だったのか」「今後どうしたら防げるのか」を冷静に考え、そこから “学ぶ” 意識をもつことを心がけましょう。
とあるように あくまで客観的に失敗の原因究明と再発防止策を考え発見することから「学ぶ」ことができるのです
ところがヒトという種の生物は 先天的には論理客観的に「本当のこと」が何なのかを識別できるようにはできていないため どうしても「他人の所為」にするか「自分はバカだ」と気分的に嘆くことが優先してしまいがちです
これは先天的本能によって促される感情や気分の方がが理性よりも優先してしまっているからであって 非合理な観念の世界に閉じこもってしまうため 論理整合性の方が後回しになってしまうためです
養老孟司は「論理整合性がないだけ開かれているではないか」などと言い出しましたが 論理客観的根拠を伴う真実を見極める理性よりも観念や感情の方が優位になっているために「開かれている(自由)」ような感覚(錯覚)になっているだけなのです
通り魔の類いが支離滅裂なことを主張するのも 養老孟司の支離滅裂さと構造は一緒であり 論理客観的根拠を伴う真実よりも既に刷り込み学習された自分の「常識」に則った観念の方を優先することで支離滅裂な主張を平気で行えるようになるのです
Ende;