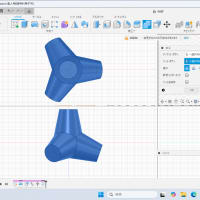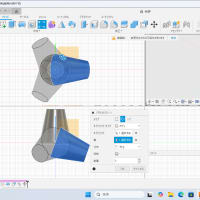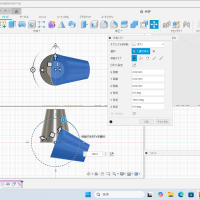○タイミングを逸する。
「質問をするタイミングを逸してしまい、黙ってしまう。」という若者がいて、本当はいつ聞いても良い内容の質問なんだろうけど、雰囲気とか空気を読み過ぎてしまって、何も聞けなくなってしまうらしい。
詳しく聞くと、幼少期に虐待を受けた経験があるそうで、多分深層心理に対人恐怖が刷り込み学習されてしまっているために、本当は何の問題もないことであっても観念的恐怖心によって萎縮して必要な質問すら出来なくなってしまっているのではないだろうか。
幼少期に虐待をされた人が対人関係が苦手なのは仕方のないことだと思う。対人関係が苦手であるならば対人関係をほとんど必要としない仕事の方が当人も楽なのではないだろうか。
「多数他人との関わりが必要。」というのは、必ずしも仕事の上でなければならないものではないと思う。当人が最も楽に続けられる、個人的にも持続可能性な生活を探した方が良いのではないか。
そう思う。おいらがそうだからだ。
「友人の人数」を幸福と置き換えるというのは、本質自発性のない茂木健一郎らしい解決策である。
最近の研究では、イジメの原因の一つとして、「友達の数で他人の価値を量る観念」が働いているという説は有力であり。本能的な社会形成習性として、友人の数に気分的安心を基準に他者の価値を推し量り差別排除の「根拠」とするのである。故に「キモい」だのといった極めて主観的好き嫌いをイジメ差別の「理由」にされてしまうのである。
茂木健一郎は、あくまで大衆からのウケ狙いで社会問題に首を突っ込んでいるだけであって、本当は「人間について。」科学的検証をしようという純粋な好奇心を持って研究しているわけではないのは明らかである。
「支え合って、絆作って、組織的に何かやらないと国際競争力なんかつかない。」:茂木健一郎
これは一面的には正しい。振り込め詐欺師集団であっても支え合い絆で結ばれているからこそ巧妙な組織的統率詐欺が可能になるのであって、その組織というものが組織内部の閉じた価値観を共有してしまうことが問題なのである。
そもそも国際競争力と個人の幸福とは直接関係するものではない。
集団組織的に何かをやるにしても、個人の基礎的能力がなければ集団から必要とされないことになるので、基本的スキルは必要である。それが必ずしも他者との関わりを必要とする能力である必要性は論理的にない。
他人との関わり合いを重要としないスキルというのもあって、アルゴリズムを考える仕事などは他者との関わり合いを必ずしも必要としないものである。他にもそういった仕事はあるはずであろう、問題なのはアルゴリズムやアイデアを搾取するバカがいることでスキルが仕事として成立しなくなってしまうことである。他者を騙して利益を得ている卑怯者が減らない限り、個人が能力を発揮出来る社会にはならない。
幼児期に虐待を受けていたりすると、どうしても個人的に何が好きなのかを探すことすら苦手になりがちな傾向があって。これは自己の能力を過小評価するように刷り込み学習されてしまっているのが原因であろう。
多分、親などの他者からバカにされ続けて育ってしまっているために、一般的(多数決的)に学力成績偏差値が必要であると「思われて」いるようなスキルを、頭から(この場合の「頭」とは無意識的な思い込みのことを指す。)プログラミングなど出来ないものだと勘違いしてしまうのではないだろうか。ホームページ制作なんぞに何万も支払うバカな経営者が多いのも、ホームページ作成を特殊技能だと勘違いしているからである。大手銀行のダミーページくらいなら振り込め詐欺師でも作れる簡単なものなのである。
また、文科系マスコミの刷り込みで、「プログラミングをするには英語語学力が必要。」だとか言い張るものだから、余計敬遠されてしまうのではないだろうか。おいらは英語も読めないし、数学も苦手だけどアルゴリズムを考えることは出来る。クソゲーなんぞバカでも作れる代物なのである。
大規模プログラミングの場合は組織的な連携が重要な場合も多いが、個別のアルゴリズムを考える仕事においては他者との関係性よか一つのことに対する粘り強さ、執着心の方が必要だったりする。
しかし実際のところ中国と一緒で日本人にもアルゴリズムの知的財産権なんぞ守る奴なんていないからプータローが増えて、国際競争力も失う。誰かが言ってたけど、「奪い合うと足りなくなって、分け合うと余る。」ってこと。シリコンバレーっていうのは分かち合いの組織だから成長するんだろう。Googleなんて直接金にならないようなことばっかりやってるけど、最終的には莫大な収益を上げている。それが出来るのは当人達に自発性があって、他人から奪うよりも何かを築き上げることの方が楽しいからであろう。
スティーブ:ジョブズが「アルゴリズムは公開しろ。」などと述べていたが、これは現実にはシリコンバレーにおいてのみ有効な手段であって、マナーもすったくれもない日本においては通用しないのである。
本質的な自発性がなければ自律も養われないのがヒトという種の生物の行動習性でもある。茂木健一郎のように、「友達さえ多ければ幸福。」などという大衆観念に基づいた無意味な解決策しか出てこないのも、そこに本質的自発性の欠落があるからであって、どんなに茂木が研究費を浪費しても不毛なクソゲーくらいしか出て来ないのは当然である。
そもそも生物学におけるパラダイムの間違いを指摘出来ない茂木健一郎というのは他の生物学者同様に科学者としてポンコツであり、表面的ウケ狙いな活動をどんなにしていても、具体的な問題解決策が出てくることはない。「友達100人支給。」などという大衆観念に基づいた対策しか出て来ない無能な者を、単に大衆人気だけで学術権威として取り扱うのは大間違いなのである。
「友達の数」を人間の価値や個人の幸福として取り扱っている時点で、茂木は「ヒト」の行動習性の問題点について無関心であることを証明しているのである。「友達の数」などという大衆観念こそがイジメや差別排除の源であって、こんなことも知らずに一体「ヒト」の行動習性について一体何を論じられるというのであろう。
日本経済の崩壊というのは、政治や行政の問題だけではなく、それらも含めた日本人全体のモラルの無さ、すなはち論理的検証性に基づく自律の欠落が原因であって。特定権威組織の問題というより、個人の倫理の問題であって、無能な者を権威として取り扱う多数の無能さが権威組織の腐敗を進行させるのである。
アナキズムを振り回して漫然と権威を批判してさえおけば社会が良くなるわけではない。具体的に誰が権威として不適格であるかを論理的に検証し、地道に批判することが社会安全性にとって重要なのである。
原発を暴走させた「ヒト」達などの心理や行動を、危険工学的見地から検証しないことには、あらゆる「人災」の再発防止には構造原理的につながることはない。茂木健一郎や川島隆太などの大衆人気取りにしか興味のない脳科学研究者達が、どんなに大衆マスコミから重宝がられても、彼らの脳から「ヒト」の危険性についての検証は一切行われることはない。なぜなら大衆がバカのままでなければ脳トレ人気体制を維持することは出来ず、人気や金にならなくなってしまうので、大衆には論理検証の出来ないバカのままでいてもらわなければならないからである。
何度も言うが、脳血流の増加は「頭が良くなる。」ことの論理科学的根拠にはならないのである。当然脳血流増加によって個人の自律判断が養われることにもならない。
Ende;
「質問をするタイミングを逸してしまい、黙ってしまう。」という若者がいて、本当はいつ聞いても良い内容の質問なんだろうけど、雰囲気とか空気を読み過ぎてしまって、何も聞けなくなってしまうらしい。
詳しく聞くと、幼少期に虐待を受けた経験があるそうで、多分深層心理に対人恐怖が刷り込み学習されてしまっているために、本当は何の問題もないことであっても観念的恐怖心によって萎縮して必要な質問すら出来なくなってしまっているのではないだろうか。
幼少期に虐待をされた人が対人関係が苦手なのは仕方のないことだと思う。対人関係が苦手であるならば対人関係をほとんど必要としない仕事の方が当人も楽なのではないだろうか。
「多数他人との関わりが必要。」というのは、必ずしも仕事の上でなければならないものではないと思う。当人が最も楽に続けられる、個人的にも持続可能性な生活を探した方が良いのではないか。
そう思う。おいらがそうだからだ。
「友人の人数」を幸福と置き換えるというのは、本質自発性のない茂木健一郎らしい解決策である。
最近の研究では、イジメの原因の一つとして、「友達の数で他人の価値を量る観念」が働いているという説は有力であり。本能的な社会形成習性として、友人の数に気分的安心を基準に他者の価値を推し量り差別排除の「根拠」とするのである。故に「キモい」だのといった極めて主観的好き嫌いをイジメ差別の「理由」にされてしまうのである。
茂木健一郎は、あくまで大衆からのウケ狙いで社会問題に首を突っ込んでいるだけであって、本当は「人間について。」科学的検証をしようという純粋な好奇心を持って研究しているわけではないのは明らかである。
「支え合って、絆作って、組織的に何かやらないと国際競争力なんかつかない。」:茂木健一郎
これは一面的には正しい。振り込め詐欺師集団であっても支え合い絆で結ばれているからこそ巧妙な組織的統率詐欺が可能になるのであって、その組織というものが組織内部の閉じた価値観を共有してしまうことが問題なのである。
そもそも国際競争力と個人の幸福とは直接関係するものではない。
集団組織的に何かをやるにしても、個人の基礎的能力がなければ集団から必要とされないことになるので、基本的スキルは必要である。それが必ずしも他者との関わりを必要とする能力である必要性は論理的にない。
他人との関わり合いを重要としないスキルというのもあって、アルゴリズムを考える仕事などは他者との関わり合いを必ずしも必要としないものである。他にもそういった仕事はあるはずであろう、問題なのはアルゴリズムやアイデアを搾取するバカがいることでスキルが仕事として成立しなくなってしまうことである。他者を騙して利益を得ている卑怯者が減らない限り、個人が能力を発揮出来る社会にはならない。
幼児期に虐待を受けていたりすると、どうしても個人的に何が好きなのかを探すことすら苦手になりがちな傾向があって。これは自己の能力を過小評価するように刷り込み学習されてしまっているのが原因であろう。
多分、親などの他者からバカにされ続けて育ってしまっているために、一般的(多数決的)に学力成績偏差値が必要であると「思われて」いるようなスキルを、頭から(この場合の「頭」とは無意識的な思い込みのことを指す。)プログラミングなど出来ないものだと勘違いしてしまうのではないだろうか。ホームページ制作なんぞに何万も支払うバカな経営者が多いのも、ホームページ作成を特殊技能だと勘違いしているからである。大手銀行のダミーページくらいなら振り込め詐欺師でも作れる簡単なものなのである。
また、文科系マスコミの刷り込みで、「プログラミングをするには英語語学力が必要。」だとか言い張るものだから、余計敬遠されてしまうのではないだろうか。おいらは英語も読めないし、数学も苦手だけどアルゴリズムを考えることは出来る。クソゲーなんぞバカでも作れる代物なのである。
大規模プログラミングの場合は組織的な連携が重要な場合も多いが、個別のアルゴリズムを考える仕事においては他者との関係性よか一つのことに対する粘り強さ、執着心の方が必要だったりする。
しかし実際のところ中国と一緒で日本人にもアルゴリズムの知的財産権なんぞ守る奴なんていないからプータローが増えて、国際競争力も失う。誰かが言ってたけど、「奪い合うと足りなくなって、分け合うと余る。」ってこと。シリコンバレーっていうのは分かち合いの組織だから成長するんだろう。Googleなんて直接金にならないようなことばっかりやってるけど、最終的には莫大な収益を上げている。それが出来るのは当人達に自発性があって、他人から奪うよりも何かを築き上げることの方が楽しいからであろう。
スティーブ:ジョブズが「アルゴリズムは公開しろ。」などと述べていたが、これは現実にはシリコンバレーにおいてのみ有効な手段であって、マナーもすったくれもない日本においては通用しないのである。
本質的な自発性がなければ自律も養われないのがヒトという種の生物の行動習性でもある。茂木健一郎のように、「友達さえ多ければ幸福。」などという大衆観念に基づいた無意味な解決策しか出てこないのも、そこに本質的自発性の欠落があるからであって、どんなに茂木が研究費を浪費しても不毛なクソゲーくらいしか出て来ないのは当然である。
そもそも生物学におけるパラダイムの間違いを指摘出来ない茂木健一郎というのは他の生物学者同様に科学者としてポンコツであり、表面的ウケ狙いな活動をどんなにしていても、具体的な問題解決策が出てくることはない。「友達100人支給。」などという大衆観念に基づいた対策しか出て来ない無能な者を、単に大衆人気だけで学術権威として取り扱うのは大間違いなのである。
「友達の数」を人間の価値や個人の幸福として取り扱っている時点で、茂木は「ヒト」の行動習性の問題点について無関心であることを証明しているのである。「友達の数」などという大衆観念こそがイジメや差別排除の源であって、こんなことも知らずに一体「ヒト」の行動習性について一体何を論じられるというのであろう。
日本経済の崩壊というのは、政治や行政の問題だけではなく、それらも含めた日本人全体のモラルの無さ、すなはち論理的検証性に基づく自律の欠落が原因であって。特定権威組織の問題というより、個人の倫理の問題であって、無能な者を権威として取り扱う多数の無能さが権威組織の腐敗を進行させるのである。
アナキズムを振り回して漫然と権威を批判してさえおけば社会が良くなるわけではない。具体的に誰が権威として不適格であるかを論理的に検証し、地道に批判することが社会安全性にとって重要なのである。
原発を暴走させた「ヒト」達などの心理や行動を、危険工学的見地から検証しないことには、あらゆる「人災」の再発防止には構造原理的につながることはない。茂木健一郎や川島隆太などの大衆人気取りにしか興味のない脳科学研究者達が、どんなに大衆マスコミから重宝がられても、彼らの脳から「ヒト」の危険性についての検証は一切行われることはない。なぜなら大衆がバカのままでなければ脳トレ人気体制を維持することは出来ず、人気や金にならなくなってしまうので、大衆には論理検証の出来ないバカのままでいてもらわなければならないからである。
何度も言うが、脳血流の増加は「頭が良くなる。」ことの論理科学的根拠にはならないのである。当然脳血流増加によって個人の自律判断が養われることにもならない。
Ende;