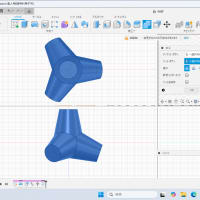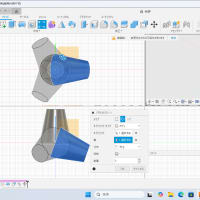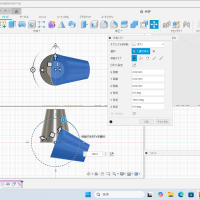家を留守にする時に鍵をかける 余程犯罪の少ない地域でなければ普通はそうだろう
家に鍵をかけるという動作は日常的に習熟しているので 玄関を出たら反射的にかけていることが多い
そのため 外出した先で「あれ? 家の鍵締めたかな…」と思い出せないことが時折ある
習熟した動作というのは意識的に「こうしよう」などと考えなくても動作が生じているものなのである
意識の上にないことは ほとんど記憶に残らないからだ
歩くという動作は 十数年程前まではロボットにやらせるのは至難の技だった 今でこそ当たり前のように2脚歩行ロボットが増えたものの やっぱり価格は高いのでPepperのような陳腐なロボットでは採用出来ないらしい
それはさておき
ヒトが歩く時に たくさんある足のどの筋肉を どの程度動かせば倒れずに前に進むことが出来るのかをいちいち意識しながら歩いているわけではない
「歩く」などという極めて複雑な動作であっても 習熟することによって無意識に行うことは可能なのである
意識をスルーして無意識に動作を行う仕組みが出来ているからである
そのため ヒトは「スマホを操作しながら歩く」という芸当も可能なのである ダメだけどね
こうした仕組みというのは いわばAIの機械学習そのものだと言える
AIは論理的に物事を考えてなどいない にも関わらず反射的に答を導き出すことが出来る
それは 反復学習をすることで 正解に最も近いものを反射的無意識に導き出しているからである
そういえば 最近の研究ではAIで錯覚を再現させた実験があるのだが AIなどの機械学習であるからこそ錯覚というのが生じてくる証拠だと言える
無意識な機械学習による反射的動作や感覚だからこそ 錯覚が生ずるのである
紙に印刷された図像を見て 動いているかのような錯覚が生じても 大抵のヒトは「本当に紙に印刷された図像が動いている。」という認識はしないだろう
紙に印刷されたものは動くことはないことを知識として知っている上に 視点の移動と図像の動きに連動のようなものが認識出来ることもあって これは錯覚だと何とか理解できるものである
錯覚を錯覚だと認識できるのは 意識的に頭の中で論理的に判断しているからである
たとえ論理的に判断しても 錯覚それ自体は消えずに 動いて見える図像ならどんなに凝視しても動いて見えてしまうものでもある
「親しく付き合いのある人なら 自分を騙したりはしないだろう。」という感覚的な信頼感は 大抵の人が抱く観念だが
嘘つきというのは むしろこうした感覚的な信頼感を利用して相手を騙すのである
しかし こうした「感覚」というものは視覚による錯視図像認識とは異なり 感情気分が促す心理的バイアスの方が正しいものであるという「知識の間違いが常識になっている」こともあり 多くの人は論理的に検証することなく感覚の方を信じ込んでしまうのである
安心感というのは あくまで主観的な感覚であって 客観的な論理的証明にはならないのだが ヒトの多くはこうした感覚が促す気分感情を短絡的に意識の本質だと「思って」いるのである
「ヒトの99.8%は戦争をしていない、そのことに気付けば戦争はなくなる。」という山際の話を聞いて 大衆マスコミの大多数は盲目的に信じ込み 誰も論理的に検証することなく鵜呑みにする
「京都大学学長」という肩書さえあれば ヒトは「権威」と見なして盲目的に信頼してしまうためである
いやもう この時点で一種の「公開アイヒマン実験」とも言える状態だと言える
「どれだけ大衆の多くが権威と見なした相手の言っている内容を鵜呑みに出来るのか。」 その公開実験みたいなものである
京都大学の学長というのは 何となくノーベル賞受賞者のような有能な科学者の多数決みたいなもので決定しているものだと思ってしまうのだが どうもそうではなくて 一種の「政治」みたいなもので決定しているらしいのだ
ノーベル賞受賞者達の多くは自分の研究で頭がいっぱいで 学内の政治とか権力闘争みたいなものには関心もなく 関わっていないようである
生物学者の大半は 進化的に獲得した性質の全ては目的のために意識的に「進化した」などという言い回しを平気でするが これが根本的に科学理論的には大嘘だということは彼らも大衆マスコミも誰も認識していない
哲学者に至っては クソの役にも立たない観念的決め付けを鵜呑みにして誰も論理検証などせず 単なる主観的な好き嫌いだけで「素晴らしい」だの「カッコイイ」だのという基準だけで 社会的には意味のないお伽話を並べているだけで 社会安全性や持続可能性にとって有効な話は全く出てこない
従って生物学者達や哲学者達によって学内政治が牛耳られていれば山際寿一のようなオカルト生物学者が京大学長に就任することもあるのだ
日本というのは年功序列という努力辛抱根性的精神論による評価が「好き」なので 実際には何の業績がなくとも長年勤めてさえいれば養老孟司が名誉教授という肩書を得ることも可能なのである
多数の学力偏差値の高い学生達であっても 彼らは就職にとって有利になるために学位学歴が欲しくて大学に行っているだけなので 教授達の言っている内容が科学論理的に間違っていようが関心はない
むしろ 生物学の間違いを鵜呑みにして 教わったことを教わった通りに覚えるバカでないと 生物学者として承認されることがないため 生物学というのはオカルト観念が一向に治らないというスパイラルにも陥っている
「感覚」という無意識が促すものの大半は 日常生活において便利ではあるのだが 時折うっかり「飲んではいけないものを口に含んでしまう」ような失敗をすることもある
口に含んだ瞬間に味が異常であることから本能的に飲み込むことを避けることも出来るのだが
先天的な権威服従性に関しては こうした拒絶反応はあまり働くことはなく 簡単に猛毒でも鵜呑みにしてしまう性質がある
スタンレー:ミルグラムによる服従心理実験 通称「アイヒマン実験」の内容を読んだ一般人の感想の中に 「それでも、権威に服従しない社会は崩壊する。」などという結論で終わっているものがあった
あのね アイヒマン実験っていうのはね 権威の命令に盲目的に服従していると重大な過失に加担してしまうことがあるから ちゃんと自分自身で権威がマトモなのかを自律的に検証しないと危ないよって話なのよ
ところが大衆観念的には 権威に服従していることが気分(感覚)的に安心であるため 感覚的な「安心」が優先して「権威に服従しない社会は崩壊する。」なんていう訳のわからぬ身勝手な決め付けが結論になってしまう
気分感情が促す感覚こそが意識の本質だという錯覚は 気分感情の程度強度によって意識が支配されてしまっているのが原因で これは先天的な欠陥なので意識的(論理検証的)に修正しないと錯覚が促す間違った行動選択は治らない
ヒトという種の生物は 別に人間としての行動を促すように先天的に出来上がっているわけではないのよ
遺伝的な進化というものは あくまで淘汰圧力の結果に過ぎないので 人間性だけが先天的に残される構造があるわけではなく 暴力的殺人者達による虐殺が進化の過程で絶対に存在しない証明なんて出来ないでしょ だって未だにあるんだから
遺伝的な進化というものは 結果的に死ななかった個体種の性質に残された性質によって より死なない傾向は組み込まれており 生存にとって有利な性質は非常に高度に進化しているものの だからといって意識的(論理検証的)な目的行動選択までもが進化の過程で組み込まれているわけではない
理性というものは それが生存にとって有利に働くために進化的に発達したとは言えるのだが これは個体の生存にとって有利に働くようにはなっているとは言えるが 人間性を発揮するために有利に働くようにはなる進化過程の力学だけが働く保障なぞないのである
振り込め詐欺師が他人を騙すことも 「生存にとっては有利な行動」ではある しかし こうした利己的行動こそが個体の生存価にとって有利に働くことからも 進化的に人間性だけが先天的に残る科学論理的証明は不可能である
リチャード:ドーキンスによる「利己的な遺伝子」のようなお伽話を信じて ヒトには先天的に人間性が組み込まれた優秀なものであると思っておけば 何も考えなくとも誰もが自動的に人間性を発揮できると勝手に勘違い錯覚して気分的に安心満足することで その感覚が促す錯覚を錯覚として認識しないようにもなるのである
脳のバカな性質が バカを加速度的に臨界状態に陥らせる性質が 先天的にヒトの脳にはあるのだ
この事実を認識し 「感覚が促す観念」と「自発的に検証する理性」との分別をキチンとつけておけば 多数派や権威に無意識に流されることなく 自律的に物事を判断することもできるようになるのである
あらゆる「人災」を避けるための これが最も根源的な対策なのである
Ende;
家に鍵をかけるという動作は日常的に習熟しているので 玄関を出たら反射的にかけていることが多い
そのため 外出した先で「あれ? 家の鍵締めたかな…」と思い出せないことが時折ある
習熟した動作というのは意識的に「こうしよう」などと考えなくても動作が生じているものなのである
意識の上にないことは ほとんど記憶に残らないからだ
歩くという動作は 十数年程前まではロボットにやらせるのは至難の技だった 今でこそ当たり前のように2脚歩行ロボットが増えたものの やっぱり価格は高いのでPepperのような陳腐なロボットでは採用出来ないらしい
それはさておき
ヒトが歩く時に たくさんある足のどの筋肉を どの程度動かせば倒れずに前に進むことが出来るのかをいちいち意識しながら歩いているわけではない
「歩く」などという極めて複雑な動作であっても 習熟することによって無意識に行うことは可能なのである
意識をスルーして無意識に動作を行う仕組みが出来ているからである
そのため ヒトは「スマホを操作しながら歩く」という芸当も可能なのである ダメだけどね
こうした仕組みというのは いわばAIの機械学習そのものだと言える
AIは論理的に物事を考えてなどいない にも関わらず反射的に答を導き出すことが出来る
それは 反復学習をすることで 正解に最も近いものを反射的無意識に導き出しているからである
そういえば 最近の研究ではAIで錯覚を再現させた実験があるのだが AIなどの機械学習であるからこそ錯覚というのが生じてくる証拠だと言える
無意識な機械学習による反射的動作や感覚だからこそ 錯覚が生ずるのである
紙に印刷された図像を見て 動いているかのような錯覚が生じても 大抵のヒトは「本当に紙に印刷された図像が動いている。」という認識はしないだろう
紙に印刷されたものは動くことはないことを知識として知っている上に 視点の移動と図像の動きに連動のようなものが認識出来ることもあって これは錯覚だと何とか理解できるものである
錯覚を錯覚だと認識できるのは 意識的に頭の中で論理的に判断しているからである
たとえ論理的に判断しても 錯覚それ自体は消えずに 動いて見える図像ならどんなに凝視しても動いて見えてしまうものでもある
「親しく付き合いのある人なら 自分を騙したりはしないだろう。」という感覚的な信頼感は 大抵の人が抱く観念だが
嘘つきというのは むしろこうした感覚的な信頼感を利用して相手を騙すのである
しかし こうした「感覚」というものは視覚による錯視図像認識とは異なり 感情気分が促す心理的バイアスの方が正しいものであるという「知識の間違いが常識になっている」こともあり 多くの人は論理的に検証することなく感覚の方を信じ込んでしまうのである
安心感というのは あくまで主観的な感覚であって 客観的な論理的証明にはならないのだが ヒトの多くはこうした感覚が促す気分感情を短絡的に意識の本質だと「思って」いるのである
「ヒトの99.8%は戦争をしていない、そのことに気付けば戦争はなくなる。」という山際の話を聞いて 大衆マスコミの大多数は盲目的に信じ込み 誰も論理的に検証することなく鵜呑みにする
「京都大学学長」という肩書さえあれば ヒトは「権威」と見なして盲目的に信頼してしまうためである
いやもう この時点で一種の「公開アイヒマン実験」とも言える状態だと言える
「どれだけ大衆の多くが権威と見なした相手の言っている内容を鵜呑みに出来るのか。」 その公開実験みたいなものである
京都大学の学長というのは 何となくノーベル賞受賞者のような有能な科学者の多数決みたいなもので決定しているものだと思ってしまうのだが どうもそうではなくて 一種の「政治」みたいなもので決定しているらしいのだ
ノーベル賞受賞者達の多くは自分の研究で頭がいっぱいで 学内の政治とか権力闘争みたいなものには関心もなく 関わっていないようである
生物学者の大半は 進化的に獲得した性質の全ては目的のために意識的に「進化した」などという言い回しを平気でするが これが根本的に科学理論的には大嘘だということは彼らも大衆マスコミも誰も認識していない
哲学者に至っては クソの役にも立たない観念的決め付けを鵜呑みにして誰も論理検証などせず 単なる主観的な好き嫌いだけで「素晴らしい」だの「カッコイイ」だのという基準だけで 社会的には意味のないお伽話を並べているだけで 社会安全性や持続可能性にとって有効な話は全く出てこない
従って生物学者達や哲学者達によって学内政治が牛耳られていれば山際寿一のようなオカルト生物学者が京大学長に就任することもあるのだ
日本というのは年功序列という努力辛抱根性的精神論による評価が「好き」なので 実際には何の業績がなくとも長年勤めてさえいれば養老孟司が名誉教授という肩書を得ることも可能なのである
多数の学力偏差値の高い学生達であっても 彼らは就職にとって有利になるために学位学歴が欲しくて大学に行っているだけなので 教授達の言っている内容が科学論理的に間違っていようが関心はない
むしろ 生物学の間違いを鵜呑みにして 教わったことを教わった通りに覚えるバカでないと 生物学者として承認されることがないため 生物学というのはオカルト観念が一向に治らないというスパイラルにも陥っている
「感覚」という無意識が促すものの大半は 日常生活において便利ではあるのだが 時折うっかり「飲んではいけないものを口に含んでしまう」ような失敗をすることもある
口に含んだ瞬間に味が異常であることから本能的に飲み込むことを避けることも出来るのだが
先天的な権威服従性に関しては こうした拒絶反応はあまり働くことはなく 簡単に猛毒でも鵜呑みにしてしまう性質がある
スタンレー:ミルグラムによる服従心理実験 通称「アイヒマン実験」の内容を読んだ一般人の感想の中に 「それでも、権威に服従しない社会は崩壊する。」などという結論で終わっているものがあった
あのね アイヒマン実験っていうのはね 権威の命令に盲目的に服従していると重大な過失に加担してしまうことがあるから ちゃんと自分自身で権威がマトモなのかを自律的に検証しないと危ないよって話なのよ
ところが大衆観念的には 権威に服従していることが気分(感覚)的に安心であるため 感覚的な「安心」が優先して「権威に服従しない社会は崩壊する。」なんていう訳のわからぬ身勝手な決め付けが結論になってしまう
気分感情が促す感覚こそが意識の本質だという錯覚は 気分感情の程度強度によって意識が支配されてしまっているのが原因で これは先天的な欠陥なので意識的(論理検証的)に修正しないと錯覚が促す間違った行動選択は治らない
ヒトという種の生物は 別に人間としての行動を促すように先天的に出来上がっているわけではないのよ
遺伝的な進化というものは あくまで淘汰圧力の結果に過ぎないので 人間性だけが先天的に残される構造があるわけではなく 暴力的殺人者達による虐殺が進化の過程で絶対に存在しない証明なんて出来ないでしょ だって未だにあるんだから
遺伝的な進化というものは 結果的に死ななかった個体種の性質に残された性質によって より死なない傾向は組み込まれており 生存にとって有利な性質は非常に高度に進化しているものの だからといって意識的(論理検証的)な目的行動選択までもが進化の過程で組み込まれているわけではない
理性というものは それが生存にとって有利に働くために進化的に発達したとは言えるのだが これは個体の生存にとって有利に働くようにはなっているとは言えるが 人間性を発揮するために有利に働くようにはなる進化過程の力学だけが働く保障なぞないのである
振り込め詐欺師が他人を騙すことも 「生存にとっては有利な行動」ではある しかし こうした利己的行動こそが個体の生存価にとって有利に働くことからも 進化的に人間性だけが先天的に残る科学論理的証明は不可能である
リチャード:ドーキンスによる「利己的な遺伝子」のようなお伽話を信じて ヒトには先天的に人間性が組み込まれた優秀なものであると思っておけば 何も考えなくとも誰もが自動的に人間性を発揮できると勝手に勘違い錯覚して気分的に安心満足することで その感覚が促す錯覚を錯覚として認識しないようにもなるのである
脳のバカな性質が バカを加速度的に臨界状態に陥らせる性質が 先天的にヒトの脳にはあるのだ
この事実を認識し 「感覚が促す観念」と「自発的に検証する理性」との分別をキチンとつけておけば 多数派や権威に無意識に流されることなく 自律的に物事を判断することもできるようになるのである
あらゆる「人災」を避けるための これが最も根源的な対策なのである
Ende;