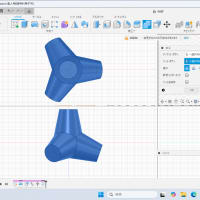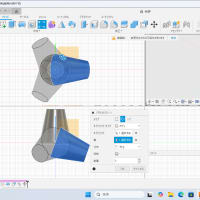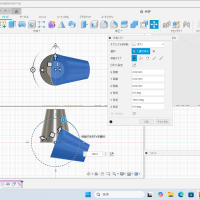「論理整合性がないだけ開かれている。」
養老孟司の言っている内容には論理整合性がない
その場限りに相手に合わせて話を「丸めて」いるだけであって そもそも論理的根拠に基づいた主体的な「考え」すらも持ち合わせていない
養老にとっての「意味」とは 大多数の大衆が望むことに過ぎない「世間的成功」だけであって 人間性や倫理などはどうでも良いことなので「それは○○の問題である。」などという他人任せにして話をはぐらかすだけである
養老の話の中には社会安全性や持続可能性にとって重要なトピックや論理的「考え」など一切出てこない
畑村洋太郎に養老孟司の著作や山極壽一の言っている内容が社会安全性にどのように応用可能なのかを聞いてみれば良い
畑村はおそらく「意味がわからない。」と答えるであろう
多くのノーベル賞受賞者も同様のはずである
そもそも養老らの言っている話には社会的にも科学的にも意味がないからである
ただし 養老の場合は相手を見て話の内容をコロコロ変えて「話を丸めて」くるので マトモな学者と「対話」をさせても養老の異常性は出てこないであろう
養老は天才的なペテン師なのである
養老がなぜ論理整合性を「開こう」とする(その場限りに話がコロコロ変わる)のかと言えば それは自分の主観的観念を「閉じる」ためには他に手段がないからである
論理整合性のない話は客観的でもなければ科学でもない そんな極めて基本的なことすら大衆マスコミの多くは認識していないのであろう
養老は自分のことを「客観的」だと言い張るが たとえ本人がそう「思って」いるとしても実際には全く客観性などなく 個人の主観的観念を正当化するためのはぐらかしの羅列に過ぎない
「論理には勝てない」
論理は「勝ち負け」の問題ではなく 真理追求 事実解明のために必要なものであって 論理的に間違ったことを言っていたからといって「負け」たことにはならないし 正しいことを言っていたからといって「勝った」ことにはならない
科学理論的議論というのは「勝ち負け」を目的としたものではない
論理的に正しいことを述べていれば マトモな学界であれば評価が得られるのかも知れないが 学界が異常ならどんなに正しいことを述べても認められることはない
刑事裁判であれば制度的に検察と弁護側の「勝ち負け」にすり替えられてしまうのだが これが社会安全性の観点からは必ずしも最適な手法ではないことは何度も述べてきたつもりである
大衆マスコミが安易に「勝ち負け」にこだわるのは 「どっちが上なのか」という序列順位を観念的に判定したいだけであって その判定基準は「社会安全性の論理的根拠を追求する」ことが目的ではなく 単に「多数派に人気があって金儲けが出来た」かどうかという観念的基準がほとんどである
ヒトという種の生物が「論理的に正しいかどうか」よりも多数決や世間的成功で「勝ち負け」という観念的基準を優先してしまうのは ヒトという種の生物には先天的に「順位序列を決定しておきたい」という外見的で上っ面な多数決に同調してしまう習性が 自律的な論理検証性よりも優先してしまうからである
科学的に「正しい」ことを述べていたからといって必ずしも社会的な成功や「勝ち」が得られるとは限らない
遺伝子の研究で有名なメンデルも生前は誰からも評価されることはなかったという
当時から天才と評されていたガリレオですら地動説では火炙りにされかかった
科学的に正しいことや 社会安全性や持続可能性にとって重要な話など 一般大衆は興味がなく 必然的にマスコミも金にならないので取り上げることもない
多数のバカな大衆の観念的「勝ち負け」論などというのは 社会安全性にとっては何の意味も為さないのである
科学は多数決ではないし 大衆の多くが物事を深く検証しないバカなら民主主義制度はバカ主義にしかならない
だから重要なのは「大多数の大衆がバカのままでは危険」なので改善しなければならないのである
本気で紛争や殺人などの犯罪を減らそうという「考え」があれば 安易に「死刑にしちまえ。」などという短絡的で乱暴な結論を鵜呑みにはしないはずである
社会がなぜ科学的真理を要求するのかと言えば それによって社会安全性が高まるからであって「中東由来の一神教がどうのこうの」といった訳のわからぬ屁理屈が根拠ではない
Ende;
養老孟司の言っている内容には論理整合性がない
その場限りに相手に合わせて話を「丸めて」いるだけであって そもそも論理的根拠に基づいた主体的な「考え」すらも持ち合わせていない
養老にとっての「意味」とは 大多数の大衆が望むことに過ぎない「世間的成功」だけであって 人間性や倫理などはどうでも良いことなので「それは○○の問題である。」などという他人任せにして話をはぐらかすだけである
養老の話の中には社会安全性や持続可能性にとって重要なトピックや論理的「考え」など一切出てこない
畑村洋太郎に養老孟司の著作や山極壽一の言っている内容が社会安全性にどのように応用可能なのかを聞いてみれば良い
畑村はおそらく「意味がわからない。」と答えるであろう
多くのノーベル賞受賞者も同様のはずである
そもそも養老らの言っている話には社会的にも科学的にも意味がないからである
ただし 養老の場合は相手を見て話の内容をコロコロ変えて「話を丸めて」くるので マトモな学者と「対話」をさせても養老の異常性は出てこないであろう
養老は天才的なペテン師なのである
養老がなぜ論理整合性を「開こう」とする(その場限りに話がコロコロ変わる)のかと言えば それは自分の主観的観念を「閉じる」ためには他に手段がないからである
論理整合性のない話は客観的でもなければ科学でもない そんな極めて基本的なことすら大衆マスコミの多くは認識していないのであろう
養老は自分のことを「客観的」だと言い張るが たとえ本人がそう「思って」いるとしても実際には全く客観性などなく 個人の主観的観念を正当化するためのはぐらかしの羅列に過ぎない
「論理には勝てない」
論理は「勝ち負け」の問題ではなく 真理追求 事実解明のために必要なものであって 論理的に間違ったことを言っていたからといって「負け」たことにはならないし 正しいことを言っていたからといって「勝った」ことにはならない
科学理論的議論というのは「勝ち負け」を目的としたものではない
論理的に正しいことを述べていれば マトモな学界であれば評価が得られるのかも知れないが 学界が異常ならどんなに正しいことを述べても認められることはない
刑事裁判であれば制度的に検察と弁護側の「勝ち負け」にすり替えられてしまうのだが これが社会安全性の観点からは必ずしも最適な手法ではないことは何度も述べてきたつもりである
大衆マスコミが安易に「勝ち負け」にこだわるのは 「どっちが上なのか」という序列順位を観念的に判定したいだけであって その判定基準は「社会安全性の論理的根拠を追求する」ことが目的ではなく 単に「多数派に人気があって金儲けが出来た」かどうかという観念的基準がほとんどである
ヒトという種の生物が「論理的に正しいかどうか」よりも多数決や世間的成功で「勝ち負け」という観念的基準を優先してしまうのは ヒトという種の生物には先天的に「順位序列を決定しておきたい」という外見的で上っ面な多数決に同調してしまう習性が 自律的な論理検証性よりも優先してしまうからである
科学的に「正しい」ことを述べていたからといって必ずしも社会的な成功や「勝ち」が得られるとは限らない
遺伝子の研究で有名なメンデルも生前は誰からも評価されることはなかったという
当時から天才と評されていたガリレオですら地動説では火炙りにされかかった
科学的に正しいことや 社会安全性や持続可能性にとって重要な話など 一般大衆は興味がなく 必然的にマスコミも金にならないので取り上げることもない
多数のバカな大衆の観念的「勝ち負け」論などというのは 社会安全性にとっては何の意味も為さないのである
科学は多数決ではないし 大衆の多くが物事を深く検証しないバカなら民主主義制度はバカ主義にしかならない
だから重要なのは「大多数の大衆がバカのままでは危険」なので改善しなければならないのである
本気で紛争や殺人などの犯罪を減らそうという「考え」があれば 安易に「死刑にしちまえ。」などという短絡的で乱暴な結論を鵜呑みにはしないはずである
社会がなぜ科学的真理を要求するのかと言えば それによって社会安全性が高まるからであって「中東由来の一神教がどうのこうの」といった訳のわからぬ屁理屈が根拠ではない
Ende;