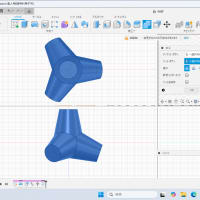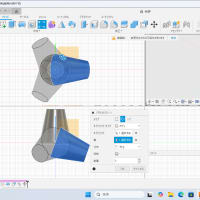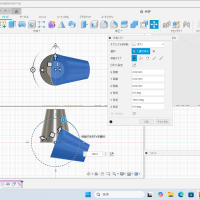オーストラリアでは1950年にアナウサギを駆除するためにミクソーマウイルスを導入する。 1950年当時は、兎粘液腫によるアナウサギの致死率は99%であった。 しかし数年後にはミクソーマウイルスが変化して弱毒化し、またアナウサギもミクソーマウイルスに対する耐性を獲得するようになったため致死率は50%まで下がる。
兎粘液腫 Wikipedia
毒性ウイルスが弱毒化する過程を考えると 変異によって弱毒株が生じただけでは弱毒化への「進化」は起きず
あくまで弱毒化していない株に感染した大多数の宿主と共に強毒株の淘汰による密の解消が必要条件である
しかし 今回の新型コロナウイルスに関しては強毒株に対する淘汰圧力は充分に働いていおらず
むしろダラダラと感染を続けてしまうことによって より感染力の強い株への進化を促してしまう可能性の方が高い
多剤耐性菌の発生の発現条件を考えてみればわかるが 遺伝的進化というものは膨大な死滅を伴う強力な淘汰圧力によって偶発的に死なずに残った個体の遺伝的性質(結果)を述べているに過ぎず
「ウイルスは必ず都合よく弱毒化して宿主と共存できるようになる」などという話は科学を逸脱したお伽話に過ぎない
遺伝子というものには意図や「目的」のようなものはなく あくまで遺伝的進化というものはシーケンシャルな「結果」以上の何ももたらすことはない
ところが 「学者」として大学や研究所に勤めている職員であっても遺伝的進化というものには目的のようなものがあって 必ず都合よく進化するはずだという非科学的妄想観念に囚われているバカは多い
免疫を持たないウサギが大量に死亡したというところから話が始まるので、ヒトとウサギは同列には扱えないが、ウイルスの目的は自己複製それ自体であって、宿主を殺すのは、逆に失敗である。だから、長い目でみれば、毒性が弱く、感染力が強いウイルスが宿主と共進化(coevolution)していく(→「ウイルス進化論」)。