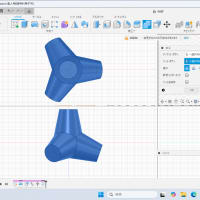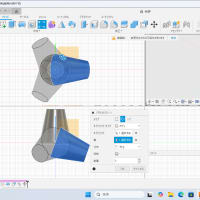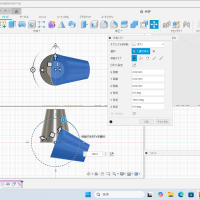文科系学者が言い出す、本能感覚的「快楽。」というものを、あたかも論理的思考を超越した優れた知性であるかのように形容するのは。本能的気分、本能的感覚が促す快楽の程度や強度が促す錯覚に過ぎない。
感覚は「知能。」ではない。知能とは感覚器官からの入力強度に依存せずに、論理的分析によって促される「考え。」である。
錯覚というものは感覚が促すものである。錯覚を錯覚と認識するのが知能である。感覚を優先していれば知能は働かない。
合理性というものを無視すれば、残るのは感覚だけであり。錯覚が促す気分的満足のまどろみだけである。
文科系の者は合理性という言葉に異常な拒絶反応をするが、これは感覚が促す錯覚しか優先させない。感覚を優先させておけば気分的には「安心。」であろう、その「安心。」こそが論理的思考を阻害することの危険性は、感覚的には優先されないのが「ヒト。」という種の生物の習性である。
これがヒトのバカたる所以であることは、マスコミは扱うことを拒絶するのである。
理由は「大衆ウケが悪いから。」である。
ゲリラのように暴力的である場合、生存価に適するかどうかは環境次第である。暴力的な者同士による協調行動が生存に適しても何ら不思議ではない。どのような個体が生存に適したかを結果だけから決定することは原理的に不可能である。
強姦されることに快楽を感じる個体の遺伝子が遺った「結果。」として、強姦されることに快楽を感じる習性があるとしても。それは個体の意識的目的とは無関係である。
虐待を連鎖する習性も「結果。」である。結果的習性に抗い、無意識的条件反射である連鎖を止めるのが「目的。」意識である。
「結果。」をどんなに枚挙しても、それが「目的。」意識を励起することにはならない。「結果。」に何を「感じて。」もである。
アイヒマン実験の結果であっても、多くのヒトは自分自身の意識の問題であるとは「思わ。」ないのである。
認識によって行動や思考を変えるのは論理的分析であり、「考え。」である。決して「思い。」や「感じ。」ではない。
従って、本質的意識とは「思い。」や「感じ。」ではない。「思い。」や「感じ。」は固定観念や本能的拒絶反応しか生み出すことはなく、不毛である。
アイヒマン実験においても、著者の分析では生物学的論証として意味のこじつけがなされている。「サイバネティクスの観点から。」と称して、断片的な有効性を枚挙しても無意識本能的服従習性が常に正しい結果しか導かないことの論証にはならないのである。
アイヒマン実験の著者であるミルグラムでさえ、その分析段階では生物学的なこじつけをしてしまう程、ヒトとは短絡的なものなのである。
end;
感覚は「知能。」ではない。知能とは感覚器官からの入力強度に依存せずに、論理的分析によって促される「考え。」である。
錯覚というものは感覚が促すものである。錯覚を錯覚と認識するのが知能である。感覚を優先していれば知能は働かない。
合理性というものを無視すれば、残るのは感覚だけであり。錯覚が促す気分的満足のまどろみだけである。
文科系の者は合理性という言葉に異常な拒絶反応をするが、これは感覚が促す錯覚しか優先させない。感覚を優先させておけば気分的には「安心。」であろう、その「安心。」こそが論理的思考を阻害することの危険性は、感覚的には優先されないのが「ヒト。」という種の生物の習性である。
これがヒトのバカたる所以であることは、マスコミは扱うことを拒絶するのである。
理由は「大衆ウケが悪いから。」である。
ゲリラのように暴力的である場合、生存価に適するかどうかは環境次第である。暴力的な者同士による協調行動が生存に適しても何ら不思議ではない。どのような個体が生存に適したかを結果だけから決定することは原理的に不可能である。
強姦されることに快楽を感じる個体の遺伝子が遺った「結果。」として、強姦されることに快楽を感じる習性があるとしても。それは個体の意識的目的とは無関係である。
虐待を連鎖する習性も「結果。」である。結果的習性に抗い、無意識的条件反射である連鎖を止めるのが「目的。」意識である。
「結果。」をどんなに枚挙しても、それが「目的。」意識を励起することにはならない。「結果。」に何を「感じて。」もである。
アイヒマン実験の結果であっても、多くのヒトは自分自身の意識の問題であるとは「思わ。」ないのである。
認識によって行動や思考を変えるのは論理的分析であり、「考え。」である。決して「思い。」や「感じ。」ではない。
従って、本質的意識とは「思い。」や「感じ。」ではない。「思い。」や「感じ。」は固定観念や本能的拒絶反応しか生み出すことはなく、不毛である。
アイヒマン実験においても、著者の分析では生物学的論証として意味のこじつけがなされている。「サイバネティクスの観点から。」と称して、断片的な有効性を枚挙しても無意識本能的服従習性が常に正しい結果しか導かないことの論証にはならないのである。
アイヒマン実験の著者であるミルグラムでさえ、その分析段階では生物学的なこじつけをしてしまう程、ヒトとは短絡的なものなのである。
end;