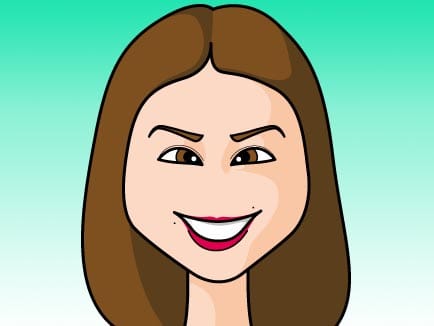噺家の三遊亭圓楽師が亡くなった。
もう30年近く前のことである。
実家の松戸にあった、駅ビルの催事で落語会が行われた。
三遊亭圓楽一門ほか、何組かの色物の芸人。
中トリ、休憩を挟んでトリはもちろん圓楽師だ。
中トリの演目は、「宮戸川」だったと記憶している。
以下、ちょっとマニアックな話になります。
ネタに関し、いちいち説明してるとキリがないので
ご興味のある方は、ご自分で検索を…
休憩時間、会場では師のレコード(CDじゃないです)やカセットが売られ
その中から「浜野矩随(はまののりゆき)」を選んで
楽屋口にいる係員に「師匠にサインを貰えないだろうか」と持ちかけてみた。
「そういうことは、しておりません」との応え。
ま、主催者側からすれば、その対応は当然だ。
サイン会でもないのに、そんな要望に応えてたらキリがない。
諦めて、レコードを持って客席に引き返そうとしたところ
師匠のマネージャーの方だと思われる方が、こっそり声をかけてくださった。
「いいよ、してもらってあげるよ」
ややすると、かのマネージャー氏、
申し訳なさそうにレコードを持って戻ってこられた。
サインペンでなく、色紙用の筆しかなかったとみえて
コーティングされたLPのジャケットは、墨をはじいてしまっていた。
代わりと言うわけでもないのだろうが、「圓楽」の文字の入った
千社札のシールを添えて持ってきていただいた。
それだってファンからすれば嬉しいものだ。
会場のトイレの脇にあったベンチで、そのLPとシールを眺めていると
そこへ、当の圓楽師が用を足しにおいでになった。
トイレから出てこられるのを待って、勇気を出して声をかけさせていただいた。
「あのぅ…、これ、ありがとうございました」
オレの顔を見た圓楽師は、気さくに応えてくださった。
「ああ、これね、はじいちゃったんで。シールになってるから貼ってね」
圓楽師の師匠で、昭和の名人と謳われた六代目三遊亭圓生師は
1978年に真打ち乱造事件で、当時所属していた「落語協会」を脱退し
圓生一門で「落語三遊協会」を創設。
一番弟子の圓楽師も、圓生師と行動を共にした。
その直後の1979年に、圓生師は死去。
残された圓楽一門は、「大日本落語すみれ会」として独立。
上記は、その当時の出来事だ。
以来、圓楽師は、オレの中で妙に親近感のあった人だった。
「星の王子様」というキャッチフレーズで人気者になった『笑点』で
タレントとなりつつあるのを「芸が荒れた」という圓生師の指摘から
一切のテレビ活動を断ち、落語の稽古に励まれ、独演会も精力的に行った。
今でも、その独演会の音源がCD化されて残っている。
得意ネタは「中村仲蔵」「文七元結」「浜野矩随」
最後の高座となった「芝浜」といった人情噺の大ネタとされているが
オレはむしろ、「宮戸川」「汲みたて」「短命」といった
軽めで笑いの多い噺にこそ、師の本領が発揮されていたと思う。
2005年、脳梗塞の病状が現れて、入院したのを機に『笑点』を勇退。
2007年に本格復帰をかけるものの、得意ネタとされた
「芝浜」の出来に満足できずに引退を決意。
「圓楽」の名跡は、2010年に現楽太郎師が襲名する予定だったという。
かつて「落語四天王」と呼ばれた人たちも
2001年に古今亭志ん朝師が亡くなり、
とうとう談志師と圓蔵師の二人だけになってしまった。
五代目三遊亭圓楽
享年76歳
心よりご冥福をお祈りいたします。
浜野矩随-1
浜野矩随2
浜野矩随3
gooのIDをお持ちの方は『からだログ』へも是非お越し下さい。
YouTubeにて動くリタ金を見てやってください。
↑ここをクリック
画像も貼れる掲示板
『無明長夜もかくばかり…画像BBS』にもお気軽にどうぞ。
もう30年近く前のことである。
実家の松戸にあった、駅ビルの催事で落語会が行われた。
三遊亭圓楽一門ほか、何組かの色物の芸人。
中トリ、休憩を挟んでトリはもちろん圓楽師だ。
中トリの演目は、「宮戸川」だったと記憶している。
以下、ちょっとマニアックな話になります。
ネタに関し、いちいち説明してるとキリがないので
ご興味のある方は、ご自分で検索を…
休憩時間、会場では師のレコード(CDじゃないです)やカセットが売られ
その中から「浜野矩随(はまののりゆき)」を選んで
楽屋口にいる係員に「師匠にサインを貰えないだろうか」と持ちかけてみた。
「そういうことは、しておりません」との応え。
ま、主催者側からすれば、その対応は当然だ。
サイン会でもないのに、そんな要望に応えてたらキリがない。
諦めて、レコードを持って客席に引き返そうとしたところ
師匠のマネージャーの方だと思われる方が、こっそり声をかけてくださった。
「いいよ、してもらってあげるよ」
ややすると、かのマネージャー氏、
申し訳なさそうにレコードを持って戻ってこられた。
サインペンでなく、色紙用の筆しかなかったとみえて
コーティングされたLPのジャケットは、墨をはじいてしまっていた。
代わりと言うわけでもないのだろうが、「圓楽」の文字の入った
千社札のシールを添えて持ってきていただいた。
それだってファンからすれば嬉しいものだ。
会場のトイレの脇にあったベンチで、そのLPとシールを眺めていると
そこへ、当の圓楽師が用を足しにおいでになった。
トイレから出てこられるのを待って、勇気を出して声をかけさせていただいた。
「あのぅ…、これ、ありがとうございました」
オレの顔を見た圓楽師は、気さくに応えてくださった。
「ああ、これね、はじいちゃったんで。シールになってるから貼ってね」
圓楽師の師匠で、昭和の名人と謳われた六代目三遊亭圓生師は
1978年に真打ち乱造事件で、当時所属していた「落語協会」を脱退し
圓生一門で「落語三遊協会」を創設。
一番弟子の圓楽師も、圓生師と行動を共にした。
その直後の1979年に、圓生師は死去。
残された圓楽一門は、「大日本落語すみれ会」として独立。
上記は、その当時の出来事だ。
以来、圓楽師は、オレの中で妙に親近感のあった人だった。
「星の王子様」というキャッチフレーズで人気者になった『笑点』で
タレントとなりつつあるのを「芸が荒れた」という圓生師の指摘から
一切のテレビ活動を断ち、落語の稽古に励まれ、独演会も精力的に行った。
今でも、その独演会の音源がCD化されて残っている。
得意ネタは「中村仲蔵」「文七元結」「浜野矩随」
最後の高座となった「芝浜」といった人情噺の大ネタとされているが
オレはむしろ、「宮戸川」「汲みたて」「短命」といった
軽めで笑いの多い噺にこそ、師の本領が発揮されていたと思う。
2005年、脳梗塞の病状が現れて、入院したのを機に『笑点』を勇退。
2007年に本格復帰をかけるものの、得意ネタとされた
「芝浜」の出来に満足できずに引退を決意。
「圓楽」の名跡は、2010年に現楽太郎師が襲名する予定だったという。
かつて「落語四天王」と呼ばれた人たちも
2001年に古今亭志ん朝師が亡くなり、
とうとう談志師と圓蔵師の二人だけになってしまった。
五代目三遊亭圓楽
享年76歳
心よりご冥福をお祈りいたします。
浜野矩随-1
浜野矩随2
浜野矩随3
gooのIDをお持ちの方は『からだログ』へも是非お越し下さい。
YouTubeにて動くリタ金を見てやってください。
↑ここをクリック
画像も貼れる掲示板
『無明長夜もかくばかり…画像BBS』にもお気軽にどうぞ。