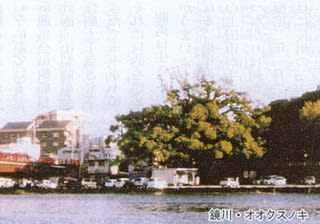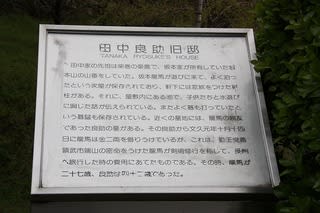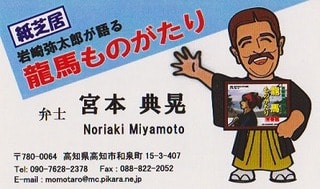龍馬十景 ⑥ 脱藩・・・龍馬の魅力
根木 勢介

「龍馬のどこが好きですか」と、よく聞かれる。 龍馬の魅力を解く鍵がある。
ひとつは「脱藩」。
勤王の志士といえども、江戸300年の幕藩体制がつくりだした藩意識や、所属する藩から自由でなかった。
勤王の志士の大半が「藩意識」からなかなか抜け出せなかった。 龍馬は早くから土佐藩を捨て「日本」という意識が高く、その視点から行動している。 そこが、近代的な人といわれる所以だろう。
ふたつ目には、脱藩の所産ともいえる「自由」。
脱藩後の彼の行動が物語っているが、自由に全国を飛び回っている。 彼の自由さを象徴するのが、倒幕側にありながら幕府側の人とも垣根なく交際している人脈の広さ。
「垣根」は、自分が作っているんだヨ、と教えてくれているようだ。 後に「龍馬を暗殺したのは、誰か」を推理する上で、問題を複雑にする要因が、その交際の広さだ。
みっつ目には、龍馬と出会った人が異口同音に言う彼の「ユニークさ」。
色々な人を訪ね歩いて意見を聞く訪問魔の龍馬。 だが、単なる聞き役ではない「発想の龍馬」の姿がそこにはある。
所属する藩(今なら会社)や立場にとらわれ自由な発想ができない我々が魅力を感ずるところだろう。
最後に、彼の海のイメージとマッチした「明るさ」。
彼の明るい人となりがよく伝わって来るのが彼の残した手紙の数々。
お龍さんへのラブレターを見たいけど、無いのは残念。
龍馬研究会発行 「龍馬研究」No.161 より転載
根木勢介さんの「龍馬十景」 シリーズ
坂本龍馬ファンクラブ
根木 勢介

「龍馬のどこが好きですか」と、よく聞かれる。 龍馬の魅力を解く鍵がある。
ひとつは「脱藩」。
勤王の志士といえども、江戸300年の幕藩体制がつくりだした藩意識や、所属する藩から自由でなかった。
勤王の志士の大半が「藩意識」からなかなか抜け出せなかった。 龍馬は早くから土佐藩を捨て「日本」という意識が高く、その視点から行動している。 そこが、近代的な人といわれる所以だろう。
ふたつ目には、脱藩の所産ともいえる「自由」。
脱藩後の彼の行動が物語っているが、自由に全国を飛び回っている。 彼の自由さを象徴するのが、倒幕側にありながら幕府側の人とも垣根なく交際している人脈の広さ。
「垣根」は、自分が作っているんだヨ、と教えてくれているようだ。 後に「龍馬を暗殺したのは、誰か」を推理する上で、問題を複雑にする要因が、その交際の広さだ。
みっつ目には、龍馬と出会った人が異口同音に言う彼の「ユニークさ」。
色々な人を訪ね歩いて意見を聞く訪問魔の龍馬。 だが、単なる聞き役ではない「発想の龍馬」の姿がそこにはある。
所属する藩(今なら会社)や立場にとらわれ自由な発想ができない我々が魅力を感ずるところだろう。
最後に、彼の海のイメージとマッチした「明るさ」。
彼の明るい人となりがよく伝わって来るのが彼の残した手紙の数々。
お龍さんへのラブレターを見たいけど、無いのは残念。
龍馬研究会発行 「龍馬研究」No.161 より転載
根木勢介さんの「龍馬十景」 シリーズ
坂本龍馬ファンクラブ