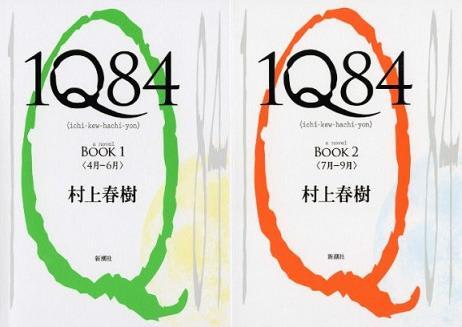今、「ミレニアム」にどっぷりハマっております。
まーね、今さらなんですが。
この作品は、スウェーデンのジャーナリストである、スティーグ・ラーソン原作のミステリーで、数年前にちょっとした特集番組を見て興味を持ちました。
なにしろ、3部作で、それぞれ上下巻に別れていて、合計6冊。
どうしようかな~~と思いつつ、そのうち映画化もされたので、まず劇場へ・・・と思ったら、いつの間にか終わっちゃって。
それじゃ、DVDでと思ったら、いつの間にかWOWOWでオンエア。
第一部の「ドラゴン・タトゥーの女」を観たら、あららら、面白い!!
で、そのうち、「ミレニアム2・火と戯れる女」、「ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士」と続けてオンエアになり、それぞれ十分な見応えがありました。
そして、とうとう原作を読み始めたのですが、あっという間に6冊読んでしまいました。
アタシは映画もそうとう面白かったし、原作に近い作品だと聞いていたのですが、いやはや。
原作は、映画以上に面白かったです。
原作者スティーグ・ラーソンはスウェーデンのジャーナリスト。
長年、ジャーナリズム界でキャリアを積み、政治系雑誌の編集長の経験もあり、「ミレニアム」を通して、女性への虐待、性犯罪、政治腐敗、などなどスウェーデンに内在する社会問題をふんだんに取り入れています。
結局は、世界で800万部の大ベストセラーとなりましたが、ラーソンは成功を見ずに心臓発作のため、亡くなりました。
「ミレニアム」は、雑誌・ミレニアムの発行責任者であるミカエルが主人公のひとりですが、もちろん、彼はスティーグ・ラーソン自身であり、もうひとりの主人公である、ナゾの調査員・リスベットは、スティーグ・ラーソンの救世主的存在じゃないかなと、アタシは思いました。
また、そのうち続きを書きたいと思います。
まーね、今さらなんですが。
この作品は、スウェーデンのジャーナリストである、スティーグ・ラーソン原作のミステリーで、数年前にちょっとした特集番組を見て興味を持ちました。
なにしろ、3部作で、それぞれ上下巻に別れていて、合計6冊。
どうしようかな~~と思いつつ、そのうち映画化もされたので、まず劇場へ・・・と思ったら、いつの間にか終わっちゃって。

それじゃ、DVDでと思ったら、いつの間にかWOWOWでオンエア。
第一部の「ドラゴン・タトゥーの女」を観たら、あららら、面白い!!
で、そのうち、「ミレニアム2・火と戯れる女」、「ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士」と続けてオンエアになり、それぞれ十分な見応えがありました。
そして、とうとう原作を読み始めたのですが、あっという間に6冊読んでしまいました。
アタシは映画もそうとう面白かったし、原作に近い作品だと聞いていたのですが、いやはや。
原作は、映画以上に面白かったです。
原作者スティーグ・ラーソンはスウェーデンのジャーナリスト。
長年、ジャーナリズム界でキャリアを積み、政治系雑誌の編集長の経験もあり、「ミレニアム」を通して、女性への虐待、性犯罪、政治腐敗、などなどスウェーデンに内在する社会問題をふんだんに取り入れています。
結局は、世界で800万部の大ベストセラーとなりましたが、ラーソンは成功を見ずに心臓発作のため、亡くなりました。
「ミレニアム」は、雑誌・ミレニアムの発行責任者であるミカエルが主人公のひとりですが、もちろん、彼はスティーグ・ラーソン自身であり、もうひとりの主人公である、ナゾの調査員・リスベットは、スティーグ・ラーソンの救世主的存在じゃないかなと、アタシは思いました。
また、そのうち続きを書きたいと思います。













 )
)



 )
)