「いつかやろう!」と思うだけで先送りしてきたXMLの勉強を始めました。
大量に本を買い込んだ中で「役に立った」「今も読んでる」本は以下のもの。
 XMLクイックリファレンス
XMLクイックリファレンス
「クイックリファレンス」と書名にはあるけど、リファレンスではないです。
#それともこれだけ具体例を挙げて説明しないとダメ、ってことかな?
実際に自分の手を動かして試行錯誤しながら身につける、って人にはこの本こそXMLの入門書にふさわしいと思います。
今は、MSXML & C++ & XML Notepad でこの本のサンプルを動かしながら勉強してます。オススメ
ちょっとした確認をしたい時は「XML デスクトップリファレンス」の方がいいかも?
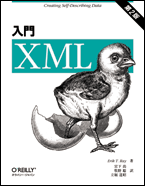 入門 XML
入門 XML
解りやすく丁寧に書いてあるんだけど、実際に手を動かして試行錯誤できる所が中盤以降なのでそこまで読むのが長くてつらい。
多分、この本だけだと途中で挫折してる。いまは「XMLクイックリファレンス」の横に並べて知識側の補完に利用させてもらってます。
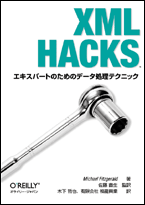 XML Hacks
XML Hacks
上の2冊での勉強に疲れた時にパラパラとめくり、「そうね、こういう事が出来るようになるのね」、と好奇心&&勉強意欲回復に使ってます。
オススメは上3冊(+動作確認環境としてXML Notepad)だけど、以下の本も「いいかな?」との印象をもちました。#でも今は読んでない
はじめて読むXML
この本のよい所は「薄くて読みやすい」。
実作業で動作確認がしやすい「XMLクイックリファレンス」、理論面での裏付け知識が身に付く「入門 XML」、両者のいいとこ取りがこの1冊で出来ます。実際に動作確認させる時に必要なツールも具体的に挙げてあり、取りかかる前段階に迷う所が少なくて良いです。
で、読まなくなった理由ですが、「ページ数が少ないので内容が物足りない」、これです。ページ数だけを見ても、「XMLクイックリファレンス」730P、「入門 XML」426P、計1156P。「はじめて読むXML」は304P。どうしても、ページ数分だけ内容が「薄く」「広く」なってしまいます。いろいろ読んでいて確認したくなる事柄が出てきた時に、この本が押さえている範囲外の事柄が多くなり、自然と読まなくなりました。
でも、内容はしっかりしていてよい本だと思いますよ。手を動かして確認しやすいし。
C++によるXML開発技法
この本もコードがたくさん書いてあって「やってみよう!」と思うんですけど、XML Parser が MSXML ではなくUnixな世界(?)が展開されていてちょっと躊躇。そうしているしている間にオライリー本に出会い、結局、今は読んでいません。添付のCDの中にはMSXML向けの情報もあったのかな?見てねーや。
う~~ん、日本人著書&&日本の出版社の本が少ないなぁ・・・
大量に本を買い込んだ中で「役に立った」「今も読んでる」本は以下のもの。
 XMLクイックリファレンス
XMLクイックリファレンス「クイックリファレンス」と書名にはあるけど、リファレンスではないです。
#それともこれだけ具体例を挙げて説明しないとダメ、ってことかな?
実際に自分の手を動かして試行錯誤しながら身につける、って人にはこの本こそXMLの入門書にふさわしいと思います。
今は、MSXML & C++ & XML Notepad でこの本のサンプルを動かしながら勉強してます。オススメ
ちょっとした確認をしたい時は「XML デスクトップリファレンス」の方がいいかも?
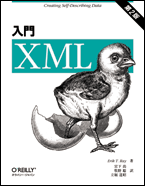 入門 XML
入門 XML解りやすく丁寧に書いてあるんだけど、実際に手を動かして試行錯誤できる所が中盤以降なのでそこまで読むのが長くてつらい。
多分、この本だけだと途中で挫折してる。いまは「XMLクイックリファレンス」の横に並べて知識側の補完に利用させてもらってます。
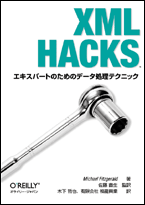 XML Hacks
XML Hacks上の2冊での勉強に疲れた時にパラパラとめくり、「そうね、こういう事が出来るようになるのね」、と好奇心&&勉強意欲回復に使ってます。
オススメは上3冊(+動作確認環境としてXML Notepad)だけど、以下の本も「いいかな?」との印象をもちました。#でも今は読んでない
はじめて読むXML
この本のよい所は「薄くて読みやすい」。
実作業で動作確認がしやすい「XMLクイックリファレンス」、理論面での裏付け知識が身に付く「入門 XML」、両者のいいとこ取りがこの1冊で出来ます。実際に動作確認させる時に必要なツールも具体的に挙げてあり、取りかかる前段階に迷う所が少なくて良いです。
で、読まなくなった理由ですが、「ページ数が少ないので内容が物足りない」、これです。ページ数だけを見ても、「XMLクイックリファレンス」730P、「入門 XML」426P、計1156P。「はじめて読むXML」は304P。どうしても、ページ数分だけ内容が「薄く」「広く」なってしまいます。いろいろ読んでいて確認したくなる事柄が出てきた時に、この本が押さえている範囲外の事柄が多くなり、自然と読まなくなりました。
でも、内容はしっかりしていてよい本だと思いますよ。手を動かして確認しやすいし。
C++によるXML開発技法
この本もコードがたくさん書いてあって「やってみよう!」と思うんですけど、XML Parser が MSXML ではなくUnixな世界(?)が展開されていてちょっと躊躇。そうしているしている間にオライリー本に出会い、結局、今は読んでいません。添付のCDの中にはMSXML向けの情報もあったのかな?見てねーや。
う~~ん、日本人著書&&日本の出版社の本が少ないなぁ・・・










