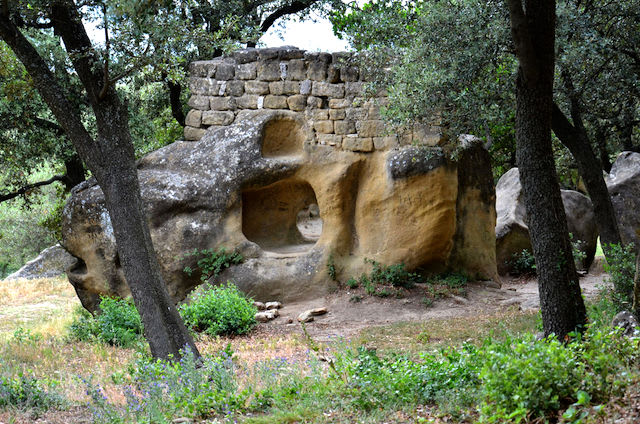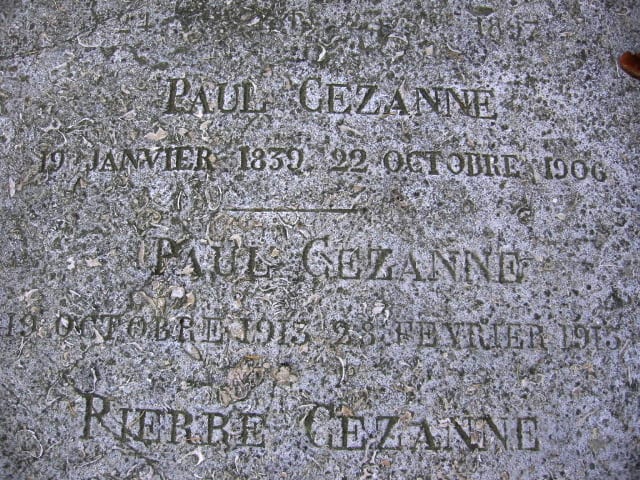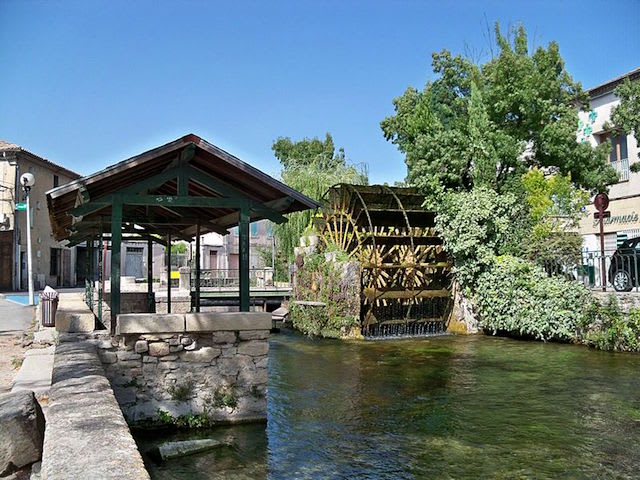ヴェルドン河渓谷の村『カステラーノ」の 夕景
ヴェルドン河の渓谷地帯は
「地方(州)自然公園」に指定されている
流域には
いくつもの魅力あふれた村々がある
それらを順にご紹介してみよう
『Allemagne-en-Provence アルマーニュ・アン・プロヴァンス村』

『Château d'Allemagne アルマーニュ城』
この村には見るべきものはそれほどないが
城は国の重要文化財に
指定されている

村名は
実はフランス語で「ドイツ」である
古代ローマを滅ぼしたゲルマンの諸族の中の
『アレマン人』たちの拠点だったのではないかいわれている
結局彼らは「ライン河「の向こう側に定着して
フランス人から「アルマン人(ドイツ人)」と呼ばれるようになった
国名はアレマン人の国で 「アルマーニュ」
ローマ化以前の原住民族『ガリア人』の
豊穣の女神『アレマノア』から来たのだという人もいる
※
『Aups オプス村』

ここの村名は
通常なら「オー」か『オップ」と発音すべきだが
実際には「オプス」と発音される

『Château de Turenne テュレンヌ城』

城壁の名残

『Tour des Sarasins サラセン人の塔』
10世紀に『サラセン人(イスラム)』に町が占領された
その当時のサラセン人が建てたと言われている塔

『Tour de l'Horloge 時計塔』
カエサルはこの辺りの原住ガリア人を征服して
この土地がいたく気に入り
「ローマで No2になるよりこの土地のトップになりたい」
と
言ったと言う伝承がある
※ ※
『Bargème バルジェーム村』

遠景

『Châtau de Bargème バルジェーム城址』

城門の名残


民家

これが
村の目抜き通り

村役場


例によって
頂上は城址と教会



『Chapelle Notre-Dame des Sept-Douleurs 七苦の聖母礼拝堂』

教会から城址を望む

車が登ってこられる道は
ちゃんと有る

※ ※
『Banon バノン村』


村の中は
当然とはい坂道だらけ

そして
行き止まりのように見えて
アーチのパッサージュだらけ



この村の頂上は
城ではなく教会

『Eglise Saint-Nicolas 聖ニコラ教会』
それとは別に
頂上のさらに外れに

さらに小さな礼拝堂あり

『Eglise Saint-Marc 聖マルコ礼拝堂』
加えて
礼拝堂の裏側に
修道院の廃墟も残っている

小さな小さな村に見えるが
当然
村の広場もあって
カフェも噴水もあるのです

最後に
ラヴェンダーの上にそびえる『バノン村』です

※ ※
『Bauduen ボーデュアン村』

何を隠そう
『サント・クロワ湖』の湖畔にある




『共同洗濯場』

教会

『Eglise Saint-Pierre 聖ペテロ教会』

側面





※ ※
『Esparron de Verdon エスパロン・ド・ヴェルドン村』

俯瞰してみると
こんなに小さな村なのに

『Château d'Esperron エスペロン城』
お城は
こんなにでかい

別の角度から見た方がよく分かる


城の門の脇の城壁にある噴水

『共同洗濯場』

『Eglise Saint-André 聖アンドレ教会』
田舎の村の教会らしく
外観は古いロマネスクの部分もかなり残っているが

中は実に素朴で
かつ
結構ゴチャゴチャしてる
実は
城のすぐ裏はヴェルドン河の小さな人口湖

そのままレジャー基地になっている

結局この村は
かなり広い斜面の位置にあり
上からも
下からも
見る事が出来る様な立地のあるのです


『ヴェルドン渓谷の美しい村々』
は
次回に持ち越します
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
【お願い】
ご感想やご意見ご要望をお間7ています
下の「コメント」ボタンからどうぞ
実名でなくとも構いません
※
旅行自体にご興味をお持ちの方は次のサイトもどうそ