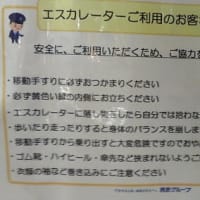11月15日(木)モンテヴェルディ/歌劇「オルフェーオ」


~北とぴあ国際音楽祭2007~
北とぴあ・さくらホール
【配役】
オルフェーオ:ジュリアン・ポッジャー/エウリディーチェ:懸田 奈緒子/音楽、プロセルピーナ:野々下 由香里/女の使者、希望:波多野 睦美/ニンファ:柴山晴美/カロンテ:若林 勉/プルトーネ:畠山 茂/アポロ:与那 城敬/牧人1、例、こだま:谷口 洋介/牧人2:長尾 譲/牧人3:弥勒 忠史 他
【演出】野村四郎、笠井賢一
【衣装】
望月通陽、細田ひな子
【演奏】寺神戸亮指揮レ・ボレアード
毎年意欲的で興味深い古楽による名作を取り上げている北とぴあ国際音楽祭での、寺神戸亮指揮レ・ボレアードの今年の演目はモンテヴェルディのオペラ「オルフェーオ」。能のプロデュースに従事しているという笠井賢一と能楽師 の野村四郎による演出ということで益々興味は尽きない。
日本の神話とも共通性のあるある有名なギリシァ神話に能楽を取り入れるというアイディアは実際とてもおもしろそうだと思ったが、そうした予想をはるかに超越した素晴らしい公演だった。
前奏曲のような形でファンファーレが舞台上で奏され(原曲にもこれはあるのだろうか?)、のぼりで演目が紹介されたあと、舞台奥の暗闇から「音楽」がすーっと幻想的に浮かび上がり、前口上を始める場面から「オルフェオ」の世界に完全に引き込まれて行く。
まず特筆すべきは舞台の美しさ。能舞台をイメージした四角の舞台とそれに繋がる橋掛かりという限られた空間を中心に、ゆっくりとした動きを基調に物語が展開するのだが、優美で落着いた色合いの印象的な衣装を身につけて、歌って演じる歌手やダンサーの何とも調和のとれた動き。
婚礼の喜ばしい場面でダンサー(後藤大、室伏美由紀)は西洋のバレエを踊るのだが、ゆっくりとした全体の動きの間を縫うように舞い踊る様が実によく全体と調和していて、舞台全体が絵のように美しい。まるでボッティチェッリの「春(プリマヴェーラ)」の世界を見ているよう。
そんな喜びの場面からエウリディーチェの死を報せる場面への暗転、能の衣装をまとった神々が登場する黄泉の国の闇の世界、終幕での野村四郎による、幻想的でこの世のものとは思われないような美しい光を放つ能の舞い… 天井から吊るされた巨大なブーケ(花がこのオペラでの「ライトモチーフ」とのこと)以外には、どの場面もアーチ型の枠の他は殆ど何もないという舞台装置のシンプルさが、演じる人たちの衣装と動きの美しさを殊更に浮かび上がらせている。このシンプルさ、美のエッセンスは能の世界なのだろう。
そんな演出では、まどろっこしい説明や謎かけめいたことは一切せず、人の動きにしても、「ライトモチーフ」である花の扱いにしても、非常に明快に物語のポイントに象徴的にスポットを当てる。
そして歌手とオーケストラの素晴らしさ!様々な珍しい古楽器を揃えたオーケストラが奏でる何ともデリケートな音の世界。ハープやチェンバロ、ギターといった撥音楽器のアルペッジョが、歌の細かな心のひだをなでるように、優美で温かな弦楽器(寺神戸亮はヴァイオリンも演奏)と共に伴奏する。そこに加わる管楽器は柔らかな天の響き。難しいはずの金管楽器をなんなく吹きこなすプレイヤーの巧さにも舌を巻く。何よりも、激することなく、押しつけがましい音の洪水とは対極的なシンプルさでここまで情景や心情を奏でる雄弁さというものを思い知る。
歌手達はこうしたデリケートなオーケストラに伴われて、細やかな心情を韻文的に歌ってゆくのだが、ベルカントオペラのように「オケの音量に負けないように」なんて気負う心配がない分、自由で解き放たれている。主役といえるオルフェーオを歌ったポッジャーの美声による自然な歌唱での雄弁さ巧みさや、エウリディーチェの死を伝える「使者」を歌った波多野睦美の心を突き動かすような緊張感のある歌唱はやはり耳を引いたが、そのほか多くの登場人物(一人3役なんて歌手もいるが)一人一人の安定度、レベルがどれも素晴らしく、そうした全員力でこのオペラを盛り立てていることを常に実感した。
冒頭からオケのBGM付きのカーテンコールに至るまで、引きつけられっぱなしだった「オルフェオ」。これが400年前に初演された作品だということを思うと、普段あまり演奏されることのないバッハ以前の音楽がなんと豊かな世界を持っているかに気づく。
そしてこのルネサンスのヨーロッパの芸術が日本の古典である能との「コラボレーション」でこれほどまでに調和のとれた美しい幽玄の世界を創り出すことの驚きはいくら賞賛してもしきれるものではない。この公演はこの「北とぴあ」だけで終わらすことなく、全世界を回ってもらいたい。きっと世界中の人々の心を魅了するに違いない。



~北とぴあ国際音楽祭2007~
北とぴあ・さくらホール
【配役】
オルフェーオ:ジュリアン・ポッジャー/エウリディーチェ:懸田 奈緒子/音楽、プロセルピーナ:野々下 由香里/女の使者、希望:波多野 睦美/ニンファ:柴山晴美/カロンテ:若林 勉/プルトーネ:畠山 茂/アポロ:与那 城敬/牧人1、例、こだま:谷口 洋介/牧人2:長尾 譲/牧人3:弥勒 忠史 他
【演出】野村四郎、笠井賢一
【衣装】
望月通陽、細田ひな子
【演奏】寺神戸亮指揮レ・ボレアード
毎年意欲的で興味深い古楽による名作を取り上げている北とぴあ国際音楽祭での、寺神戸亮指揮レ・ボレアードの今年の演目はモンテヴェルディのオペラ「オルフェーオ」。能のプロデュースに従事しているという笠井賢一と能楽師 の野村四郎による演出ということで益々興味は尽きない。
日本の神話とも共通性のあるある有名なギリシァ神話に能楽を取り入れるというアイディアは実際とてもおもしろそうだと思ったが、そうした予想をはるかに超越した素晴らしい公演だった。
前奏曲のような形でファンファーレが舞台上で奏され(原曲にもこれはあるのだろうか?)、のぼりで演目が紹介されたあと、舞台奥の暗闇から「音楽」がすーっと幻想的に浮かび上がり、前口上を始める場面から「オルフェオ」の世界に完全に引き込まれて行く。
まず特筆すべきは舞台の美しさ。能舞台をイメージした四角の舞台とそれに繋がる橋掛かりという限られた空間を中心に、ゆっくりとした動きを基調に物語が展開するのだが、優美で落着いた色合いの印象的な衣装を身につけて、歌って演じる歌手やダンサーの何とも調和のとれた動き。
婚礼の喜ばしい場面でダンサー(後藤大、室伏美由紀)は西洋のバレエを踊るのだが、ゆっくりとした全体の動きの間を縫うように舞い踊る様が実によく全体と調和していて、舞台全体が絵のように美しい。まるでボッティチェッリの「春(プリマヴェーラ)」の世界を見ているよう。
そんな喜びの場面からエウリディーチェの死を報せる場面への暗転、能の衣装をまとった神々が登場する黄泉の国の闇の世界、終幕での野村四郎による、幻想的でこの世のものとは思われないような美しい光を放つ能の舞い… 天井から吊るされた巨大なブーケ(花がこのオペラでの「ライトモチーフ」とのこと)以外には、どの場面もアーチ型の枠の他は殆ど何もないという舞台装置のシンプルさが、演じる人たちの衣装と動きの美しさを殊更に浮かび上がらせている。このシンプルさ、美のエッセンスは能の世界なのだろう。
そんな演出では、まどろっこしい説明や謎かけめいたことは一切せず、人の動きにしても、「ライトモチーフ」である花の扱いにしても、非常に明快に物語のポイントに象徴的にスポットを当てる。
そして歌手とオーケストラの素晴らしさ!様々な珍しい古楽器を揃えたオーケストラが奏でる何ともデリケートな音の世界。ハープやチェンバロ、ギターといった撥音楽器のアルペッジョが、歌の細かな心のひだをなでるように、優美で温かな弦楽器(寺神戸亮はヴァイオリンも演奏)と共に伴奏する。そこに加わる管楽器は柔らかな天の響き。難しいはずの金管楽器をなんなく吹きこなすプレイヤーの巧さにも舌を巻く。何よりも、激することなく、押しつけがましい音の洪水とは対極的なシンプルさでここまで情景や心情を奏でる雄弁さというものを思い知る。
歌手達はこうしたデリケートなオーケストラに伴われて、細やかな心情を韻文的に歌ってゆくのだが、ベルカントオペラのように「オケの音量に負けないように」なんて気負う心配がない分、自由で解き放たれている。主役といえるオルフェーオを歌ったポッジャーの美声による自然な歌唱での雄弁さ巧みさや、エウリディーチェの死を伝える「使者」を歌った波多野睦美の心を突き動かすような緊張感のある歌唱はやはり耳を引いたが、そのほか多くの登場人物(一人3役なんて歌手もいるが)一人一人の安定度、レベルがどれも素晴らしく、そうした全員力でこのオペラを盛り立てていることを常に実感した。
冒頭からオケのBGM付きのカーテンコールに至るまで、引きつけられっぱなしだった「オルフェオ」。これが400年前に初演された作品だということを思うと、普段あまり演奏されることのないバッハ以前の音楽がなんと豊かな世界を持っているかに気づく。
そしてこのルネサンスのヨーロッパの芸術が日本の古典である能との「コラボレーション」でこれほどまでに調和のとれた美しい幽玄の世界を創り出すことの驚きはいくら賞賛してもしきれるものではない。この公演はこの「北とぴあ」だけで終わらすことなく、全世界を回ってもらいたい。きっと世界中の人々の心を魅了するに違いない。