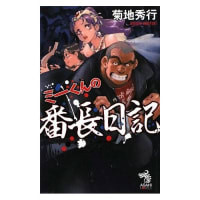『チチキトク スグカエレ』
まるでドラマのような電報が届いた。
父が危篤ということよりも、未だ電報が存在することのほうが千鶴子を驚かせた。
携帯電話の番号も、メールアドレスも知らせていないのでは仕方がない。住所と家の電話番号を変えていないのが救いか。もっとも、家の電話に出ることはない。だから、このような手段にでたのだろう。母には悪いことをした。
上京して以来、父とは一度も顔を合わせていない。
記憶にある父は常に眉間に皺を寄せ、よく千鶴子と口論をした。
大概は千鶴子に非があるのだが、若さ故か、千鶴子はそれを認めようとせず、父も口下手であったため、最後は必ず父の平手打ちで決着がついた。
暴力でしか物事を解決出来ない男。
父親にそんなレッテルを貼るのに、そう時間はかからなかった。
二度と会いたくない。
逃げるように家を飛び出して十年になる。
たまに母が訪ねてくるが、いつも一人だった。
どことなく寂しげな顔で、帰ってくる気はないのかと聞かれるが、その度に父の顔が脳裏をよぎり、千鶴子に二の足を踏ませるのだった。
今さら合わせる顔などない。
千鶴子は気分転換に散歩にでることにした。
仕事に追われ、せかせかと歩く道も、無目的で歩いてみると様々な発見がある。
立ち並ぶ家々。
庭に水を撒く夫人。
犬とじゃれる子供。
意識して見なければこの先も気付くことはなかったろう。
だったら。
千鶴子は入ったことのない道を選んだ。
何やら騒がしい。
そこは公園だった。
子供たちが楽しげに遊んでいる。
ベンチに腰を下ろすと、煙草に火をつけた。
ゆっくりと煙を吐き出す。
滑り台やジャングルジム、ブランコにシーソー。どれも遊んだことのある遊具だ。
「千鶴子?」
顔を上げると女が立っていた。年の頃は千鶴子と変わらない。女は千鶴子と目が合うなり興奮した様子で言った。
「やっぱり千鶴子だ。あたしよ、あたし。覚えてる?」
千鶴子が怪訝そうな顔をすると、
「やだ、覚えてないの?中学時代、部活で一緒だった八重垣結維」
ああ、言われてみれば昔の面影がある。
結維は千鶴子の隣に腰掛けると近況を話しだした。
結維は結婚して、一児の母になったという。
「ほら、砂場にいるでしょ?ウチの旦那と息子」
砂場の成人男性は一人しかいない。あれが旦那か。とすると、隣にいるのが息子。
まだ二歳くらいであろう子供を父親が暖かく見守っている。
「ホント、ウチの人って子煩悩なのよね」
そういえば、あんな頃もあったのか。
千鶴子にもあった子供時代。
父とよく公園に遊びに行き、砂山を作ったものだ。お世辞にも手先が器用とはいえなかった千鶴子は、砂山にトンネルを掘ろうとして山を崩落させた。何度やってもうまくいかず、ついに泣き出しそうになったとき、父は千鶴子の泥だらけになった手を握って、頑張れ、と言った。そしてにっこりと笑いかけるその眼指しはとても暖かかった。
今にして思えば、ブランコ漕いでいるときも、滑り台を滑るときも、傍らには必ず父がいた。
いったいどこで間違えてしまったのか。
気付けば午後五時を過ぎていた。
「あら、もうこんな時間?それじゃ、夕飯の用意があるから。あたしね、あそこの社宅に住んでるの。二○二号室。よかったら遊びにきてね」
結維は息子のところに駆け寄ると、千鶴子に手を振った。旦那は息子を抱き上げ千鶴子に一礼し、かつての同級生一家は家に帰っていった。
煙草に火をつける。
ゆっくりと煙を吐き出す。
右頬を涙が伝っていった。
携帯電話を取りだし、番号をプッシュする。
「もしもし、母さん?……うん、明日には帰れるから。だから、それまで父さんのことよろしくね」
会ってなんと言えばいいのかもわからない。もしかしたら間に合わないかもしれない。それでも、なにもしないよりはいい。
千鶴子は涙を拭き、公園を後にした。
完
まるでドラマのような電報が届いた。
父が危篤ということよりも、未だ電報が存在することのほうが千鶴子を驚かせた。
携帯電話の番号も、メールアドレスも知らせていないのでは仕方がない。住所と家の電話番号を変えていないのが救いか。もっとも、家の電話に出ることはない。だから、このような手段にでたのだろう。母には悪いことをした。
上京して以来、父とは一度も顔を合わせていない。
記憶にある父は常に眉間に皺を寄せ、よく千鶴子と口論をした。
大概は千鶴子に非があるのだが、若さ故か、千鶴子はそれを認めようとせず、父も口下手であったため、最後は必ず父の平手打ちで決着がついた。
暴力でしか物事を解決出来ない男。
父親にそんなレッテルを貼るのに、そう時間はかからなかった。
二度と会いたくない。
逃げるように家を飛び出して十年になる。
たまに母が訪ねてくるが、いつも一人だった。
どことなく寂しげな顔で、帰ってくる気はないのかと聞かれるが、その度に父の顔が脳裏をよぎり、千鶴子に二の足を踏ませるのだった。
今さら合わせる顔などない。
千鶴子は気分転換に散歩にでることにした。
仕事に追われ、せかせかと歩く道も、無目的で歩いてみると様々な発見がある。
立ち並ぶ家々。
庭に水を撒く夫人。
犬とじゃれる子供。
意識して見なければこの先も気付くことはなかったろう。
だったら。
千鶴子は入ったことのない道を選んだ。
何やら騒がしい。
そこは公園だった。
子供たちが楽しげに遊んでいる。
ベンチに腰を下ろすと、煙草に火をつけた。
ゆっくりと煙を吐き出す。
滑り台やジャングルジム、ブランコにシーソー。どれも遊んだことのある遊具だ。
「千鶴子?」
顔を上げると女が立っていた。年の頃は千鶴子と変わらない。女は千鶴子と目が合うなり興奮した様子で言った。
「やっぱり千鶴子だ。あたしよ、あたし。覚えてる?」
千鶴子が怪訝そうな顔をすると、
「やだ、覚えてないの?中学時代、部活で一緒だった八重垣結維」
ああ、言われてみれば昔の面影がある。
結維は千鶴子の隣に腰掛けると近況を話しだした。
結維は結婚して、一児の母になったという。
「ほら、砂場にいるでしょ?ウチの旦那と息子」
砂場の成人男性は一人しかいない。あれが旦那か。とすると、隣にいるのが息子。
まだ二歳くらいであろう子供を父親が暖かく見守っている。
「ホント、ウチの人って子煩悩なのよね」
そういえば、あんな頃もあったのか。
千鶴子にもあった子供時代。
父とよく公園に遊びに行き、砂山を作ったものだ。お世辞にも手先が器用とはいえなかった千鶴子は、砂山にトンネルを掘ろうとして山を崩落させた。何度やってもうまくいかず、ついに泣き出しそうになったとき、父は千鶴子の泥だらけになった手を握って、頑張れ、と言った。そしてにっこりと笑いかけるその眼指しはとても暖かかった。
今にして思えば、ブランコ漕いでいるときも、滑り台を滑るときも、傍らには必ず父がいた。
いったいどこで間違えてしまったのか。
気付けば午後五時を過ぎていた。
「あら、もうこんな時間?それじゃ、夕飯の用意があるから。あたしね、あそこの社宅に住んでるの。二○二号室。よかったら遊びにきてね」
結維は息子のところに駆け寄ると、千鶴子に手を振った。旦那は息子を抱き上げ千鶴子に一礼し、かつての同級生一家は家に帰っていった。
煙草に火をつける。
ゆっくりと煙を吐き出す。
右頬を涙が伝っていった。
携帯電話を取りだし、番号をプッシュする。
「もしもし、母さん?……うん、明日には帰れるから。だから、それまで父さんのことよろしくね」
会ってなんと言えばいいのかもわからない。もしかしたら間に合わないかもしれない。それでも、なにもしないよりはいい。
千鶴子は涙を拭き、公園を後にした。
完