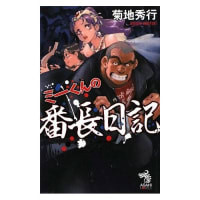しばらくすると俊が戻ってきた。
持っている皿に乗っているのはうなぎの蒲焼である。
新メニューというからどんなものが出てくるか、期待半分、構え半分の誠一郎であったが、自身ありげな俊の顔を見る限りただの蒲焼ではないようだ。
「いろいろ試してみたんですが、現状では一番おいしくできてます」
一口食べてみる。
うなぎ自体もさることながら、タレもよくできている。
脂がのって濃厚な身を、それだけでは終わらないようにタレが支えている。
「タレも自家製か?」
「ええ。基本的な作り方は関西風ですが、どこにでもある蒲焼じゃお客さんは来ませんから。僕の店だけの味を、そして僕にしか作れないものを目指しました」
「関西風ということは関東風もあるのか」
「はい。うなぎの開き方や串の刺し方、焼き方など細かく違います。一番の違いは味ですね」
「ほう」
「関東の蒲焼は素焼きした後せいろで蒸して脂を落とすので、柔かく淡白な味になります。関西のそれは素焼きの後、タレをつけて本焼きするので濃厚な味になります」
語る俊の目は輝いているように見えた。喋りたくて仕方ないのだろう。
「うまい。素人の俺が言うのもなんだが、これならすぐ店に出せるんじゃないか」
「そうですか。そう言ってもらえると安心です」
ぱくぱくとうなぎを食べる誠一郎を俊は満足げに眺めていた。
やがて食べ終えると、
「どんな人なんだ」
と、誠一郎は聞いてきた。
「なにがですか?」
「交際相手だ」
「そうですね、摑み所がない人、ですかね」
「摑み所がない」
誠一郎は眉をひそめた。摑み所がないとは理解しにくい人間を指す。まさか妙な人間では?
そんな父の様子を見て、
「ああ、いや、悪い人じゃないんですよ。美人ですし、貯金もしています。考え方もしっかりしてますし、なにより僕を支えてくれます。それに今食べたうなぎのアイデアも、一部は彼女が出したものなんですよ」
と、俊は慌てて言った。
「なら、どの辺が摑み所がないんだ」
「多少、その、放浪癖がありまして。旅行好きといえば聞こえはいいんですが」
「大丈夫なのか?」
「そのことでけんかもしましたが、彼女もわかってくれました。実は、近いうちに彼女を連れて会いに行こうと思ってたんです」
この様子では何も問題なさそうだ。
誠一郎は一瞬の胸のざわめきをかき消した。
「ところで、父さんはうなぎの捌き方をご存知ですか?」
「いや、知らん」
突然の質問に誠一郎はある種のしこりを感じた。
話を逸らされた?
「うなぎってヌルヌルして摑めないでしょう。でも、ちゃんと持ち方がありまして、中指で挟むように持つんです。これも慣れが必要でして。ボクも最初はよく逃げられました。そうしたら専用の包丁でしめます。骨まで包丁を入れて、でも頭を落とさないように刃を入れます。しめたら氷水で黙らせます。うなぎって意外と力が強いんですよ。暴れられてまいりました」
俊の目は上を向いている。
そのときの様子を思い出しているのか。さも苦労したというような顔をしている。
「そして目打ちを打ちます。錐みたいなものでうなぎを固定するんです。後は身を開いていくだけです。まあ、骨とかも取りますが、それは置いときましょう」
「ちょ、ちょっと待ってくれ」
「なんですか?」
「用を足してくる」
「でしたら、そこの廊下の突き当りを右へ」
「ああ、すぐ戻る」
誠一郎はトイレに入るとふう、と肩で息を吐いた。
突然うなぎの捌き方を語りだした俊はやはり様子がおかしい。
なにかあるな、と思った。
この家に入ったときから感じていた違和感。
どことなくおかしい息子。
そもそも誠一郎は調理に興味はない。食べるほう専門である。俊が知らないはずはない。
その父に調理法を語り聞かせるとは。
誠一郎の疑問は膨らむばかりだった。
持っている皿に乗っているのはうなぎの蒲焼である。
新メニューというからどんなものが出てくるか、期待半分、構え半分の誠一郎であったが、自身ありげな俊の顔を見る限りただの蒲焼ではないようだ。
「いろいろ試してみたんですが、現状では一番おいしくできてます」
一口食べてみる。
うなぎ自体もさることながら、タレもよくできている。
脂がのって濃厚な身を、それだけでは終わらないようにタレが支えている。
「タレも自家製か?」
「ええ。基本的な作り方は関西風ですが、どこにでもある蒲焼じゃお客さんは来ませんから。僕の店だけの味を、そして僕にしか作れないものを目指しました」
「関西風ということは関東風もあるのか」
「はい。うなぎの開き方や串の刺し方、焼き方など細かく違います。一番の違いは味ですね」
「ほう」
「関東の蒲焼は素焼きした後せいろで蒸して脂を落とすので、柔かく淡白な味になります。関西のそれは素焼きの後、タレをつけて本焼きするので濃厚な味になります」
語る俊の目は輝いているように見えた。喋りたくて仕方ないのだろう。
「うまい。素人の俺が言うのもなんだが、これならすぐ店に出せるんじゃないか」
「そうですか。そう言ってもらえると安心です」
ぱくぱくとうなぎを食べる誠一郎を俊は満足げに眺めていた。
やがて食べ終えると、
「どんな人なんだ」
と、誠一郎は聞いてきた。
「なにがですか?」
「交際相手だ」
「そうですね、摑み所がない人、ですかね」
「摑み所がない」
誠一郎は眉をひそめた。摑み所がないとは理解しにくい人間を指す。まさか妙な人間では?
そんな父の様子を見て、
「ああ、いや、悪い人じゃないんですよ。美人ですし、貯金もしています。考え方もしっかりしてますし、なにより僕を支えてくれます。それに今食べたうなぎのアイデアも、一部は彼女が出したものなんですよ」
と、俊は慌てて言った。
「なら、どの辺が摑み所がないんだ」
「多少、その、放浪癖がありまして。旅行好きといえば聞こえはいいんですが」
「大丈夫なのか?」
「そのことでけんかもしましたが、彼女もわかってくれました。実は、近いうちに彼女を連れて会いに行こうと思ってたんです」
この様子では何も問題なさそうだ。
誠一郎は一瞬の胸のざわめきをかき消した。
「ところで、父さんはうなぎの捌き方をご存知ですか?」
「いや、知らん」
突然の質問に誠一郎はある種のしこりを感じた。
話を逸らされた?
「うなぎってヌルヌルして摑めないでしょう。でも、ちゃんと持ち方がありまして、中指で挟むように持つんです。これも慣れが必要でして。ボクも最初はよく逃げられました。そうしたら専用の包丁でしめます。骨まで包丁を入れて、でも頭を落とさないように刃を入れます。しめたら氷水で黙らせます。うなぎって意外と力が強いんですよ。暴れられてまいりました」
俊の目は上を向いている。
そのときの様子を思い出しているのか。さも苦労したというような顔をしている。
「そして目打ちを打ちます。錐みたいなものでうなぎを固定するんです。後は身を開いていくだけです。まあ、骨とかも取りますが、それは置いときましょう」
「ちょ、ちょっと待ってくれ」
「なんですか?」
「用を足してくる」
「でしたら、そこの廊下の突き当りを右へ」
「ああ、すぐ戻る」
誠一郎はトイレに入るとふう、と肩で息を吐いた。
突然うなぎの捌き方を語りだした俊はやはり様子がおかしい。
なにかあるな、と思った。
この家に入ったときから感じていた違和感。
どことなくおかしい息子。
そもそも誠一郎は調理に興味はない。食べるほう専門である。俊が知らないはずはない。
その父に調理法を語り聞かせるとは。
誠一郎の疑問は膨らむばかりだった。