
昨日、素焼きの窯を焚きました。
前面に開いた大きい四角い穴は色見穴と呼ばれていて、焚き上がりのころ、ここから
中の色味と呼ばれる陶片を出して焼き上がりをチェックするのですが、
窯を焚いているのになんでこの穴を空けているかというと、素焼きの大敵・水蒸気を逃がしているため。
素焼きのときは特に土に水分が含まれており(そのときの乾燥具合にもよりますが)
土が水分を含んだまま急激に温度があがると、土の中の水分が急激に膨張して、作品爆裂!ということに・・・(涙)。
そのような事態を防ぐためにも、素焼きは特に慎重に温度をあげていく必要があります。
なので、火をつけて1時間くらいは扉は半開き、扉を閉めた後もこのような色見穴や空気穴を開けたまま温度を上げていきます。
穴に手をかざして、手のひらが少し湿るような感じがするうちは、まだ水蒸気が蒸発しているということ。
穴に手をかざしてもさらっとしているようならいよいよ穴に蓋をして(写真)温度を上げていきます。
窯を焚くとき、『魔の温度』といわれているのが、573度。
このとき、もっとも急激に土(珪酸分)が膨張するんですって。
あと、200度から300度までも慎重に、といわれています。
これは、200度くらいまでは窯の中で、「付着水」という土の組成物質に分子レベルで結合している水分、
通常の乾燥では抜けない性質の水分が蒸発していくからで、
この温度までに急熱すると付着水が気化するときの膨張で、作品が「焚き割れ」を起こす、といわれているのです。
だいたい温度上昇の目安は1時間につき100度。
ゆっくり焚くときで1時間に70~80度の温度上昇。
灯油窯の場合は、温度を見ながら、油量と風量で調節していきます。
色味穴の下にささっているコードのついた棒のようなものが温度計です。
素焼きの温度はだいたい700度から800度まで。
それ以上温度を上げると、釉薬をかけるときの吸水性がなくなっていってしまいます。
今回はちょっと高めで770度くらいまであげて、火を止めました。
で、このあと、窯が急に冷えるのも、また今度は「冷め割れ」という破損の原因になってしまうというわけで、
火を止めたら、今度はダンパーと呼ばれる鉄の板で、煙道に蓋をして、温度が急激に低下するのを防ぎます。
窯から焼いたものを出せるのは窯の温度が100度以下に下がってから、といわれていて
これもやはり、冷め割れを防ぐためなのですが、こればっかりは次の作業が押していたりすると
そうもいっていられない!という事情もあって、200度を下ったあたりから徐々に色味穴をあけたり、蓋をあけたり
なんとか徐々に、かつ強引に冷まして、まだ熱々のうちに出してしまうことも・・・。
さ、素焼きがすんだら今度は施釉して本焼きです。
ふー、完成まであと一息!
なんか今回はかなり焼き物やっぽいページじゃないですか(笑)。
わたくし実はこういうことも陰で地味~にやっているのです・・・。(っていうか一応こっちが本業で!・笑)
前面に開いた大きい四角い穴は色見穴と呼ばれていて、焚き上がりのころ、ここから
中の色味と呼ばれる陶片を出して焼き上がりをチェックするのですが、
窯を焚いているのになんでこの穴を空けているかというと、素焼きの大敵・水蒸気を逃がしているため。
素焼きのときは特に土に水分が含まれており(そのときの乾燥具合にもよりますが)
土が水分を含んだまま急激に温度があがると、土の中の水分が急激に膨張して、作品爆裂!ということに・・・(涙)。
そのような事態を防ぐためにも、素焼きは特に慎重に温度をあげていく必要があります。
なので、火をつけて1時間くらいは扉は半開き、扉を閉めた後もこのような色見穴や空気穴を開けたまま温度を上げていきます。
穴に手をかざして、手のひらが少し湿るような感じがするうちは、まだ水蒸気が蒸発しているということ。
穴に手をかざしてもさらっとしているようならいよいよ穴に蓋をして(写真)温度を上げていきます。
窯を焚くとき、『魔の温度』といわれているのが、573度。
このとき、もっとも急激に土(珪酸分)が膨張するんですって。
あと、200度から300度までも慎重に、といわれています。
これは、200度くらいまでは窯の中で、「付着水」という土の組成物質に分子レベルで結合している水分、
通常の乾燥では抜けない性質の水分が蒸発していくからで、
この温度までに急熱すると付着水が気化するときの膨張で、作品が「焚き割れ」を起こす、といわれているのです。
だいたい温度上昇の目安は1時間につき100度。
ゆっくり焚くときで1時間に70~80度の温度上昇。
灯油窯の場合は、温度を見ながら、油量と風量で調節していきます。
色味穴の下にささっているコードのついた棒のようなものが温度計です。
素焼きの温度はだいたい700度から800度まで。
それ以上温度を上げると、釉薬をかけるときの吸水性がなくなっていってしまいます。
今回はちょっと高めで770度くらいまであげて、火を止めました。
で、このあと、窯が急に冷えるのも、また今度は「冷め割れ」という破損の原因になってしまうというわけで、
火を止めたら、今度はダンパーと呼ばれる鉄の板で、煙道に蓋をして、温度が急激に低下するのを防ぎます。
窯から焼いたものを出せるのは窯の温度が100度以下に下がってから、といわれていて
これもやはり、冷め割れを防ぐためなのですが、こればっかりは次の作業が押していたりすると
そうもいっていられない!という事情もあって、200度を下ったあたりから徐々に色味穴をあけたり、蓋をあけたり
なんとか徐々に、かつ強引に冷まして、まだ熱々のうちに出してしまうことも・・・。
さ、素焼きがすんだら今度は施釉して本焼きです。
ふー、完成まであと一息!
なんか今回はかなり焼き物やっぽいページじゃないですか(笑)。
わたくし実はこういうことも陰で地味~にやっているのです・・・。(っていうか一応こっちが本業で!・笑)










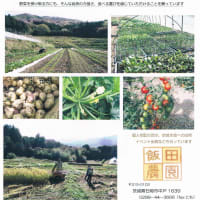









どんな作品を焼いたのか、早く見てみたいです。
忙しさの中で本業に熱中する貴重な時間はどんなに幸せなのでしょうね!!!
こちらからもブログに書き込みにいきます~!