
半年前までは、リアルに集まるのが当たり前だったけど、
会うこと自体が「避けるべし」な風潮になって半年。
否応なくオンラインの講座とかが増えて、
するのにも、受けるのにも、慣れました。
移動しなくていいってめっちゃラクチン~~!!とか、
「心」や「考え」は言葉でキャッチボールできるから一緒だ!とか、
オンラインならではの良さも、あれこれ実感できました。
ところが、こないだ久しぶりにリアルに会って、
半日一緒に入れ替わり立ちかわり、
のんびりとくつろいでいた時、昔の感覚を思い出した。
あ、いちおー言っておくと、
ソーシャルディスタンスとやらも意識して
お外のベンチで離れてゆったり座ってね。
サンシェードはありつつも外はやっぱり暑いし、
おなかもいっぱいになって、夕暮れ時。
一緒に夕焼けを見ながら何も話さず風を感じていても、
飲んだ人がそのまま寝ちゃっても、
オンラインと違って、ただそこに居ることが許される。
オンラインで、ここまでくつろいだことはない。
何かを進めないといけないし、時間は限られているし、
何かの目的に向けて行動や発言を求められる。
それはそれでホントに便利なんだけどね。
意思決定や、何かを伝えたりするのには。
だけど、リアルに会って感じる、
ゆったりした感覚も忘れたくないな~、と。
オンラインとの決定的な違いは、
「ただ居るだけでいい」っていうこと。
※昨日、帰ってきた直後にサラッと印象を書いたので、
ご興味ありましたら、どうぞ。
https://blog.goo.ne.jp/oneby1/e/420286672c81d3f5473ef30cd162c41c
「なんだろな~、この感覚の違い…」。
一日経って思い出しました。
「現代社会がストレス社会になってきたのは、
社会の基盤が共同体から機能集団になってきたからだ」という
早稲田大学の名誉教授、加藤諦三さんの説を。
つまり、共同体というのは、おじいちゃんも、赤ちゃんも含み、
「あなたがここに居ること」に意味がある場所。
赤ちゃんが育っていくことや、おばあちゃんがにこにこ座っていることが、
そのままで周りも嬉しい、というような場所。
一方、機能集団は、
会社の部長は、部長の役目を果たすことが、
野球部のエースは、相手バッターを打ち取れることが
そこに存在するための条件、という厳しい場所。
その条件を満たさなくなれば、
その場所を誰かにゆずらなければいけない。
周りに居る人は、みんなライバル。
受験だってそうかもね。
そういう、
役立たないと存在を許されない、というプレッシャーが、
社会でストレスがどんどん増えて行く大きな要因だ、
というのです。
会社はもちろんだけど、家庭ですら
(リアルには聞いたことないけど)、
「そんな子はウチの子じゃありません」とか、
「ウチの嫁ならこうあるべき」とか、
機能を求められて殺伐とする空気、ありそうだもの。
「何もしなくてもいることが許されてる安心感、たまらんなぁ!」
って感じた、あの感覚。
よく考えたら、犬や猫だってそうだよね。
赤ちゃんや友人だってそうだよね。
…って並列で書くのもどうかと思うけど、ゴメンなさい。
あ! 親だってそうだ。
子どもが小さかった時、親は、
美人じゃなくても、運動ができなくても、
資格がなくても、料理や片づけが下手でも、
理路整然と話せなくても(…以下永遠に続く)、
一緒にいるだけで喜んでくれる存在だった。
トイレでも行って一瞬目の前から消えるだけで、
泣きながら探しに来てくれるほどに。
あんなに存在まるごとを肯定されたことはなかった。
自分が赤ちゃんの時も、きっとそうだっただろうけど、
残念なことに覚えてない。
(とーちゃん、かーちゃんありがとう!)
共同体ベースの社会。
存在するだけで喜ばれる社会。
規模の大きいのは無理だし、常時ってのも無理だけど…。
私だって、自分の身の回り、2~3人の関係なら、
時々はできそうな気がする。
したい人が、したい所で、したい範囲で、
意識的にそういう場を作れば、それは確かな一歩だ。












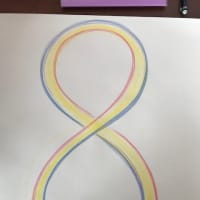







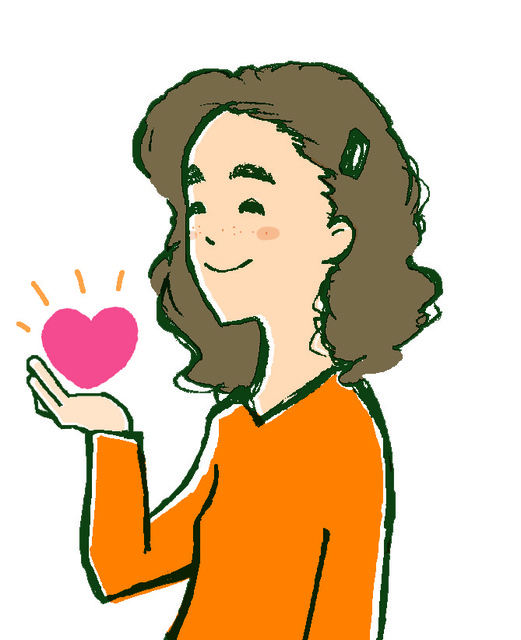

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます