早朝ウォーキングの二人連れが,咲いているユリを見ながら、会話していました。「あの白いのはテッポウユリよね」と一人が言えば、相方は「近頃のテッポウユリには赤い筋のもあるわねぇ。新種なのかしら」云々かんぬん。

初めて遭った方達でしたが、聞こえたからには “赤い筋が入っているのは、タカサゴユリですよ~。" とお教えしたかったのですが、余計なことは言うまいと思い、そのまま聞こえなかったかのような顔をして暫く、前後に並んで歩いていました。
すると、「赤い線があろうと無かろうと、ユリはユリよ~」と言う一人の言葉に「そうよねぇ。ユリでいいのよねぇ」と応えて、その話は終わって次の話題へ。同じに見える植物の、あれとこれはどこが違うのだろうと、いつも比較したくなる性癖のある私からすれば、直(すなお)に「そうね、ユリでいいわよ」とは思えず、我ながら困った性分だと苦笑しました。 苦笑しながら、あまり興味のない人にとっては、「ユリという大きな括りでいいのかもしれない。」と妙に納得したのです。
この話をご近所のYさんに話すと、「トルコのガイドさんに“日本の人は、あの花の名前は?、この花の名前は?"と度々訊かれますが、トルコではバラとチュ-リップ以外はひっくるめて花と云います」と言われた・・・とYさんは話されました。
しかし私自身としては、ユリはユリでも、いろいろあるのだから、やはり違いは知っておくにこしたことはないと思い、暑さをものともせず、附近のユリを撮りに廻ったのですが、会話に出ていたテッポウユリの開花期は5~6月で、既に終わっており、残念無念。
テッポウユリは、6月撮影の画像の中にあったはず・・・、今度はパソコンの中を駆け回り、漸く見つけてヤレヤレでした。拘りを持つのは結構しんどいです。ウォ-キングのお二人やトルコの人のような考え方の方が、楽な生き方が出来るかもしれません。
■テッポウユリ Lilium longiflorum に話を戻しましょう。

テッポウユリは、日本固有のユリとして知られています。ラッパに似た花を横向きに咲かせますが、自生地によりかなり変化が多く葉姿や花の咲き方が微妙に違います。切り花用として出回っているテッポウユリは、“ひのもと”という品種です。
明治時代には海外へ輸出され、他の種類と交雑しやすいことから、多くの品種が作られています。「百合の女王」として人気の高い“カサブランカ”は、日本の百合の原種数種をもとに作られた園芸品種です。“イースターリリー”と呼ばれる香りの強い大きなトランペット状の白い花を咲かせる品種は、テッポウユリ・タカサゴユリなどをもとに作られた園芸品種です。
百合の原種は世界に約100種あるそうですが、その中で日本原産のものは15種類、そのうちヤマユリ、ササユリ、オトメユリ、テッポウユリ、カノコユリ、サクユリ、タモトユリ、ウケユリの8種類が日本の固有種です。近年出回っている人気の高い百合の園芸品種の大部分は、日本の百合を使って作られていますが、百合の品種改良について、日本は海外に大きく後れを取っていて、ほとんどが外国で行われてるそうです。ちょっと口惜しい気がしますねぇ。
●テッポウユリの特徴 ⇒ 高さ50~100センチの多年草で、茎は直立、葉は柄がなく、長さ10~15センチ、幅1~1,5センチの表面に光沢がある披針形の葉は互生します。花は、6月~7月、白色で花筒が長く花被片の先端が反り返る花を咲かせます。6本の雄しべは黄色で、花被より短く雌しべの先端の柱頭は丸く3裂しています。花後、果実は5~6cmの長楕円形筒状の蒴果を結びます。
利用⇒食用に。10~11月頃、地下の鱗茎を掘り採り、水洗いg後、熱湯をかけて殻天日で乾燥させた物を、生薬では百合(ひゃくごう)と呼びます。鱗茎は苦味が強いのですが、昔から食用としていました。
薬効 ⇒ 打撲に(沖縄地方の民間療法)生の鱗茎を砕いて潰し、食酢を加えてつき砕いてから木綿の袋に入れて、其れを患部に湿布するように当てます。
■タカサゴユリ Lilium formosanu

台湾原産のユリで、帰化植物です。鑑賞用として大正時代に導入され、現在では各地で野生化しています。テッポウユリに似ていますが、茎は太めで丈も高くなります。テッポウユリより大型になり、葉が細く、花被の外面には赤紫色の線が入っているのが特徴です。自然状態で、種子から2,3年で開花します。初年度は茎や花を出さずに数枚の葉を出すだけで球根を太らせ、球根が充分太ると翌年度以降に茎を伸ばして大型の花をいくつも咲かせます。その場所の日当たり具合により球根の太り方に差があり、球根の状態により茎丈や花の数などに差が生じます。芳香があり、高さは60cm程です。変種は3種類あるそうで、花の大きさ、葉の長さ、葉の中脈の有無などに違いがあるようです。
■シンテッポウユリ Lilium formosanum x Lilium longiflorum

シンテッポウユリは、1951年に日本でつくられた園芸品種です。自然交雑もおきやすいようで、交雑を繰り返し、花被片は外面が紫赤色を帯びない純白色のものが多く、今ではテッポウユリと見分けがつかなくなっています。蒴果や種子もタカサゴユリとよく似ています。種子繁殖力が強く、播種後8~10ヶ月で開花し、増殖します。
花卉を扱う市場の方のコメントにシンテッポウユリの香りについて、「蕾の開きと上向き性に優れ、さらには香りの良さも魅力の一つで、他品種に比べ柑橘系(ミカンの皮)の香りが強めです。最も香りが強まる深夜には、スイセンに似た深い香りに柑橘系の爽やかな香りが混ざります。オリエンタル百合のような独特のクセがない為、仏花としてではなく芳香花として玄関先で楽しむこともできます。」とあります。
そのうち、シンテッポウユリがユリ界を席巻するかもしれませんね。
注)百合根として食用になるのは、ヤマユリ、オニユリ、コオニユリ、カノコユリです

















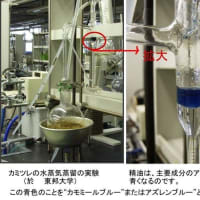

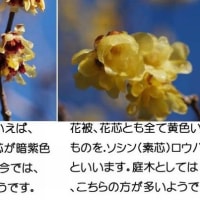
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます