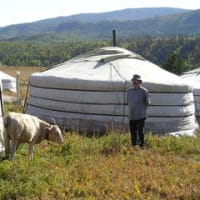軍事訓練?
■モンゴル帝国の騎馬兵は、その驚異的な機動力と強力な弓の攻撃力で怖れられました。キャンプ地内を歩き回っていると、子牛一頭分ぐらいの皮が張られているのを見つけまして、どう見ても弓の的(まと)であろうと思ってガイドさんに尋ねると、やはりモンゴル弓で遊べる施設でした。しかし、商売っ気に乏しい人達はこれを積極的に売り込むつもりはぜんぜん無く、管理人一家が暮らしているゲルから持ち出されたのは羽がすっかり寂しくなった3本の矢と、練習用の蒙古弓でした。
■蒙古弓の特徴はそのコンパクトさにあります。大きく湾曲した短い弓は木製ですが、その内側に薄く削った骨を膠(にかわ)で貼り付けてあるので、見た目と違って大変な威力を秘めているのです。この強力なバネとなる骨は、不思議なことに弓の弦を引き絞る時にはあまり苦になりません。素人が力任せにグイッと引けば簡単に格好が付きます。弦は毛皮を紐状に捩(ね)じり合わせた物で日本の弓よりも太いようです。さて、的に向かって蒙古の騎馬兵を気取って射撃体勢に入ると、すかさず管理人さんが止めに掛かりました。日本の弓道のように姿勢や呼吸など細かい注意が与えられるかと思ったら、ガイドさんの通訳によりますと「矢が逆です」という話でした。つまり、左手で握った弓の向かって右側に矢を番(つが)えた日本人を見たモンゴル人が驚いたというわけです。
■矢を持つのは右手ですから、右側に矢を番える方が動作は楽です。しかし、蒙古兵は腰の箙(えびら)から右手で引き抜いた矢を、弓の左側に番えて身構えるのです。何本かモンゴル映画を観たり、ナーダムの祭りを報道するニュースの映像を観たりすると、時々、「矢が逆」に番えられているような気がしたものでしたが、多くの部族や民族を統合して構成されていたチンギス汗帝国でしたから、日本の弓道のように決まった型などは無いのかなあ、などとぼんやりと考えていたのですが、モンゴルの弓は、「矢は左」と決まっていると知ったのは、ちょっとした旅の収穫でした。でも、真似事で日本の弓を引いた経験が有ると、どうも照準を合わせるのに違和感が有ります。弦を右に寄せて張ってあるというわけでもなさそうなので、左側に矢を番えて狙いを付けると、どうも矢が左方向に流れて行きそうで不安になります。
■もたもたしていると、管理人さんが見本を見せてくれたのですが、彼の動きで「矢は左」の謎が氷解したような思いがしました。彼は弓を持ち上げずに腰の位置に有る時に矢を弓の左側に宛がったのです。つまり、弓を握っている左手が下がっている状態で、弓に矢を「載せ」てから直ぐに弦に番えますから、その時の矢はまだ地面を向いていることになります。弦を引き上げるようにしながら引き絞り、放つ位置まですいっと弓を持ち上げて見当が付いた所で矢が放たれました。日本の弓道では、射手は不動の姿勢を取ったままで弓と矢を左右の腰の位置に定め、矢は番える時から放たれるまで、ほぼ水平に保たれているので、その所作と姿が美しいわけですが、それに比べて蒙古の弓は気ままに扱われているような印象を受けます。
■こちらも和風を捨てて蒙古風に矢を番えて引いてみましたが、どうも姿勢が決まりません。それを見ていた管理人さんは、何と笑いながら弓自体を水平に構えて放って見せました!弓と矢の位置関係は弩(いしゆみ)=ボー・ガンとまったく同じです。西欧では機械仕掛けの強力な各種の弩が開発されましたが、持ち運びに不便な大型の弩は蒙古兵の気に入らなかったようで、騎馬兵は常に湾曲した剣と軽快な弓を愛用していました。日本に「騎馬民族」が到来したかどうかの議論が盛んに行われた時に、日本では一度も大きく湾曲した剣が作られていない事から、騎馬民族は来なかったという論拠とされたようです。疾走する馬に乗ったままで敵を切り殺すには限りなく円に近い曲線を持つ剣が必要なのだそうです。アラブの騎馬兵もモンゴルと同様に三日月のような剣を愛用していました。僅かに湾曲した日本刀では、敵の体に食い込んで騎馬武者自身が落馬してしまう危険が大きいとも言われます。
■最近日本史の或る研究者が、戦国時代から江戸時代初期までの「戦死者」の死因を調査した結果、最も殺傷力が高かったのは「槍」で、次が「弓矢」、刀で殺された者は驚くほど少ないのだそうです。日本の騎馬武者には「槍持ち」と呼ばれる個人的な補給役が付き従っていたそうですから、どうやら、馬で戦場に移動して敵を発見したら止まった馬上から矢を射掛け、矢が尽きたら槍を受け取って突進して突き殺して歩いたもののようです。武田信玄が鍛え上げた日本最強の騎馬軍団も、槍を構えて長篠の合戦場でも突進を繰り返して火縄銃の餌食になったもののようですが、蒙古騎馬軍団であったらどうでしょう?直線的に敵陣に向かって突進などせずに、車がかりの戦法を採って火縄銃の照準を惑わしながら矢の雨を降らせて鉄砲隊を無力化しておいて、湾曲した剣を振りかざして織田軍に雪崩れ込んだかも知れません。
■敵陣から飛んで来る矢を避けるには、馬上で身をかがめてやり過ごす必要が有りますから、日本風の長い弓では射撃姿勢が採り難いと思われます。敵の矢をかい潜(くぐ)りながら矢で反撃するには、必然的に弓を横に構えて矢を放たねばなりません。しかも疾走する馬の上からの攻撃となれば、弓に番えた矢が落下する危険が有りますから、弓の上、つまり左側に矢を載せて放つ方が理屈に合っているのではないでしょうか?弓が立っていようが寝ていようが、確実に敵陣に向かって数多くの矢を射掛ければ良い、織田信長の鉄砲戦術に通じる考え方です。その伝統が今のナーダムの祭りにも引き継がれているらしく、男性は75メートル、女性は65メートル先に置かれた標的に「当たれば良い」というわけで、姿勢も型も自由のようです。ナーダムと言えば、「相撲・騎馬・弓」が男の三種競技というのも象徴的です。剣道に類する競技は見当たらず、西欧で発達した馬の槍大会も無い!つまり、ひたすら馬で移動して敵に遭遇したら遠距離から弓で矢を射掛け、その後は剣を振り回すか敵兵と組み合って倒すだけだったのでしょう。
■遊び半分でモンゴルの弓を引いた経験から、日本の大相撲でモンゴル力士が実戦的な動きをして出世している理由がちょっと分かったようなきがしたのでした。