四国(お遍路)の旅は今回で三度目になります。
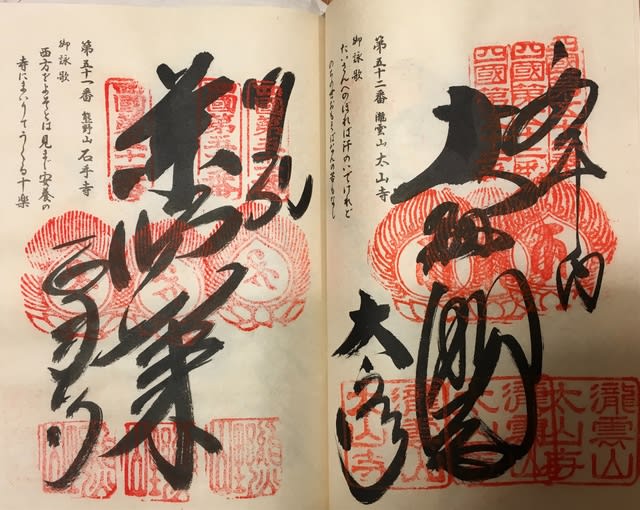
一番最初は旅行会社の4月から12月まで10回に分けてのバスツアーを通して、先達ガイドからお遍路の基本的なことを学びました。

二回目は昨年5月、キャンプ小屋を軽トラに乗せての試運転の旅で、新緑の風景も楽しみました。
今回は塩飽諸島(本島)と金刀比羅宮参りを中心に秋の紅葉を楽しむ旅でした。

塩飽と青森との間に大きな結びつきがあることもわかり、青森への旅が心待ちにになりました。
塩飽諸島(本島)を訪問して見聞したことを少し列挙してみます。
・小中学校児童生徒数は現在17名で来年度から小中一貫校になる
・塩飽水軍、船大工、宮大工で全国に知られた塩飽衆も現在その片鱗は皆無に近い
・塩飽の歴史を知る年齢層も70代になり、若い人への伝承が大きな課題となっている
島内に飾られているブイキャラは小中学校の手による作品だそうです。




島の持続といった特殊性もあって小中一貫校も延々と進まなかったが、次年度から実施の至りになったそうです。
ここから廃校の道へまっしぐらと進まないでほしいです。
宮大工専門学校まであった島内に今では工務店は一軒もなく、四国本土から大工さんがわざわざ家の修理にやってくるそうです。
島に戻ってくる人は皆無に近く、放置された空き家の数は年々増加し、小さな集落が一つずつ消滅しているのが実状だそうです。
塩飽水軍、廻船関係の歴史文化も風化・消滅してしまうことが懸念され、伝承のあり方が模索されます。
瀬戸大橋の袂にある塩飽諸島(本島)の10年後20年後がどうなっているのか、南紀の旅と同様、ゆくすえが気になります。
次回のお遍路がいつになるかわかりませんが、また必ず訪れたいです。











































