
ほんとに今年の夏は暑いですね。この週末の土日、神戸にスカイマーク球場では、今年唯一のマリーンズとバッファローズとの二連戦がありました。例年なら観戦に行くのですが、ことしは、7連敗のあとのバッファローズ戦。しかも、先発も吉見と新外国人のペン。まったく計算が立たない二人ですので、今年はやめておこう!と決心しました。おうちのテレビ(スカパー!です)で観戦しておりました。すると案の定、二人の投手の好投もあって、連勝!。行かなかったらこんなもんですねえ。まあ、しょうがありまへん。とほほ。
ということで、お盆の直前。今日から4泊5日で単身で岡山に行きます。向こうでは掃除などがまっており、憂欝であります。まあ年に一度の行事ですのでしかたありませんが…。
さて、今回は一ヶ月振りのモーツァルト。ピアノ協奏曲であります。少し前にBOOKOFFで見つけた中古CDでありますが、ゲザ・アンダ(ピアノと指揮)、ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカによる演奏で、21番と23番でした。いやー、この人は懐かしいですねえ。レコードのころによく廉価盤などでよく見ました。今はもうめっきり名前を聞かなくなりましたね。1976年に50代半ばで逝去されたのは、惜しい限りでありますねえ。アンダは、1960年代にモーツァルトのピアノ協奏曲全集を録音しています。アンダの最良の遺産でしょうが、その中から1961年5月の録音で、ピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467。この演奏は、1967年のスウェーデン映画の『みじかくも美しく燃え(Elvira Madigan)』でその第2楽章が用いられたことでも、一躍有名になりましたね。といっても、この映画は見たことはないのですが…。
モーツァルトのピアノ協奏曲には、周知のとおりいろんな演奏があります。この21番においても、グルダ(アバド)、カサドシュ(セル)、バレンボイム(BPO)などの演奏が、これまでいいなって思ったものとして、パッと思いつきます。これに対しても、アンダの演奏は、決して引けを取らないものですよ。まず、ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカのたいへんみずみずしい演奏がいいです。小編成のオケなんでしょうが、弦がさわやかで情感たっぷりの演奏を聴かせてくれます。そして、木管も実に味わい深いですね。そして、アンダが指揮をしているのですが、アンダの意図に対して、オケがしっかり応えています。このあたりの統一感もいいです。このオケは、1980年代にシャーンドル・ヴェーグの指揮でモーツァルトの優れた演奏を聴かせてくれるのですが、この時期もなかなか派手さはないにしても、しっかりとしたオケであります。決してオケが出しゃばらず、ピアノの引き立てる役割に徹しています。第1楽章の冒頭から、ピアノが登場するまでの期待感や愉悦感あふれるオケの表情はいいです。第2楽章での弦の主題も清新で、さわやかです。そして、アンダのピアノなんですが、これも着実な演奏です。それほど力の入った演奏のようには思わないのですが、芯の一本通った力強さや自信があります。そして、モーツァルトはこう演奏するんだ、という自負を感じますねえ。まさに自家薬籠中のもののようにモーツァルトを弾いているのです。全体的には、第1楽章は、あふれるような明るさと期待に胸があふれるようなピアノが満開です。そして、第2楽章では、憂いに満ちたところはあるにしても、絶望的な暗さとはほど遠い感情の吐露が聴かれますし、この楽章の美しさは比類なきものです。そして、第3楽章では、この憂いを克服するような明るさ一杯のピアノの独壇場になっています。実に、モーツァルトのピアノ協奏曲のお手本のような印象を強く感じる演奏であります。
このアンダの全集は、DGから5000円と少しで購入できます。他の曲も聴いてみたい気持ちで一杯になりました。今日は岡山に行きます。お盆であります。
(DG UCCG-5069 The Best 1000 2006年)
ということで、お盆の直前。今日から4泊5日で単身で岡山に行きます。向こうでは掃除などがまっており、憂欝であります。まあ年に一度の行事ですのでしかたありませんが…。
さて、今回は一ヶ月振りのモーツァルト。ピアノ協奏曲であります。少し前にBOOKOFFで見つけた中古CDでありますが、ゲザ・アンダ(ピアノと指揮)、ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカによる演奏で、21番と23番でした。いやー、この人は懐かしいですねえ。レコードのころによく廉価盤などでよく見ました。今はもうめっきり名前を聞かなくなりましたね。1976年に50代半ばで逝去されたのは、惜しい限りでありますねえ。アンダは、1960年代にモーツァルトのピアノ協奏曲全集を録音しています。アンダの最良の遺産でしょうが、その中から1961年5月の録音で、ピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467。この演奏は、1967年のスウェーデン映画の『みじかくも美しく燃え(Elvira Madigan)』でその第2楽章が用いられたことでも、一躍有名になりましたね。といっても、この映画は見たことはないのですが…。
モーツァルトのピアノ協奏曲には、周知のとおりいろんな演奏があります。この21番においても、グルダ(アバド)、カサドシュ(セル)、バレンボイム(BPO)などの演奏が、これまでいいなって思ったものとして、パッと思いつきます。これに対しても、アンダの演奏は、決して引けを取らないものですよ。まず、ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカのたいへんみずみずしい演奏がいいです。小編成のオケなんでしょうが、弦がさわやかで情感たっぷりの演奏を聴かせてくれます。そして、木管も実に味わい深いですね。そして、アンダが指揮をしているのですが、アンダの意図に対して、オケがしっかり応えています。このあたりの統一感もいいです。このオケは、1980年代にシャーンドル・ヴェーグの指揮でモーツァルトの優れた演奏を聴かせてくれるのですが、この時期もなかなか派手さはないにしても、しっかりとしたオケであります。決してオケが出しゃばらず、ピアノの引き立てる役割に徹しています。第1楽章の冒頭から、ピアノが登場するまでの期待感や愉悦感あふれるオケの表情はいいです。第2楽章での弦の主題も清新で、さわやかです。そして、アンダのピアノなんですが、これも着実な演奏です。それほど力の入った演奏のようには思わないのですが、芯の一本通った力強さや自信があります。そして、モーツァルトはこう演奏するんだ、という自負を感じますねえ。まさに自家薬籠中のもののようにモーツァルトを弾いているのです。全体的には、第1楽章は、あふれるような明るさと期待に胸があふれるようなピアノが満開です。そして、第2楽章では、憂いに満ちたところはあるにしても、絶望的な暗さとはほど遠い感情の吐露が聴かれますし、この楽章の美しさは比類なきものです。そして、第3楽章では、この憂いを克服するような明るさ一杯のピアノの独壇場になっています。実に、モーツァルトのピアノ協奏曲のお手本のような印象を強く感じる演奏であります。
このアンダの全集は、DGから5000円と少しで購入できます。他の曲も聴いてみたい気持ちで一杯になりました。今日は岡山に行きます。お盆であります。
(DG UCCG-5069 The Best 1000 2006年)












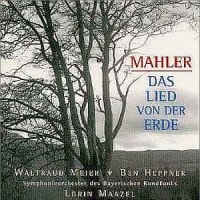
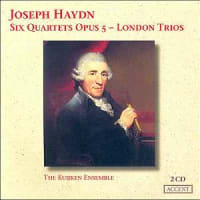
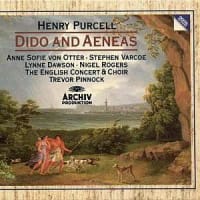










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます