
6月ですねえ。先週は大阪天王寺の大阪市立美術館での『日本国宝展』です。これでやっと京都・奈良・大阪の万博絡みの特別展を見終わりました。平日に行きましたが、入場に40分くらいの待ち。会場もかなり混雑してました。その中に国宝名品が目白押し。ここが、モノの見応えという点では、一番だったと思いますねえ。神護寺の伝頼朝像などの似絵が最も目を引きました。薬師寺聖観音像も光背なしで、後ろ姿もバッチリ見えました。光琳燕子花図屏風の青もキレイでした。
ということで、国宝展に加えて、先週末には神戸文化ホールでの神戸市室内管弦楽団第168回定期演奏会『トルコ趣味はいかが?』に行ってきました。指揮は音楽監督の鈴木秀美さん。演目は、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番イ長調KV219「トルコ風」、ハイドンの交響曲第100番ト長調「軍隊」、ベートーヴェン交響曲第2番ニ長調作品36。曲目が魅力的ですよねえ。ハイドンとベートーヴェンは、その昔、中学生のころから大好きだった曲です。
まず、曲順ですが、私的にはハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンが順当だろうと思ってました。協奏曲は二曲目が多い、からですね。今回はヴァイオリン協奏曲が最初。少し戸惑ったんですが、これは時代順に並べて、その変化を追う狙いがあったのか。モーツァルトは1775年、ハイドンは1794年、ベートーヴェンは1802年のそれぞれ作曲ですからねえ。実際にそれを意識して聴くと、ハイドンの多様性、ベートーヴェンの革新性がとてもよくわかりました。それを鈴木さん、できる範囲で当時の演奏法も意識しながら、ということか、と勝手に思いました。
ヴァイオリン独奏は、オランダのロザンネ・フィリッペンス。モーツァルトを全身を使った体当たり的な躍動感いっぱいの演奏で、気持ちがつたわってくる。テンポも少し速めで、一気に駆け抜けるようでしたね。鈴木さんは、非常に控え目で、ヴァイオリンを引き立てることに終始。最初の方では、フィリッペンスさんの速さについて行けないようなところも…。とは言え、フィリッペンスさんの、躍動感に満ちた情熱的なモーツァルトは、とても新鮮でした。そして、アンコールでは、バッハの無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番のジーク。一転して非常に穏やかなバッハ。モーツァルトの第2楽章でも聴かせてくれた繊細な表情がここでも聴けて、とてもよかったです。しかし、こんなときに奏でられるバッハは感動的に聴けますねえ。
そして休憩か、と思いきや、オケを増員し鈴木さん、ハイドン、ベートーヴェンを渾身的に演奏。まずハイドン。ハイドンの交響曲はたくさんあって十把一絡げ的と思ってしまいますが、いやいやいろんな工夫や革新性もあり、一曲一曲の個性を楽しめるのであります。この軍隊もいろいろと仕掛けもあって面白い。そして、そんなハイドンの面白さや斬新さがよく伝わって来ました。特に、大太鼓やシンバル、トライアングルを駆使し、古楽器の明るく迫力満点の演奏には、驚きとともに耳を奪われ、興奮すらしました。大太鼓は出番の直前までは白布で隠していたのにも笑いました。古典派のよさに加えて、ハイドンの斬新性、多様性を感じさせてくれた演奏でした。
最後はベートーヴェン。先のハイドンの比べると、遥に斬新な新しい音楽。古楽器の音色は、鋭く時代を切り拓こうとする意欲と勢いを存分に表現することが出来る演奏でしたね。私は、この一般に人気の少ないが、こんな2番は大好き。最近、落ち着いた雰囲気の演奏ばかりを耳にしていた。その点では、強烈なパワーとエネルギーを実感しましたねえ。打楽器の強打に、金管が煌びやかな咆哮、ドライブの効いた弦楽器のストレートな響きの中で展開されるベートーヴェンの新機軸。オケの繊細な表情や表現力はさておき、それはモーツァルトやハイドンにはない音楽、そして新しく躍動(この言葉はあまり使いたくないのですが…)する音楽にこころを踊らされました。
神戸市室内管弦楽団の演奏は、昨年の年末のハイドン『天地創造』に続いてでした。2000円でとても満足。11月には、ベートーヴェンの『ミサ・ソレムニス』。これも聴きたいなと思ったのでありました。
ということで、国宝展に加えて、先週末には神戸文化ホールでの神戸市室内管弦楽団第168回定期演奏会『トルコ趣味はいかが?』に行ってきました。指揮は音楽監督の鈴木秀美さん。演目は、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番イ長調KV219「トルコ風」、ハイドンの交響曲第100番ト長調「軍隊」、ベートーヴェン交響曲第2番ニ長調作品36。曲目が魅力的ですよねえ。ハイドンとベートーヴェンは、その昔、中学生のころから大好きだった曲です。
まず、曲順ですが、私的にはハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンが順当だろうと思ってました。協奏曲は二曲目が多い、からですね。今回はヴァイオリン協奏曲が最初。少し戸惑ったんですが、これは時代順に並べて、その変化を追う狙いがあったのか。モーツァルトは1775年、ハイドンは1794年、ベートーヴェンは1802年のそれぞれ作曲ですからねえ。実際にそれを意識して聴くと、ハイドンの多様性、ベートーヴェンの革新性がとてもよくわかりました。それを鈴木さん、できる範囲で当時の演奏法も意識しながら、ということか、と勝手に思いました。
ヴァイオリン独奏は、オランダのロザンネ・フィリッペンス。モーツァルトを全身を使った体当たり的な躍動感いっぱいの演奏で、気持ちがつたわってくる。テンポも少し速めで、一気に駆け抜けるようでしたね。鈴木さんは、非常に控え目で、ヴァイオリンを引き立てることに終始。最初の方では、フィリッペンスさんの速さについて行けないようなところも…。とは言え、フィリッペンスさんの、躍動感に満ちた情熱的なモーツァルトは、とても新鮮でした。そして、アンコールでは、バッハの無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番のジーク。一転して非常に穏やかなバッハ。モーツァルトの第2楽章でも聴かせてくれた繊細な表情がここでも聴けて、とてもよかったです。しかし、こんなときに奏でられるバッハは感動的に聴けますねえ。
そして休憩か、と思いきや、オケを増員し鈴木さん、ハイドン、ベートーヴェンを渾身的に演奏。まずハイドン。ハイドンの交響曲はたくさんあって十把一絡げ的と思ってしまいますが、いやいやいろんな工夫や革新性もあり、一曲一曲の個性を楽しめるのであります。この軍隊もいろいろと仕掛けもあって面白い。そして、そんなハイドンの面白さや斬新さがよく伝わって来ました。特に、大太鼓やシンバル、トライアングルを駆使し、古楽器の明るく迫力満点の演奏には、驚きとともに耳を奪われ、興奮すらしました。大太鼓は出番の直前までは白布で隠していたのにも笑いました。古典派のよさに加えて、ハイドンの斬新性、多様性を感じさせてくれた演奏でした。
最後はベートーヴェン。先のハイドンの比べると、遥に斬新な新しい音楽。古楽器の音色は、鋭く時代を切り拓こうとする意欲と勢いを存分に表現することが出来る演奏でしたね。私は、この一般に人気の少ないが、こんな2番は大好き。最近、落ち着いた雰囲気の演奏ばかりを耳にしていた。その点では、強烈なパワーとエネルギーを実感しましたねえ。打楽器の強打に、金管が煌びやかな咆哮、ドライブの効いた弦楽器のストレートな響きの中で展開されるベートーヴェンの新機軸。オケの繊細な表情や表現力はさておき、それはモーツァルトやハイドンにはない音楽、そして新しく躍動(この言葉はあまり使いたくないのですが…)する音楽にこころを踊らされました。
神戸市室内管弦楽団の演奏は、昨年の年末のハイドン『天地創造』に続いてでした。2000円でとても満足。11月には、ベートーヴェンの『ミサ・ソレムニス』。これも聴きたいなと思ったのでありました。















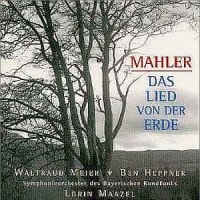
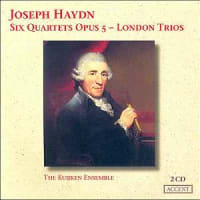
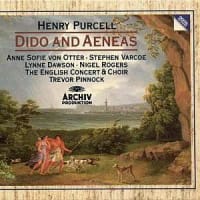







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます