
最近、東野圭吾さんの本といくつか読みました。BOOKOFFさんでは、一冊100円ではあまりないのですが、一軒、たくさん100円で売っているお店がありまて、何冊か買いました。『手紙』『秘密』『悪意』『赤い指』『同級生』などなどです。多少どうなんや、と思うこともあるのですが、よくよく考えてみれば、うーんそうなんか、ということもけっこうあって、おもしろく読んでいます。『秘密』での娘を亡くした母や、『赤い指』の老母は胸をうちました。『悪意』が一番スリリングでしたかねえ。
ということで、三回続けてのモーツァルトであります。今回は、セレナード第9番ニ長調K.320『ポストホルン』です。1779年8月3日にザルツブルクで完成したこの曲は、第6楽章の第2トリオでポストホルンが使用されていることからこの名があります。当時、ザルツブルクの大司教との関係が悪くなっていたモーツァルトが、ポストホルンを用いてザルツブルクを去りたい気持ちを表したと言われています。しかし一方で、フィナールムジーク、ザルツブルク大学の夏学期の終了という公的な祝典のために作曲され、ポストホルンは修了して郵便馬車で旅立つ学生のシンボル化とするという考えもありますねえ。前者の方がおもしろいですが…。
それで、この演奏ですが、バリリ弦楽四重奏団とVPO木管G。1954年6月の録音です。これはその昔、心斎橋の中古レコードやさんで買ったLPでよく聴いていたものです。先頃買ったウエスミンスターの室内楽のBOXには入っていなかったので、なんでや、と思っていました。というのも、このセレナーデを室内楽的なメンバーで演奏したのと、この顔ぶれの演奏で、かなりのお気に入りだったのです。この曲が管弦楽曲であることもあり、BOXにはなかったのでしょうね。そして、先日このCDを元町の中古やさんで見つけて、迷わず購入しました。
バリリとVPO木管Gといえば、まさに当時のVPOのミニチュア版。正確には、バリリの4人にオットー・リュームのコントラバス、木管Gの8人、そしてトランペット2人とティンパニが加わり、合計16名による演奏であります。まず、この少人数での演奏であることから、響きに透明感と引き締まったところは、なかなか他では聴けません。これに慣れると管弦楽による通常の演奏が重く、もたれるようにも感じてしまうから不思議です。そして、当時のVPOのウィーン情緒あふる音色は、ほんとに他に代え難い魅力があります。ゆったりとして甘美な響きは、他では聴けないものであります。
バリリのヴァイオリンはどの楽章でも聴け、その甘美な響きと情感たっぷりの独奏は、この演奏の最大の魅力でしょう。特に、唯一の短調である第5楽章アンダンティーノでのバリリは、他では聴けない悲しみと輝きに満ちていますねえ。他にも随所随所でのヴァイオリンに、耳が奪われます。そして、第3・4楽章のフルート、オーボエ、ファゴットの協奏曲的な楽章でも、VPOの木管の渋さがたっぷり聴けます。
しかし、そういった室内楽的な魅力だけではなく、全体的にも、低音のしっかりとした極めて安定した、またこれだけの人数とは思えないような充実した響きを聴くことができますね。第7楽章フィナーレは堂々とした質感と量感に満ちた立派な演奏になっています。甘美で情感的な弦の響きと、渋いだけではなく、引き締まって安定感たっぷりの木管とによるハーモニーが、この曲の最大の良さを形作っています。私はこの曲のベストと思っています。
とはいうのものの、このポストホルンには、ベーム盤やヴァント盤なども、極めて充実した演奏を聴かせてくれます。うーん、いろんな素晴らしい演奏で聴けることも幸せであります。
(Westminster MVCW-19015 1996年)
ということで、三回続けてのモーツァルトであります。今回は、セレナード第9番ニ長調K.320『ポストホルン』です。1779年8月3日にザルツブルクで完成したこの曲は、第6楽章の第2トリオでポストホルンが使用されていることからこの名があります。当時、ザルツブルクの大司教との関係が悪くなっていたモーツァルトが、ポストホルンを用いてザルツブルクを去りたい気持ちを表したと言われています。しかし一方で、フィナールムジーク、ザルツブルク大学の夏学期の終了という公的な祝典のために作曲され、ポストホルンは修了して郵便馬車で旅立つ学生のシンボル化とするという考えもありますねえ。前者の方がおもしろいですが…。
それで、この演奏ですが、バリリ弦楽四重奏団とVPO木管G。1954年6月の録音です。これはその昔、心斎橋の中古レコードやさんで買ったLPでよく聴いていたものです。先頃買ったウエスミンスターの室内楽のBOXには入っていなかったので、なんでや、と思っていました。というのも、このセレナーデを室内楽的なメンバーで演奏したのと、この顔ぶれの演奏で、かなりのお気に入りだったのです。この曲が管弦楽曲であることもあり、BOXにはなかったのでしょうね。そして、先日このCDを元町の中古やさんで見つけて、迷わず購入しました。
バリリとVPO木管Gといえば、まさに当時のVPOのミニチュア版。正確には、バリリの4人にオットー・リュームのコントラバス、木管Gの8人、そしてトランペット2人とティンパニが加わり、合計16名による演奏であります。まず、この少人数での演奏であることから、響きに透明感と引き締まったところは、なかなか他では聴けません。これに慣れると管弦楽による通常の演奏が重く、もたれるようにも感じてしまうから不思議です。そして、当時のVPOのウィーン情緒あふる音色は、ほんとに他に代え難い魅力があります。ゆったりとして甘美な響きは、他では聴けないものであります。
バリリのヴァイオリンはどの楽章でも聴け、その甘美な響きと情感たっぷりの独奏は、この演奏の最大の魅力でしょう。特に、唯一の短調である第5楽章アンダンティーノでのバリリは、他では聴けない悲しみと輝きに満ちていますねえ。他にも随所随所でのヴァイオリンに、耳が奪われます。そして、第3・4楽章のフルート、オーボエ、ファゴットの協奏曲的な楽章でも、VPOの木管の渋さがたっぷり聴けます。
しかし、そういった室内楽的な魅力だけではなく、全体的にも、低音のしっかりとした極めて安定した、またこれだけの人数とは思えないような充実した響きを聴くことができますね。第7楽章フィナーレは堂々とした質感と量感に満ちた立派な演奏になっています。甘美で情感的な弦の響きと、渋いだけではなく、引き締まって安定感たっぷりの木管とによるハーモニーが、この曲の最大の良さを形作っています。私はこの曲のベストと思っています。
とはいうのものの、このポストホルンには、ベーム盤やヴァント盤なども、極めて充実した演奏を聴かせてくれます。うーん、いろんな素晴らしい演奏で聴けることも幸せであります。
(Westminster MVCW-19015 1996年)













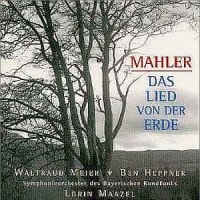
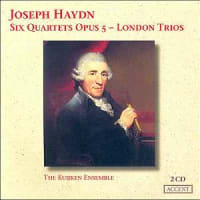
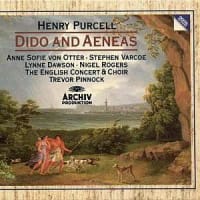









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます