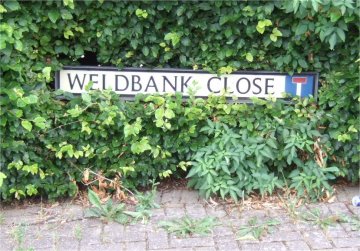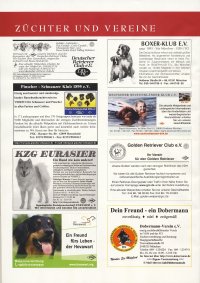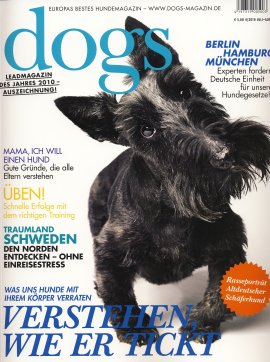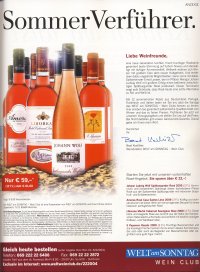前回の投稿から4ヶ月余りが経過してしまいました。
その間に話題が無かった訳ではなく、また前回の「ピアチェーレ」完成の前にもアメリカのモンゴメリー・ドッグショーを観戦に行ったり掲載すべき話題は沢山あったのですが、なにしろ最近仕事が忙しくなってしまって・・・・
それと最近はFACEBOOKに投稿(浮気)するのに忙しかったのもここのご無沙汰の原因の一つです。
そこで今回はこれまでの分を一気に紹介しますが、さすがに昨年まで遡るのは大変なので今年に入ってからの分とします。
まずは正月休み明け早々にハワイに出張しました。1月5日出発で、世の中はまだ正月気分が抜けないうちにリゾートでの仕事です。

ホノルル空港からホテルに向かうハイウェイから見えた米国太平洋艦隊総司令部の建物(丘の中腹に見えるピンク色の建物)

モンキーポットの林の向こうに見える白いドームは、米軍のXバンドレーダー。元々はアラスカに設置されていたのだけれど、北朝鮮のテポドン発射の後、ここに移されて北朝鮮のミサイル発射を監視しています。今回の出張は軍関係だったので、実際はこのレーダーのすぐ近くまで行ったのですが、その辺りは写真撮影禁止区域になっていたので、この様な遠景しか撮れませんでした。

ホテル前のビーチの日没。こんな場所で仕事をしているのが恨めしい。
往路のフライトでは、野球の松坂大輔選手、サッカーのゴン中山選手などと乗り合わせ、夕食に行ったレストランにはサッカーの小野伸二選手一家が来ていました。正月休みの終盤で一般の観光客が帰り始め、入れ替わりに有名人が休みを過ごしに来始めていた時期なのでしょうか。
さて、
1月の後半は中国出張です。
始めに上海で日中政府のある部局同士の定例会合に民間が初めて同行して行なわれたセミナーに参加。

正面の赤い服の女性は日本の国土交通省に相当する「住宅・都市農村建設部」の副局長さん。

中国各地で盛んな「エコシティ」開発の状況の紹介を聞きました。


上海から天津に移動して、有名な「天津エコシティ」を訪問。かつてのドバイの様に建設クレーンが林立しています。

天津市人民政府の偉い方との懇談。正面に日本政府の代表と並んで座る政府高官。我々民間人は手前に「コ」の字型に並んでいます。

天津での仕事を終えて北京天津新幹線(京津高速鉄道)で北京南駅に向かいました。

車内はこんな感じです。

時速350キロで走るという触れ込みでしたが、実際に達した最高速度は327キロでした。天津から北京までは20分余りという距離なので高速で走れる区間もあまりありません。
2月にはマレーシアのクアラルンプールに出張しました。

クアラルンプールのシンボルのツインタワーです。

朝食はホテルから歩いてこの様なお店で「肉骨茶」(バクテー)を食べました。

豚肉などを「お茶」で煮込んだシチューをご飯にぶっかけて食べます。美味、美味。健康にも良さそう!

クアラルンプールの南に建設された新首都プトラジャヤ。人造湖を配してそれぞれ特徴のある中央官庁の建物が建ち並んでいます。この写真の大通りの突き当たりに見えるモスクの様な建物が首相官邸です。

クアラルンプールの交通のハブの"KL Sentral"駅。空港からの鉄道や市内を走る地下鉄、モノレールなどが集まっています。

日本人の旅行者も多いのでしょう。案内板には日本語も書かれています。

現地ではこれを「LRT」と呼んでいます。LRTはLight Rail Transitで、日本では通常路面電車の様な軽便な鉄道を指します。この電車は高架だったり地下だったりするので地下鉄は言い難いですが、いわゆるメトロで、LRTとはイメージが違うなぁと思いつつ利用しました。

車内はこんな感じです。
さて、3月3日にかねてアメリカの友人ハンドラーにお願いして買ってもらい、アメリカでチャンピオンを取った
「龍馬」がいよいよ我が家にやって来ました。
という訳で龍馬の写真をいくつか。(
既にFACEBOOKでご覧になった写真もありますが・・)

山梨のセカンドハウスでの1枚。向かって右端が龍馬です。

同じく山梨のセカンドハウス。右手前の床の上にいるのが龍馬。

こんな顔をしています。

そして東京の家の門の前で。

龍馬(向かって右)とピアチェーレ(同左)は本当に仲良しで、よく口の辺りをなめ合ったりして、いつもくっついています。

手前:ピエタ。奥右:龍馬。奥左:ピアチェーレです。
さて、
最も最近の話題は先週のスイス、モントルーへの出張です。

成田を飛び立ってフランクフルトに向かう機中から。中禅寺湖と男体山(手前)。

フランクフルトで乗り継いてジュネーヴに向かう機中から。スイス・アルプスを遥かに望む。

モントルーはジャズフェスティバルで有名な、レマン湖畔のリゾート地です。「レマン湖」は対岸のフランスの地名に由来しているので、スイスの人たちは「ジュネーヴ湖」と呼んでいます。
この写真はホテルの部屋から、夜明けで徐々に明るくなってくる湖と街の情景です。

ホテルを出て湖畔のプロムナードから同じ方向を望んでいます。

出張目的の国際会議の会場で。会議が開かれた施設は"Montreux Music and Convention Center"と呼ばれ、略称は「2M2C」と書かれていました。施設内の各ホールには"Miles Davis Hall"と名前が付けられていて、さすがにジャズフェスティバルの街です。

スイスでの夕食と言えば「フォンデュー」。手前の鍋がビーフを油に漬けて食べるもの、左奥の鍋がチーズフォンデューの鍋。

会議が終わって帰国便に乗る日の午前中は時間があったので、登山電車に乗って標高2042メートルのRochers-de-Nayeに行ってみました(モントルーの標高は意外と低くて370メートル)。

Rochers-de-Nayeからの眺望。眼下にジュネーヴ湖を望みます。

上の写真と反対側の眺望。遥かにアルプスの山並みが続きます。

登山電車はすごい急勾配をアプト式で登って行きます。この窓の傾きを見て戴けるとどんなに急な坂を登っているかお判り戴けるでしょう。

登山電車から見えた「シオン城」です。
さてさて、
お待ちかねのモントルーのワンコ事情のご紹介です。

湖畔のプロムナードを散歩している市民の方に愛犬の写真を撮らせて戴きました。向かって右がティベタン・スパニエル、左がティベタン・テリアです。よほどチベットがお好きなのでしょうね。

湖畔のプロムナードの街路灯の柱にはところどころこの様な標識がついたものがあります。ここに犬を繋ぎなさいというのか、ここでオシッコをさせても良いというのか・・・?
更にすごいのが・・・

プロムナードや道路にほぼ50メートルおきにゴミ箱が配置されているのもすごいけれど、ゴミ箱の正面の赤いのは???

引っ張り出すと、この様な「ウンチ袋」が出て来ます。犬の排泄物はこの袋に入れてゴミ箱に捨てることになっています。これはすごい。日本でもこういうのがあると住民に迷惑を掛けないのだけれど、袋を別の目的に持って行ってしまう不心得者がいて、いつも袋が品切れになってしまうかもしれない。
という訳で長い長い投稿になってしまいましたが、やっと現在の状況に追いつきました。