普代村でも追悼式が行われた。遺族の方からすればまだ癒えぬ心の傷を引きずっている。この教訓をどう生かしていくのかは、生きているものの責務と思うが、それでも原発は必要と主張している。それでも巨大防潮提で自然と勝負を挑もうとしている。
<防潮提>
防潮提の耐用年数は50年から60年という。
普代村ももしかしてそろそろその時期ではないのだろうか?
いずれにしても100年はもたないという。
その老朽化を防ぐための維持管理または造り替えのコストは膨大となる。
岩手県から福島まで、今回の津波を防ぐだけのの海岸線の防潮提を造るのに
8千数百億かかるという。
海の見えない海岸線ができあがる。
「海が見えない」危険も、今回の震災で経験している。
偉大な自然に敬意をはらいながら、高台に引く選択はむずかしいのだろうかと思う。
2011年11月に岩手医大の救命救急の秋富先生はじめ、東大の建築学の先生、環境デザイン都市安全学の先生など専門家が9人で作成したレポート「安全で活力ある生活を 明日から取り戻すためのいたって現実的なプログラム」
と言うのがある。
色んな事実、検証を示したあとで、次ぎのような記述がある。
●安全の理念
・いかなる津波も危険
今回のような巨大津波に限らず、いかなる津波も「どの方向から、いかなる周期か、いかなる
速度か、いかなる高さか」設定できないことから危険である。
・物理的にも社会的にも最も弱いところが被災する
被災の形態、被害の規模は、そのときの最も弱いところに被害が生まれ、波及していく。
・堤防高で安全を決められない
安全を得るための絶対的な堤防高は、いくら議論しても永久に解を見いだすことはできない。
・ 自然との賭けは行わない
原発の経験からも、巨大自然災害に対して技術と手続きに、全面的に頼ることは出来ない。
・海の様子が見える
海の見えない計画は、生活者が自ら海の様子を確認し判断できないという自律性を失うと言う
意味で危険である。それだけでなく、海と共に暮らしと風景を創ってきた地域の文化を破壊し住
民と自然との乖離をつくってしまうことが問題である。
さらに、「安全の体系」として一番の高台に高齢者施設、公共機関、次に教育施設となって
迎えに行かなくて済むシステムを上げている。
その意味では、普代小中学校の位置は逆のシステムを作っている。
あそこが安全か、そうでないかは「いくら議論しても永久に解を見出すことはできない。」
技術と「安全予想」に頼るしか安全という解はない。
レポートの言い方を借りれば、それは「自然との賭け」となる。
<福島原発事故>
東京都内で脱原発を訴える講演会で、福島大学の清水修二という教授が
「原発事故で一人も死んでいないと言うのはうそ。大変な人的被害だ」と影響の大きさを訴えた。
「福島県では15万人近い人が今も避難している。震災関連死は1300人を超えた」と指摘。
「避難は犠牲を伴うが、多くは原発事故の放射能によるものだ」と述べた。
と伝えられている。
<防潮提>
防潮提の耐用年数は50年から60年という。
普代村ももしかしてそろそろその時期ではないのだろうか?
いずれにしても100年はもたないという。
その老朽化を防ぐための維持管理または造り替えのコストは膨大となる。
岩手県から福島まで、今回の津波を防ぐだけのの海岸線の防潮提を造るのに
8千数百億かかるという。
海の見えない海岸線ができあがる。
「海が見えない」危険も、今回の震災で経験している。
偉大な自然に敬意をはらいながら、高台に引く選択はむずかしいのだろうかと思う。
2011年11月に岩手医大の救命救急の秋富先生はじめ、東大の建築学の先生、環境デザイン都市安全学の先生など専門家が9人で作成したレポート「安全で活力ある生活を 明日から取り戻すためのいたって現実的なプログラム」
と言うのがある。
色んな事実、検証を示したあとで、次ぎのような記述がある。
●安全の理念
・いかなる津波も危険
今回のような巨大津波に限らず、いかなる津波も「どの方向から、いかなる周期か、いかなる
速度か、いかなる高さか」設定できないことから危険である。
・物理的にも社会的にも最も弱いところが被災する
被災の形態、被害の規模は、そのときの最も弱いところに被害が生まれ、波及していく。
・堤防高で安全を決められない
安全を得るための絶対的な堤防高は、いくら議論しても永久に解を見いだすことはできない。
・ 自然との賭けは行わない
原発の経験からも、巨大自然災害に対して技術と手続きに、全面的に頼ることは出来ない。
・海の様子が見える
海の見えない計画は、生活者が自ら海の様子を確認し判断できないという自律性を失うと言う
意味で危険である。それだけでなく、海と共に暮らしと風景を創ってきた地域の文化を破壊し住
民と自然との乖離をつくってしまうことが問題である。
さらに、「安全の体系」として一番の高台に高齢者施設、公共機関、次に教育施設となって
迎えに行かなくて済むシステムを上げている。
その意味では、普代小中学校の位置は逆のシステムを作っている。
あそこが安全か、そうでないかは「いくら議論しても永久に解を見出すことはできない。」
技術と「安全予想」に頼るしか安全という解はない。
レポートの言い方を借りれば、それは「自然との賭け」となる。
<福島原発事故>
東京都内で脱原発を訴える講演会で、福島大学の清水修二という教授が
「原発事故で一人も死んでいないと言うのはうそ。大変な人的被害だ」と影響の大きさを訴えた。
「福島県では15万人近い人が今も避難している。震災関連死は1300人を超えた」と指摘。
「避難は犠牲を伴うが、多くは原発事故の放射能によるものだ」と述べた。
と伝えられている。















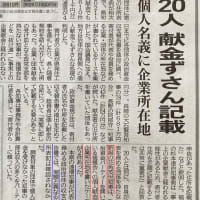
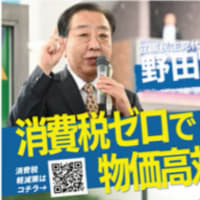


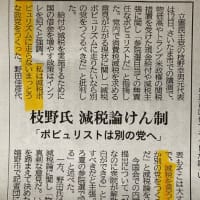
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます