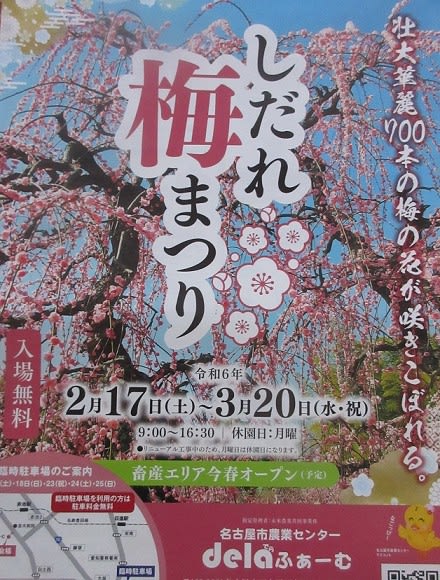春の使者のひとつ、ピンク色の小さな花。ホトケノザ(別名・三階草)です。散歩道にある畑地の脇で見かけましたが、これほどの群生状態に出会ったのは初めてです。
春の七草にも同名の植物がありますが、全くの別物。こちらのホトケノザは雑草扱いされながらも、可愛い姿にかがみ込んでカメラに収めたくなります。
シソ科オドリコソウ属。地上を這う20㌢前後の茎に葉が襟巻のように付き、その付け根に筒状の唇形の花を咲かせます。ホトケノザの名の由来は葉が仏が座る台座に似ていること、別名の三階草も葉が三段階に付いているからのようです。
花言葉は輝く心、小さな幸せだそうです。