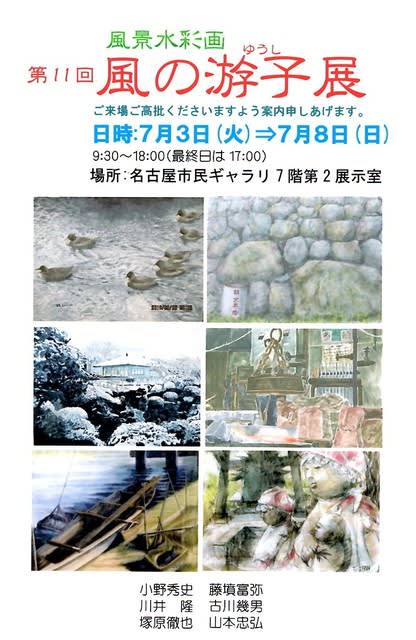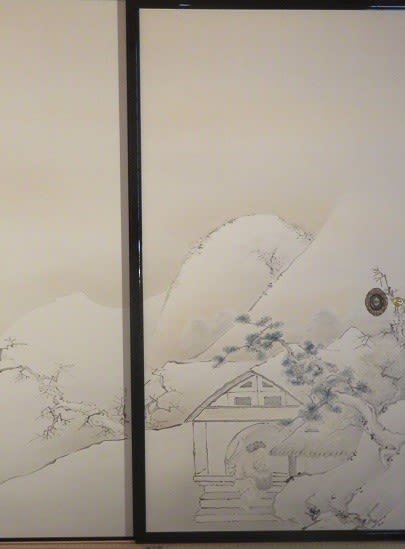ちょっと大げさかもしれませんが、「何事も、あきらめてはいけないな」と思うことがありました。
名古屋港ガーデンふ頭の散策道沿いにある「雑草広場」で、モジズリソウ(ネジバナ)群生している場所を何カ所も見つけたのです。
梅雨空が青空に変わった21日午後、久しぶりにガーデンふ頭へ。岸壁に停泊していた巡視船などを見た後、家路につこうと散策道を歩き始めた時、「もしかしたら、モジズリソウが咲いているかも」と道の両側にある雑草の広場に目が向きました。
モジズリソウは、一株に1~2本伸びた背丈が10~20㌢ほどの細い茎に、小さなピンクの花を咲かせます。その姿はらせん状になっており、図鑑などによると、筆でひらがな文字の文章を書くような意味でモジズリソウ、あるいはネジバナとかネジリバナなどと呼ばれ、古くから愛好家も少なくないそうです。
しかし、もう一つの特徴は、生育にはラン系植物の根に付く菌の助けが必要だと言われていること。言い換えれば雑草地が好適地というわけで、放置状態の我が家の庭でも例年6~7株が芽生え、この時期に可憐な姿を見せてくれます。
一方で「私は雑草ではありませんよ」とばかり、数が増えることはなく密集した様子も見たことはありません。名古屋市農業センターの雑草がはびこる広場でもモジズリソウを見かけますが、孤独を楽しむかのように数㍍間隔で咲いています。
僕も種子らしいものを別のところへ散らしたり、土のまま掘り起こして移動を試みましたが、いずれも成功していません。
ガーデンふ頭のここは、我が家の庭以上の雑草に覆われています。「これ以上の適地はない」と長々と続く雑草広場に入り、目をこらして歩きました。
でも、そんな気持ちを見透かしたように、歩いても、歩いても、見当たりません。
歩き疲れて座り込み、しばらくして立ち上がった時でした。道を隔てた向かい側の雑草地に小さなピンク色が見えます。
2株、4本のモジズリソウでした。
それにしても、こんなに広い所に咲いているのはこれだけとは・・・。改めてモジズリソウの不思議さに驚きつつ、あと数本でいいから見つけてやろうと、立木の下の雑草地を過ぎ、さらに次の雑草地を歩いている時でした。
「群落」に出会ったのです。
畳1枚ほどのところに、まさに雑草のように伸び、咲いています。
数えてみたら100本を超えました。面積は狭いけど群生地というべきか、群落というべきか、とにかく驚きました。
カメラに収め、さらに隣接する雑草地へ。
なんと同じような、いやさらに広い面積で群生しているところが次々に見つかりました。人為的に種が蒔かれたのではと思うほどですが、そんなことはないでしょう。
ひょっとしたら、こんなのはよくある光景なのでしょうか。でも、僕にとっては、あきらめずに歩き、探した発見でした。




ディエゴが咲く広場の雑草の中にも群生地がありました