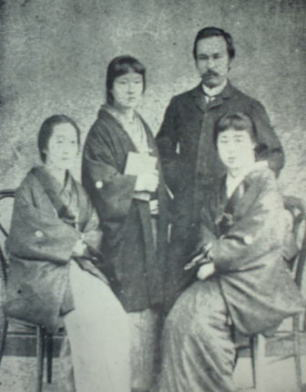高知市観光ボランティア・ガイドの人達と、高知市上町1丁目 第四小学校前 にある婦人参政権碑を訪ねました。

◆会社の近くに、こんな碑があります。◆
婦人参政権が認められたのは、1945年10月、閣議決定されました。
しかし、それよりも60年以上前に、ここ高知市上町町議会で日本ではじめて女性の選挙権・被選挙権が認められたのです。
これを記念して記念碑が建てられました。(1990年)


◆会社の近くに、こんな碑があります。◆
明治13年6月16日、高知の上町町会は女性の選挙権・被選挙権を認める町会規則を県令(今の県知事)に提出しました。その案文は次のようなものです。
「第十七条 本会ノ議員ハ全員五拾名ト定メ町内一般人民ヨリ公選スベシ
但シ議員ト為ルヲ得ベキ者ハ左ノ条款ヲ除ク(中略)__ニ十年未満ノ者」
つまり、20歳以上の男女に選挙権・被選挙権を認める内容のものです。(現在は、被選挙権は25歳以上の男女)
この案文に対しては、直ちに県令(県知事)が、「二十年未満ノ者」を「二十年未満ノ者及ヒ婦女」という内容に訂正してきました。婦人の参政権を認めなかったのですね。
しかし、上町町会の3ヶ月にわたる抗議行動に県令もなんとか折れて、明治13年(1880年)9月20日、日本で始めての女性参政権を認める法令が成立しました。明治維新からわずか13年後のことでした。
その後、隣の小高坂村でも同様の条項を実現しました。
この当時、世界でも女性参政権を認めていたのはアメリカのワイオミング州議会だけでしたので、高知県の上町・小高坂村の動きは世界で2番目に女性参政権を実現したものでした。
そもそも、高知で、最初に女性の参政を叫んだのは、楠瀬喜多という一人の婦人でした。彼女は夫、楠瀬実の死去後の、明治11年、区議会議員の選挙で投票できず、「戸主として納税しているのに、女だから選挙権がないというのはおかしい。本来義務と権利は両立するのがものの道理、選挙権がないのなら納税しない」と県に対して講義した。しかし、県には受け入れてもらえず、喜多は内務省に訴えた。これは、婦人参政権運動の始めての実力行使となり、東京日日新聞などにも報道された。

隣には、このような記念碑もありました。嶽洋社址、河野万寿弥誕生地跡

H16.06.20高知:地図高知市上町2-1
HN:史跡探訪者
婦人参政権碑 に関する記事
HN:史跡探訪者 さんの記事