
れんちゃんのおみやげの『ピーターラビット展』の図録は、上製本で、なかなかゴージャスだった。
しかし天や地や小口が、なんだか波打っている。あまりにもガタガタしているので、とびだす絵本のように何か仕掛けがしてあるのかと思ったくらいだ。
まさかアンカット?
アンカット、つまり断裁していないということ。
岩波文庫、新潮文庫、ハヤカワ文庫の「天アンカット」は本好きにはよく知られている。
通常の本は、表紙のカバーを巻いた時点で、「天」(本を立てたとき上になる部分)、「地」(同じく下になる部分)、小口(本を開くとき手前に来る部分)の三方を断裁機で断裁する(三方断裁)。天アンカットとは、地と小口のみ断裁する手法である。
製本職人の紙積みはコンマ1単位の熟練の技ではあるけれど、それでも微妙な差は出る。アンカット(袋とじ)の折丁をペーパーナイフで切り開きながら読み進めたフランス装の本の小洒落た感じが出せるというわけだ。これは老舗出版社のこだわりである。

ご自宅に文庫本があったら、岩波・新潮・早川の三社と、それ以外の出版社の分魂本を見比べていただきたい。他社の文庫は紙がきれいに揃っているけれど、岩波・新潮・早川の三社は、32ページごとに、紙の束(折丁)が地層のように積み重なっていることが確認できるだろう。指で触れてみたら一発で違いがわかる。

左が岩波文庫、右が講談社学術文庫
写真:しんぎんぐきゃっと氏(ウィキペディアより)
しかし、『ピーターラビット展』の図録は、天だけでなく、地も小口までガタガタしている。あたかもフランス装のアンカット本のようである。
「やらかしてしまったなあ」と、私は苦笑いせざるをえなかった。これは立派な事故物件であり、欠陥品である。
まあ、反面教師として、本づくりを志す若い人の教材にはなる。なぜこんなことになってしまったのか、正確なところはわからないが、私自身、おさらいの意味で、上製本のポイントをまとめておきたい。
むかし、上製本は納期が三か月といわれた。
印刷直後の刷り上がったばかりの紙は、工場内の空気中の湿気を吸って膨張して、波打ち現象を起こしている。だから印刷済の用紙(刷本 すりほん)を倉庫に積んでおいて、一か月以上寝かせて放湿させ、紙のコンディションが安定してから製本作業に入るのが鉄則だった。
しかしこの図録は印刷後すぐに製本に回してしまったらしい。おじさんの愚痴になるが、最近の若い人は、本がマテリアルであり、紙が呼吸する生き物であることを忘れているように見える。
この図録も、三方断裁した時点ではページがきれいに揃っていたにちがいない。
しかし紙の放湿は終わっていない。水分をまだたっぷり含んでいる。インキの量、色によっても乾燥スピードは異なる。このため、乾きの早いページ、乾きの遅いページがある。乾燥を均等化するために最低1か月は寝かせるのだが、それを怠ったがために、紙のサイズがまちまちになってしまったのだろう。
ピーターの上着のイメージに合わせて、この図録のテーマカラーが青だったことも、この不具合を助長した。
しかし、オフセット印刷のいわゆるCMYK、シアン・マゼンダ・イエロー・ブラック(藍・紅・黄・墨)の印刷インキのうち、青色の主成分のシアンは、特に乾燥スピードが遅い。
昭和レトロなお店で、青く退色したポスターが残っているのをよく見かける。シアンは乾きが遅く、実際には半永久的に乾くことがないのが原因である。看板でも、青色と墨色は退色しにくく、赤や黄色は退色しやすい「飛び出し注意」の「注意」が消えて、「飛び出し 」になっている残念な看板をよく見かけるのは、そのためである。
この図録では、全面ブルーのベタだったり、ページの端を青く縁取りしたページは、他のページより乾きが遅くなり、つまり水分含有量が高いままで、ポコンと飛び出してしまうことになった。これがアンカット製本でもないのに、ページがガタガタになってしまった理由であろう。
対処法は、本のサイズは小さくなってしまうけれど、もう一回断裁をやり直すしかないのではないか。
奥付には名だたる美術館、新聞社、映画会社、印刷会社が名を連ねている。最近は上製本を作る機会が激減して、作り方を知っている人も少なくなってしまったのだろう。上製本の職人の減少は深刻であり、このままでは上製本という文化は終焉してしまうだろう。
図録の解説そのものは、なかなかおもしろかっただけに残念である。
興味を惹かれたのは、現在に至るも《ピーターラビットのおはなし》の版元になっているウォーン社は、1899年に出版された、グラント・リチャーズ社の《ちびくろサンボのおはなし》の小型本に競合するような絵本の出版を考えていたというエピソードだ。
ビアトリクス・ポターも、当時のベストセラーだった《ちびくろサンボのおはなし》(The Story of Little Black Sambo)を意識していたようである。
《サンボ》が「おはなし」に Story を使っているのに対し、ビアトリクスは tale を使うことにした。この tale(おはなし)は、作品に登場するうさぎ、ねずみ、りすといった動物が持つ tail(尻尾)とのかけことばである。The Tale of Peter Rabbit というタイトルには、「ピーターラビットの(かわいい)尻尾」という意味もこめられている。
ビクトリアスはことば遊びが大好きだった。冒頭の挿絵は、モミの根元で、尻尾をこちらに向けるピーターが描かれるが、モミの木は fir で動物の毛のfur と同音異義語で、「ウサギの毛のようにモフモフした物語が始まるよ」というイメージがしのばされているらしい。
図録も、出品作品の原画の解説にかえて、『ピーターラビットのおはなし』を全ページ収録するアイデアはよかったが、原文もあればなおのことよかった。英語の格好のテクストになったにちがいない。
《ちびくろサンボのおはなし》の作者も女性で、元は手作り絵本だったという点は、《ピーターラビットのおはなし》と一緒である。《サンボ》の作者のヘレン・バンナーマンは、軍医であった夫とインドに滞在していたスコットランド人で、自分の子どもたちのためにこの話をかいた。
トラが出てくることでわかるように、オリジナルのサンボとその家族はインド人であり、パンケーキというよりは、ナンあるいはチャパティのようである。
《サンボ》については、残念ながら、日本で紹介されてきたのは、オリジナルではなく、アメリカで流布していた多くの海賊版のうちの一つであるマクミラン社版だった。ヘレン・バナマン自身によるオリジナルは『ちびくろさんぼのおはなし』(灘本昌久訳)として1999年に径書房から出版されているけれど、定着しなかったのは、彼女のイラストが素人の域を出なかったからだろう。
絵に関しては、《ピーターラビットのおはなし》のビアトリクス・ポターに完全に軍配が上がる。ウサギの精密な観察に基づいたリアリズムと、ファンタジーの世界が共存している素晴らしい作画だ。
そして、この作品は、作品の生みの親であるビアトリクス、そしてその継承者たちによって、しっかり守られてきた。ビアトリクスは、絵本のキャラクターを商品化するための特許を取得した世界初めての人だった。これは1903年12月、ロンドンの老舗百貨店ハロッズの広告に、ドイツ製の粗悪なピーターのぬいぐるみが掲載されていたことがきっかけとなった。
《ピーターラビット》や《ちびくろサンボ》の時代の著作権の扱いはいい加減だった。《サンボ》はアメリカで海賊版が流布され、私達が読んだ岩波書店版も、こうしたアメリカ版の1つであるマクミラン社版(1927年刊)で、絵も原作者のヘレン・バナマンではなくフランク・ドビアスの絵である。
《サンボ》はアメリカで海賊版が流布される過程で、アフリカ系黒人に改変される。ヘレン・バナマンの原作にも、インド人への偏見や差別があるのは否めないが、アメリカの海賊版は、それに輪をかけて、黒人に対する人種差別や偏見を増長するものだったといえよう。《ちびくろサンボ》には、トラが高速回転してバター(ギー)になり、パンケーキを山のように積み上げて食べるという、一度読んだら忘れられない、一生こころに残るであろう名場面があるだけに残念である。
《サンボ》では、帽子や洋服を新調して散歩にでかけたサンボが、出会ったトラたちに食べられそうになったので、身に着けているものを譲ることで許しを得る。しかしトラたちは戦利品をめぐって仲間割れを起こし、ヤシの木の周りをぐるぐる回っているうちに、バターに(ギー)なってしまう。サンボは奪われた服を取り返し、「トラバター」(Tiger Ghee)”を使ってパンケーキを焼いて食べる。ちなみに1980年代の絶版で、最近の若い人にはこの「トラバター」が通じなくなっているという。
西欧風の身なりで、豊かな生活を送るサンボの家族は、イギリス帝国主義の植民地支配に協力的なごく一握りの富裕層なのだろう。サンボから衣服を取り上げるトラは植民地主義の犠牲になった大多数のインド民衆の比喩というべきか。しかし西欧風の衣服を奪われたサンボは、トラよりも弱い存在に貶められてしまう。裸にむかれたサンボは、彼の本来の姿なのだ。原作にも、物語の出だしの時点で、日に焼けたインド人が西欧人のような格好をしていることを滑稽視する視点が、そこにはなかったか。
《サンボ》は、西欧化・文明化された愛すべき「野蛮人」の物語にすぎなかったが、《ピーターラビット》は母親に与えられた上着や靴を失い、ウサギ本来の野生の姿に返ることで危機を脱するのである。同時代の作品でありながら、《サンボ》が忘れかけられ、《ピーターラビット》がいまも生命力を保っているのは、この馴致されえない野生のいのちの輝きに満ちているからだろう。











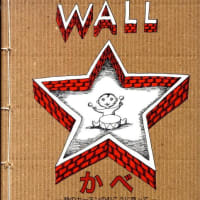








グローバル資本主義の未来についてドゥルーズ=ガタリ「アンチ・オイディプス」で述べていたことも、極めて単純にいえばそういうことですね。
今や労働力の高速回転は留まるところを忘れ去ってひたすら加速するばかりの資本循環がさらなる悪循環サイクルを出現させていくばかり。
人間は誰もが薄っぺらい記号へ還元されて力尽き、逆に人間身体から抽出された<労働力・強度・力>と絶滅寸前の自然界だけが剰余価値の源泉として利子を叩き出していますが、この<労働力・強度・力>が何度も繰り返し商品交換され剰余価値を実現させるごとに、逆説的に<労働力・強度・力>は加速的に「高速回転してバター(ギー)にな」るほかないと。
ではでは。
最後の方、今朝のTwitterでの紹介文をふくらませて、追記をしています。しっぽのtailもtaleになっていたのを修正しました。
「胡麻の油と百姓は絞れば絞るほど出るもの」といいますが、インドにはトラと脂をからめたことわざがあったんでしょうか。日本には「トラのあぶら」という民話が伝わっていますね。
http://hukumusume.com/douwa/eto/tora/j02.htm
サンボはれんちゃんにもソウル絵本ですが、父親手作りのリメイク版で読んだようです。