先日、とても残念なニュースが入ってきました。
あの
『スウィング・ジャーナル』が7月号を最後に63年の歴史にピリオドを
打ち、休刊になると言うものでした。
ショックでした・・・
あちこちで行われるコンサートやライブハウス、CD売り場の状況から
JAZZを取り巻く環境の変化はひしひしと感じてはいましたが、最後の
砦たる『スウィング・ジャーナル』までも・・・と言う想いです。
『スウィング・ジャーナル』の歴史は真に日本のJAZZの歴史でもあり、
その影響力は計り知れないものがあります。
『スウィング・ジャーナル』を始めて手にしたのは38年前、高校生の時に
友人に誘われて始めて入ったJAZZ喫茶『BOP』でした。
それ以来JAZZの洗礼を受け、どっぷりとハマってしまい、この『SJ』と
『BOP』には本当にお世話になりました。
その『SJ』も下宿生活の高校生には買える筈も無く、毎月発売日を楽しみに
『BOP』に行き、コーヒー一杯で何時間も読みあさったものです。
中でもお目当ての記事は、毎月発売されるレコードの新譜紹介と各アーティストの
ディスコ・グラフィー、それらを参考に店でリクエストしたものです。

アート・ペッパーのディスコグラフィー
その当時、函館で新譜レコードの情報と言えばNHK-FMと『SJ』
位しかありませんでした。
その『スイング・ジャーナル』には日本を始め世界中のミュージシャンの
ホットなライブ情報などが満載、おまけにアンプやスピーカーなど
オーディオに関する情報まで載っており、仲間とやれJBLだアルティク
だ、このシンバルのアタック音がどうのこうのと、持ち寄った新譜を
聴きながら喧々諤々とやったものでした。
今にして思えば、その当時はJAZZと言う『音楽』では無くJAZZの『音』を
聴いていた様な気がします。
この様にJAZZファンにオーディオマニアが多いのも少なからず、
『スウィングジャーナル』が影響しているように思います。

ディスクレビューのオジサンマーク
毎月、沢山発売されるアルバム、JAZZ初心者にとっては何を選んだら
良いのか分からず、このディスクレビューに付いている5段階評価の
この「オジサンマーク」が頼り。
中でも亡くなった「油井正一」さんの評論は、決して演奏者や
レコード会社に媚びない、時には励ましにも似た愛のある辛口の
評論で、私にとっては羅針盤的な存在でした。
自分が密かに「これは良い」と思っていたアルバムに油井さんが★を
五つ付けてくれたり、選定『ゴールドディスク』に選ばれた時などは、
鼻高々でした。
このレコードの購入にも逸話があり、勤め先のJAZZが好きな仲間
3人と話の勢いから普段買えない様なアルバムを10万円分カードで買い
毎月せっせとローンを払ったと言う馬鹿な事もやりました。(笑い)
そんな『スウィング・ジャーナル』も油井さんが亡くなり、段々
マンネリ化した内容につまらなさを感じ、あの「こぶ平」の記事が
載り始めた頃から何時しか買わなくなってしまいました。
もう~何年になるでしょうね~・・・?

ディスクレビュー
そんな休刊のニュースの後、本屋で見つけ手に取ると表紙は大好きな若き日の
「ビル・エバンス」連載は「名盤のウラに記された真実・ビル・エバンス」
とあります。
中を覗いてみるとディスコグラフィーまで復活しているでは有りませんか
もう~たまらず、買ってしまいました。
夜一杯やりながら感じたのは、たまたま6月号がノスタルジックな内容
なのか?昔との余りの変化のなさに驚いたと共に、この変わりの無さが
この度の休刊の要因の1つの様な気がして複雑な気持ちになりました。
6月19日発売の7月号をもって休刊になってしまいますが、
日本のJAZZ界の為にも一刻も早い『スウィング・ジャーナル』の復活を
願ってやみません。
この
スイング・ジャーナルオフィシャルBlogはそのまま継続されるようです。
『スウィング・ジャーナル』よ原点に帰って頑張れ!!










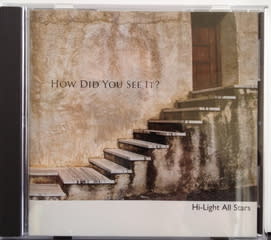














 アート・ペッパーのディスコグラフィー
アート・ペッパーのディスコグラフィー ディスクレビューのオジサンマーク
ディスクレビューのオジサンマーク  ディスクレビュー
ディスクレビュー













