
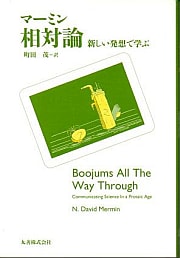 4日ほどかけて、この「ゼロから学ぶ量子力学」を読み終えた。本の帯に「分かりやすさの新本格、ネコさえ笑うオモシロさ!かるーく越える高い壁」とあるが、僕の期待を裏切らなかった。量子論の入門書としておすすめだ。
4日ほどかけて、この「ゼロから学ぶ量子力学」を読み終えた。本の帯に「分かりやすさの新本格、ネコさえ笑うオモシロさ!かるーく越える高い壁」とあるが、僕の期待を裏切らなかった。量子論の入門書としておすすめだ。科学雑誌ニュートンでは文章とイラストでの説明に終始していたが、この本ではシュレディンガーの波動方程式をはじめ、さまざまな量子力学の方程式をユーモラスでわかりやすく解説している。「ゼロから学ぶ~」というタイトルにはちょっと嘘がある。少なくとも高校卒業程度の数学知識は必要だ。でも、量子論の知識はゼロの人を対象としているというのなら、このタイトルに嘘はない。
僕の日記の読者のほとんどは「数式を見るだけで拒否反応をおこす」人だと思うが、あらためて「もし数式を全く理解しない前提でこの本を読んだら」とページをめくり返してみると、なかなかどうして不思議なものである。文章のところだけ読んでも面白いし、ニュートンとはまた別の側面から量子論を理解できる。さすがだ。
入門書だから仕方がないが、僕としてはもう少し数学的な方法でこの理論のいろいろな側面を理解したかった。いきなり方程式が提示されて、即座に受け入れていいものだろうかと思う箇所が目立つ。しかし、その後に続く説明を読むと方程式の意味はちゃんとわかるようになっているし、方程式から別の式を導いて量子論の別の側面を数学的に説明することに成功している。また、より抽象化、一般化された数学手法を使うことで、量子論的現象がより明確に浮き彫りになり、量子論が数学と密接に結びついていることを実感できたのが僕にはうれしかった。そのことは、今後どのような分野の数学を学習したらよいかの道しるべとなるからだ。
この本で、電子が粒子性と波動性を同時に持つことや重ね合わせの原理、不確定性原理、存在確率、エネルギー準位、電子のスピン、トンネル効果、電子と電子のからみ合い、量子のポテンシャル、量子の行列力学、場の量子論などについてかなりはっきりとしたイメージをつかむことができた。それは視覚化できるイメージではなく感覚的なものだ。今後、より高度な本で勉強していく中で壁にぶち当たったとき、この本に戻って復習することがきっとあるだろう。
僕にとって何よりうれしかったのは、巻末により高度な量子論についての書籍を紹介してくれていることだ。書籍名だけではなく、どれくらい難しいかとか、どういう感じの本かということも書いてくれているので非常に助かる。僕のような初心者は書店の物理・数学書コーナーに行くと、目移りしてしまってどれを買っていいものか迷い、結局選ぶのに何時間もかかっているから。
著者は竹内薫さんという方で僕より2歳年上だ。東大理学部物理学科卒、マギール大学大学院博士課程修了。学者にはならずに、科学ライターとしての道を選んだ方だ。詳細は彼のHPをご覧いただきたい。
竹内薫さんのHP:
http://kaoru.to/
アマゾンでこの本を:見てみる
ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。























