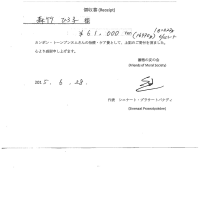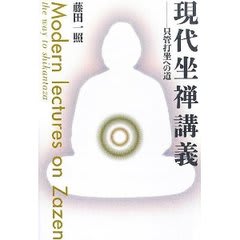
購入した本の帯には「坐禅のつもりで 坐禅になってない 坐禅がある
──この本の読者には、そんなことはさせられない」と挑発的なコピーが……
近く、坐禅の指導を受ける可能性があり、再読。
サンフランシスコの曹洞宗国際センター所長の藤田一照禅師が、満を持して「只管打座の坐禅」だけを主題としてとり上げた一冊。まずは哲学者パスカルや詩人のキーツが重視した「くつろぐ能力(ネガティブ・ケイパビリティ)の賛同からはじまり、言葉で表すことはできないとされたいた「只管打座」を、多方面から光を当て、描線を引き、誠実に検証されていきます。
初読ではユニークな洞察にみちた前半の理論部分に関心が向きましたが、再読することで後半の実践的な部分ががぜん面白みを増しました。また機会があるごとに読み返したい一冊です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
読書メモ
自己の正体を見失っているからこそ、安心してくつろいでいることができずに、自己の幻影を追いかけてさまよい歩いてしまうのです。
内山興正老師は「思いは頭の分泌物だ」と言いました。胃が胃液を分泌するように生きている脳は思いを分泌すると言うのです。そして「胃液が出すぎると胃酸過多で困るように、思いが分泌過多になって困っている人が多すぎるね」とも言っておられました。
坐相が全一的なものとして成り立つためには調身が調息、調心と一緒に進行していかなければならないのです。
坐禅の作法に従って脚、手、口、アタマをしかるべきあり方、状態におさめるということは、それらを普段の生活活動においてやっているように、自分の都合のためには一切使いませんと無言で宣言していることなのです。
坐禅は決して外界を遮断して自分を閉ざした「内面への沈黙」ではなく、さっきお見せした写真の赤ちゃんがはっきり示しているように、自分をオープンにしてしっかりと外界を受けとめ、それと深い繋がりを持つことなのです。
綱渡りがうまくなる上で大事なことは、怪我をしないように上手に落ちること、そしてまたフレッシュに綱の上に乗ること、落ちたらまた乗る、これを楽しむことです。