自分勝手な今日の復習の部屋。
『態度変容』に関しての記述で、最も妥当なものはどれか。
(国Ⅰ 平14)
-------------------------------------------------------
A.
接種理論によれば、親友の持つ信念に反することを説得するのは、
些か抵抗があるので、事前に第三者に同様の説得を試みることで、
説得者に免疫ができ心理的抵抗は軽減されると考えられる。
-------------------------------------------------------
B.
恋人から禁煙するように強く説得され、
好きな喫煙をやめたという態度変容は、
ブーメラン効果によって説明される。
-------------------------------------------------------
C.
あまり親しくない同級生から与えられた情報をすぐには信じなかったが、
少したってから、そのとおりであると思い直した態度変容は、
スリーパー効果によって説明できる。
-------------------------------------------------------
D.
バランス理論によれば、
二人の友人からほぼ同時に遊びに行こうと誘われた場合、
心理的葛藤を解消するための抑圧機制が発動されるので、
両方の申し出を拒否する行動が生じると考えられる。
-------------------------------------------------------
E.
リアクタンス理論によれば、
先輩から親しく交際している友人とはつきあわない方がよいと忠告された場合、
先輩との葛藤を生じないように、忠告に従う行動が生じやすいと考えられる。
-------------------------------------------------------
解答は、最下部。
それぞれの理論を簡単に解説すると以下になる。
【接種理論】
McGuire.W.J.が提唱した説得への抵抗力のつけ方についての理論。
この理論で扱われるのは「自明の理」、
一般に広く受け入れられていて反論の余地のないものである。
しかし「自明の理」は反論に対して免疫がないため、
反論や攻撃を受けると容易に説得され、態度変容が起こってしまう。
しかし事前に軽い反論を受けておけば免疫ができ、
本格的に反論を受けたときに説得されにくくなるという考え。
【ブーメラン効果】
説得的コミュニケーションにおいて生じる説得への抵抗のうち、
態度が唱導方向とは逆に変化すること。
この現象が生じる要因については、テーマに関する自己関連度の度合いや
受け手と送り手の立場の違い、送り手からの圧力の強さなど、
さまざまな指摘がある。
説得への抵抗のなかでも積極的な抵抗で、
やぶへび効果とも呼ばれる。
心理的リアクタンス理論では、
高圧的な説得的コミュニケーションが行われることによって、
受け手は態度の自由に対する脅威を感じ、
その自由を回復するべく唱導方向とは逆に態度が変化すると説明している。
バランス理論説明すると、
好ましくない、あるいは外集団である他者が自分と同じ意見を主張すると、
その他者とは異なる方向に意見を変えることが起こりうる。
【スリーパー効果】
信憑性の低い送り手からの説得も時間が経つと効果が出ること。
メッセージの受け手は、説得直後は送り手の信憑性が低いため、
メッセージの内容を割り引いて受け取り、態度変化は生じない。
しかし時間の経過とともに送り手の情報とメッセージの内容が分離するために
相対的に説得効果があがる。
【バランス理論】
Heider.F.
認知的均衡理論、P-O-Xモデルなどともよばれる。
P-O-Xの3者関係についての認知を取り扱ってりいる。
P:認知する主体
O:他者
X:認知対象
①ユニット関係
⇒ 二者がひとまとまりに認知される関係(関係があれば+、なければ-)。
②センチメント関係
⇒好き嫌い、賛成反対などの評価の関係(肯定的+、否定的-)
三者関係の符号の積が+になれば均衡状態、
不均衡状態にあるときには認知を変化させ、均衡化を図ろうとする。
【心理リアクタンス理論】
Brehm.J.W.によって提唱された説得への抵抗を説明する有力な理論。
人は自分の意見や態度を自由に決定したいという動機を持っており、
これが脅かされたとき、人は自由を回復をめざすべく動機づけられる。
この動機づけ状態を心理的リアクタンスと呼ぶ。
生起するリアクタンスの大きさは、自由が確保されているほど、
自由が重要であるほど、自由への脅威が大きいほど、大きくなる。
人が説得を受けるとき、唱導方向に態度を変えるよう圧力をかけられると、
受け手は態度決定の自由が脅かされたと感じ、
唱導された態度を取らないことで
自由を回復しようとするブーメラン効果なのだとこの理論では説明する。
■解答:C
さーて昼飯~
『態度変容』に関しての記述で、最も妥当なものはどれか。
(国Ⅰ 平14)
-------------------------------------------------------
A.
接種理論によれば、親友の持つ信念に反することを説得するのは、
些か抵抗があるので、事前に第三者に同様の説得を試みることで、
説得者に免疫ができ心理的抵抗は軽減されると考えられる。
-------------------------------------------------------
B.
恋人から禁煙するように強く説得され、
好きな喫煙をやめたという態度変容は、
ブーメラン効果によって説明される。
-------------------------------------------------------
C.
あまり親しくない同級生から与えられた情報をすぐには信じなかったが、
少したってから、そのとおりであると思い直した態度変容は、
スリーパー効果によって説明できる。
-------------------------------------------------------
D.
バランス理論によれば、
二人の友人からほぼ同時に遊びに行こうと誘われた場合、
心理的葛藤を解消するための抑圧機制が発動されるので、
両方の申し出を拒否する行動が生じると考えられる。
-------------------------------------------------------
E.
リアクタンス理論によれば、
先輩から親しく交際している友人とはつきあわない方がよいと忠告された場合、
先輩との葛藤を生じないように、忠告に従う行動が生じやすいと考えられる。
-------------------------------------------------------
解答は、最下部。
それぞれの理論を簡単に解説すると以下になる。
【接種理論】
McGuire.W.J.が提唱した説得への抵抗力のつけ方についての理論。
この理論で扱われるのは「自明の理」、
一般に広く受け入れられていて反論の余地のないものである。
しかし「自明の理」は反論に対して免疫がないため、
反論や攻撃を受けると容易に説得され、態度変容が起こってしまう。
しかし事前に軽い反論を受けておけば免疫ができ、
本格的に反論を受けたときに説得されにくくなるという考え。
【ブーメラン効果】
説得的コミュニケーションにおいて生じる説得への抵抗のうち、
態度が唱導方向とは逆に変化すること。
この現象が生じる要因については、テーマに関する自己関連度の度合いや
受け手と送り手の立場の違い、送り手からの圧力の強さなど、
さまざまな指摘がある。
説得への抵抗のなかでも積極的な抵抗で、
やぶへび効果とも呼ばれる。
心理的リアクタンス理論では、
高圧的な説得的コミュニケーションが行われることによって、
受け手は態度の自由に対する脅威を感じ、
その自由を回復するべく唱導方向とは逆に態度が変化すると説明している。
バランス理論説明すると、
好ましくない、あるいは外集団である他者が自分と同じ意見を主張すると、
その他者とは異なる方向に意見を変えることが起こりうる。
【スリーパー効果】
信憑性の低い送り手からの説得も時間が経つと効果が出ること。
メッセージの受け手は、説得直後は送り手の信憑性が低いため、
メッセージの内容を割り引いて受け取り、態度変化は生じない。
しかし時間の経過とともに送り手の情報とメッセージの内容が分離するために
相対的に説得効果があがる。
【バランス理論】
Heider.F.
認知的均衡理論、P-O-Xモデルなどともよばれる。
P-O-Xの3者関係についての認知を取り扱ってりいる。
P:認知する主体
O:他者
X:認知対象
①ユニット関係
⇒ 二者がひとまとまりに認知される関係(関係があれば+、なければ-)。
②センチメント関係
⇒好き嫌い、賛成反対などの評価の関係(肯定的+、否定的-)
三者関係の符号の積が+になれば均衡状態、
不均衡状態にあるときには認知を変化させ、均衡化を図ろうとする。
【心理リアクタンス理論】
Brehm.J.W.によって提唱された説得への抵抗を説明する有力な理論。
人は自分の意見や態度を自由に決定したいという動機を持っており、
これが脅かされたとき、人は自由を回復をめざすべく動機づけられる。
この動機づけ状態を心理的リアクタンスと呼ぶ。
生起するリアクタンスの大きさは、自由が確保されているほど、
自由が重要であるほど、自由への脅威が大きいほど、大きくなる。
人が説得を受けるとき、唱導方向に態度を変えるよう圧力をかけられると、
受け手は態度決定の自由が脅かされたと感じ、
唱導された態度を取らないことで
自由を回復しようとするブーメラン効果なのだとこの理論では説明する。
■解答:C
さーて昼飯~
















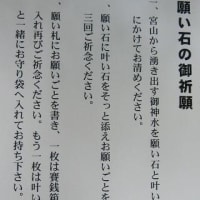




三回読んでやっと何とか6割かな…。答えはわかったけど。
朝から脳みそ使いすぎて知恵熱…。
ボケーとしてる今見ると、
まったく頭に入りません…
なんじゃこりゃー
ヒデキ感激♪
■てるてる、
ブーメラン ブーメランって、
腰をぐわんぐわん回すんじゃありません!