極私的映画論ー観る立場よりー
「メルヘンの闇」
本堂は映画である。
今月初めの5日、午前中に知り合いから電話、「教え子が死んだ!」「相談がある」とのこと。とりあえずその日の午後に合う約束をする。
彼は児童養護施設、情緒障害児施設などを経営している、社会福祉法人の理事長?で、長い間その様な福祉関係の仕事に携わってきた人物である。
訪ねてきた彼は早速「5歳の頃から~18歳までその施設で面倒を見てきた男の子で、やっと仕事も決まり、4年間今の職場で仕事をしていた」「今日の朝、死んだ。22歳で…」……とのことであった。「なんとか葬儀をしてやりたい」とうつむいたまま語った。
それから、また死者になっ た彼の身の上話を始めた。「兄弟が6人とか…」「その兄弟も父母がそれぞれ違う…?」とか、「複雑な家庭事情…」「家庭内暴力…」とか、ある意味闇を抱えての人生、そんな闇からの解放を願い,やっと自立の方向に向かう矢先の教え子の死である。先生にとっては忸怩たる想いや、やり切れなさや、複雑な想いが交錯している様子であった。


さらに、その先生と死者とその母親は、2009年に上映されたドキュメンタリー映画「葦牙」に出演しているのである。この「葦牙」というrドキュメント映画は、その道では有名な監督小池柾人が、その社会福祉法人の全面協力の基製作した映画であった。その映画のパンフレットには、「児童虐待の当事者となった人達!今、こどもたちが自ら未来を語りはじめた」と、あるように子どもたちの強い生命力が明るく描かれている。また同パンフレットには、やはりその道では有名な映画評論家で映画大学・現学長の佐藤忠男氏が「虐待を受けて保護されている子どもたちというと、心にトラウマを抱えていじけてしまっているのではないか,と思ってしまうのだが、この映画にみる子どもたちは皆、普通の子どもたちである。むしろこの子たちは、よほど苦労を知り,大人びているとさえ思われる。
たとえばひとりの男の子はスケート部の練習に打ち込む,何か自分を鍛えるということに自覚的であるという様子がうかがえる。彼はいう『暴力の連鎖を自分の世代で止めて幸せな家庭を築きたいと』…………」と述べている。
そのスケート部の練習に打ち込んでいる男の子が死者になった。
「どうしても葬儀をやりたい!」「お金はない」確かに、母親は居る。その母親も何番目かの男が居るみたいであるが,連絡が取れない。小学生の女の子は同居しているが,後の子どもたちは皆上記の施設にいる、とのこと。挙げ句その母親は、生活保護受給者である。ちなみに、生活保護受給者の身内の葬儀の費用は火葬までで、それ以上は受給できない。5~6万か……?
「火葬だけでは寂し!」「どうにか葬儀をしたい」とのこと、結局、お金はいいから葬儀はやろう、ということになった。
「おれ、明日までに弔辞を考えてくる」知り合いのその先生と死者との関係が垣間見えた。
映画の中で、死者の県内でも有数の高校スピード・スケート部での練習ぶりや、県高校選手権の様子(確か良い成績であった)や、そして母親の応援など、それまでの彼の人生の悪戦苦闘を感じさせない、何か達成感のある表情の、それぞれのカットが、お経の途中で次々に思い浮かび、祭壇に飾ってある遺影が生者のような感じで、「ひょっとしてこれ葬儀?」妙な感覚の葬式であった。
家庭内暴力、母、もしくは父が変わる度ごとの、それぞれからの虐待。母も暮らしの為に男を変える……。そんな中での生活、文字通りいのちのやり取りの場所、修羅場の生活?
明と闇の分かれ道、闇と明の境、人間誰でもが抱えている問題。運命だけで被けられない事柄。死者になることを選んだ彼に、残された生者は、言葉も届かず,何も出来なかった忸怩たる想いを抱え、生きざるを得ないのか?いずれ闇だけは残る…………。
意外に多かった会葬者の香典をその場で開け「これお礼です」と差し出す、数々の修羅場を知っている知り合いの、ホッとしたような,しないような,複雑な表情が印象に残る。
現実的には死者になった若い彼、映画の中では永遠の生者である。
いずれ闇だけは残る。
本堂に国境はない!境があるとすれば、あの世とこの世の境である。あの世とこの世の境としての空間が本堂である。したがって本堂は生者と死者の境目の空間でもある。決して、ただ単に生者のエゴによって象られた空間ではない。生者は、死者の声を素直に聞けるか!それが問題でもある。今の一連の世界情勢は、死者=他者を無視した生者のそれぞれに勝手なエゴでしか動いていない。
だからと言って何でもいいわけではない。国境には関所があり入出のチェックがある。それを決めるのは、閻魔大王である。その閻魔様に条件を聞くと「面白いこと」の一言。うーんさすが閻魔大王………?
昔、古い本堂の頃、留学生の交流会をしたことがあった。その時、イスラム教の留学生が、午後の5時頃お祈りをしたいので、良い場所はないですか?と聞かれ,座敷でどうぞ、と云った覚えがある。その学生お寺に入ってきた時は、寺の廊下をスリッパと勘違いしたのか、雪駄でチャカチャカと歩いていた。この野郎(笑)!。また、アメリカのネイティブインディアン2~30人に、日本人のサポートやはり2~30人(日本山妙法寺の坊さんも含む)総勢5~60人が本堂に宿泊した時があった。その時はその時で、ネイティブインディアンは、裸足で家の外と内を出入りしていた。この野郎(笑)!
「本堂に国境はない」でした。けど閻魔大王はいる、でした。

長い動画です。適当に選んで観て下さい。
お寺って・・・・・?
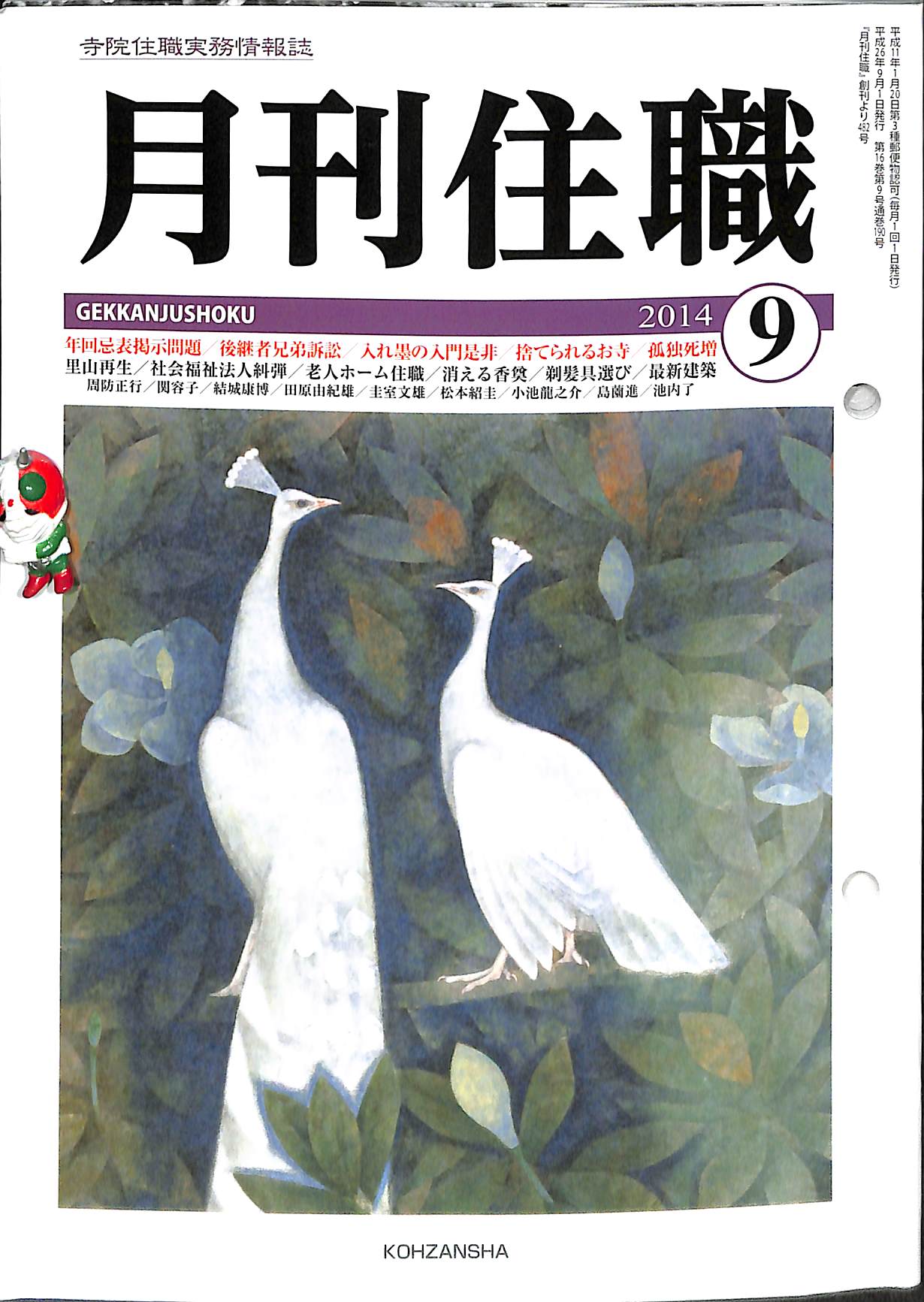
この様な雑誌がある。知ってる人は知っている、業界紙である。とはいっても、どこかの宗派が発行しているわけではなく、色々な宗派の寺院を取り上げる、仏教界の情報誌である。ゴシップあり、住職の生き方ありの色々な記事が載っている。それなりに多い記事は,やはりゴシップである。
そんな雑誌に次のような記事が載った。

このページから8ページにもわたっていて、それぞれの言い分(それぞれに味方する門徒の意見も含め)が掲載されている。この盛岡・真宗大谷派本誓寺とは、何を隠そう我が寺の隣の寺である。

地方の街で暮らしている一介の坊主から見れば、曲がりなりにも全国誌である仏教業界誌に掲載されたことは一大事件でもある。掲載された内容は兎も角、掲載されたと云うことにビックリである。誰がかがチクったのか?はたまた、変な匂いを嗅ぎ付けたのか?わざわざ記者が東京より駆けつけ取材をしたんだろうねぇ・・・。
掲載記事の内容は、大きなお寺にはよくある話の後継者争いで、それが裁判沙汰にまでなっている。と、云う記事である。ほんと!まあー良くある話で、隣近所に住まってる者から見れば、証言も含め胡散臭い記事内容である。
なぜお寺を継ぎたいのか?なぜお寺に住まいしているのか?なぜ住みたいのか、それがハッキリしない。ただ自分たちは、檀家が1000軒近くもある、大寺院に住まっているという、自意識過剰がそうさせているだけである。
いずれ、これも弱小寺院に住まっている者の偏見か!!!!。
掲載記事も、それなりの事実関係は押さえてあるのかもしれないが、薄っぺらで含みのない記事である。なぜなら、成る可くして成ってしまった後継者問題である。なぜ,その様な問題が起ったのか?端から見ていると、起るのは当たり前でしょ~である。つまり、歴史的過程が見えない記事である。大げさか?では言葉を変えよう、日々の暮らし振りが感ぜられない記事である。

いずれ、お寺あるいはそこに住まっている人は、それなりに檀家を含め地域の人々から、ある意味好奇の目で見られている。庶民的好奇心である。これは以外と馬鹿に出来ない、祭り上げられたり落とされたりである。文字通り風評である。ただそれが、直接の利害に関わってくるものでないだけによけい厄介である。
「大きくて立派な本堂で・・・」「歴史があるんでしょう・・・・」「檀家さんは多いのでしょう・・・」「1000軒位はあるみたいで・・・」その寺を取り巻く環境でそのように囁かれる。その様な囁きは、ある意味どうでもいいし無責任なものでもある。が、その渦中に住まってきた者、住まっている者にとっては、必要以上に気になってくるものでる。それ以外にも、お寺は仏教の教えも抱え込まざるを得ない。それは「坊さんらしい,お坊さん・・・」「お説教も上手だし、わかりやすい・・・」というようなことまで気を使わなければならないのである。下世話な風評と、仏教的布教者のダブルバインド(二重拘束)である。これは寺に住まっている者のメンタリティーでもあるのか?

これはしんどいのではないのかなぁ~、大きな寺になればなるほど・・・・に。
その様な囁きの渦中に住まったいる者は、日々の暮らしの中で「~らしければよい」が培われ、それがそのまま寺で住まっている者の,生活のスタイルになってくし、それが知らず知らずの内に生活習慣にもなる。それは虚栄と名利心にしがみ付かざるを得ないし、虚栄の寺にならざるを得ない。
ヤバイ!ヤバい!
「本堂のメリークリスマス」と題してコンサートを始めて三年目になる。教(おしえ)の原理原則から云えば、全く罰当たりな企画でもある。
お寺の本堂でのクリスマスコンサート、背後にはご本尊の阿弥陀様が控えている。クリスマスとは、イエス・キリストの降誕の日でもある。その場は、神の子と仏がイメージとして混在する空間でもある。利害抜きで神の子と仏が同席する空間でもあるし、その様な場でもある。ある意味、和洋折衷的適当な空間でもある。
教えの原理原則が生み出されてくる場、それが「混々沌々」と云う空間でもある。その様な空間から改めて「精神の共和国」の可能性を考えてみる。ひょっとすると、その様な空間に自由な時が現れるかもしれない?
いずれ、適当な話でもあり、いい加減な企画でもある。

来場下さい!
葬儀とは何だろう?またまた本題から話がそれる。チョット寄り道を・・・・・。
まあー多少は関係のない話ではないのだが。
葬送儀礼は人間的営みである。人間以外の生き物は、葬儀もしないし、墓も持たない。葬式は人間に固有な営みである。そこに、人間の悲喜劇が生まれる。葬式は死から始まる。ある意味突然に!・・・・・である。
もともと死は誕生と同時に、我々の日々の暮らしに潜在している。それが日々の暮らしの中に、突然死が露出してくる。むろん、日々の暮らしの中ではあまり死の事等、考えたくもないし考えようともしない。「縁起でもない」である。死とはやはり負(マイナス)なのか?これは死に対する観念なのか?いずれ、人間は死と死の観念を持つのは必然のようである。そこにはやはり色々なドラマが生まれてくる。
通夜、葬式、葬儀屋をシチュエーションとした映画が結構ある。ある落語家の死から、その通夜での出来事をドラマにした映画「寝ずの番」、またそのものズバリの題名の映画「お葬式」そしてアカデミー外国映画賞に輝いた映画「おくりびと」とやはり、けっこうある。また、有名な黒澤明監督の映画「生きる」にも確か主人公が癌で死んで、その通夜の席が重要なシチュエーションにもなっていた。
ヒューマンドラマであり、悲喜交々の人間模様のドラマであり、それぞれが面白い映画でもあった。


映画「お葬式」予告編
映画「おくりびと」予告編











