OLYMPUS E-PM2[1]と遊星號[2,3]用い、金星[4]の直焦点撮影を試みた[5]。

2020-04-07 20:56 金星(等級:-4.4、視半径:13.8")[6]
OLYMPUS E-PM2, 遊星號 800mm F16[2]
Sモード、ISO400, 800mm x2(デジタルテレコン), F16, 1/400 sec, MF, 太陽光

2020-04-07 20:56 金星(等級:-4.4、視半径:13.8")[6]
OLYMPUS E-PM2, 遊星號 800mm F16[2]
Sモード、ISO400, 800mm x2(デジタルテレコン), F16, 1/400 sec, MF, 太陽光
※iPhotoでトリミング
・対物レンズ口径:50mm
・ドーズの分解能:2.32"[7]
・イメージセンサ分解能:1.93"相当[7]
(イメージセンサ画素ピッチ:3.74μm[7])
遊星號のように、F値[8]が大きなアクロマート鏡筒[11]は、アポクロマート鏡筒[12]なみの色収差[9,10]に抑えることができるようだ(「2.4Dの経験則」と言うようである)[13-17]。
しかしながら、今回、遊星號で撮影した金星では、前回コルキットスピカ[18-19](コルキットスピカも「2.4Dの経験則」を満たしている)で撮影した金星と比較すると、若干ではあるが色収差が目立つ結果となった。
参考文献:
(1)OLYMPUS PEN mini E-PM2 主な仕様
(2)アメリカン!遊星號(三脚台座1/4雌ネジ付)
(3)スターライト・コーポレーション-Wikipedia
(4)金星-Wikipedia
(5)OLYMPUS E-PM2と遊星號を用いた直焦点撮影-goo blog
(6)今日のほしぞら-国立天文台暦計算室
(7)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog
(8)F値-Wikipedia
(9)収差-Wikipedia
(10)色収差-Wikipedia
(11)アクロマート-Wikipedia
(12)アポクロマート-Wikipedia
(13)天体撮影可能なアクロマート鏡筒
(14)やっぱり色収差が出まくりでした 2010/10/05
(15)5cmF14屈折望遠鏡……小型望遠鏡を楽しく使う方法を考える…… (現在進行中)
(16)口径60mm双眼望遠鏡 その1
(17)アストロ R-70型 その2
(18)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(5)-goo blog
(19)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(8)-goo blog

2020-04-07 20:56 金星(等級:-4.4、視半径:13.8")[6]
OLYMPUS E-PM2, 遊星號 800mm F16[2]
Sモード、ISO400, 800mm x2(デジタルテレコン), F16, 1/400 sec, MF, 太陽光

2020-04-07 20:56 金星(等級:-4.4、視半径:13.8")[6]
OLYMPUS E-PM2, 遊星號 800mm F16[2]
Sモード、ISO400, 800mm x2(デジタルテレコン), F16, 1/400 sec, MF, 太陽光
※iPhotoでトリミング
・対物レンズ口径:50mm
・ドーズの分解能:2.32"[7]
・イメージセンサ分解能:1.93"相当[7]
(イメージセンサ画素ピッチ:3.74μm[7])
遊星號のように、F値[8]が大きなアクロマート鏡筒[11]は、アポクロマート鏡筒[12]なみの色収差[9,10]に抑えることができるようだ(「2.4Dの経験則」と言うようである)[13-17]。
しかしながら、今回、遊星號で撮影した金星では、前回コルキットスピカ[18-19](コルキットスピカも「2.4Dの経験則」を満たしている)で撮影した金星と比較すると、若干ではあるが色収差が目立つ結果となった。
参考文献:
(1)OLYMPUS PEN mini E-PM2 主な仕様
(2)アメリカン!遊星號(三脚台座1/4雌ネジ付)
(3)スターライト・コーポレーション-Wikipedia
(4)金星-Wikipedia
(5)OLYMPUS E-PM2と遊星號を用いた直焦点撮影-goo blog
(6)今日のほしぞら-国立天文台暦計算室
(7)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog
(8)F値-Wikipedia
(9)収差-Wikipedia
(10)色収差-Wikipedia
(11)アクロマート-Wikipedia
(12)アポクロマート-Wikipedia
(13)天体撮影可能なアクロマート鏡筒
(14)やっぱり色収差が出まくりでした 2010/10/05
(15)5cmF14屈折望遠鏡……小型望遠鏡を楽しく使う方法を考える…… (現在進行中)
(16)口径60mm双眼望遠鏡 その1
(17)アストロ R-70型 その2
(18)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(5)-goo blog
(19)OLYMPUS E-PM2とコルキットスピカを用いた直焦点撮影(8)-goo blog











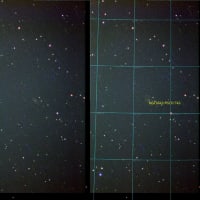














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます