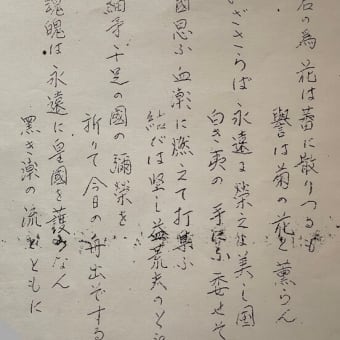57.極東軍事裁判判決
裁判の審理は昭和23年4月16日に終了した。
これまでに法廷に喚問された証人は419人、口供書提出者779人、開かれた法廷回数は800回を超えていた。
審査終了し判決書が作成された。
その翻訳作業は東京芝白金の服部時計店の邸宅ハットリハウスで行われた。
東大教授横田喜三郎を中心とする翻訳者、速記者、タイピスト達は外部に判決が漏れるのを防ぐため、一歩もハウスの外に出ることを許されなかった。
横田喜三郎
法学者。昭和56年(1981年)文化勲章受章
昭和24年(1949年)の著書『天皇制』などにおいて、積極的な天皇制否定論を提唱していた。
しかし昭和35年(1960年)最高裁長官など政府高官に就任すると、過去の天皇制否定論を自身の地位の都合の悪いものとして隠蔽するようになる。
特に、東京中の古本屋を回って著書『天皇制』を買い集め、自分のかつての天皇否定論の痕跡を消そうとしたのは有名な話である。

昭和23年11月4日(木)法廷は七ヶ月ぶりに再開され、判決が下されることになった。
判決本文は,英文で1,200ページに及ぶ膨大なものであり、10章に亘る判決文章の朗読は週末の休廷を含めて約 1週間を要した。
その判決は、裁判所憲章は裁判所にとって絶対であり法廷を拘束する、「平和に対する罪」「人道に対する罪」は「事後法」によるものではなく、現行国際法を明文化したものであるとし、弁護側の主張を殆ど取り入れず、裁判の冒頭に問題とされた、この裁判の管轄権についても、ニュールンベルグの判例を根拠に簡単に裁定を下していた。
裁判長は判決に当たり判事団の中に少数意見があったことを述べた。
極東軍事裁判所条例は、これ等少数意見の内容を法廷で朗読するよう定めており、弁護側はこれを実行するよう求めたが、裁判長はこれが長文であり、朗読に数日要するとの理由で却下した。
少数意見は5名の判事によるものであった。
<極東軍裁判判事 前列中央がウエッブ裁判長>

57.1.判決朗読
昭和23年11月4日(木)判決が下された。

9時30分に裁判が開廷し裁判長が判決文の朗読を始めた。
判決文はA、B、Cで構成され、朗読は7日間続き、終了したのは11月12日だった。
<裁判判決文の構成>
A部
第一章 本裁判所の設立及び審理
第ニ章 法
(イ)本裁判所の管轄権
(ロ)捕虜に関する戦争免罪の責任
(ハ)起訴状
第三章 日本の負担した義務及び取得した権利
B部
第四章 軍部による日本支配と戦争準備
第五章
第一節 満州への侵入と占領
第二節 満州統一と開発
第三節 中国にさらに進出する計画
第四節 盧溝橋事件
第五節 華北の臨時政府
第六節 大東亜共栄圏
第七節 満州と中国の他の地域とに対する日本の経済支配
第六章 ソビエト連邦に対する日本の侵略
第七章 太平洋戦争
第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為)
C部
第九章 起訴状の訴因について(*1)
第十章 判定
(*1)
裁判の訴因は最終的に10項目に纏められ、これについての裁判となった。
(訴因番号は全部で55項目あり、このうちの次の10項目以外は他の訴因と重複するとの理由により除外された)
(1) 侵略戦争遂行の共同謀議(*)
(27) 対中国侵略戦争遂行
(29) 対米侵略戦争遂行
(31) 対英侵略戦争遂行
(32) 対蘭侵略戦争遂行
(33) 対仏侵略戦争遂行
(35) 張鼓峰事件遂行
(36) ノモンハン事件遂行
(54) 違反行為の命令、授権、許可による法規違犯
(55) 違犯行為防止責任無視による法規違犯
57.2.裁判の管轄権
裁判の冒頭に弁護人から問題とされた、この裁判の管轄権などの違法性についてはウエッブ裁判長は、弁護人からの動議は総て却下されたと申し渡し、理由は将来宣告するとしていた。
この件に関して、判決文では第二章の中で次のように述べた。
少し長いが、この部分を次に載せる。
A部 第二章 法
我々の意見では、裁判所条例の法は、本裁判所にとって決定的であり、これを拘束するものである。
本裁判所は、最高司令官が連合国から与えられた権能に基いて設置した特別な裁判所である。
その管轄権の根拠は裁判所条例にある。
この裁判では、裁判所条例の中にあるものを除いては、裁判官はどのような管轄権ももっていない。
本裁判所の裁判官を任命した最高司令官の命令は、次のように述べている。『本裁判所の裁判官の責任、権力及び任務は同裁判所条例に規定せられあり・・・・・・』。
その結果として、もし右のようなことがなければ、本裁判所の裁判官は、被告の裁判に関して、まつたく権限をもっていないのであるが、本裁判所を構成し、かれらを裁判官として任命した文書によって、被告を裁判する権限を与えられたのである。
ただし、いかなる場合にも、裁判所条例に定められた法を裁判に適用するという義務と責任の下に常に立たされている。
右に選べた意見は、つぎに述べるような見解が主張されることがあるとしても、その見解か支持するものと解釈してはならない。
その見解というのは、連合国またはどの戦勝国でも、戦争犯罪人の裁判と処罰について規定するにあたって、確立した国際法またはその規則もしくは原則と矛盾する法律を制定または公布したり、それらと矛盾する権限を自国の裁判所に与えたりする権利を国際法上でもっているという見解である。
このような戦争犯罪人の裁判と処罰という目的のために、裁判所を創設する権利を行使し、その裁判所に権限を与えるにあたって、交戦国は国際法の範用内で行動することができるにすぎないのである。
起訴状に含まれている起訴事実を審理し、判決を下す本裁判所の管轄権に対して、弁護側が抗弁したおもな理由は次の通りである。
(一)連合国は、最高司令官を通じて、『平和に対する罪』(第五条イ)を裁判所条例に含め、これを裁判に付し得るものと指定する権能をもっていない。
(二)侵略戦争はそれ自体として不法なものではなく、国家的政策の手段としての戦争を放棄した一九二八年のパリ条約は、戦争犯罪の意味を拡げてもいないし、戦争を犯罪であるとしてもいない。
(三) 戦争は国家の行為であり、それに対して、国際法上で個人的資任はない。
(四)裁判所例の規定は、『事後』法であり、従って不法である。
(五)ポツダム宜言の実施を定めている降伏文書は、この宣言の当時(一九四五年七月二十六日)の国際法によって認められていた通例の戦争犯罪だけが訴追される半罪であるという条件を課している。
(六)交戦中の殺害行為は、交戦法規または戦争の法規慣例の違反を構成する場合を除いて、戦争に通常伴うものであって、殺人ではない。
(七)被告のうちの数名は捕虜であるから、一九二九年のジュネーブ条約の規定に従って、軍法会議で裁判することはできるが、本裁判所で裁判することはできない。
「裁判所条例の法は、本裁判所にとって決定的であり、これを拘束するものであるから、弁護側が申立てた右の七つの主張のうちで、初めの四つについては、本裁判所はこれを却下すべき形式上の拘束を受けている。
しかし、これに関連する法の諸問題が非常に重要であることにかんがみ、本裁所は、これらの問題に関する裁判所の意見を記録しておく。
一九四六年五月に、裁判所は、この弁護側の申し立てを却下し、裁判所条例の効力とそれに基づく裁判所の管轄権とを確認し、この決定の理由は後に申渡すであろうと述べたが、その後に、ニュールンベルグで開かれた国際軍事裁判所は、一九四六年十月一日に、その判決を下した。
同裁判所は、他のことと共に次の意見を発表した。
『裁判所条例は、戦勝の側で権力を恣意的に行使したものではなく、その制定の当時に存在していた国際法を表示したものである。』
『問題は、この条約(一九二八年八月二十七日のパリ条約)の法的効果は何であったかということである。この条約に調印し、またはこれに加わった諸国は、政策の手段として戦争に訴えることを将来に向って無条件に不法であるとし、明示的にそれを放棄した。この条約に調印した後は、国家的政策の手段として戦争に訴える国は、どの国でも、この条約に違反するのである。
本裁判所の意見では、国家的政策の手段としての戦争を厳粛に放棄したことは、必然的に次の命題を含蓄するものである。その命題というのは、このような戦争は国際法上で不法であるということ、避けることのできない、恐ろしい結果を伴うところの、このような戦争を計画し、遂行する者は、それをすることにおいて犯罪を行いつつあるのだということである。』
『ある事情のもとでは、国家の代表者を保護する国際法の原則は、国際法によって犯罪的なものとして不法化されている行為には、適用することができない。これらの行為を行った者は、適当な裁判による処罰を免れるために、公職の陰にかくれることはできない。』
『「法なければ処罪なし」という法律格言は、主権を制限するものではなく、一般的な正義の原則である。条約や誓約を無視して、警告なしに、隣接国を攻撃した者を処罰するのは不当であると主張することは、明らかに間違っている。なぜなら、このような事情のもとでは、攻撃者は自分が不法なことをしていることを知っているはずであり、従って、かれを処罰することは、不当であるどころでなく、もしかれの不法行為が罰せられないですまされるならば、それこそ不当なのである。』
『裁判所条例は次のように明確に規定している。・・「被告人が自己の政府又は上司の命令に従い行動せる事実は被告人をして責任を免れしむるものにあらず。但し刑の軽減の為考慮することを得。」この規定は、すべての国の法と一致している。…程度は色々であるが、大多数の国の刑事法の中に見られる真の基準は、命令の存在ということではなく、事実において心理上の選択が可能であったかどうかということである。』
ニュールンベルグ裁判所の以上の意見とその意見に到達するにあたっての推論に、本裁判所は完全に同意する。
これらの意見は、先に挙げたところの、弁護側の強調した理由の初めの四つに対して、完全な答えを表わすものである。
本裁判所とニュールンベルグ裁判所との条例が、重要な点において、すべて同一であることに鑑み、本裁判所は、ニュールンベルグ裁判所の意見であって本件に関連のあるものには、無条件の賛意を表するものである。
いくらか違った言葉で問題を新たに論じ、そのために、両裁判所の述べた意見について抵触する解釈が行われるようになつて、論争の起る途を開くよりは、その方がよいと考える。
本裁判所の管轄権を弁護側が争つた第五の理由は、降伏文書とポツダム宣言によれば、裁判を行うべきものと考えられていた犯罪は、ポツダム宣言の当時の国際法によって認められていた戦争犯罪だけであるから、それは裁判所条例の第五条(ロ)に遠べられている通例の戦争犯罪だけであるというのである。
侵略戦争は、ポツダム宜言の当時よりずっと前から、国際法上の犯罪であったのであったと、弁護側が裁所条例に与えようと試みている限定された解釈をする根拠は全然ない。
いずれにしても、日本政府が降伏文書の条項を受諾することに同意したときには、戦争に対して責任があるといわれていた日本人が訴追されるということは、実際において日本政府が了解していなかつたという、特別な議論が申立てられた。
この議論には、実際においてなんの基礎もない。本裁判所が満足と認める程度に立証されたところによれば、降伏文害に調印する前に、問題の点はすでに日本政府によって考慮されていたのであり、降伏文書の受諾を唱えた当時の閣僚は、戦争に対して責任があるといわれた者が裁判に付せられるであろうということを予想していたのである。
早くも一九四五年八月十日に、すなわち、降伏文書の調印よりも三週間前に、天皇は被告木戸に対して、『戦争責任者の処罰・・・・・・を思うと恐び難いものがある・・・・・・而し今日は忍び難きを忍ばねばならぬ時と思う』といった。
弁護側の第六の主張、すなわち、殺人を行ったという起訴事実に関する主張は、後に論ずることにする。
これらの主張の第七は、捕虜として降伏した四名の被告、すなわち、板垣、木村、武藤及び佐藤のために行われている。
彼らのために行われた申し立ては、彼らはもと日本の軍隊に属していた者であり、また捕虜であるから、捕虜に関する一九二九年のジュネーヴ条約の条分、特に第六十条と第六十三条に従って、捕虜として軍法会議で裁判し得るものであって、この条約に基かないで構成された裁判所では、裁判し得ないというのである。
この点こそ、山下事件において、アメリカ合衆国最高裁判所が決定したところである。
故ストーン最高裁判所長官は、この裁判所の多数を代表して判決を言い渡すにあたって、次のようにいった。
『以上に挙げた諸規定の文章のかかり具合からして、第三節とそれに含まれている第六十三条とは、捕虜である間に犯した罪について、捕虜に対して行われる裁判手続だけに適用されるものであることが明らかであると我々は考える。
この部分が第三章の第一節と第二節に言及されているもの以外の罪を取扱うものとして定められているということは、第五款には少しも示されていない。』この結論とこの結論に到達するにあたっての推論に、本裁判所は敬意をもって同意するものである。
本裁判所の管轄権を奪うことは、まったく成立しない。
次回は起訴状の訴因についての認定、刑の宣告、そして判事の少数意見の概要について記載する。
<続く>