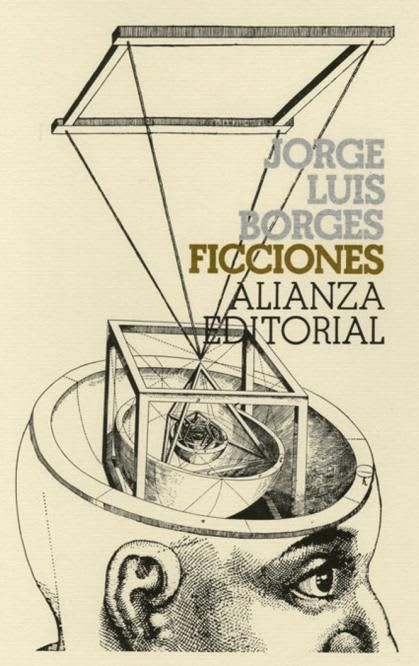この短編の第二部では、語り手が、1937年にアルゼンチンで死んだ英国人ハーバート・アッシュが残したトレーン第一百科事典(オルヴィス・テルティウスという印が押されている)の11巻に基づいて、空想世界トレーンにおける現実知覚の実態を描きだす。この11巻は1001ページもある。語り手はとにかく要約が好きな人なのだ。また、11巻ということは10巻や12巻もあるはずで、これについてはマルティネス・エストラーダのような実在する作家が想像を巡らせているような記述があり、アルフォンソ・レイエスが「いっそのこと残りの巻はみんなでつくったらどうか」と持ち掛けるというジョークまで。エクス・ウングエ・レオネム、細部を見れば全体が想像できるはず、という信念に基づいて……とあって、本書の序文で「すっかり口述するのにわずか数分しかかからないことに500ページを費やす」ことを desvarío laborioso y empobrecedor(困難で疲弊させられる愚行)と呼ぶなど、世の大長編作家を馬鹿にし続けていたボルヘスらしい、ウィットに富んだ挿話と言えるが、いっぽうで百科事典という現実の「縮小版コピー」をつい夢想してしまう文系人間、というよりスペイン語世界で伝統の長い《文献学》のエートスをちらりとユーモラスにのぞかせてもいる。
いったいこの百科事典を編纂したのは誰なのか。答は第三部で明らかにされるだろう。語り手はこのトレーンの concepto del universo (宇宙に関する概念)について説明すると述べ、いよいよ核心部に入っていく。
トレーンの人々はバークリー流の観念論(idealismo)を徹底して実践している。それを集約しているのがこの文章だろう。El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial.(26)<彼らにとっての世界とは空間にある一連の事物ではなく、独立した行為の不均質な連続だ。連続的、時間的で、空間的ではない。>先で具体例が示されいるので読めばわかるが、敢えてここだけを考えてみると、トレーンでは一定の時空という制限内にある一観測者の知覚したことのみが現実とみなされる。観測者Aの知覚した現実もあれば、観測者Bの知覚した現実もあり、いっぽう仮説のレベルでも存在し得ないのはAにもBにも同じ不動の月、いわば一種「あらゆる人間にとっての均質的な月 luna homogénea para todos」という不思議な現象ということになる。私たちは un concurso de objetos(一連のモノ、モノの同時的存在)があって世界が成り立っていると考えている。地球、月、木、蟻、職場、職場の同僚等々。ところがトレーンでは世界とは「各自のなかに知覚として立ち上がる何か」にすぎないので、Aが見た月とBが見た月とを架橋する思考回路が成立しない。すべては異なる観測者による「行為の異質な連続」、すなわち無限に増殖するすべてが異質な知覚のひとつとみなされてしまう。だからこそ、万人が等しく客観として受容する対象を示す語、すなわち名詞が、トレーンの少なくとも祖語には存在しなかった。月という一般名詞は存在せず、観測者の前で刻一刻と移ろいゆく時間的現象を表現する「名詞以外の語」しかそこにはない。そして現在のトレーンでは文学が名詞をつくれば、そこに新たな現実が生まれるという、詩人にとって夢のような世界になっている。指示対象の実在を誰も信じないから、名詞が無限に生まれてくるという皮肉な事態が起きている。
このような、客体という次元の措定そのものを放棄した究極の主観世界論が強く働く状況というと、多くの人は、文学などイマジネーションを用いた表現行為の創造的可能性と、現実の世界で進行している、たとえばネット上のフェイク言説のような真実の存在を否定する(もしくは信じない)ニヒリズムという、よく似ているけれど方向はまるで違う二つの現象を連想するだろう。
トレーン語をスペイン語に置き換えた「月する」に類するくだりを読んでいたとき、私はボルヘスと同時代か少し前にラプラタ川の両岸で奇妙な人生を送っていた(これは過去完了形)二人の詩人を思い浮かべた。ひとりはレオポルド・ルゴーネスで彼には実際に月をテーマにした詩があり、読み返してみると、それは名詞にあふれた、少し都会的なアイロニーに彩られた、非常に繊細な作品で、私がなんとなく勝手に記憶していた準アヴァンギャルドとは程遠かった。ルゴーネスは生き方のほうがアヴァンギャルドだったかもしれない。
もうひとりはウルグアイのフリオ・エレラ・イ・レイシグで、後期モデルニスモ(スペイン語では post modernismo というがこれは英語のポストモダニズムの語源でも何でもないのだ、とフレドリック・ジェイムソンが困惑気味に書いていたのを思い出す)という、モデルニスモの軽佻浮薄路線を加速したような、グラムロックが退廃してヘヴィメタ化したようなスタイルを代表する人で、若い頃のセサル・バジェホが模倣していたので私も昔よく読んだ。さっそくアギラールの全集を開けてみたところ、彼もやはり名詞だらけのソネットを書きまくっていて、どうも人の記憶とはあてにならないものである。バジェホは各品詞だけを20個ずつまとめたみたいな詩を書いているが、その種の詩的実験はボルヘスがこの本を書いていた時に同時進行していたものだ。アッシュが死んだ1937年にバジェホが推敲を加えていた詩(のタイプ原稿と直筆の訂正や注解)を見ていると、彼が客体、すなわち詩的言語の指示対象をページからいかに抹消しようと苦労していたかがわかって興味深い。客体から自立した詩的言語、これは象徴主義以降の横文字詩人たちが人生のどこかで一度は抱いた夢想だった。ボルヘスはその種の冒険から次第に遠ざかっていくのだが、ロベルト・ボラーニョが若き日の詩的愚行を共にした世界の果てのマイナーポエットたちにこだわり続けたように、ボルヘスにもそうした20世紀型の詩的冒険を懲りずに試み続けた奇妙な人々への愛着の念があったのかもしれない。同時代人として。これについては「ドン・キホーテの著者、ピエール・メナール」で考えてみることにしよう。
客体が主観の下位に来るトレーンでは、当然ながら科学は成立しない。
<スピノザは外延と思考の属性をその尽きることない神性に帰しているが、トレーンでは(ある種の状態の典型にすぎない)外延と思考――宇宙の完全なる同義語――の並置を理解できないだろう。他の言葉で言えば、彼らは空間的なものが時間のなかで持続するとは考えない。地平線に煙を、次に草原の炎を、次にその炎を生んだ消し忘れの煙草を看取することは、観念の結びつきの例とみなされる。
このような一元論あるいは完全な観念論は科学を無効化する。ある事実を説明する(か判断する)というのはそれを別の事実に結び付けることだが、そのような結合は、トレーンにおいては、ものの事前の状態に影響を与えたり光を当てたりすることはあり得ない事後の状態である。精神状態とはすべからく分割不能なもので、それを名付けること――すなわち分類すること――は捏造を持ちこむ。(28-29)>
いや、それのどこが捏造なの?と思ってしまうわけだが、仮に地球上の全個人の主観による知覚が「宇宙の同義語」であるのなら、自分を宇宙並みに過大評価しているどこかの国の指導者が「選挙に不正があった」と彼の脳内現実を言い立てても、それは「選挙は公正に行われた客観的事実による修正」を受け付けない、すなわちまさに irreductible (分割不能)なものだから、彼的には捏造を(彼の)現実に持ち込むことになってしまう。客観的事実の措定が共有されない場に科学は存在し得ない。なんだかトレーンではなくてこの地球の話みたいになってきましたね。
スピノザに言われずとも、外延(概念が適用される事実の集合体)も思考(一度きりの生を生きる人間の主観)も共に神聖なもの、侵すべからざる領域であり、私たちはそれを知っているから科学も学べば絵や文学も愛する。しかしトレーンにはこの二つの領域を併存させるという発想がない。
いやですよね、そんな社会。
科学がないのはともかく、正義もなさそうで。
<形而上学者が真実や真実的なものすら探求せず、驚異を探求する(29)>トレーンとは詩人たちのユートピアであり、同時に悪夢の支配するディストピアでもある。刊行当時から世界中の読者がそのようにこの短編の第二部を読んできたのだと思います。そして、なぜこんな小説がこの時代にアルゼンチンで書かれたのか。それについては第三部を読んで考えることにしたい。