記紀の国生み説話
ヤマトの名は、記紀の初めにある国生みの説話にすでに見られる。まず、天浮橋(天上浮橋)から天沼矛(天之瓊矛)を下して掻き混ぜ、潮が凝りて淤能碁呂島(磤馭廬嶋)となったところで、イザナキとイザナミが御合(遘合(共為夫婦・為夫婦・合為夫婦))をした。その結果、いくつかの島(洲)ができたなかの一つが、大倭豊秋津島(大日本豊秋津洲)であった。
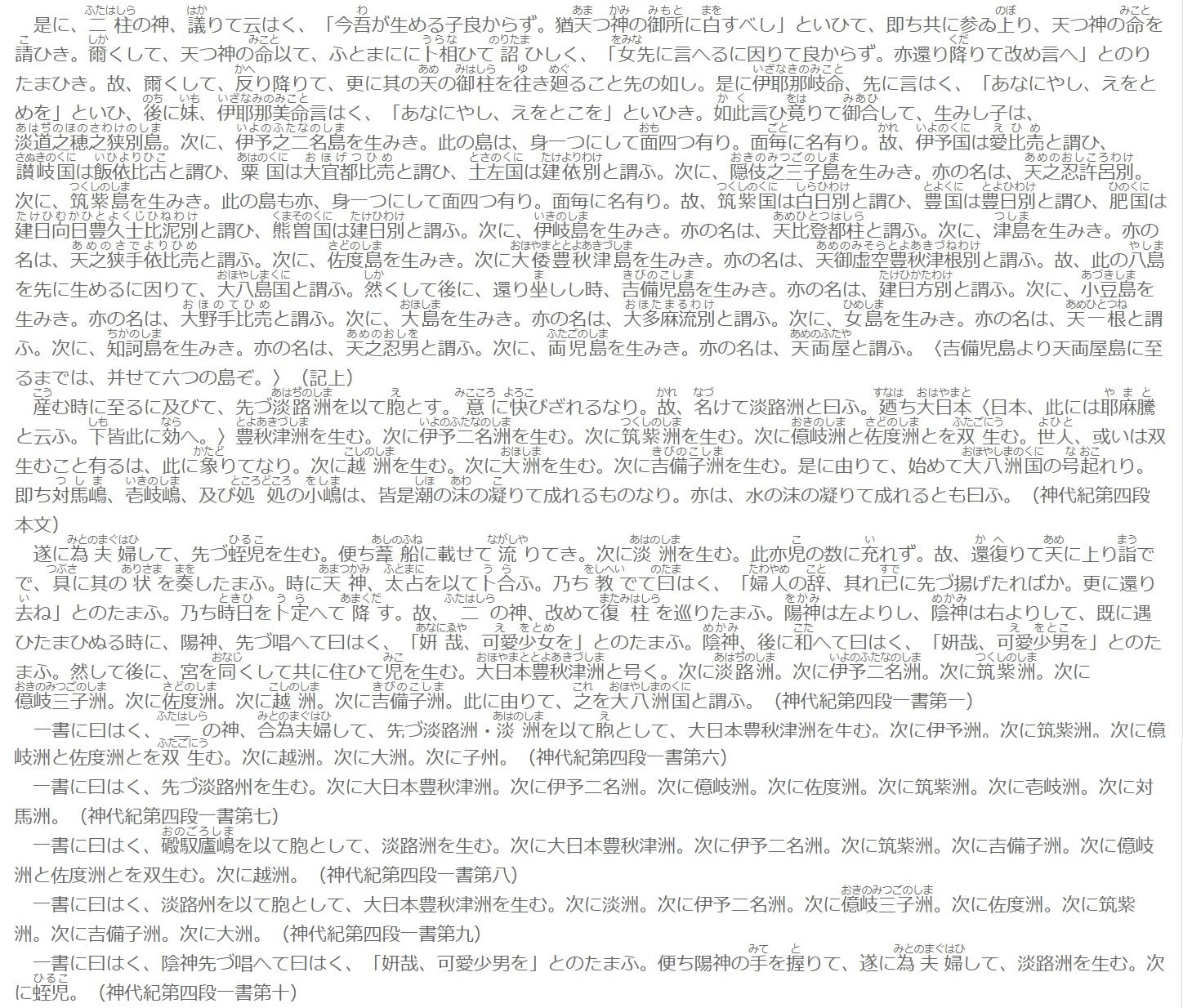
記では、それぞれの「島」について、亦の名の神名を記す。一方、紀では、「洲」の名を連ねるに止まる。記では、淡道之穂之狭別島、伊予之二名島、隠伎之三子島、筑紫島、伊岐島、津島、佐度島を生んでから大倭豊秋津島を生んでいる。以上から大八島国といったとする。その後、吉備児島、小豆島、大島、女島、知訶島、両児島を生んだとしている。紀本文では、「及二至産時一、先以二淡路洲一為レ胞。」とあり、すぐに大日本豊秋津洲を生んでいる。「胞」とは胞衣のことで、胎児をくるむ羊膜である。通常、臍帯などと同じく、後産として子の出たあとから娩出される。これらをすべて、胞衣と称するようになっている。胞が先に出てきて子が後から出て来ているのが問題で、順序が逆になっている。その後、伊予二名洲、筑紫洲、億岐洲、佐度洲、越洲、大洲、吉備子洲の順で生み、以上で大八洲国の名前ができたとする。淡路洲は胞だから大八洲の勘定に入れていない。また、対馬島、壱岐島とその他の諸々の島々は、みな潮の泡が凝り固まってできたものであるとしている。洲と島とを使い分け、厳密な表記を心掛けている。
紀一書第一では、胞の話はなく、大日本豊秋津洲、淡路洲の順で、大島が除かれて大八洲国としている。一書第二から一書第五までは国々の記載はなく、一書第六は、淡路洲・淡洲を胞として大日本豊秋津洲を生み、以下本文に同じである。一書第七は、淡路洲、大日本豊秋津洲、伊予二名洲、億岐洲、佐度洲、筑紫洲、壱岐洲、対馬洲の順である。一書第八になると、磤馭慮嶋が胞にされ、淡路洲を生み、次に大日本豊秋津洲、伊予二名洲、筑紫洲、吉備子洲、億岐洲、佐度洲である。一書第九では、淡路洲を胞として大日本豊秋津洲、その後に淡洲が登場し、伊予二名洲、億岐三子洲、佐度洲、筑紫洲、吉備子洲、大洲、一書第十では、淡路洲、蛭児を生んで終わっている。異同が多い点が、かえって厳密に記そうとしていた意図を伝えることになっている。
アハヂの謎(虻蜂取らず・蜘蛛の子を散らす)
生まれる順として、淡路島を出発点に、本州から四国、九州、日本海側、瀬戸内海へと回るか、四国の次に隠岐、佐渡があって九州が後回しにされるか、記のように本州が大八島国の最後になるかいろいろである。紀に見られる「胞」は、国が生まれるときの梃子として効いており、淡路島がキーになっている。紀本文に「意所レ不レ快。故、名之曰二淡路洲一。」とある。何が気に入らなかったのか、また、アハヂという名がどうして不快を表す名に値するのか。大系本日本書紀に、「第一子は産みそこないをするという当時の伝承がある通り、その第一子は生みそこないであったので、その第一子にアハヂ(吾恥)の島と名づけたという意(これはアハヂ島という、当時すでに存在していた島の名の地名起源説話の一つがここにからんだもの)。意に満たないので、この島は、おそらく流し捨てたのであろう。ここでは淡路州は大八洲の数に入っていない。この部分は古事記のヒルコの話に相当する。」((一)331頁)とある。新編全集本日本書紀には、それに加えて、「あるいは軽蔑する意の「淡あはむ」をかけたか。」(①27頁)ともある。淡路島はヒルコと違って流されずに現在も大きく存在する。国生みの話は、記、紀本文、一書第一~第十まであるが、一書の第二以降は大雑把で噺のレベルに達しておらず、説話として体を成しているのは、記、紀本文および一書第一だけであり、紀本文にのみ、何食わぬ顔で淡路島の悪口が書かれている。
大系本にいうとおり、すでに存在していた地名に託けた地名譚であろう。先に阿波という地名があり、それに引きずられてできたであろう淡路という地名があった。そのアハヂという地名にからんで説話が創られている。そして、後先かまわず胞が先に出てきていることから、ちぐはぐさを感じさせる内容を表しているものと考えられる。おそらくこれは、諺の「虻蜂取らず」の訛った形の頓知であろう。虻蜂取らずとは、どっちつかずや中途半端なことの譬えに用いられている。abu+fati→afadi である。自ら張った巣の中央にクモがおり、巣の対角線上にアブとハチとが同時にかかった。両者ともクモにとっては獲物として大物で魅力的だが力も強い。クモは、どちらを捕ろうかと迷っているうちにどちらも捕れないまま逃げられてしまう(注1)。すなわち、畿内にある朝廷は、西方からの侵入者に対し、明石、鳴門の両海峡を防ごうとして、淡路島の真ん中に城を一つ構えて守ろうとしたが叶わなかった。それを虻蜂取らずの淡路島と洒落ている。
クモの巣は高いところできらきらしている。移動に際して糸を伸ばして風に乗り、海を越える種もあるという。それを糸遊と呼ぶ。3~7mmの成体のクモが細い糸を吐き、風に乗って移動する現象である(注2)。ただし、一般に糸遊といえば陽炎のことを指す。現象としてはいずれもぼやぼやっとしてちらちらっと目に映る。漢語の「遊糸」は、梁の簡文帝の詩賦などに見えており、芸文類聚にいくつも例が載る。本邦では和漢朗詠集や菅家文章にも見え、また、和訳して「糸遊」という語も作られている。空海は仏典に拠って「陽燄」の語を用いており、陽炎と遊糸がイメージのなかで混同しているとも考えられている。平安朝の仮名文学においても、「かげろふ」はほのかな光の揺らぎ、光ってはかげり、かげっては光る心もとない現象として想起され、人の世やわが身のはかなさの譬えとして表現されている。
 糸遊イメージ(National Geographic「How Spiders Use Electricity to Fly | Decoder」https://www.youtube.com/watch?v=Ja4oMFOoK50。The New York Times「How Spiders Use Silk to Fly | ScienceTake」https://www.youtube.com/watch?v=VDL9VxLqdvw参照)
糸遊イメージ(National Geographic「How Spiders Use Electricity to Fly | Decoder」https://www.youtube.com/watch?v=Ja4oMFOoK50。The New York Times「How Spiders Use Silk to Fly | ScienceTake」https://www.youtube.com/watch?v=VDL9VxLqdvw参照)
秋津島は淡路島を胞として出てきた。淡路島は、古代以来、一つの島で一つの国、淡路国を形作る。その胞を破って、蜘蛛の子を散らすような状態になった(注3)。ものすごい数のもじゃもじゃが現れた。一つの島(本州)にたくさんの国(近江、丹波、信濃、上総、出雲、伊勢、吉備、紀伊、伊豆、美濃、播磨、……)がある。淡路島と本州との間は明石海峡である。明石はタコが名産である。そのタコを特に蜘蛛蛸と呼んでいる。「蛸」の字は、中国ではアシタカグモのことを指し、巣を張らずに家にいてゴキブリなどを食べて生きている。そんな「蛸」に似た水中の昆虫といえば、トンボの幼虫、ヤゴである。


 左:アシタカグモ雌成虫(Jinn様「アシダカグモ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/アシダカグモ)、中:明石のタコ(松岡明芳様「明石市内の商業地区魚の棚で販売される明石ダコ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/明石ダコ)、右:コヤマトンボのヤゴ(Keisotyo様「ヤゴ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ヤゴ)
左:アシタカグモ雌成虫(Jinn様「アシダカグモ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/アシダカグモ)、中:明石のタコ(松岡明芳様「明石市内の商業地区魚の棚で販売される明石ダコ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/明石ダコ)、右:コヤマトンボのヤゴ(Keisotyo様「ヤゴ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ヤゴ)
成虫のトンボは空を飛び、糸遊のように高いところで羽根がきらきらしている。したがって、カゲロフである。透き通った羽根がぼやぼやっとちらちらっと見えるのは、縁紋と呼ばれるステンドグラスの鉛線のような筋が入っていて、模様となっているからである。
大倭豊秋津島(大日本豊秋津洲)の秋津とはトンボのことで、蜻蛉と記される。和名抄に、「蜻蛉 本草に云はく、蜻蛉〈精霊の二音〉は一名に胡〓〔勑冠に虫〕〈音は勅、加介呂布〉といふ。釈薬性に云はく、一名に蝍蛉〈上の音は即〉といふ。兼名苑に云はく、虰蛵〈丁香の二音〉は一名に胡蝶は蜻蛉なりといふ。」とある。「蜉蝣」とは、今いうカゲロウ目やウスバカゲロウのようなアミメカゲロウ目の昆虫だけでなく、トンボ一般のことを指した。そして、「陽炎」は、光がちらちらと揺れ動くように見える現象をいい、「かぎろひ(ギ・ロは甲類、ヒは乙類)」の転とされ、ヒは火の意である。万葉集では、炎・蜻火・蜻蜓火といった字を当てている(注4)。
万葉集中に、アキヅとして記される例は全部で21例である。内訳は、地名のアキヅが7例(「秋津」(万36・911・1368・1713)、「蜻蛉」(万907)、「飽津」(万926)、「蜻」(万3065))、地名のアキヅノが6例(「秋津野」(万693・1345・1406)、「蜻野」(万1405)、「蜓野(万2292・3179))、枕詞のアキヅシマが5例(「蜻嶋」(万2・3250・4254)、「秋津嶋」(万3333)、「安吉豆之萬」(万4465))、昆虫としてのアキヅが2例(「秋津羽」(万376)、「蜻領巾」(万3314))である。
秋津羽の 袖振る妹を 玉くしげ 奥に思ふを 見たまへ吾が君(万376)
…… たらちねの 母が形見と 吾が持てる まそみ鏡に 蜻領巾 負ひ並め持ちて 馬替へ吾が背(万3314)
「秋津羽の袖」は羅製の袖、「蜻領巾」はオーガンジーの領巾のことである。いずれも透けるだけでなく、トンボの羽根の縁紋のように模様が施されていて、きらきらと輝くものであったものと思われる。
トンボの羽根模様と秋津島
このように、アキヅが特別な言葉として扱われた理由は、国生みの説話と関係があるからであろう。トンボは秋になって成熟し、交尾できるようになると、その縁紋は左右の羽根でぴったり揃うようになる。交尾して産卵できるようになった証拠である。万376番歌は、題詞に「湯原王宴席歌二首」とある。女性が成長して高貴な皇子と婚約を発表した宴席に、湯原王が侍して祝った歌と思われる。トンボの縁紋を画に描くと、本州(大倭豊秋津島・大日本豊秋津洲)にたくさんの国のある様を描いた日本地図のようになる。
 大日本図(拾芥抄、慶長12年(1607)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)
大日本図(拾芥抄、慶長12年(1607)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)
今日に伝わる古い日本地図としては、14世紀初めの仁和寺蔵日本図や金沢文庫蔵日本図、14世紀半ばのものを伝える拾芥抄所収の大日本国図が知られている。中世までの日本図を総称して行基図という。仁和寺蔵日本図に「行基菩薩御作」、拾芥抄に「大日本国図は行基菩薩の図する所也」と注記されている。いずれも、今日のものと比べ、本州に関東地方部分からの北方向への屈曲が少なく、また、諸国が丸みを帯びた形でつなぎ描かれている。行基図は独鈷図ともいう。まんなか辺がくびれているのを密教の法具の独鈷に見立てたようである。拾芥抄に、「此の土の形、独鈷の頭の如し。仍りて仏法滋く盛ん也。其の形、宝形の如し。故に金銀銅鉄等の珍宝有り。五穀豊稔也」とある。地理的には、列島は若狭湾から琵琶湖を通って伊勢湾へ抜けるところが細くなっているから、それが独鈷の中心ということであろう(注5)。
また、金沢文庫蔵日本図に、我が国を取り巻くように、ヘビか何かのような鱗状の模様が描かれている。その外側の異域の記述は、今昔物語集に典拠があるとする考証が、応地1996.にある。また、鱗状の模様については、龍を描いて国土が守られるようなデザインであるとの考証が、黒田2003.に行われている。龍が描かれるにいたった根源には、龍が雨水を導く雷神と深い関係がある点にあるという。五行説では、青龍は東の方位と位置づけられるが、国を巡る形で描かれていることは、古代末期以降の雨の神としての龍神信仰によるものとしている(注6)。ただ、地図は古代からあったと考えるのが自然である。我が国の場合、諸国の編成に分国はあっても異民族に分断されたこともなく、大勢に変化はない。また、宗教的なドグマに支配された暗黒時代も訪れず、名称の点にのみ、行基図、独鈷図と呼ばれた程度で、特段に形が抽象化されたり偏向が行われた形跡は見られない。おそらく、既存の地図を目にしながら、模写や修正を繰り返して新しい地図は作られ続け、結果的に現存する行基図へとつながり、一部に龍のような芸術性を伴ったものが現れたのであろうと推測される。
古代の地図が仁和寺蔵日本図に遠くないものとすれば、東西に延びている国々の様子は、トンボが羽を広げた姿に準えられて考えられたのではないか。その特徴を一言でいうなら縁紋的であるといえよう。棚田の広がる風景が、縁紋のつづく様子に合致することも重ね合わせて納得されたに違いあるまい。なかでも赤トンボの生育環境として、田圃ほどふさわしい場所はなく、水田稲作の展開によって我が国では赤トンボがたくさん見られるようになったといわれている。本州は、大倭豊秋津島(大日本豊秋津洲)、赤トンボの島とイメージされたのである(注7)。
 稲穂にとまるナツアカネ(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)
稲穂にとまるナツアカネ(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)
国生みのはじめが淡路島なのは、明石海峡の地名によっている。アカシ(証)になるのがアカシ(明石・赤石)である。
白髪天皇、尋ぎて小楯を遣して、節を持ち、左右の舎人を将て、赤石に至りて迎へ奉る。(仁賢即位前紀)
 杜虎符(中国、秦時代、Antolavoasio様「杜虎符」ウィキペディアコモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:杜虎符.jpg)
杜虎符(中国、秦時代、Antolavoasio様「杜虎符」ウィキペディアコモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:杜虎符.jpg)
勅使の証は「節」である。竹の節を割ると、左右で合うものはほかにないから証明になる。節度使とは、竹の節によって勘合したことからくる名である。上に示した中国の虎符は銅製で、金の象嵌が篆文で施されている。銘に、「兵甲の符、右は君に在り、左は杜[咸陽の南に位置する県名]に在り。卂[迅]に士を興して甲を被らしめ、兵を用ふること五十人以上ならば、必ず君の符に会[合]はせん、……(兵甲之符、右在君、左在杜。凡興士被甲、用兵五十人以上、必会君符、……)」とある。和名抄に、蜻蛉の一名を「胡〓〔勑冠に虫〕」とあり、〓が勅の虫と記されていたのには深い意味があったようである。成熟したトンボの左右の羽の縁紋の形は、まるで「節」のように対称に揃っている。赤トンボは、子孫を残せるほど成熟した証として、縁紋が揃いもし、赤くもなって、二羽が合わさって交尾をし、水田で子どもがたくさん生まれる。水田で稲が赤く熟するのと良く合致している。紀では、「秋津は赫赫にして」(継体紀七年十二月)、「熟稲」(皇極紀元年五月)と表現されている。
秋津島では、秋になると蜻蛉の縁紋が合う。辻褄が合うという言葉で譬えられよう。辻褄とは、万葉集にいう「秋津羽」、「蜻領巾」同様、服飾用語である。辻は縫い目が十文字に合う所をいい、褄は着物の裾の左右がそろう所をいう。そこから、辻褄が合うとは、合うべきところがきちんと合って物事の道理が合うことをいい、辻褄が合わないとは、ちぐはぐなことをいう。先に胞となって出てしまった淡路島は、ヤゴではなかった。辻褄の合わない、すなわち、成熟してもトンボにならない蜘蛛、蛸、また、蜘蛛蛸のことを言っていたわけである。ヤマト朝廷の勢力が本州部分において、稲作にかなう地として東西に版図を広げていくなか、文様が左右対称状になっているのを正当なこととするようにニュアンスしていた。それが、aki(秋)+tudituma(辻褄)→akidusima(秋津島)である。
トンボと太鼓と雷
トンボという名は飛ぶ棒の訛りかという。飛ぶ棒といえば、太鼓を叩く桴(枹)が連想される。和名抄に、「大皷〈枹付〉 ……兼名苑に云はく、槌は一名に枹〈音は浮、字は亦、桴に作る。俗に豆々美乃波知と云ふ〉は大鼓を撃つ所以なりといふ。」とある。国生みの話では、当初、イザナキとイザナミの御合(遘合(共為夫婦・為夫婦・合為夫婦))において、「あなにやし(あなにえや)」と唱える順序が逆であったため、蛭児や淡洲が生れて失敗している。そこで、「故、還復上二詣於天一」している。できちゃった結婚(授かり婚)は駄目で、神前できちんと結婚式をしてからでなければならない。順序がちぐはぐでは罰が当たるという戒めになっている(注8)。文字の点からいえば、「桴」の字は、淡路島は、明石、鳴門とも海峡に挟まれていることから連想される。「峡」に挟まれている。秋になってできる稲穂とは「稃」である。また、「枹」の字は、「胞」の字から連想される。「枹」の字はまた、ケラ(螻蛄)をも指す。形はヤゴによく似、地中で生活する。
 ケラ(Didier Descouens様「ケラ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ケラ)
ケラ(Didier Descouens様「ケラ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ケラ)
ヤゴは別名をタイコムシという。人々にとって、太鼓の原体験はでんでん太鼓である。抱っこされながらあやされるのに用いられる。記紀説話の最初の舞台、淤能碁呂島(磤馭廬嶋)は、雷公をイメージしていたようである。オ(感嘆符のOh!)+ノ(助詞)+ゴロ(擬音語)、つまり、雷鳴を表すと考えられる。天沼矛(天之瓊矛)のヌとは、玉飾りのことである。そのような装飾が鞘などに施された、あるいは刀身自体の形容であるなら、きらきら光る矛を高いところから下ろしたとは、稲光をイメージした表現ということになる。民俗で稲妻とは、稲を稔らせるパートナーの意であるとされている(注9)。
でんでん太鼓を背負って桴を振り回している様は、風神雷神図として描かれている。現存する古いものとしては、北野天神縁起絵巻や三十三間堂の彫像などが知られる。


 左:でんでん太鼓(守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592414/4)、中:雷神(北野天神縁起、メトロポリタン美術館蔵、ウィキペディア「風神雷神図」https://ja.wikipedia.org/wiki/風神雷神図)、右:雷神(蓮華王院三十三間堂HPhttp://sanjusangendo.jp/b_2.html)
左:でんでん太鼓(守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592414/4)、中:雷神(北野天神縁起、メトロポリタン美術館蔵、ウィキペディア「風神雷神図」https://ja.wikipedia.org/wiki/風神雷神図)、右:雷神(蓮華王院三十三間堂HPhttp://sanjusangendo.jp/b_2.html)
その雷神の持物は桴に違いなかろうが、中がくびれて両端が膨らんだ形をしているようにも思われる。太鼓をたたくふつうの桴ではなく、でんでん太鼓のための桴、すなわち、玉を糸で止めたものに近いようにも感じられる。両方に振られるのを異時同図に描けば、桴の先端が膨らんでいると捉えれば独鈷にも見立て得るから、日本図を独鈷図と呼んでいたことに通じる。そして、雷は雲のなかに起こる。雷神が握っている物は、雲を掴むようなクモ、つまり、蜘蛛や蛸のようなものだと洒落を言っているように聞こえる。それらから総合的に推察すると、古代においては、雷神の桴の形としても秋津島は見られていたことになる。紀では黄泉の国へ行った後、イザナキは結果的に雷を生むことになっている。
一書に曰はく、伊弉諾尊、剣を抜きて軻遇突智を斬り、三段に為す。其の一段は是雷神と為る。(神代紀第五段一書第七)
時に伊弉冉尊、脹満れ太高へり。上に八色の雷公有り。伊弉諾尊、驚きて走げ還りたまふ。是の時に、雷等、皆起ちて追ひ来る。時に、道の辺に大きなる桃の樹有り。故、伊弉諾尊、其の樹の下に隠りて、因りて其の実を採りて、以て雷に擲げしかば、雷等、皆退走きぬ。此桃を用て鬼を避く縁なり。時に伊弉諾尊、乃ち其の杖を投てて曰はく、「此より以還、雷敢来じ」とのたまふ。是を岐神と謂す。此、本の号は、来名戸の祖神と曰す。八の雷と所謂ふは、首に在るは大雷と曰ふ。胸に在るは火雷と曰ふ。腹に在るは土雷と曰ふ。背に在るは稚雷と曰ふ。尻に在るは黒雷と曰ふ。手に在るは山雷と曰ふ。足の上に在るは野雷と曰ふ。陰の上に在るは裂雷と曰ふ。(神代紀第五段一書第九)
秋のヤマトと「山跡」とアキヅシマ
秋津(蜻蛉)なる赤トンボが飛んでくるのが秋である。稲を刈り、市へ持ってゆき、売り買いする。秋だから商という。分量をはかるのに必要なのが秤で、天秤棒に吊るす。価値が釣り合うようにしなければならない(注10)。天秤棒の大型のものは杠秤(扛秤)といい、雷神の桴に似て棒の中ほどが支点となり多少細くなっている。左右が釣り合ったところが辻褄が合うところである。もとは織機の経糸を巻く円柱の榺、すなわち、緒巻に由来するという。和名抄に、「榺 四声字苑に云はく、榺〈音は勝負の勝、楊氏漢語抄に知岐利と云ふ〉は織機の経を巻く木なりといふ。」とある。契りとは約束、因縁のことである。今でも契約書には割印を捺す。勘合により確かめられる。
秋には雁も渡ってくる。季節をはかる鳥である。肥えた獲物を探して狩りにもゆく。トンボのような形の、火鑽杵のような形の弓矢を使って射ると、手負いの獣は血痕を残しながら逃げていく。どこへ、いつごろ逃げて行ったかは、地面に残る血の跡を見れば推しはかれる。和名抄に、「蹤血は波加利」とある。山に残る跡だから、秋津島は一つの意味として、「山跡」と結びつくことになる。
万葉集でのヤマトの用字では、「山跡」が18例(万1・91・303・319・484題詞・551・570・1219・1221・1376・1677・1956・2128・3248・3249・4245・4254・4264)、「倭」が22例(万29・同或云・35・64・70・71・73・105・112題詞脚注・255・280・894(2例)・944・954・966・1129題詞・3128・3236・3250・3254・3333)、「日本」が17例(万44・52・63・359・366・367・389・810題詞・956・967・1047・1787・1175・1328題詞・2834・3295・3326)、その他に11例(「山常」(万2)、「八間跡」(万2)、「夜麻登」(万3363・3457・3648・4487)、「夜麻等」(万3608左注)、「也麻等」(万3688)、「大和」(万4277左注(行政単位としての国名))、「夜萬登」(万4465)、「夜末等」(万4466))がある。
「倭」の用字は魏志による。「日本」は聖徳太子、あるいは、天武天皇時代に新たに作られた国号とされている。それらと同等に数多い用字に「山跡」がある。この表記が好まれたのは、秋津島(洲)との関わりがあったからに違いない。もともとのアキヅシマは、奈良盆地南部の地名、御所市室の小地名にすぎなかったのではないかと考えられている。孝安天皇の都の名は、「葛城の室之秋津島宮」(記中)、「秋津嶋宮」(孝安紀)である。それが奈良盆地全体へと拡張した。トンボが交尾して胴体を丸くしたときの形が、畿内の大和国を取り巻く外輪山に準えられたかららしい。
三十有一年の夏四月の乙酉の朔に、皇輿巡り幸す。因りて腋上の嗛間丘に登りまして、国の状を廻らし望みて曰はく、「姸哉、国を獲つること。〈姸哉、此には鞅奈珥夜と云ふ。〉内木綿の真迮国と雖も、猶し蜻蛉の臀呫の如くにあるかな」とのたまふ。是に由りて、始めて秋津洲の号有り。(神武紀三十一年四月)
倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭しうるはし(記30)
 アキアカネの交尾(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)
アキアカネの交尾(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)
アキヅシマの地理的範囲の拡張は、ちょうど倭が、三輪山や巻向山の山麓付近の一地名であったのが、今の奈良盆地を表す大和、列島全体を表す日本へと拡張していったようにである。神武紀に、「由レ是、始……」と注意書きされるのは、秋津洲の意味合いも拡張していったことを含意していよう。それは、朝鮮半島南部の加羅が、半島全体の韓、中国の唐まで指すようになったのと同様である。アキヅシマがヤマトにかかる枕詞となっている例には、先にあげた万葉集の5例のほか、紀62・63歌謡にも見られる。水田稲作の広がりこそがヤマトの広がりであるとの意識が底流にあったようである。日本図に見られる田一枚を一国とするような描きぶりは、ヤマトの版図が、トンボが羽化して羽根を広げていくことに準えていたのではないか。
国生みで生んだのはシマである。紀ではシマに「洲」字を当てて表していた。地形的には川の中州のように現れたり消えたりするところでありながら、「洲」は「水中可レ居者曰レ洲」(爾雅・釈水)、「聚也、人及鳥物所二聚息一之処也」(釈名)と説明されている。アキヅシマという言い方をすれば、トンボが集まり憩うところということになる。水田が何面も広がって拡大していく版図のことをアキヅシマと名づけて得意になっていたようである。ヤマトコトバの言語体系において論理的な最適解を得、矛盾なく統合的に表すことができている。縁紋の話だけに、話の辻褄が合っている。
でんでん太鼓の枹のこと
縁紋のように畦は田の水を取り巻いている。取り巻きといえば女なら芸者、男なら太鼓持ちのことをいう。倭の字は女が身をくねらせて舞っている様を表す。舞は見ていてちらちらする。目がくるめきちらちらするのは眩暈である。舞舞はかたつむりである。その貝殻はぐるぐる巻いている。頭部の突起がでんでん太鼓の桴に似るからか、でんでん虫という。カタツムリの通った跡は粘液できらきらしている。でんでん太鼓は、また、張鼓、振鼓という。立派なものとしては、雅楽に用いられる鼗がある。双方に張った小鼓を柄で貫き、両側に糸の玉を垂れた楽器で、柄を振れば玉が鼓の皮に当たって鳴る仕掛けである。和名抄に、「◆(鼗の上下逆)皷 周礼注に云はく、◆〈徒刀反、字は亦、鞉に作る。不利豆々美〉は皷の如くして小さく、其の柄を持ちて之れを揺すらば、則ち旁の耳還りて自ら之を撃つといふ。」とある。雅楽のほか、追儺の行事で、最後に群臣が鬼を追うのにも用いられた。

 左:奚婁(信西古楽図、鼗鼓、国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1194190をトリミング合成)、右:鼗(画像石、後漢時代、1~2世紀、東博展示品)
左:奚婁(信西古楽図、鼗鼓、国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1194190をトリミング合成)、右:鼗(画像石、後漢時代、1~2世紀、東博展示品)
海野2004.は、仁和寺蔵日本図の奥書の最後を、追儺関連の記述と見て次のような興味深い解説を行っている。
すなわち、陰暦の十二月、追儺行事のために、仁和寺蔵日本図は描かれたものではないかとするのである。宮中での追儺より以前から、寺院において鬼やらいは行われていたのであろうが、その点は措く。この仁和寺蔵本には、金沢文庫蔵本のような龍様の囲みはない。龍が穢悪疫鬼を防ぐのではなく、追儺の行事を以て異域へと追い払うという解釈である。
追儺の行事としては、本邦では当初、周礼をもとに考案されたと考えられている。赤、青、黄の3匹の鬼を、黄金四つ目の仮面を著けた方相氏が大声を上げながら矛と盾を打ち鳴らし、追い払う。その後、公卿が清涼殿の階から桃の弓で矢を放ち、また、殿上人らはでんでん太鼓を振って邪気を一掃した(注11)。鬼を追う全体の様態は、雷神が羯鼓を鳴らしながら暴れ回って驚かせるのととてもよく似ており、準えられるものとして受け容れられたのではなかろうか。そして、そのでんでん太鼓とは、トンボつりの時に赤トンボがブリという飛び道具によって絡め捕られる様子にとてもよく似ており、だからこそ準えられたのではなかろうか。
 ブリの図(「絵本家賀御伽」国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266553/80)
ブリの図(「絵本家賀御伽」国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266553/80)
ブリとはトンボ捕りの際に用いられる疑似餌釣りである。糸の両端に、小石などを結びつけ、投げあげる。トンボが小石を餌と間違えて飛びつくと、石についている糸が体に絡みつき、そのまま地上に落下したところを生け捕りにする。かなり高度なテクニックを要するが、夏から秋にかけての夕暮れ時など、トンボが餌を求めて群がり飛んでいる時には、上手に放物線を描けば引っかかってくれるという。
つまり、でんでん太鼓の真ん中に居る雷神は、秋になると赤くなっていく赤トンボ同様、色変化していくものと考えられていたのであろう(注12)。そしてそれは、ヤマトの国の、秋になると稲穂が赤く色づいて一面に拡がる田圃の風景と呼応しているのである。令集解・職員令の鼓吹司に、「伴に、吹の音は呼飢反と云ふ。山海経に曰く、『東海の中に流波山有り。獣有りて牛の如く、蒼身にして角无く、水に出入すれば則ち必ず風雨有り。其の光は日月の如く、其の声は雷の如し。其の名を夔と曰ふ。黄帝之を得て、其の皮を以て鼓を作り、声五百里に聞え、以て天下を威す』といふ。周礼・地官・司徒上に曰く、『鼓人は六鼓を教ふるを掌る。雷鼓を以て神祀を鼓す。〈雷鼓は八面鼓也。〉霊鼓を以て社祭を鼓す。〈霊鼓は六面鼓也。社祭は地祇を祭る也。〉路鼓を以て鬼享を鼓す。〈路鼓は四面鼓也。鬼享は宗廟を享す也。〉賁鼓を以て軍事を鼓す。〈大鼓は之を賁と謂ふ。賁鼓は長さ八尺也。〉鼛鼓を以て役事を鼓す。〈鼛鼓は長さ丈二尺也。〉晋鼓を以て金奏を鼓す。〈晋鼓は長さ六尺六寸。金奏は楽を謂ひ、編鐘を撃つに作る。〉』といふ。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570154/25~26)とある。雷神の鼓は8つと決まっていたらしい。クモやタコが8本足であったのに対し、昆虫のトンボは6本だから、叩く手が2本足りない。そこで、秤にもなる杠秤のような亜鈴型の桴が考案され、ないし、トンボ捕りのブリが引き合いに出され、8つの鼓を同時に叩けるとのオチに及んだようである。
トラの話
鼗同様の打楽器としては、外来の銅鑼がある。銅鑼は反響が激しく、近場に本当に雷が落ちたほどになる。目上の人が大声で猛烈に怒るのを、雷が落ちるという。虎が吼えるほど恐い。同じく外来の物に名づけられたと思われる語である。銅鑼は船の出港のときに鳴らす。もやいを河岸から外すと船はふらふら揺れ始める。トラはネコのようであるが、身体に比べて頭が大きい。バランスが悪いから頭をふらふらさせている。首の揺れる張り子の虎の起源である。

 左:張り子の虎(信貴山の縁起物)、右:秋の棚田(日本財団・海と日本PROJECT in 京都「伊根町「新井の棚田」稲刈り体験」https://kyoto.uminohi.jp/event/20170914/をトリミング)
左:張り子の虎(信貴山の縁起物)、右:秋の棚田(日本財団・海と日本PROJECT in 京都「伊根町「新井の棚田」稲刈り体験」https://kyoto.uminohi.jp/event/20170914/をトリミング)
酔っ払って管を巻いている人のことをトラという。頭がふらふらしている。眠気がさしてまどろむようにとろとろの状態だからである。片栗粉のとろみ、まぐろの身の脂肪に富んだ部位のとろ、川の水深が深くて流れが緩やかな瀞、雷鳴の音のどろどろ、水が混じって粘性を増した土の泥、煮炊きに勢いの乏しいとろ火、皆同じ感覚から生まれた言葉であろう。神武紀元年正月条に、「妖気を掃ひ蕩かせり。」とある。列島にいなかったタイガーのことを渡来人から聞いて、その頭のとろとろの揺れと、どろどろの雷のような吼え声からトラと名づけた。蕩かすとは、人に本心をすっかり見失わせて完全に迷わせることをいう。確かに、トラを前にしたらすっかり参ってしまうであろう。そして、トラの模様は棚田を高いところから見たような縞模様であり、虎符として節の形としても用いられていた。
「倭」の字は、前漢書地理誌に、「楽浪の海中に倭人有り。分れて百余国を為す。(楽浪海中有倭人、分為百余国。)」の場合、音はワである。説文にはヰの音で、「順ふ㒵なり。人に从ひ委声。詩に曰く、周道倭遅たり」と、詩経・小雅・鹿鳴之什の四牡を引いている。倭は佞と同義で、諂う、媚びる、阿るの意味である。相手の気に入られるように取り入って振舞い、迎合して空気を読み、追従口、おべっか、お世辞を言って回ることである。太鼓持ちの所作をいう。おもねるとは、面練ること、顔を左右に向けることが原義という。トラが首を左右に振っているのは、本来は獲物を探しているのかもしれないが、張り子の虎は阿っていると捉えられた(注13)。
まとめに代えて
記の上巻や神代紀の叙述について、今日の一般的な解説では、天皇による支配の正統性を主張するために祖先神話が語られているという(注14)。けれども、当の紀の巻一初めの「神世七代」以外に、カミノヨと訓むべき箇所はない。伊奘諾尊、伊奘冉尊までが「神世」である。巻一・巻二を「神代上」・「神代下」とするのは、他の巻の漢風諡号同様、後の時代に加筆されたものと考証されている。初めに神があったとするのは伊奘諾尊、伊奘冉尊の出現までで、以降は始めに言葉ありきである。紀冒頭で、淮南子を引きながら作為している箇所には次のようにある。
其れ清陽なるものは、薄靡きて天と為り、重濁れるものは、淹滞ゐて地と為るに及びて、精妙なるが合へるは搏偏り易く、重濁れるが凝りたるは竭り難し。(神代紀第一段本文)
きらきら輝くものがひらひらと天になって、うまい具合にできているものがぴったり合って群がっているとする。まさに赤トンボの形容であろう。本稿で見てきた国生みの話は、全体を俯瞰すれば、ヤマトにかかる枕詞、アキヅシマという言葉をめぐっての壮大ななぞなぞ体系である。倭人がオリジナルに創作したと思しき記・神代紀第四段の国生みの説話に代表される。そこにも、上空できらきら輝くものがぴったりと符合すると語られている。すなわち、紀の冒頭は、その連想から漢籍の字面を引きながら自らの考えを表したものである(注15)。修文、潤色の範囲を超えておらず、和魂漢才の記述である。
国生みによって生まれた島は、本州、四国、九州とその周辺の島であった。それらの地域をヤマト朝廷が版図におさめたのは、5世紀、倭の五王の時代である。豊秋津島たる本州を、東は伊勢、西は出雲まで治めるに至ったのは、その少し前のことであろう。聖徳太子等が記紀の種本となる天皇記・国記・本記を録したのは推古28年(620)のことである。その時点で、つい数百年前に過ぎない最近のできごとであり、伝えられてきていた説話をシリーズ化したということであろう。基本的に無文字社会であった上代人の文化、観念がわかれば、記紀の説話は民族の祖先神話でも、天皇家を正統化する神話でもなく、手の込んだなぞなぞ話であることは理の当然と了解される。そこにあるのはヤマトコトバだけである。無文字に暮らした上代の人たちは知識を盾にして生きたのではない。知恵のかたまりのなかに生きていたのであった。
(注)
(注1)虻蜂取らず、という言葉の源や、古い用例について詳細は不明である。拙稿「允恭紀、淡路島の狩りの逸話、明石の真珠について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/17d842a2bc10d3783b29a39e7b44b4e8参照。
(注2)錦2005.参照。糸遊は山形県米沢地方で「雪迎え」と呼ばれている現象で、gossamerのことであると特定されている。
(注3)蜘蛛の子を散らす、という言葉の源や、古い用例について詳細は不明である。
(注4)白川1995.の「かぎろひ」の項に、「蜻火・蜻蜓火のように、とんぼの羽の繊細なかがやきとして表現するのは、おそらく他に例をみないような細やかな感覚である。」(209頁)とするが、疑問なしとしない。拙稿「履中記、墨江中王の反乱譚における記75・76歌謡について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/c6370f98a94cfed6b157be80bdffc5d6参照。
(注5)黒田2003.は次のようにまとめている。
 独鈷杵(日光男体山頂遺跡出土品、平安~鎌倉時代、10~13世紀、二荒山神社蔵、東博展示品)
独鈷杵(日光男体山頂遺跡出土品、平安~鎌倉時代、10~13世紀、二荒山神社蔵、東博展示品)
(注6)淮南子・墬形訓に、「雷沢に神有り、龍身にして人頭、其の腹を鼓ちて煕む。(雷沢有神、龍身人頭、鼓其腹而熙。)」、山海経・海内東経に、「雷沢中に雷神有り。龍身にして人頭、其の腹を鼓し、呉の西に在り。(雷沢中有雷神、龍身而人頭、鼓其腹、在呉西。)」とある。
(注7)赤トンボと称されるトンボが種として何に当たるかについて、西日本では主としてウスバキトンボ、東日本では主としてアキアカネのことを指すようである。上田哲行氏は、人間に与えるインパクトの共通性という意味で、「文化的同一種」という言葉を提唱しており、示唆的である。いずれの種も、田圃という人為的に管理され、安定した生息環境によって多数発生し、それを人々が親しんで、「風景としての赤とんぼ」と化しているわけである(東・沢辺・上田2004.)。上代の人が赤トンボをいかに捉えたかは、生物学ではなく、文化人類学的な考察が必要である。
(注8)罰が当たるという言葉のバチという慣用音については、仏典によるとも思われるが、上代の用例は不明である。
(注9)雷電のことをイナヅマ(稲妻)というのは、稲が共寝をして子を宿して稔るからという理屈が箋注和名抄や東雅に唱えられ、民俗学で通説化している。和名抄には、「雷公〈霹靂電付〉 ……玉篇に云はく、電〈音は甸、和名は以奈比加利。一に以奈豆流比と云ひ、又、以奈豆末と云ふ〉は雷の光なりといふ。」とある。しかし、植物の稲に交尾の譬えをして上代の人々に通じたのか、俄かには信じがたい。
(注10)釣り合わない例として、「高麗の使人、羆の皮一枚を持ちて其の価を称りて曰はく、『綿六十斤』といふ。市司、咲ひて避去りぬ。」(斉明紀五年是歳)とある。
(注11)夏官・方相氏に、「方相氏。熊皮を蒙り、黃金の四目、玄衣・朱裳、戈を執り盾を揚げ、百隸を帥ひて時に儺し、以て室を索めて疫を敺ることを掌る。大喪に匶に先だつ。墓に及びて壙に入り、戈を以て四隅を擊ち、方良を敺る。(方相氏。掌蒙熊皮、黃金四目、玄衣朱裳、執戈揚盾、帥百隸而時難、以索室驅疫。大喪先柩。及墓入壙、以戈擊四隅、驅方良。)」とある。本邦での実際の様子としては、栄花物語に、「例の有様どもありて、はかなく年も暮れぬれば、今の上、童におはしませば、つごもりの追儺に、殿上人振鼓などして参らせたれば、上ふり興ぜさせ給もをかし。」(巻第一・月の宴)、「つごもりになりぬれば、追儺とのゝしる。上いと若うおはしませば、ふり鼓などしてまゐらするに、君たちもおかしう思ふ。」(巻第三・さまざまの悦)、大江匡房・江家次第に、「殿上人於長橋内射方相、主上於南殿密覧、還御之時、扈従人忌三最前方逢二方相一、振鼓・儺木・儺法師等種々事〈皆故実有〉……」(十一十二月)とある。
(注12)一説に、雷神の肌の色は儀軌に赤と定められていたとされる(田沢2014.320頁)が、根拠は不明である。
(注13)拙稿「お練供養と当麻曼荼羅」参照。
(注14)諸説をあげることに及ばない。「神話」という語が明治時代に訳語として登場していることを承知のうえで行われている。平成から令和時代のはじめにかけてドグマと化している。
(注15)拙稿「日本書紀冒頭部の訓みについて─原文の「搏」や「埸(堨)」とは何か─」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/2836f8be437ba9abb1a6d157fc9eb3c4参照。
(引用・参考文献)
海野2004. 海野一隆『地図の文化史』八坂書房、2004年。
応地1996. 応地利明『絵地図の世界像』岩波書店(岩波新書)、1996年。
黒田2003. 黒田日出男『龍の棲む日本』岩波書店(岩波新書)、2003年。
産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/
白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。
新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』小学館、1994年。
千田2003. 千田稔「聖なる場としての国家領域─「神国」の表象─」『聖なるものの形と場』18号、2003年3月。日文研オープンアクセスhttps://doi.org/10.15055/00002965
大系本日本書紀 坂本太郎・井上光貞・家永三郎・大野晋校注『日本書紀(一)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。
田沢2014. 田沢裕賀「風神雷神図屏風 俵屋宗達筆」(解説)東京国立博物館・読売新聞社・NHK・NHKプロモーション編『特別展 栄西と建仁寺』読売新聞社・NHK・NHKプロモーション、2014年。
錦2005. 錦三郎『飛行蜘蛛』笠間書院、2005年。(丸ノ内出版、1972年初出。)
東・沢辺・上田2004. 東和敬・沢辺京子・上田哲行「もう一つの赤とんぼ」上田哲行編著『トンボと自然観』京都大学学術出版会、2004年。
※本稿は、2014年5月稿を2020年8月、2021年8月の訂正を経て、2024年2月に再度補正しつつルビ形式にしたものである。
ヤマトの名は、記紀の初めにある国生みの説話にすでに見られる。まず、天浮橋(天上浮橋)から天沼矛(天之瓊矛)を下して掻き混ぜ、潮が凝りて淤能碁呂島(磤馭廬嶋)となったところで、イザナキとイザナミが御合(遘合(共為夫婦・為夫婦・合為夫婦))をした。その結果、いくつかの島(洲)ができたなかの一つが、大倭豊秋津島(大日本豊秋津洲)であった。
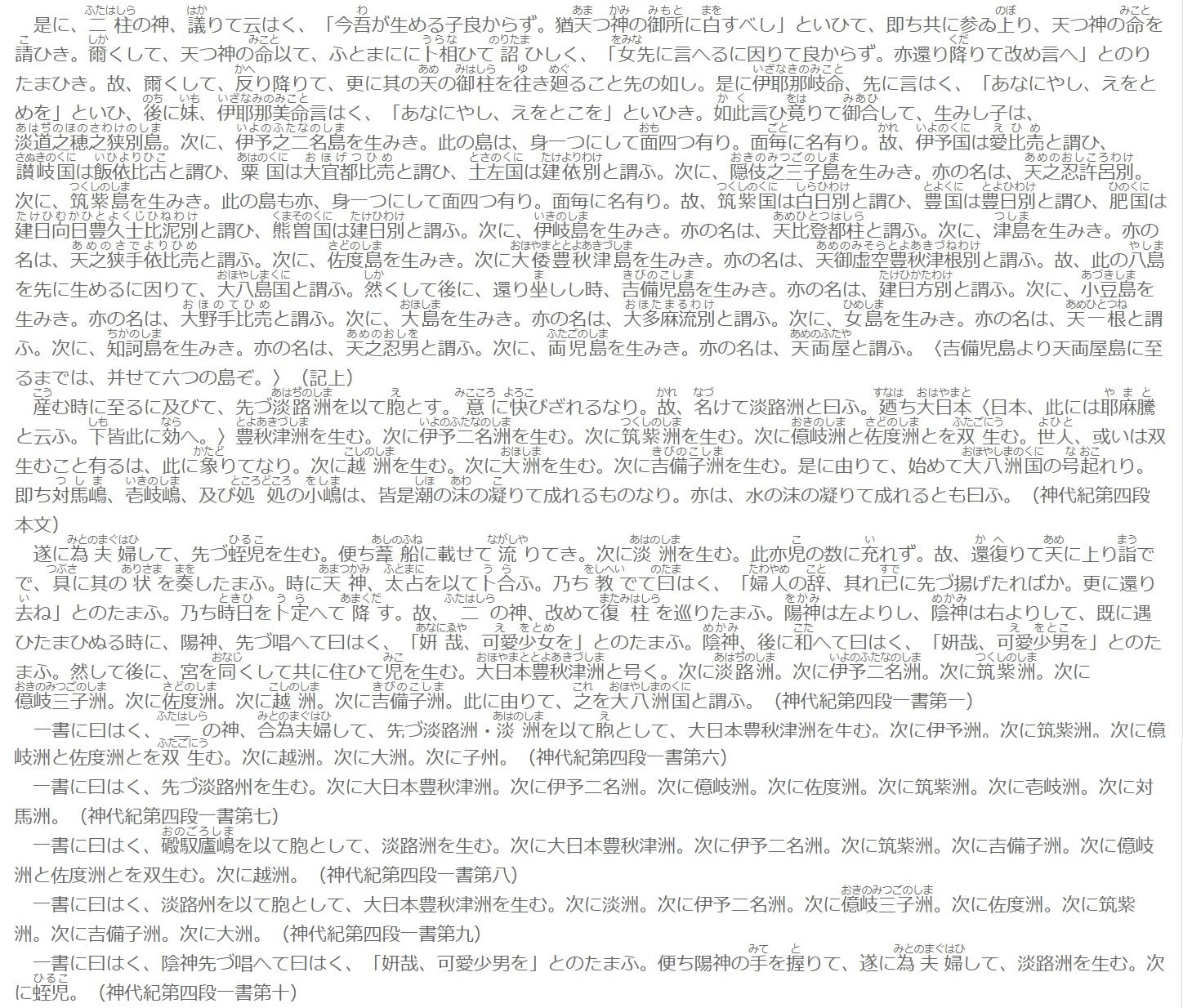
記では、それぞれの「島」について、亦の名の神名を記す。一方、紀では、「洲」の名を連ねるに止まる。記では、淡道之穂之狭別島、伊予之二名島、隠伎之三子島、筑紫島、伊岐島、津島、佐度島を生んでから大倭豊秋津島を生んでいる。以上から大八島国といったとする。その後、吉備児島、小豆島、大島、女島、知訶島、両児島を生んだとしている。紀本文では、「及二至産時一、先以二淡路洲一為レ胞。」とあり、すぐに大日本豊秋津洲を生んでいる。「胞」とは胞衣のことで、胎児をくるむ羊膜である。通常、臍帯などと同じく、後産として子の出たあとから娩出される。これらをすべて、胞衣と称するようになっている。胞が先に出てきて子が後から出て来ているのが問題で、順序が逆になっている。その後、伊予二名洲、筑紫洲、億岐洲、佐度洲、越洲、大洲、吉備子洲の順で生み、以上で大八洲国の名前ができたとする。淡路洲は胞だから大八洲の勘定に入れていない。また、対馬島、壱岐島とその他の諸々の島々は、みな潮の泡が凝り固まってできたものであるとしている。洲と島とを使い分け、厳密な表記を心掛けている。
紀一書第一では、胞の話はなく、大日本豊秋津洲、淡路洲の順で、大島が除かれて大八洲国としている。一書第二から一書第五までは国々の記載はなく、一書第六は、淡路洲・淡洲を胞として大日本豊秋津洲を生み、以下本文に同じである。一書第七は、淡路洲、大日本豊秋津洲、伊予二名洲、億岐洲、佐度洲、筑紫洲、壱岐洲、対馬洲の順である。一書第八になると、磤馭慮嶋が胞にされ、淡路洲を生み、次に大日本豊秋津洲、伊予二名洲、筑紫洲、吉備子洲、億岐洲、佐度洲である。一書第九では、淡路洲を胞として大日本豊秋津洲、その後に淡洲が登場し、伊予二名洲、億岐三子洲、佐度洲、筑紫洲、吉備子洲、大洲、一書第十では、淡路洲、蛭児を生んで終わっている。異同が多い点が、かえって厳密に記そうとしていた意図を伝えることになっている。
アハヂの謎(虻蜂取らず・蜘蛛の子を散らす)
生まれる順として、淡路島を出発点に、本州から四国、九州、日本海側、瀬戸内海へと回るか、四国の次に隠岐、佐渡があって九州が後回しにされるか、記のように本州が大八島国の最後になるかいろいろである。紀に見られる「胞」は、国が生まれるときの梃子として効いており、淡路島がキーになっている。紀本文に「意所レ不レ快。故、名之曰二淡路洲一。」とある。何が気に入らなかったのか、また、アハヂという名がどうして不快を表す名に値するのか。大系本日本書紀に、「第一子は産みそこないをするという当時の伝承がある通り、その第一子は生みそこないであったので、その第一子にアハヂ(吾恥)の島と名づけたという意(これはアハヂ島という、当時すでに存在していた島の名の地名起源説話の一つがここにからんだもの)。意に満たないので、この島は、おそらく流し捨てたのであろう。ここでは淡路州は大八洲の数に入っていない。この部分は古事記のヒルコの話に相当する。」((一)331頁)とある。新編全集本日本書紀には、それに加えて、「あるいは軽蔑する意の「淡あはむ」をかけたか。」(①27頁)ともある。淡路島はヒルコと違って流されずに現在も大きく存在する。国生みの話は、記、紀本文、一書第一~第十まであるが、一書の第二以降は大雑把で噺のレベルに達しておらず、説話として体を成しているのは、記、紀本文および一書第一だけであり、紀本文にのみ、何食わぬ顔で淡路島の悪口が書かれている。
大系本にいうとおり、すでに存在していた地名に託けた地名譚であろう。先に阿波という地名があり、それに引きずられてできたであろう淡路という地名があった。そのアハヂという地名にからんで説話が創られている。そして、後先かまわず胞が先に出てきていることから、ちぐはぐさを感じさせる内容を表しているものと考えられる。おそらくこれは、諺の「虻蜂取らず」の訛った形の頓知であろう。虻蜂取らずとは、どっちつかずや中途半端なことの譬えに用いられている。abu+fati→afadi である。自ら張った巣の中央にクモがおり、巣の対角線上にアブとハチとが同時にかかった。両者ともクモにとっては獲物として大物で魅力的だが力も強い。クモは、どちらを捕ろうかと迷っているうちにどちらも捕れないまま逃げられてしまう(注1)。すなわち、畿内にある朝廷は、西方からの侵入者に対し、明石、鳴門の両海峡を防ごうとして、淡路島の真ん中に城を一つ構えて守ろうとしたが叶わなかった。それを虻蜂取らずの淡路島と洒落ている。
クモの巣は高いところできらきらしている。移動に際して糸を伸ばして風に乗り、海を越える種もあるという。それを糸遊と呼ぶ。3~7mmの成体のクモが細い糸を吐き、風に乗って移動する現象である(注2)。ただし、一般に糸遊といえば陽炎のことを指す。現象としてはいずれもぼやぼやっとしてちらちらっと目に映る。漢語の「遊糸」は、梁の簡文帝の詩賦などに見えており、芸文類聚にいくつも例が載る。本邦では和漢朗詠集や菅家文章にも見え、また、和訳して「糸遊」という語も作られている。空海は仏典に拠って「陽燄」の語を用いており、陽炎と遊糸がイメージのなかで混同しているとも考えられている。平安朝の仮名文学においても、「かげろふ」はほのかな光の揺らぎ、光ってはかげり、かげっては光る心もとない現象として想起され、人の世やわが身のはかなさの譬えとして表現されている。
 糸遊イメージ(National Geographic「How Spiders Use Electricity to Fly | Decoder」https://www.youtube.com/watch?v=Ja4oMFOoK50。The New York Times「How Spiders Use Silk to Fly | ScienceTake」https://www.youtube.com/watch?v=VDL9VxLqdvw参照)
糸遊イメージ(National Geographic「How Spiders Use Electricity to Fly | Decoder」https://www.youtube.com/watch?v=Ja4oMFOoK50。The New York Times「How Spiders Use Silk to Fly | ScienceTake」https://www.youtube.com/watch?v=VDL9VxLqdvw参照)秋津島は淡路島を胞として出てきた。淡路島は、古代以来、一つの島で一つの国、淡路国を形作る。その胞を破って、蜘蛛の子を散らすような状態になった(注3)。ものすごい数のもじゃもじゃが現れた。一つの島(本州)にたくさんの国(近江、丹波、信濃、上総、出雲、伊勢、吉備、紀伊、伊豆、美濃、播磨、……)がある。淡路島と本州との間は明石海峡である。明石はタコが名産である。そのタコを特に蜘蛛蛸と呼んでいる。「蛸」の字は、中国ではアシタカグモのことを指し、巣を張らずに家にいてゴキブリなどを食べて生きている。そんな「蛸」に似た水中の昆虫といえば、トンボの幼虫、ヤゴである。


 左:アシタカグモ雌成虫(Jinn様「アシダカグモ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/アシダカグモ)、中:明石のタコ(松岡明芳様「明石市内の商業地区魚の棚で販売される明石ダコ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/明石ダコ)、右:コヤマトンボのヤゴ(Keisotyo様「ヤゴ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ヤゴ)
左:アシタカグモ雌成虫(Jinn様「アシダカグモ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/アシダカグモ)、中:明石のタコ(松岡明芳様「明石市内の商業地区魚の棚で販売される明石ダコ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/明石ダコ)、右:コヤマトンボのヤゴ(Keisotyo様「ヤゴ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ヤゴ)成虫のトンボは空を飛び、糸遊のように高いところで羽根がきらきらしている。したがって、カゲロフである。透き通った羽根がぼやぼやっとちらちらっと見えるのは、縁紋と呼ばれるステンドグラスの鉛線のような筋が入っていて、模様となっているからである。
大倭豊秋津島(大日本豊秋津洲)の秋津とはトンボのことで、蜻蛉と記される。和名抄に、「蜻蛉 本草に云はく、蜻蛉〈精霊の二音〉は一名に胡〓〔勑冠に虫〕〈音は勅、加介呂布〉といふ。釈薬性に云はく、一名に蝍蛉〈上の音は即〉といふ。兼名苑に云はく、虰蛵〈丁香の二音〉は一名に胡蝶は蜻蛉なりといふ。」とある。「蜉蝣」とは、今いうカゲロウ目やウスバカゲロウのようなアミメカゲロウ目の昆虫だけでなく、トンボ一般のことを指した。そして、「陽炎」は、光がちらちらと揺れ動くように見える現象をいい、「かぎろひ(ギ・ロは甲類、ヒは乙類)」の転とされ、ヒは火の意である。万葉集では、炎・蜻火・蜻蜓火といった字を当てている(注4)。
万葉集中に、アキヅとして記される例は全部で21例である。内訳は、地名のアキヅが7例(「秋津」(万36・911・1368・1713)、「蜻蛉」(万907)、「飽津」(万926)、「蜻」(万3065))、地名のアキヅノが6例(「秋津野」(万693・1345・1406)、「蜻野」(万1405)、「蜓野(万2292・3179))、枕詞のアキヅシマが5例(「蜻嶋」(万2・3250・4254)、「秋津嶋」(万3333)、「安吉豆之萬」(万4465))、昆虫としてのアキヅが2例(「秋津羽」(万376)、「蜻領巾」(万3314))である。
秋津羽の 袖振る妹を 玉くしげ 奥に思ふを 見たまへ吾が君(万376)
…… たらちねの 母が形見と 吾が持てる まそみ鏡に 蜻領巾 負ひ並め持ちて 馬替へ吾が背(万3314)
「秋津羽の袖」は羅製の袖、「蜻領巾」はオーガンジーの領巾のことである。いずれも透けるだけでなく、トンボの羽根の縁紋のように模様が施されていて、きらきらと輝くものであったものと思われる。
トンボの羽根模様と秋津島
このように、アキヅが特別な言葉として扱われた理由は、国生みの説話と関係があるからであろう。トンボは秋になって成熟し、交尾できるようになると、その縁紋は左右の羽根でぴったり揃うようになる。交尾して産卵できるようになった証拠である。万376番歌は、題詞に「湯原王宴席歌二首」とある。女性が成長して高貴な皇子と婚約を発表した宴席に、湯原王が侍して祝った歌と思われる。トンボの縁紋を画に描くと、本州(大倭豊秋津島・大日本豊秋津洲)にたくさんの国のある様を描いた日本地図のようになる。
 大日本図(拾芥抄、慶長12年(1607)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)
大日本図(拾芥抄、慶長12年(1607)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)今日に伝わる古い日本地図としては、14世紀初めの仁和寺蔵日本図や金沢文庫蔵日本図、14世紀半ばのものを伝える拾芥抄所収の大日本国図が知られている。中世までの日本図を総称して行基図という。仁和寺蔵日本図に「行基菩薩御作」、拾芥抄に「大日本国図は行基菩薩の図する所也」と注記されている。いずれも、今日のものと比べ、本州に関東地方部分からの北方向への屈曲が少なく、また、諸国が丸みを帯びた形でつなぎ描かれている。行基図は独鈷図ともいう。まんなか辺がくびれているのを密教の法具の独鈷に見立てたようである。拾芥抄に、「此の土の形、独鈷の頭の如し。仍りて仏法滋く盛ん也。其の形、宝形の如し。故に金銀銅鉄等の珍宝有り。五穀豊稔也」とある。地理的には、列島は若狭湾から琵琶湖を通って伊勢湾へ抜けるところが細くなっているから、それが独鈷の中心ということであろう(注5)。
また、金沢文庫蔵日本図に、我が国を取り巻くように、ヘビか何かのような鱗状の模様が描かれている。その外側の異域の記述は、今昔物語集に典拠があるとする考証が、応地1996.にある。また、鱗状の模様については、龍を描いて国土が守られるようなデザインであるとの考証が、黒田2003.に行われている。龍が描かれるにいたった根源には、龍が雨水を導く雷神と深い関係がある点にあるという。五行説では、青龍は東の方位と位置づけられるが、国を巡る形で描かれていることは、古代末期以降の雨の神としての龍神信仰によるものとしている(注6)。ただ、地図は古代からあったと考えるのが自然である。我が国の場合、諸国の編成に分国はあっても異民族に分断されたこともなく、大勢に変化はない。また、宗教的なドグマに支配された暗黒時代も訪れず、名称の点にのみ、行基図、独鈷図と呼ばれた程度で、特段に形が抽象化されたり偏向が行われた形跡は見られない。おそらく、既存の地図を目にしながら、模写や修正を繰り返して新しい地図は作られ続け、結果的に現存する行基図へとつながり、一部に龍のような芸術性を伴ったものが現れたのであろうと推測される。
古代の地図が仁和寺蔵日本図に遠くないものとすれば、東西に延びている国々の様子は、トンボが羽を広げた姿に準えられて考えられたのではないか。その特徴を一言でいうなら縁紋的であるといえよう。棚田の広がる風景が、縁紋のつづく様子に合致することも重ね合わせて納得されたに違いあるまい。なかでも赤トンボの生育環境として、田圃ほどふさわしい場所はなく、水田稲作の展開によって我が国では赤トンボがたくさん見られるようになったといわれている。本州は、大倭豊秋津島(大日本豊秋津洲)、赤トンボの島とイメージされたのである(注7)。
 稲穂にとまるナツアカネ(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)
稲穂にとまるナツアカネ(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)国生みのはじめが淡路島なのは、明石海峡の地名によっている。アカシ(証)になるのがアカシ(明石・赤石)である。
白髪天皇、尋ぎて小楯を遣して、節を持ち、左右の舎人を将て、赤石に至りて迎へ奉る。(仁賢即位前紀)
 杜虎符(中国、秦時代、Antolavoasio様「杜虎符」ウィキペディアコモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:杜虎符.jpg)
杜虎符(中国、秦時代、Antolavoasio様「杜虎符」ウィキペディアコモンズhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:杜虎符.jpg)勅使の証は「節」である。竹の節を割ると、左右で合うものはほかにないから証明になる。節度使とは、竹の節によって勘合したことからくる名である。上に示した中国の虎符は銅製で、金の象嵌が篆文で施されている。銘に、「兵甲の符、右は君に在り、左は杜[咸陽の南に位置する県名]に在り。卂[迅]に士を興して甲を被らしめ、兵を用ふること五十人以上ならば、必ず君の符に会[合]はせん、……(兵甲之符、右在君、左在杜。凡興士被甲、用兵五十人以上、必会君符、……)」とある。和名抄に、蜻蛉の一名を「胡〓〔勑冠に虫〕」とあり、〓が勅の虫と記されていたのには深い意味があったようである。成熟したトンボの左右の羽の縁紋の形は、まるで「節」のように対称に揃っている。赤トンボは、子孫を残せるほど成熟した証として、縁紋が揃いもし、赤くもなって、二羽が合わさって交尾をし、水田で子どもがたくさん生まれる。水田で稲が赤く熟するのと良く合致している。紀では、「秋津は赫赫にして」(継体紀七年十二月)、「熟稲」(皇極紀元年五月)と表現されている。
秋津島では、秋になると蜻蛉の縁紋が合う。辻褄が合うという言葉で譬えられよう。辻褄とは、万葉集にいう「秋津羽」、「蜻領巾」同様、服飾用語である。辻は縫い目が十文字に合う所をいい、褄は着物の裾の左右がそろう所をいう。そこから、辻褄が合うとは、合うべきところがきちんと合って物事の道理が合うことをいい、辻褄が合わないとは、ちぐはぐなことをいう。先に胞となって出てしまった淡路島は、ヤゴではなかった。辻褄の合わない、すなわち、成熟してもトンボにならない蜘蛛、蛸、また、蜘蛛蛸のことを言っていたわけである。ヤマト朝廷の勢力が本州部分において、稲作にかなう地として東西に版図を広げていくなか、文様が左右対称状になっているのを正当なこととするようにニュアンスしていた。それが、aki(秋)+tudituma(辻褄)→akidusima(秋津島)である。
トンボと太鼓と雷
トンボという名は飛ぶ棒の訛りかという。飛ぶ棒といえば、太鼓を叩く桴(枹)が連想される。和名抄に、「大皷〈枹付〉 ……兼名苑に云はく、槌は一名に枹〈音は浮、字は亦、桴に作る。俗に豆々美乃波知と云ふ〉は大鼓を撃つ所以なりといふ。」とある。国生みの話では、当初、イザナキとイザナミの御合(遘合(共為夫婦・為夫婦・合為夫婦))において、「あなにやし(あなにえや)」と唱える順序が逆であったため、蛭児や淡洲が生れて失敗している。そこで、「故、還復上二詣於天一」している。できちゃった結婚(授かり婚)は駄目で、神前できちんと結婚式をしてからでなければならない。順序がちぐはぐでは罰が当たるという戒めになっている(注8)。文字の点からいえば、「桴」の字は、淡路島は、明石、鳴門とも海峡に挟まれていることから連想される。「峡」に挟まれている。秋になってできる稲穂とは「稃」である。また、「枹」の字は、「胞」の字から連想される。「枹」の字はまた、ケラ(螻蛄)をも指す。形はヤゴによく似、地中で生活する。
 ケラ(Didier Descouens様「ケラ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ケラ)
ケラ(Didier Descouens様「ケラ」ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ケラ)ヤゴは別名をタイコムシという。人々にとって、太鼓の原体験はでんでん太鼓である。抱っこされながらあやされるのに用いられる。記紀説話の最初の舞台、淤能碁呂島(磤馭廬嶋)は、雷公をイメージしていたようである。オ(感嘆符のOh!)+ノ(助詞)+ゴロ(擬音語)、つまり、雷鳴を表すと考えられる。天沼矛(天之瓊矛)のヌとは、玉飾りのことである。そのような装飾が鞘などに施された、あるいは刀身自体の形容であるなら、きらきら光る矛を高いところから下ろしたとは、稲光をイメージした表現ということになる。民俗で稲妻とは、稲を稔らせるパートナーの意であるとされている(注9)。
でんでん太鼓を背負って桴を振り回している様は、風神雷神図として描かれている。現存する古いものとしては、北野天神縁起絵巻や三十三間堂の彫像などが知られる。


 左:でんでん太鼓(守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592414/4)、中:雷神(北野天神縁起、メトロポリタン美術館蔵、ウィキペディア「風神雷神図」https://ja.wikipedia.org/wiki/風神雷神図)、右:雷神(蓮華王院三十三間堂HPhttp://sanjusangendo.jp/b_2.html)
左:でんでん太鼓(守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592414/4)、中:雷神(北野天神縁起、メトロポリタン美術館蔵、ウィキペディア「風神雷神図」https://ja.wikipedia.org/wiki/風神雷神図)、右:雷神(蓮華王院三十三間堂HPhttp://sanjusangendo.jp/b_2.html)その雷神の持物は桴に違いなかろうが、中がくびれて両端が膨らんだ形をしているようにも思われる。太鼓をたたくふつうの桴ではなく、でんでん太鼓のための桴、すなわち、玉を糸で止めたものに近いようにも感じられる。両方に振られるのを異時同図に描けば、桴の先端が膨らんでいると捉えれば独鈷にも見立て得るから、日本図を独鈷図と呼んでいたことに通じる。そして、雷は雲のなかに起こる。雷神が握っている物は、雲を掴むようなクモ、つまり、蜘蛛や蛸のようなものだと洒落を言っているように聞こえる。それらから総合的に推察すると、古代においては、雷神の桴の形としても秋津島は見られていたことになる。紀では黄泉の国へ行った後、イザナキは結果的に雷を生むことになっている。
一書に曰はく、伊弉諾尊、剣を抜きて軻遇突智を斬り、三段に為す。其の一段は是雷神と為る。(神代紀第五段一書第七)
時に伊弉冉尊、脹満れ太高へり。上に八色の雷公有り。伊弉諾尊、驚きて走げ還りたまふ。是の時に、雷等、皆起ちて追ひ来る。時に、道の辺に大きなる桃の樹有り。故、伊弉諾尊、其の樹の下に隠りて、因りて其の実を採りて、以て雷に擲げしかば、雷等、皆退走きぬ。此桃を用て鬼を避く縁なり。時に伊弉諾尊、乃ち其の杖を投てて曰はく、「此より以還、雷敢来じ」とのたまふ。是を岐神と謂す。此、本の号は、来名戸の祖神と曰す。八の雷と所謂ふは、首に在るは大雷と曰ふ。胸に在るは火雷と曰ふ。腹に在るは土雷と曰ふ。背に在るは稚雷と曰ふ。尻に在るは黒雷と曰ふ。手に在るは山雷と曰ふ。足の上に在るは野雷と曰ふ。陰の上に在るは裂雷と曰ふ。(神代紀第五段一書第九)
秋のヤマトと「山跡」とアキヅシマ
秋津(蜻蛉)なる赤トンボが飛んでくるのが秋である。稲を刈り、市へ持ってゆき、売り買いする。秋だから商という。分量をはかるのに必要なのが秤で、天秤棒に吊るす。価値が釣り合うようにしなければならない(注10)。天秤棒の大型のものは杠秤(扛秤)といい、雷神の桴に似て棒の中ほどが支点となり多少細くなっている。左右が釣り合ったところが辻褄が合うところである。もとは織機の経糸を巻く円柱の榺、すなわち、緒巻に由来するという。和名抄に、「榺 四声字苑に云はく、榺〈音は勝負の勝、楊氏漢語抄に知岐利と云ふ〉は織機の経を巻く木なりといふ。」とある。契りとは約束、因縁のことである。今でも契約書には割印を捺す。勘合により確かめられる。
秋には雁も渡ってくる。季節をはかる鳥である。肥えた獲物を探して狩りにもゆく。トンボのような形の、火鑽杵のような形の弓矢を使って射ると、手負いの獣は血痕を残しながら逃げていく。どこへ、いつごろ逃げて行ったかは、地面に残る血の跡を見れば推しはかれる。和名抄に、「蹤血は波加利」とある。山に残る跡だから、秋津島は一つの意味として、「山跡」と結びつくことになる。
万葉集でのヤマトの用字では、「山跡」が18例(万1・91・303・319・484題詞・551・570・1219・1221・1376・1677・1956・2128・3248・3249・4245・4254・4264)、「倭」が22例(万29・同或云・35・64・70・71・73・105・112題詞脚注・255・280・894(2例)・944・954・966・1129題詞・3128・3236・3250・3254・3333)、「日本」が17例(万44・52・63・359・366・367・389・810題詞・956・967・1047・1787・1175・1328題詞・2834・3295・3326)、その他に11例(「山常」(万2)、「八間跡」(万2)、「夜麻登」(万3363・3457・3648・4487)、「夜麻等」(万3608左注)、「也麻等」(万3688)、「大和」(万4277左注(行政単位としての国名))、「夜萬登」(万4465)、「夜末等」(万4466))がある。
「倭」の用字は魏志による。「日本」は聖徳太子、あるいは、天武天皇時代に新たに作られた国号とされている。それらと同等に数多い用字に「山跡」がある。この表記が好まれたのは、秋津島(洲)との関わりがあったからに違いない。もともとのアキヅシマは、奈良盆地南部の地名、御所市室の小地名にすぎなかったのではないかと考えられている。孝安天皇の都の名は、「葛城の室之秋津島宮」(記中)、「秋津嶋宮」(孝安紀)である。それが奈良盆地全体へと拡張した。トンボが交尾して胴体を丸くしたときの形が、畿内の大和国を取り巻く外輪山に準えられたかららしい。
三十有一年の夏四月の乙酉の朔に、皇輿巡り幸す。因りて腋上の嗛間丘に登りまして、国の状を廻らし望みて曰はく、「姸哉、国を獲つること。〈姸哉、此には鞅奈珥夜と云ふ。〉内木綿の真迮国と雖も、猶し蜻蛉の臀呫の如くにあるかな」とのたまふ。是に由りて、始めて秋津洲の号有り。(神武紀三十一年四月)
倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭しうるはし(記30)
 アキアカネの交尾(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)
アキアカネの交尾(産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/)アキヅシマの地理的範囲の拡張は、ちょうど倭が、三輪山や巻向山の山麓付近の一地名であったのが、今の奈良盆地を表す大和、列島全体を表す日本へと拡張していったようにである。神武紀に、「由レ是、始……」と注意書きされるのは、秋津洲の意味合いも拡張していったことを含意していよう。それは、朝鮮半島南部の加羅が、半島全体の韓、中国の唐まで指すようになったのと同様である。アキヅシマがヤマトにかかる枕詞となっている例には、先にあげた万葉集の5例のほか、紀62・63歌謡にも見られる。水田稲作の広がりこそがヤマトの広がりであるとの意識が底流にあったようである。日本図に見られる田一枚を一国とするような描きぶりは、ヤマトの版図が、トンボが羽化して羽根を広げていくことに準えていたのではないか。
国生みで生んだのはシマである。紀ではシマに「洲」字を当てて表していた。地形的には川の中州のように現れたり消えたりするところでありながら、「洲」は「水中可レ居者曰レ洲」(爾雅・釈水)、「聚也、人及鳥物所二聚息一之処也」(釈名)と説明されている。アキヅシマという言い方をすれば、トンボが集まり憩うところということになる。水田が何面も広がって拡大していく版図のことをアキヅシマと名づけて得意になっていたようである。ヤマトコトバの言語体系において論理的な最適解を得、矛盾なく統合的に表すことができている。縁紋の話だけに、話の辻褄が合っている。
でんでん太鼓の枹のこと
縁紋のように畦は田の水を取り巻いている。取り巻きといえば女なら芸者、男なら太鼓持ちのことをいう。倭の字は女が身をくねらせて舞っている様を表す。舞は見ていてちらちらする。目がくるめきちらちらするのは眩暈である。舞舞はかたつむりである。その貝殻はぐるぐる巻いている。頭部の突起がでんでん太鼓の桴に似るからか、でんでん虫という。カタツムリの通った跡は粘液できらきらしている。でんでん太鼓は、また、張鼓、振鼓という。立派なものとしては、雅楽に用いられる鼗がある。双方に張った小鼓を柄で貫き、両側に糸の玉を垂れた楽器で、柄を振れば玉が鼓の皮に当たって鳴る仕掛けである。和名抄に、「◆(鼗の上下逆)皷 周礼注に云はく、◆〈徒刀反、字は亦、鞉に作る。不利豆々美〉は皷の如くして小さく、其の柄を持ちて之れを揺すらば、則ち旁の耳還りて自ら之を撃つといふ。」とある。雅楽のほか、追儺の行事で、最後に群臣が鬼を追うのにも用いられた。

 左:奚婁(信西古楽図、鼗鼓、国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1194190をトリミング合成)、右:鼗(画像石、後漢時代、1~2世紀、東博展示品)
左:奚婁(信西古楽図、鼗鼓、国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1194190をトリミング合成)、右:鼗(画像石、後漢時代、1~2世紀、東博展示品)海野2004.は、仁和寺蔵日本図の奥書の最後を、追儺関連の記述と見て次のような興味深い解説を行っている。
行基の名を日本図に結びつけたのは、ほかならぬ悪鬼を払う追儺の儀式であったと考えられる。根拠の一つとして挙げられるのは、行基の作であることが明記される仁和寺所蔵図……に「嘉元三年大呂(一二月)寒風ヲ謝シテ之ヲ写ス。外見ニ及ブ可カラズ」(原漢文)とあって、書写という行為における自己強制と図そのものの非公開性が強調されていることである。その第二としては、行基を開基とする山崎(山城国)の宝積寺の縁起に、追儺のはじまりが慶雲三年(七〇六)の行基の奏上にあるとしていることである(『和漢三才図会』巻四儺の項)。かつて追儺が朝廷における大晦日の行事であったことは、『延喜式』の記事からも明らかであるが、のち広く寺院でも行われ、その際疫鬼が入ってはならない国土の範囲を視覚に訴えるため、日本図が用意されたものと思われる。仁和寺所蔵図の書写の時期すなわち一二月は、この推定を裏付ける有力な証拠である。(91頁)
すなわち、陰暦の十二月、追儺行事のために、仁和寺蔵日本図は描かれたものではないかとするのである。宮中での追儺より以前から、寺院において鬼やらいは行われていたのであろうが、その点は措く。この仁和寺蔵本には、金沢文庫蔵本のような龍様の囲みはない。龍が穢悪疫鬼を防ぐのではなく、追儺の行事を以て異域へと追い払うという解釈である。
追儺の行事としては、本邦では当初、周礼をもとに考案されたと考えられている。赤、青、黄の3匹の鬼を、黄金四つ目の仮面を著けた方相氏が大声を上げながら矛と盾を打ち鳴らし、追い払う。その後、公卿が清涼殿の階から桃の弓で矢を放ち、また、殿上人らはでんでん太鼓を振って邪気を一掃した(注11)。鬼を追う全体の様態は、雷神が羯鼓を鳴らしながら暴れ回って驚かせるのととてもよく似ており、準えられるものとして受け容れられたのではなかろうか。そして、そのでんでん太鼓とは、トンボつりの時に赤トンボがブリという飛び道具によって絡め捕られる様子にとてもよく似ており、だからこそ準えられたのではなかろうか。
 ブリの図(「絵本家賀御伽」国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266553/80)
ブリの図(「絵本家賀御伽」国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1266553/80)ブリとはトンボ捕りの際に用いられる疑似餌釣りである。糸の両端に、小石などを結びつけ、投げあげる。トンボが小石を餌と間違えて飛びつくと、石についている糸が体に絡みつき、そのまま地上に落下したところを生け捕りにする。かなり高度なテクニックを要するが、夏から秋にかけての夕暮れ時など、トンボが餌を求めて群がり飛んでいる時には、上手に放物線を描けば引っかかってくれるという。
つまり、でんでん太鼓の真ん中に居る雷神は、秋になると赤くなっていく赤トンボ同様、色変化していくものと考えられていたのであろう(注12)。そしてそれは、ヤマトの国の、秋になると稲穂が赤く色づいて一面に拡がる田圃の風景と呼応しているのである。令集解・職員令の鼓吹司に、「伴に、吹の音は呼飢反と云ふ。山海経に曰く、『東海の中に流波山有り。獣有りて牛の如く、蒼身にして角无く、水に出入すれば則ち必ず風雨有り。其の光は日月の如く、其の声は雷の如し。其の名を夔と曰ふ。黄帝之を得て、其の皮を以て鼓を作り、声五百里に聞え、以て天下を威す』といふ。周礼・地官・司徒上に曰く、『鼓人は六鼓を教ふるを掌る。雷鼓を以て神祀を鼓す。〈雷鼓は八面鼓也。〉霊鼓を以て社祭を鼓す。〈霊鼓は六面鼓也。社祭は地祇を祭る也。〉路鼓を以て鬼享を鼓す。〈路鼓は四面鼓也。鬼享は宗廟を享す也。〉賁鼓を以て軍事を鼓す。〈大鼓は之を賁と謂ふ。賁鼓は長さ八尺也。〉鼛鼓を以て役事を鼓す。〈鼛鼓は長さ丈二尺也。〉晋鼓を以て金奏を鼓す。〈晋鼓は長さ六尺六寸。金奏は楽を謂ひ、編鐘を撃つに作る。〉』といふ。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570154/25~26)とある。雷神の鼓は8つと決まっていたらしい。クモやタコが8本足であったのに対し、昆虫のトンボは6本だから、叩く手が2本足りない。そこで、秤にもなる杠秤のような亜鈴型の桴が考案され、ないし、トンボ捕りのブリが引き合いに出され、8つの鼓を同時に叩けるとのオチに及んだようである。
トラの話
鼗同様の打楽器としては、外来の銅鑼がある。銅鑼は反響が激しく、近場に本当に雷が落ちたほどになる。目上の人が大声で猛烈に怒るのを、雷が落ちるという。虎が吼えるほど恐い。同じく外来の物に名づけられたと思われる語である。銅鑼は船の出港のときに鳴らす。もやいを河岸から外すと船はふらふら揺れ始める。トラはネコのようであるが、身体に比べて頭が大きい。バランスが悪いから頭をふらふらさせている。首の揺れる張り子の虎の起源である。

 左:張り子の虎(信貴山の縁起物)、右:秋の棚田(日本財団・海と日本PROJECT in 京都「伊根町「新井の棚田」稲刈り体験」https://kyoto.uminohi.jp/event/20170914/をトリミング)
左:張り子の虎(信貴山の縁起物)、右:秋の棚田(日本財団・海と日本PROJECT in 京都「伊根町「新井の棚田」稲刈り体験」https://kyoto.uminohi.jp/event/20170914/をトリミング)酔っ払って管を巻いている人のことをトラという。頭がふらふらしている。眠気がさしてまどろむようにとろとろの状態だからである。片栗粉のとろみ、まぐろの身の脂肪に富んだ部位のとろ、川の水深が深くて流れが緩やかな瀞、雷鳴の音のどろどろ、水が混じって粘性を増した土の泥、煮炊きに勢いの乏しいとろ火、皆同じ感覚から生まれた言葉であろう。神武紀元年正月条に、「妖気を掃ひ蕩かせり。」とある。列島にいなかったタイガーのことを渡来人から聞いて、その頭のとろとろの揺れと、どろどろの雷のような吼え声からトラと名づけた。蕩かすとは、人に本心をすっかり見失わせて完全に迷わせることをいう。確かに、トラを前にしたらすっかり参ってしまうであろう。そして、トラの模様は棚田を高いところから見たような縞模様であり、虎符として節の形としても用いられていた。
「倭」の字は、前漢書地理誌に、「楽浪の海中に倭人有り。分れて百余国を為す。(楽浪海中有倭人、分為百余国。)」の場合、音はワである。説文にはヰの音で、「順ふ㒵なり。人に从ひ委声。詩に曰く、周道倭遅たり」と、詩経・小雅・鹿鳴之什の四牡を引いている。倭は佞と同義で、諂う、媚びる、阿るの意味である。相手の気に入られるように取り入って振舞い、迎合して空気を読み、追従口、おべっか、お世辞を言って回ることである。太鼓持ちの所作をいう。おもねるとは、面練ること、顔を左右に向けることが原義という。トラが首を左右に振っているのは、本来は獲物を探しているのかもしれないが、張り子の虎は阿っていると捉えられた(注13)。
まとめに代えて
記の上巻や神代紀の叙述について、今日の一般的な解説では、天皇による支配の正統性を主張するために祖先神話が語られているという(注14)。けれども、当の紀の巻一初めの「神世七代」以外に、カミノヨと訓むべき箇所はない。伊奘諾尊、伊奘冉尊までが「神世」である。巻一・巻二を「神代上」・「神代下」とするのは、他の巻の漢風諡号同様、後の時代に加筆されたものと考証されている。初めに神があったとするのは伊奘諾尊、伊奘冉尊の出現までで、以降は始めに言葉ありきである。紀冒頭で、淮南子を引きながら作為している箇所には次のようにある。
其れ清陽なるものは、薄靡きて天と為り、重濁れるものは、淹滞ゐて地と為るに及びて、精妙なるが合へるは搏偏り易く、重濁れるが凝りたるは竭り難し。(神代紀第一段本文)
きらきら輝くものがひらひらと天になって、うまい具合にできているものがぴったり合って群がっているとする。まさに赤トンボの形容であろう。本稿で見てきた国生みの話は、全体を俯瞰すれば、ヤマトにかかる枕詞、アキヅシマという言葉をめぐっての壮大ななぞなぞ体系である。倭人がオリジナルに創作したと思しき記・神代紀第四段の国生みの説話に代表される。そこにも、上空できらきら輝くものがぴったりと符合すると語られている。すなわち、紀の冒頭は、その連想から漢籍の字面を引きながら自らの考えを表したものである(注15)。修文、潤色の範囲を超えておらず、和魂漢才の記述である。
国生みによって生まれた島は、本州、四国、九州とその周辺の島であった。それらの地域をヤマト朝廷が版図におさめたのは、5世紀、倭の五王の時代である。豊秋津島たる本州を、東は伊勢、西は出雲まで治めるに至ったのは、その少し前のことであろう。聖徳太子等が記紀の種本となる天皇記・国記・本記を録したのは推古28年(620)のことである。その時点で、つい数百年前に過ぎない最近のできごとであり、伝えられてきていた説話をシリーズ化したということであろう。基本的に無文字社会であった上代人の文化、観念がわかれば、記紀の説話は民族の祖先神話でも、天皇家を正統化する神話でもなく、手の込んだなぞなぞ話であることは理の当然と了解される。そこにあるのはヤマトコトバだけである。無文字に暮らした上代の人たちは知識を盾にして生きたのではない。知恵のかたまりのなかに生きていたのであった。
(注)
(注1)虻蜂取らず、という言葉の源や、古い用例について詳細は不明である。拙稿「允恭紀、淡路島の狩りの逸話、明石の真珠について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/17d842a2bc10d3783b29a39e7b44b4e8参照。
(注2)錦2005.参照。糸遊は山形県米沢地方で「雪迎え」と呼ばれている現象で、gossamerのことであると特定されている。
(注3)蜘蛛の子を散らす、という言葉の源や、古い用例について詳細は不明である。
(注4)白川1995.の「かぎろひ」の項に、「蜻火・蜻蜓火のように、とんぼの羽の繊細なかがやきとして表現するのは、おそらく他に例をみないような細やかな感覚である。」(209頁)とするが、疑問なしとしない。拙稿「履中記、墨江中王の反乱譚における記75・76歌謡について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/c6370f98a94cfed6b157be80bdffc5d6参照。
(注5)黒田2003.は次のようにまとめている。
行基図の謎解きによって浮かび上がったのは、〈日本図〉が独鈷の〈かたち〉をしていたという事実である。その〈日本図〉を、中世人は役行者・聖徳太子・天照大神などと同体の仏神である行基菩薩が製作したものと考えた。中世人にとって、聖なる存在は同体だったのである。聖なるモノである独鈷の〈かたち〉も融通無碍であり、棒状・柱状をした聖なるモノは、何でも独鈷とイメージで結びつき、独鈷になりえた。結局のところ、行基図とは、仏神が描いた聖なる〈日本図〉なのであり、天皇の印である神璽でもあった。〈国土〉は独鈷の〈かたち〉に荘荘りたてられ、〈日本〉・震旦・天竺の三国は、それぞれ独鈷・三鈷・五鈷とするシンボリズムによって、厳な世界としてイメージされるに至ったのである。(54頁)
 独鈷杵(日光男体山頂遺跡出土品、平安~鎌倉時代、10~13世紀、二荒山神社蔵、東博展示品)
独鈷杵(日光男体山頂遺跡出土品、平安~鎌倉時代、10~13世紀、二荒山神社蔵、東博展示品)(注6)淮南子・墬形訓に、「雷沢に神有り、龍身にして人頭、其の腹を鼓ちて煕む。(雷沢有神、龍身人頭、鼓其腹而熙。)」、山海経・海内東経に、「雷沢中に雷神有り。龍身にして人頭、其の腹を鼓し、呉の西に在り。(雷沢中有雷神、龍身而人頭、鼓其腹、在呉西。)」とある。
(注7)赤トンボと称されるトンボが種として何に当たるかについて、西日本では主としてウスバキトンボ、東日本では主としてアキアカネのことを指すようである。上田哲行氏は、人間に与えるインパクトの共通性という意味で、「文化的同一種」という言葉を提唱しており、示唆的である。いずれの種も、田圃という人為的に管理され、安定した生息環境によって多数発生し、それを人々が親しんで、「風景としての赤とんぼ」と化しているわけである(東・沢辺・上田2004.)。上代の人が赤トンボをいかに捉えたかは、生物学ではなく、文化人類学的な考察が必要である。
(注8)罰が当たるという言葉のバチという慣用音については、仏典によるとも思われるが、上代の用例は不明である。
(注9)雷電のことをイナヅマ(稲妻)というのは、稲が共寝をして子を宿して稔るからという理屈が箋注和名抄や東雅に唱えられ、民俗学で通説化している。和名抄には、「雷公〈霹靂電付〉 ……玉篇に云はく、電〈音は甸、和名は以奈比加利。一に以奈豆流比と云ひ、又、以奈豆末と云ふ〉は雷の光なりといふ。」とある。しかし、植物の稲に交尾の譬えをして上代の人々に通じたのか、俄かには信じがたい。
(注10)釣り合わない例として、「高麗の使人、羆の皮一枚を持ちて其の価を称りて曰はく、『綿六十斤』といふ。市司、咲ひて避去りぬ。」(斉明紀五年是歳)とある。
(注11)夏官・方相氏に、「方相氏。熊皮を蒙り、黃金の四目、玄衣・朱裳、戈を執り盾を揚げ、百隸を帥ひて時に儺し、以て室を索めて疫を敺ることを掌る。大喪に匶に先だつ。墓に及びて壙に入り、戈を以て四隅を擊ち、方良を敺る。(方相氏。掌蒙熊皮、黃金四目、玄衣朱裳、執戈揚盾、帥百隸而時難、以索室驅疫。大喪先柩。及墓入壙、以戈擊四隅、驅方良。)」とある。本邦での実際の様子としては、栄花物語に、「例の有様どもありて、はかなく年も暮れぬれば、今の上、童におはしませば、つごもりの追儺に、殿上人振鼓などして参らせたれば、上ふり興ぜさせ給もをかし。」(巻第一・月の宴)、「つごもりになりぬれば、追儺とのゝしる。上いと若うおはしませば、ふり鼓などしてまゐらするに、君たちもおかしう思ふ。」(巻第三・さまざまの悦)、大江匡房・江家次第に、「殿上人於長橋内射方相、主上於南殿密覧、還御之時、扈従人忌三最前方逢二方相一、振鼓・儺木・儺法師等種々事〈皆故実有〉……」(十一十二月)とある。
(注12)一説に、雷神の肌の色は儀軌に赤と定められていたとされる(田沢2014.320頁)が、根拠は不明である。
(注13)拙稿「お練供養と当麻曼荼羅」参照。
(注14)諸説をあげることに及ばない。「神話」という語が明治時代に訳語として登場していることを承知のうえで行われている。平成から令和時代のはじめにかけてドグマと化している。
(注15)拙稿「日本書紀冒頭部の訓みについて─原文の「搏」や「埸(堨)」とは何か─」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/2836f8be437ba9abb1a6d157fc9eb3c4参照。
(引用・参考文献)
海野2004. 海野一隆『地図の文化史』八坂書房、2004年。
応地1996. 応地利明『絵地図の世界像』岩波書店(岩波新書)、1996年。
黒田2003. 黒田日出男『龍の棲む日本』岩波書店(岩波新書)、2003年。
産総研HP「赤トンボはなぜ赤い?動物で初めて見つかった驚きのメカニズム」https://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/bluebacks/no23/
白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。
新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』小学館、1994年。
千田2003. 千田稔「聖なる場としての国家領域─「神国」の表象─」『聖なるものの形と場』18号、2003年3月。日文研オープンアクセスhttps://doi.org/10.15055/00002965
大系本日本書紀 坂本太郎・井上光貞・家永三郎・大野晋校注『日本書紀(一)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。
田沢2014. 田沢裕賀「風神雷神図屏風 俵屋宗達筆」(解説)東京国立博物館・読売新聞社・NHK・NHKプロモーション編『特別展 栄西と建仁寺』読売新聞社・NHK・NHKプロモーション、2014年。
錦2005. 錦三郎『飛行蜘蛛』笠間書院、2005年。(丸ノ内出版、1972年初出。)
東・沢辺・上田2004. 東和敬・沢辺京子・上田哲行「もう一つの赤とんぼ」上田哲行編著『トンボと自然観』京都大学学術出版会、2004年。
※本稿は、2014年5月稿を2020年8月、2021年8月の訂正を経て、2024年2月に再度補正しつつルビ形式にしたものである。














