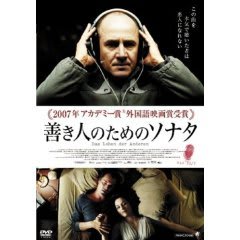
「善き人のためのソナタ」(2006年制作 ドイツ)
監督 フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク
出演 ウルリッヒ・ミューエ/マルティナ・ゲデック/セバスチャン・コッホ
(第79回アカデミー最優秀外国語映画賞を受賞)
■1984年の東ドイツ
最初に驚いたのは、この映画の舞台が1984年の東ドイツだということ。1989年のベルリンの壁崩壊数年前で、もちろん東西冷戦の中にあったことも知っていたけれど、こんなふうに体制に抵抗する人々を盗聴したり、活動を制限したり、ということが公然と(ではないのかな)行われていた、という事実。私の無知なんだろうけれど、それは大きな驚きだった。
1984年に私はどんなふうに暮らしていただろうかと、つい振り返ってしまった。
国家保安省(シュタージ)については、その後もタブー視されていて、この映画で初めて事実が明らかになった部分も多いらしい。
シュタージの局員であるヴィースラーが若い局員たちの前で、思想犯の取り調べについて講義しているところから映画は始まる。冷徹なヴィースラーは、睡眠もとらせずに取り調べをするのは非人道的ではないか、と意見を述べる局員の名前に冷やかにチェックを入れる。冷酷なビデオを見せながら、いかに「おとす」かのノウハウを述べるようすに、この人物がどんなふうにこの体制の中を生きてきたかが想像される。
家族も、たぶん心を許す友人も恋人もいないであろう彼は、国家に限りない忠節を誓って、この先も同じような日々を送り、そして死んでいくのだろう。疑いもなくそう想像させるシーンが静かに進んでいく。
感情の動きをみせることもない主人公を、ウルリッヒ・ミューエが淡々と演じている。
■変わっていくヴィースラー
その彼が少しずつ変わっていくのは、劇作家ドライマンとその恋人である女優クリスタ・マリア・ジーラントの生活を盗聴し始めてからだ。
彼らの思想に危険なものを察知した当局が、彼らの生活の一部始終を盗聴するようにヴィースラーに命じ、彼は部下と交代でその任務を遂行する。
盗聴器を住居全体に取り付けるときの局員たちの素早さ、その行動に気づいた隣人に脅しをかける際の静かな口調の怖さ…。
そして彼は昼間の間、その任務を続け、報告書をタイプする。「○時○分、帰宅。二人はセックスをする」というように、すべてが記録されていく。
けれど、二人の暮らしはヴィースラーのそれとはまったくの別世界だったのだろう。芝居を語り、音楽を楽しみ(ここで流れたのが「善き人のためのソナタ」)、愛し合う毎日。これといってドラマチックなことはない中で、ヴィースラーが少しずつ変わっていく。
部屋に忍び込んだ際に持ってきたブレヒトの本を読んだり、ドライマンの弾くピアノに耳を傾けるようになる。
そして、西側のメディアに東ドイツの実態を伝えるレポートを送る計画を始めたドライマンとその仲間の行動を、彼は報告しようとはしない。彼らは劇の脚本を共同で執筆している、とタイプする。この主人公の変化を、ウルリッヒ・ミューエは表にあらわれない何かで私たちに伝える。それが秀逸だ。演技ではない何か…。
■一級品のサスペンス
恋人たちの信頼関係には恋愛を超えた確実なものがあったけれど、当局の弾圧はその関係さえ危ういものに変えていく。
女優としての将来を脅かされたクリスタは苦悩の末、ドライマンの情報を当局に売る(彼女に目をつけた政治家の行為は醜悪このうえない!)。
それを知ったヴィースラーは身を挺して彼を守るのだけれど、愛する人を裏切ったクリスタは命を落としてしまう。その死を目の当たりにしたヴィースラーの無念はその感情を表さない表情から、むしろ強く私たちに伝わる。
ヴィースラーの行動は当局にも知られることになり、閑職に追いやられ、ベルリンの壁崩壊のニュースを知ったのも、地下の一室で手紙の開封という仕事をしているときだった。彼はそのとき、どんな気持ちでいたのだろう。
このあたりのシンプルな話の流れは、描き方が乾いているせいもあって、一級のサスペンスの彩りだ。
■「私の本だ」
新しい世界が開けたあとも、恋人の死から芝居を書けなくなっていたドライマンは、実は自分が東ドイツ時代にずっと盗聴されていたことを知る。そして、そのレポートを見て、そこに書かれた内容が全く改ざんされたものであることに気づく。誰かが自分を守ってくれたこと、そして救ってくれたことに驚く。そのレポートには報告者として暗号のような文字が書いてあった。
その後日談が、ヴィースラーとドライマンのそれぞれを日常を淡々と描いて進んでいく。ヴィースラーが郵便受けにチラシ?を配る仕事を続け、孤独に生きていることが伝わる。
ある日、本屋の前でドライマンの著作を見つける。彼があれから初めて執筆したものだ。本のタイトルは「善き人のためのソナタ」。本を手にしてページをめくると、謝辞のところに「感謝する」として、彼の盗聴の際の暗号の名前が記されている。
本をレジにもっていくヴィースラー。レジの男が尋ねる。
「贈り物ですか」
彼は答える。
「いや、私の本だ」
あえて言うまでもないことだけど、「贈り物ではなく私のための本」ではなく、「私のために書かれた本」とでもいえばいいのだろうか。
あなたのおかげで、私はまた芝居を書くことができるようになった…。ドライマンの感謝の気持ちが本を通してヴィースラーに伝わる。
会うことのなかった二人の男が、誰に知られることもなく、こうしてつながっていたという事実に、不覚の涙です。
■「善き人のためのソナタ」
映画の原題は、ドイツ語で「他人の生活」。
邦題でがっかりする映画もあるけど(ああ、原題のほうがよかったのに、って)、この映画は「善き人のためのソナタ」がすべてを語ってくれているような気がする。
盗聴していたときに聴いたこの音楽がそれほど大きな比重を占めているようには感じなかったけれど、でも最後の本のタイトルで、すべて納得した。
ベルリンの壁が崩壊しても、ヴィースラーの暮らしに彩りが加わることはなかったと思うけれど、この本を手にして謝辞を目にしたとき、それでもまだ無表情なヴィースラーの中に芽生えたものを想像して、胸が熱くなる。
シュタージの局員として生きていた長い年月の最後に行き着いた劇作家との一方的なつながりで、ヴィースラーは人としての何かを取り戻し、それで幸せになったとは思えないけれど、でもどこかでうなずけるものを得たのだろうか。
そういうことを、映画を見てからずっと想像している。
監督 フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク
出演 ウルリッヒ・ミューエ/マルティナ・ゲデック/セバスチャン・コッホ
(第79回アカデミー最優秀外国語映画賞を受賞)
■1984年の東ドイツ
最初に驚いたのは、この映画の舞台が1984年の東ドイツだということ。1989年のベルリンの壁崩壊数年前で、もちろん東西冷戦の中にあったことも知っていたけれど、こんなふうに体制に抵抗する人々を盗聴したり、活動を制限したり、ということが公然と(ではないのかな)行われていた、という事実。私の無知なんだろうけれど、それは大きな驚きだった。
1984年に私はどんなふうに暮らしていただろうかと、つい振り返ってしまった。
国家保安省(シュタージ)については、その後もタブー視されていて、この映画で初めて事実が明らかになった部分も多いらしい。
シュタージの局員であるヴィースラーが若い局員たちの前で、思想犯の取り調べについて講義しているところから映画は始まる。冷徹なヴィースラーは、睡眠もとらせずに取り調べをするのは非人道的ではないか、と意見を述べる局員の名前に冷やかにチェックを入れる。冷酷なビデオを見せながら、いかに「おとす」かのノウハウを述べるようすに、この人物がどんなふうにこの体制の中を生きてきたかが想像される。
家族も、たぶん心を許す友人も恋人もいないであろう彼は、国家に限りない忠節を誓って、この先も同じような日々を送り、そして死んでいくのだろう。疑いもなくそう想像させるシーンが静かに進んでいく。
感情の動きをみせることもない主人公を、ウルリッヒ・ミューエが淡々と演じている。
■変わっていくヴィースラー
その彼が少しずつ変わっていくのは、劇作家ドライマンとその恋人である女優クリスタ・マリア・ジーラントの生活を盗聴し始めてからだ。
彼らの思想に危険なものを察知した当局が、彼らの生活の一部始終を盗聴するようにヴィースラーに命じ、彼は部下と交代でその任務を遂行する。
盗聴器を住居全体に取り付けるときの局員たちの素早さ、その行動に気づいた隣人に脅しをかける際の静かな口調の怖さ…。
そして彼は昼間の間、その任務を続け、報告書をタイプする。「○時○分、帰宅。二人はセックスをする」というように、すべてが記録されていく。
けれど、二人の暮らしはヴィースラーのそれとはまったくの別世界だったのだろう。芝居を語り、音楽を楽しみ(ここで流れたのが「善き人のためのソナタ」)、愛し合う毎日。これといってドラマチックなことはない中で、ヴィースラーが少しずつ変わっていく。
部屋に忍び込んだ際に持ってきたブレヒトの本を読んだり、ドライマンの弾くピアノに耳を傾けるようになる。
そして、西側のメディアに東ドイツの実態を伝えるレポートを送る計画を始めたドライマンとその仲間の行動を、彼は報告しようとはしない。彼らは劇の脚本を共同で執筆している、とタイプする。この主人公の変化を、ウルリッヒ・ミューエは表にあらわれない何かで私たちに伝える。それが秀逸だ。演技ではない何か…。
■一級品のサスペンス
恋人たちの信頼関係には恋愛を超えた確実なものがあったけれど、当局の弾圧はその関係さえ危ういものに変えていく。
女優としての将来を脅かされたクリスタは苦悩の末、ドライマンの情報を当局に売る(彼女に目をつけた政治家の行為は醜悪このうえない!)。
それを知ったヴィースラーは身を挺して彼を守るのだけれど、愛する人を裏切ったクリスタは命を落としてしまう。その死を目の当たりにしたヴィースラーの無念はその感情を表さない表情から、むしろ強く私たちに伝わる。
ヴィースラーの行動は当局にも知られることになり、閑職に追いやられ、ベルリンの壁崩壊のニュースを知ったのも、地下の一室で手紙の開封という仕事をしているときだった。彼はそのとき、どんな気持ちでいたのだろう。
このあたりのシンプルな話の流れは、描き方が乾いているせいもあって、一級のサスペンスの彩りだ。
■「私の本だ」
新しい世界が開けたあとも、恋人の死から芝居を書けなくなっていたドライマンは、実は自分が東ドイツ時代にずっと盗聴されていたことを知る。そして、そのレポートを見て、そこに書かれた内容が全く改ざんされたものであることに気づく。誰かが自分を守ってくれたこと、そして救ってくれたことに驚く。そのレポートには報告者として暗号のような文字が書いてあった。
その後日談が、ヴィースラーとドライマンのそれぞれを日常を淡々と描いて進んでいく。ヴィースラーが郵便受けにチラシ?を配る仕事を続け、孤独に生きていることが伝わる。
ある日、本屋の前でドライマンの著作を見つける。彼があれから初めて執筆したものだ。本のタイトルは「善き人のためのソナタ」。本を手にしてページをめくると、謝辞のところに「感謝する」として、彼の盗聴の際の暗号の名前が記されている。
本をレジにもっていくヴィースラー。レジの男が尋ねる。
「贈り物ですか」
彼は答える。
「いや、私の本だ」
あえて言うまでもないことだけど、「贈り物ではなく私のための本」ではなく、「私のために書かれた本」とでもいえばいいのだろうか。
あなたのおかげで、私はまた芝居を書くことができるようになった…。ドライマンの感謝の気持ちが本を通してヴィースラーに伝わる。
会うことのなかった二人の男が、誰に知られることもなく、こうしてつながっていたという事実に、不覚の涙です。
■「善き人のためのソナタ」
映画の原題は、ドイツ語で「他人の生活」。
邦題でがっかりする映画もあるけど(ああ、原題のほうがよかったのに、って)、この映画は「善き人のためのソナタ」がすべてを語ってくれているような気がする。
盗聴していたときに聴いたこの音楽がそれほど大きな比重を占めているようには感じなかったけれど、でも最後の本のタイトルで、すべて納得した。
ベルリンの壁が崩壊しても、ヴィースラーの暮らしに彩りが加わることはなかったと思うけれど、この本を手にして謝辞を目にしたとき、それでもまだ無表情なヴィースラーの中に芽生えたものを想像して、胸が熱くなる。
シュタージの局員として生きていた長い年月の最後に行き着いた劇作家との一方的なつながりで、ヴィースラーは人としての何かを取り戻し、それで幸せになったとは思えないけれど、でもどこかでうなずけるものを得たのだろうか。
そういうことを、映画を見てからずっと想像している。
























