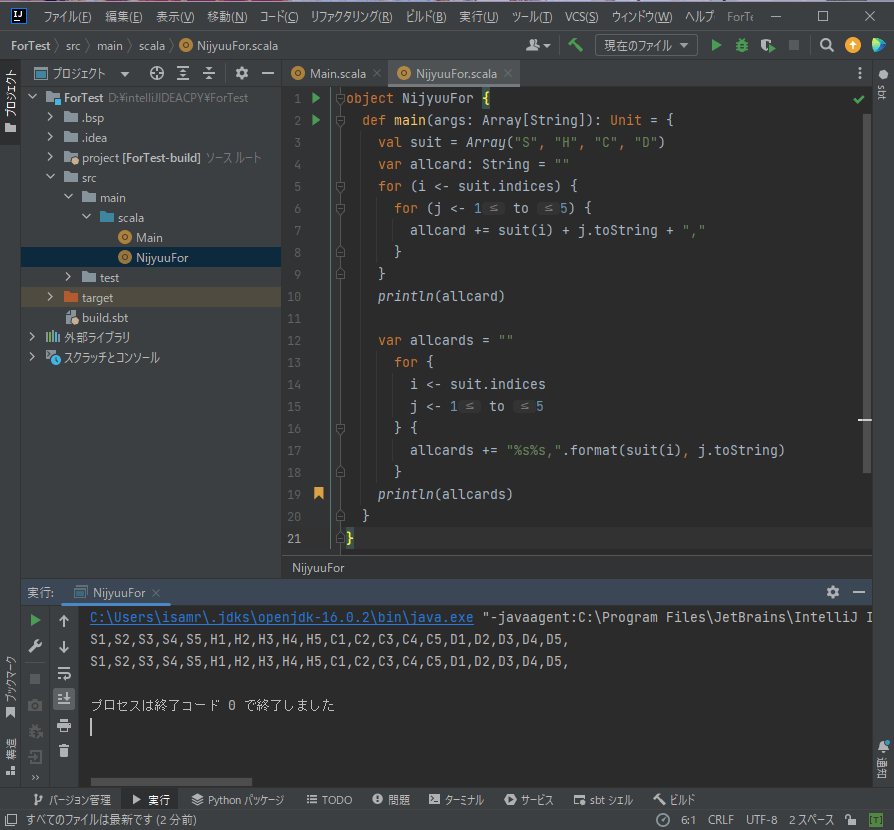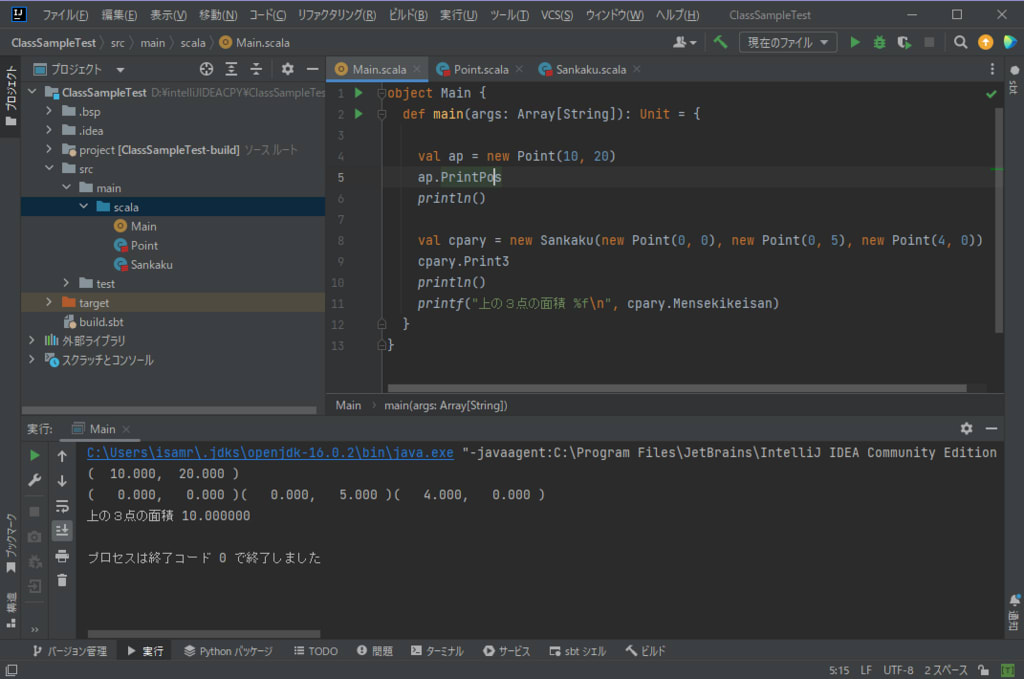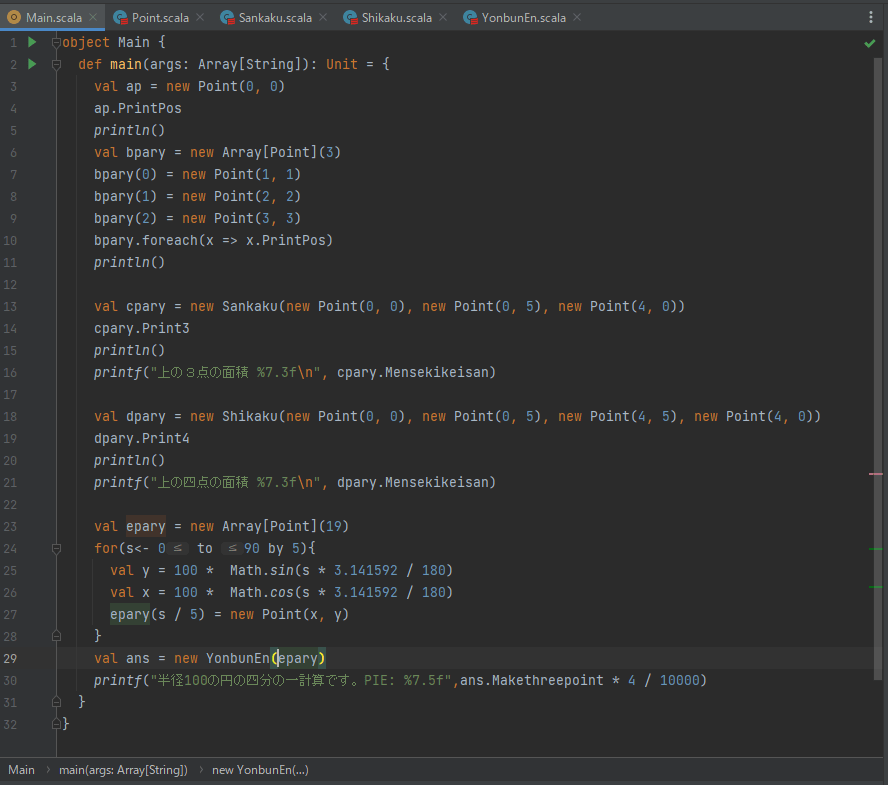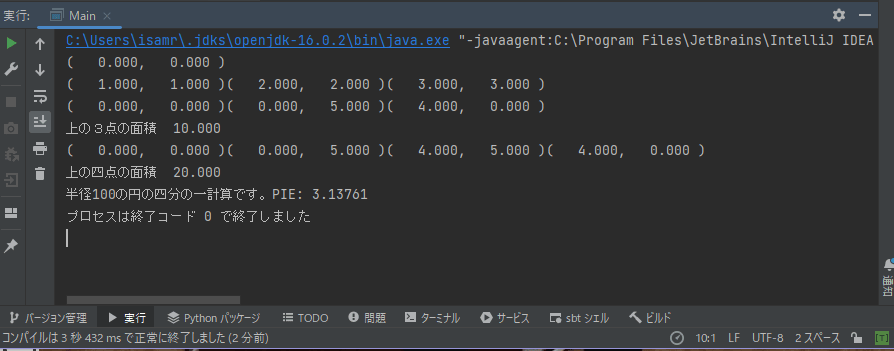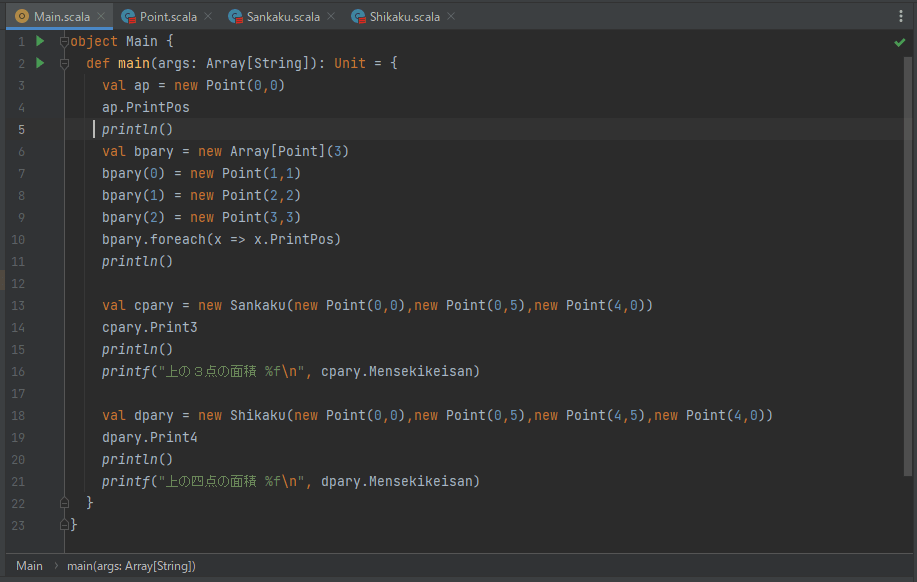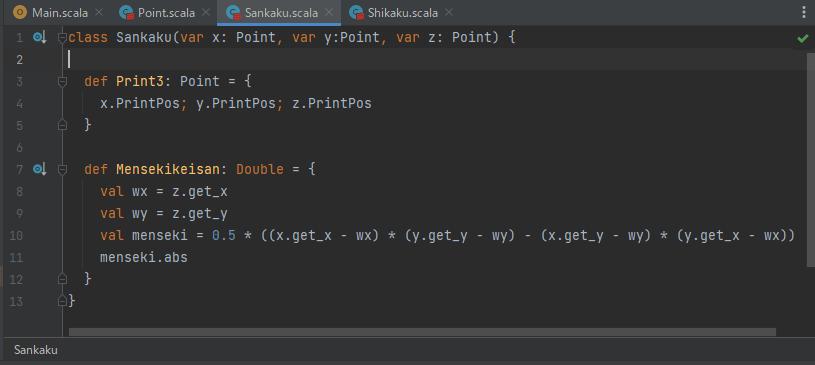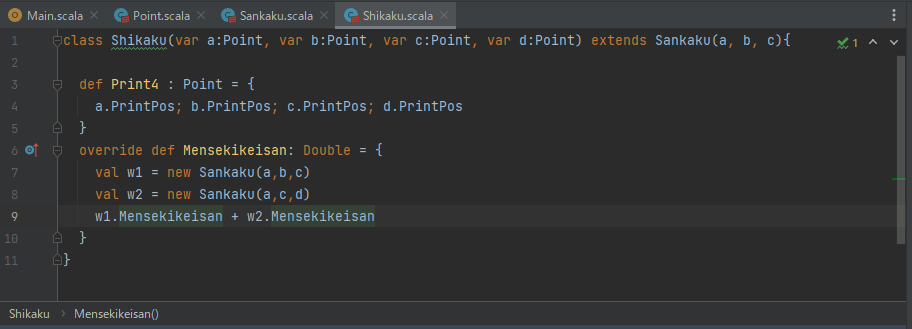前は、env.read.eval.printで一連の処理でしたが、入力でエラーが有ったとき、終了したいときの処理がうまく出来ませんでした。27行目に終了したいときの処理を入れました。

cLass Jyoukenは変更なし。

env.readも同じ。

ローカルな関数def str2Intを見つけたので、"e"が入力されたときの判断にInt.MaxValueを使います。エラーの時はInt.MinValueになるので、エラーの時はループします。

env.printも変わりない。下は実行した画面。
答えのとこで、"e"と入力で終了します。に変更。