1か月の連続休暇を与えた末に致死性不整脈により死亡したケースにも、賠償責任が認められた。長時間勤務が生じてしまった場合には、その後のケアをいかに尽くしても、使用者側の責任は、消えないということだろうか?
31歳という若さで死亡した女性のご家族には、ここらからお悔やみを申し上げる。一方で、直前に連続休暇を取るなど、一定のケアをしていたように見える会社に対して、判決は、「特に自殺未遂前の時間外労働時間は長く、脳・心疾患の発症をもたらす過重なもので、会社は休暇を取らせるなど具体的な措置をとっていなかった」との判断を示している。つまり、過去において長時間労働をさせた場合、その埋め合わせは、簡単にできるものではないということだ。企業の管理者、人事担当者にとっては、大変厳しい判断となった。
女性SE、過酷勤務で死亡…勤務先に賠償命令(読売新聞) - goo ニュース
女性SE、過酷勤務で死亡…勤務先に賠償命令
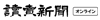 2012年10月12日(金)11:58
2012年10月12日(金)11:58
情報処理システム会社の福岡事業所に勤務していた福岡市のシステムエンジニアの女性(当時31歳)が急死したのは過酷な労働が原因として、両親が同社合併後にできた「アドバンストラフィックシステムズ」(本社・東京)に対し、慰謝料など計約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、福岡地裁であった。
府内覚裁判官は「死亡と会社の業務との間には因果関係がある」として、同社に計約6800万円の支払いを命じた。
判決によると、女性はシステム移行などを担当し、2007年2月の時間外労働が約127時間に上った。3月に仕事上のミスなどが原因で自殺未遂し、約1か月間休養した。その後復職したが、深夜残業など過酷な勤務が続き、5日後、東京出張中に致死性不整脈で死亡。福岡中央労基署は09年、労災認定した。
同社側は「亡くなる直前に約1か月の連続休暇を取得しており、死亡と業務に因果関係はない」などと主張した。しかし、府内裁判官は「特に自殺未遂前の時間外労働時間は長く、脳・心疾患の発症をもたらす過重なもので、会社は休暇を取らせるなど具体的な措置をとっていなかった」と述べた。









