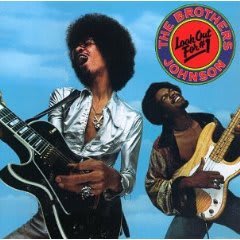今週の一枚は、とてもお得な作品を紹介。
ファンク・バンドの最高峰、タワー・オブ・パワーのライヴ盤『40th Anniversary』(2011年発表)だ。
このアルバムのお得なところは二つある。
結成40周年を記念して、バンドのOBまで集合した超豪華ライヴが堪能できる事。
そしてDVDがオマケについてくる事。
ん?この場合はCDがオマケか。
どちらにしてもCDとDVDの両方で楽しめると。
しかもDVDにはメンバーのインタビュー映像まで付いてくる。
これは豪華だわさ!
ライヴはフィルモア・オーディトリアムで行なわれたもの。
1905年に建設された歴史ある劇場で、内装も時代を感じさせる格調高いところ。
彼らの40周年を飾るには相応しい場所だ。
演奏はTOPならではのキレはそのままに、そそり立つホーンの壁が凄まじい音圧で観客をぶちのめす感じ。
ただでさえ大所帯のバンドがリズム隊も含めて倍以上に膨れ上がってステージがパンパンですわ。
DVDでは楽曲の途中でOBを含むメンバーのインタビューをカットインさせてバンドの歴史を振り返るという構成のため、人によってはこの編集を不満に思う人がいるかもしれない。
だが、その部分はCDでしっかり補完されているので、個人的にはOKだ。
全17曲とボリュームもたっぷり。
40年の振り返るにはこれでも足りないかもしれないが、ベスト盤的にも楽しめる。
何と言っても、既に孫がいるオッサンたちがパワフルに暴れているのが良い。
それにつけても、やっぱりファンクはライヴだねえ。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ
ファンク・バンドの最高峰、タワー・オブ・パワーのライヴ盤『40th Anniversary』(2011年発表)だ。
このアルバムのお得なところは二つある。
結成40周年を記念して、バンドのOBまで集合した超豪華ライヴが堪能できる事。
そしてDVDがオマケについてくる事。
ん?この場合はCDがオマケか。
どちらにしてもCDとDVDの両方で楽しめると。
しかもDVDにはメンバーのインタビュー映像まで付いてくる。
これは豪華だわさ!
ライヴはフィルモア・オーディトリアムで行なわれたもの。
1905年に建設された歴史ある劇場で、内装も時代を感じさせる格調高いところ。
彼らの40周年を飾るには相応しい場所だ。
演奏はTOPならではのキレはそのままに、そそり立つホーンの壁が凄まじい音圧で観客をぶちのめす感じ。
ただでさえ大所帯のバンドがリズム隊も含めて倍以上に膨れ上がってステージがパンパンですわ。
DVDでは楽曲の途中でOBを含むメンバーのインタビューをカットインさせてバンドの歴史を振り返るという構成のため、人によってはこの編集を不満に思う人がいるかもしれない。
だが、その部分はCDでしっかり補完されているので、個人的にはOKだ。
全17曲とボリュームもたっぷり。
40年の振り返るにはこれでも足りないかもしれないが、ベスト盤的にも楽しめる。
何と言っても、既に孫がいるオッサンたちがパワフルに暴れているのが良い。
それにつけても、やっぱりファンクはライヴだねえ。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ