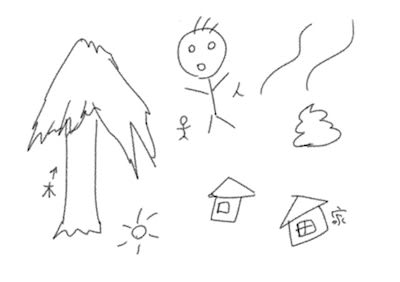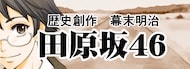流行ってますな。「おそ松さん」。
さて、チラチラとBLで長身、八頭身イケメンとか、自己流アレンジ二次創作のおそ松さんが流れてくる一方で
これは無い、やめてほしいという意見もまたチラチラお見受けいたします昨今です。
さて。
本日はなぜ、それを違和感と思う人がいるのかについてです。
ところで先日、テレビでは野々村議員の裁判の様子が報じられていました。
あの人なんかは、もう自分の生きている「世間」という限定的な空間の常識が、
一般社会とはズレていたからついやってしまった、悪いとそんなに思ってない、という悲劇なのでしょうか。
小保方さんにしろ、最近思いますのは、特に日本人は21世紀のツールをさずかったはいいが、
相変わらず、それぞれの閉鎖的な空間にいて、同族を待っているかと。
広い社会とつながるツール、
自分が何者で何をやっているのか説明するのではなく、
ただひたすら自分のテリトリー、つまり「場」において、その場にのみ理解される専門用語や
象徴、記号をぶら下げて、「交流」というより「同調」できる仲間を待っている。
そんなかんじの時、ありますね。
まるっきり異質な者を理解するには、理解力と説明が必要でして
それには遠近法や説明が必要であると、前の記事で考察いたしました。
でも、やっぱり違うものを考えて、受け入れる、あるいは理解されるようにプレゼンする、
というプロセスは、一苦労であり、ストレスではあるわけです。
しかし、同じものを共有する「輪」をどこまでも押し広げていけば、自分が理解しようとしなくても具合が良い。
布教が嫌われるのはここですが、世界中が自分と同じ感性であれば、世界は1つ、
違う事に悩まなくてすむものね。
さて、リツイートされてくるイラスト。
これ難しいですね。私は好きだと思っても、「おそ松さんクラスタ」限定のアカウントではないあたり。
「おそ松さん」で同人誌を描いたりしている人の中で
「こんなにも誰でも知っている大きなジャンルだから、皆知ってるだろうし
みんな喜んでくれる」とだけ思っている人がいた場合。
その「みんな」って誰。
そしてその画像を誰がどこで見るのかを意識しておらず
自分の周囲は全て、「おそ松さん」のファンで、これを見ればわかるはず、喜んでくれるはず
と、思い込んでいる閉鎖的な所にしかいない場合で、
「外」の認識とぶつかった場合、その違和感は起きるのではと思います。
同族で同じもののファンジャンル、つまり「身内」にあたる人の輪の中では、
いちいち「赤塚不二夫が描いた漫画が新しくアニメ化されましてね、その中に出てくる6つ子は
顔が同じだけど、性格が違ってます。そのキャラクターの1人にちょっと野獣的でナルシストな次男がいてね…」
という長々とした説明にはじまる、「なぜ自分はカラ松を八頭身で攻で描いたか」
にあたる説明部分は、知ってる人同士なら、やるだけ野暮です。
「そんなの、見りゃわかるじゃん」
「感覚的なものなんだよ」
という、「見りゃわかるだろ」「感覚でわかれ」という隠語の連鎖、それが記号化、象徴化だと思います。
記号論の話になって、難しいですが
美術史を見ても、その「わかる人にはわかるので、わかってくれる人を待つためのアイテム」
として、そこに至る説明を諦めた時、あるいは略した時、象徴記号は誕生するのだと思います。
「わかって下さるために」根気よく説明するスキルを用いて、起承転結だの「なぜ」だの
あるいは、先日ここでもやった「遠近法的立ち位置の説明」をするならば、
感覚では理解されなくても、人はその理由から、意を汲む事ぐらいはわかるでしょう。
しかし、完全な「記号」はおそらく、「潜伏化」を意味すると思います。
そこに一種、外の社会との断絶が見えるのは、もう必然的にそうなのかもしれません。
そんなわけで140字とイラストのツイッターは特に「なぜ」の部分はすっとばして、
シチュエーションのみパッ、とわかれば、後は感覚のみを享受、共有する。
感覚というのは、真に感覚的になればなるほど、異なる感覚を持つ者に対しての説明が難しいものです。
表現は自由に簡単になった。でも、そのせいで「楽」でも許してくれる空間もできた。
これ、19世紀末に批評家ラスキンが、現代画家の走りになったホイッスラーと戦った時も、
そこは1つのポイントだったのではと思います。
現代芸術は自由になったと同時に、ある独特でマニアックな空間に閉じ込められた。
自由であるので、何時間もかけて背景パースと、調べ上げた歴史的背景の細密描写なんてしなくてよくなった。
でも、その事で「誰にでもわかるような表現、より多くの人に理解させる」事をやめた。
それを狂気だと言わせず、尊厳を守ろうとしたゆえに、アメリカの批評家はわざわざ、
「わかる人にはわかるものは素晴らしい、わかりやすいものは下衆なもの」としたのかもしれません。
「なにゆえにカラ松が八頭身で…」を説明するには、ツイッターや1枚ぴらっとイラスト落書きでは短すぎる。
でも、そういうのやってる同士だと
「あっ、カッコいい~これってカラ松ですよね」ってわかるわけ。
ところが同じ感覚ではつながってない、外の人に対しては不親切すぎるわけです。
そして当然ながら、そのイラストを見る側というのも、これまたポーダーの曖昧な世界にいる。
…というか、システム上そうならざるを得ないのですが。
絵やイラストというのは、ある程度こちらは見ればわかるものと無意識にそう思っている。
文字をダラダラ読むよりは、さっとわかるものだと。
でも、その「見てわかる」には、あらかじめこちらで、ある程度イメージや感覚を用意しているものなのです。
その「見てわかる」ものが、アニメの「おそ松さん」でなくて元ネタの「おそ松くん」だった場合
見る側というのは、認識のベースとして、「赤塚不二夫のナンセンスギャグマンガ」
というのを持ってるわけです。記号そのものは「借り物」のパロディですからね…。
この、記号と意味のズレというのは、
出した側が意図するものと、見る側があらかじめ認識しているものの間のズレでおこりやすいです。
卍はナチスのマークでなくて、お寺の記号だったのに、なんて。
息子の大学で、軽い気持ちでデザインに「意味」のある記号を使って「かわいいと思いました♡」
といった女子学生を、「なんでそこまで」というくらい教授が叱り飛ばして半泣きにさせたそうな。
先生、叱りすぎかもしれないけど、こういう「認識のズレ」がとんでもない事に発展する時代は
シンボルの扱いには気をつけておかないと、という事なんでしょう。
こちらではエロ無しの明るい←厳密に言うとこれも結構、認識のズレで、赤塚漫画が全く道徳的に健全であるとは私は思いませんが…
子供が見るギャグアニメ、としか思ってなかった場合に
勝手に内輪の記号解釈を押しつけられて、そこに何の説明もない。そこが、違和感を生む原因なんでしょう。
でもね、少女同士はよくやるのよね。「あたしたちだけの秘密」の会話。
少女の世界ってのは、詩的でもあり、秘密結社的なんですよね。
どこまでが感覚で、どこまでが説明なのか
全ての人を同一空間に押し込めるのは、そりゃちょっと難しい。
ならば、どうせ理解なんかされないからと、同族言語を作り続けるのか。
これ、今のアメリカとかヨーロッパではどうなんだろう。
自分がリツイートするの時は充分に気をつけようと思います。
さて、チラチラとBLで長身、八頭身イケメンとか、自己流アレンジ二次創作のおそ松さんが流れてくる一方で
これは無い、やめてほしいという意見もまたチラチラお見受けいたします昨今です。
さて。
本日はなぜ、それを違和感と思う人がいるのかについてです。
ところで先日、テレビでは野々村議員の裁判の様子が報じられていました。
あの人なんかは、もう自分の生きている「世間」という限定的な空間の常識が、
一般社会とはズレていたからついやってしまった、悪いとそんなに思ってない、という悲劇なのでしょうか。
小保方さんにしろ、最近思いますのは、特に日本人は21世紀のツールをさずかったはいいが、
相変わらず、それぞれの閉鎖的な空間にいて、同族を待っているかと。
広い社会とつながるツール、
自分が何者で何をやっているのか説明するのではなく、
ただひたすら自分のテリトリー、つまり「場」において、その場にのみ理解される専門用語や
象徴、記号をぶら下げて、「交流」というより「同調」できる仲間を待っている。
そんなかんじの時、ありますね。
まるっきり異質な者を理解するには、理解力と説明が必要でして
それには遠近法や説明が必要であると、前の記事で考察いたしました。
でも、やっぱり違うものを考えて、受け入れる、あるいは理解されるようにプレゼンする、
というプロセスは、一苦労であり、ストレスではあるわけです。
しかし、同じものを共有する「輪」をどこまでも押し広げていけば、自分が理解しようとしなくても具合が良い。
布教が嫌われるのはここですが、世界中が自分と同じ感性であれば、世界は1つ、
違う事に悩まなくてすむものね。
さて、リツイートされてくるイラスト。
これ難しいですね。私は好きだと思っても、「おそ松さんクラスタ」限定のアカウントではないあたり。
「おそ松さん」で同人誌を描いたりしている人の中で
「こんなにも誰でも知っている大きなジャンルだから、皆知ってるだろうし
みんな喜んでくれる」とだけ思っている人がいた場合。
その「みんな」って誰。
そしてその画像を誰がどこで見るのかを意識しておらず
自分の周囲は全て、「おそ松さん」のファンで、これを見ればわかるはず、喜んでくれるはず
と、思い込んでいる閉鎖的な所にしかいない場合で、
「外」の認識とぶつかった場合、その違和感は起きるのではと思います。
同族で同じもののファンジャンル、つまり「身内」にあたる人の輪の中では、
いちいち「赤塚不二夫が描いた漫画が新しくアニメ化されましてね、その中に出てくる6つ子は
顔が同じだけど、性格が違ってます。そのキャラクターの1人にちょっと野獣的でナルシストな次男がいてね…」
という長々とした説明にはじまる、「なぜ自分はカラ松を八頭身で攻で描いたか」
にあたる説明部分は、知ってる人同士なら、やるだけ野暮です。
「そんなの、見りゃわかるじゃん」
「感覚的なものなんだよ」
という、「見りゃわかるだろ」「感覚でわかれ」という隠語の連鎖、それが記号化、象徴化だと思います。
記号論の話になって、難しいですが
美術史を見ても、その「わかる人にはわかるので、わかってくれる人を待つためのアイテム」
として、そこに至る説明を諦めた時、あるいは略した時、象徴記号は誕生するのだと思います。
「わかって下さるために」根気よく説明するスキルを用いて、起承転結だの「なぜ」だの
あるいは、先日ここでもやった「遠近法的立ち位置の説明」をするならば、
感覚では理解されなくても、人はその理由から、意を汲む事ぐらいはわかるでしょう。
しかし、完全な「記号」はおそらく、「潜伏化」を意味すると思います。
そこに一種、外の社会との断絶が見えるのは、もう必然的にそうなのかもしれません。
そんなわけで140字とイラストのツイッターは特に「なぜ」の部分はすっとばして、
シチュエーションのみパッ、とわかれば、後は感覚のみを享受、共有する。
感覚というのは、真に感覚的になればなるほど、異なる感覚を持つ者に対しての説明が難しいものです。
表現は自由に簡単になった。でも、そのせいで「楽」でも許してくれる空間もできた。
これ、19世紀末に批評家ラスキンが、現代画家の走りになったホイッスラーと戦った時も、
そこは1つのポイントだったのではと思います。
現代芸術は自由になったと同時に、ある独特でマニアックな空間に閉じ込められた。
自由であるので、何時間もかけて背景パースと、調べ上げた歴史的背景の細密描写なんてしなくてよくなった。
でも、その事で「誰にでもわかるような表現、より多くの人に理解させる」事をやめた。
それを狂気だと言わせず、尊厳を守ろうとしたゆえに、アメリカの批評家はわざわざ、
「わかる人にはわかるものは素晴らしい、わかりやすいものは下衆なもの」としたのかもしれません。
「なにゆえにカラ松が八頭身で…」を説明するには、ツイッターや1枚ぴらっとイラスト落書きでは短すぎる。
でも、そういうのやってる同士だと
「あっ、カッコいい~これってカラ松ですよね」ってわかるわけ。
ところが同じ感覚ではつながってない、外の人に対しては不親切すぎるわけです。
そして当然ながら、そのイラストを見る側というのも、これまたポーダーの曖昧な世界にいる。
…というか、システム上そうならざるを得ないのですが。
絵やイラストというのは、ある程度こちらは見ればわかるものと無意識にそう思っている。
文字をダラダラ読むよりは、さっとわかるものだと。
でも、その「見てわかる」には、あらかじめこちらで、ある程度イメージや感覚を用意しているものなのです。
その「見てわかる」ものが、アニメの「おそ松さん」でなくて元ネタの「おそ松くん」だった場合
見る側というのは、認識のベースとして、「赤塚不二夫のナンセンスギャグマンガ」
というのを持ってるわけです。記号そのものは「借り物」のパロディですからね…。
この、記号と意味のズレというのは、
出した側が意図するものと、見る側があらかじめ認識しているものの間のズレでおこりやすいです。
卍はナチスのマークでなくて、お寺の記号だったのに、なんて。
息子の大学で、軽い気持ちでデザインに「意味」のある記号を使って「かわいいと思いました♡」
といった女子学生を、「なんでそこまで」というくらい教授が叱り飛ばして半泣きにさせたそうな。
先生、叱りすぎかもしれないけど、こういう「認識のズレ」がとんでもない事に発展する時代は
シンボルの扱いには気をつけておかないと、という事なんでしょう。
こちらではエロ無しの明るい←厳密に言うとこれも結構、認識のズレで、赤塚漫画が全く道徳的に健全であるとは私は思いませんが…
子供が見るギャグアニメ、としか思ってなかった場合に
勝手に内輪の記号解釈を押しつけられて、そこに何の説明もない。そこが、違和感を生む原因なんでしょう。
でもね、少女同士はよくやるのよね。「あたしたちだけの秘密」の会話。
少女の世界ってのは、詩的でもあり、秘密結社的なんですよね。
どこまでが感覚で、どこまでが説明なのか
全ての人を同一空間に押し込めるのは、そりゃちょっと難しい。
ならば、どうせ理解なんかされないからと、同族言語を作り続けるのか。
これ、今のアメリカとかヨーロッパではどうなんだろう。
自分がリツイートするの時は充分に気をつけようと思います。