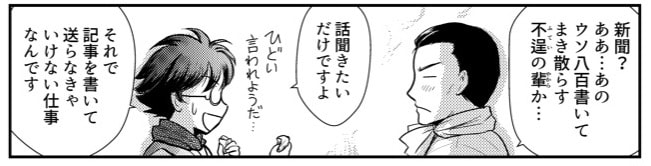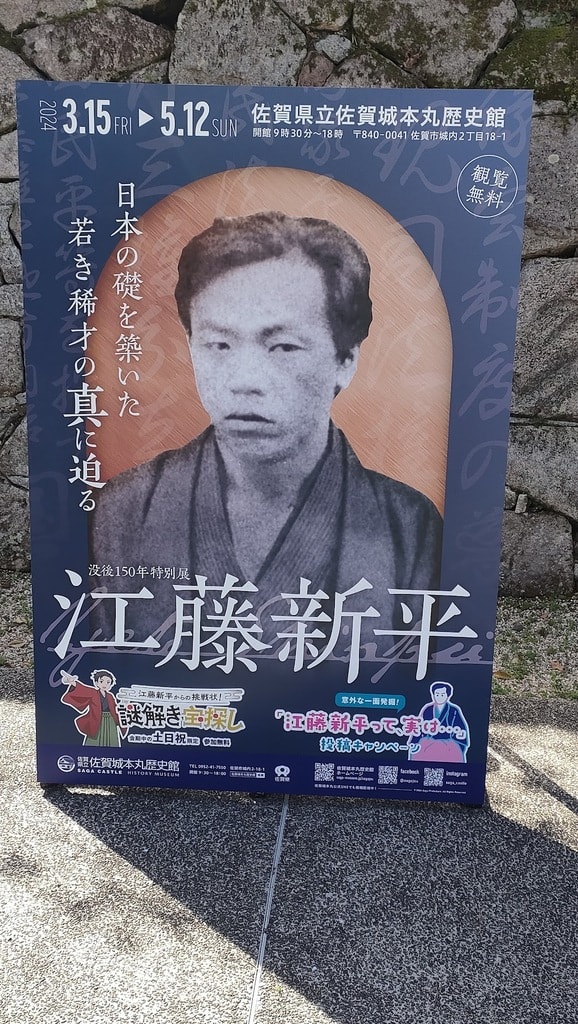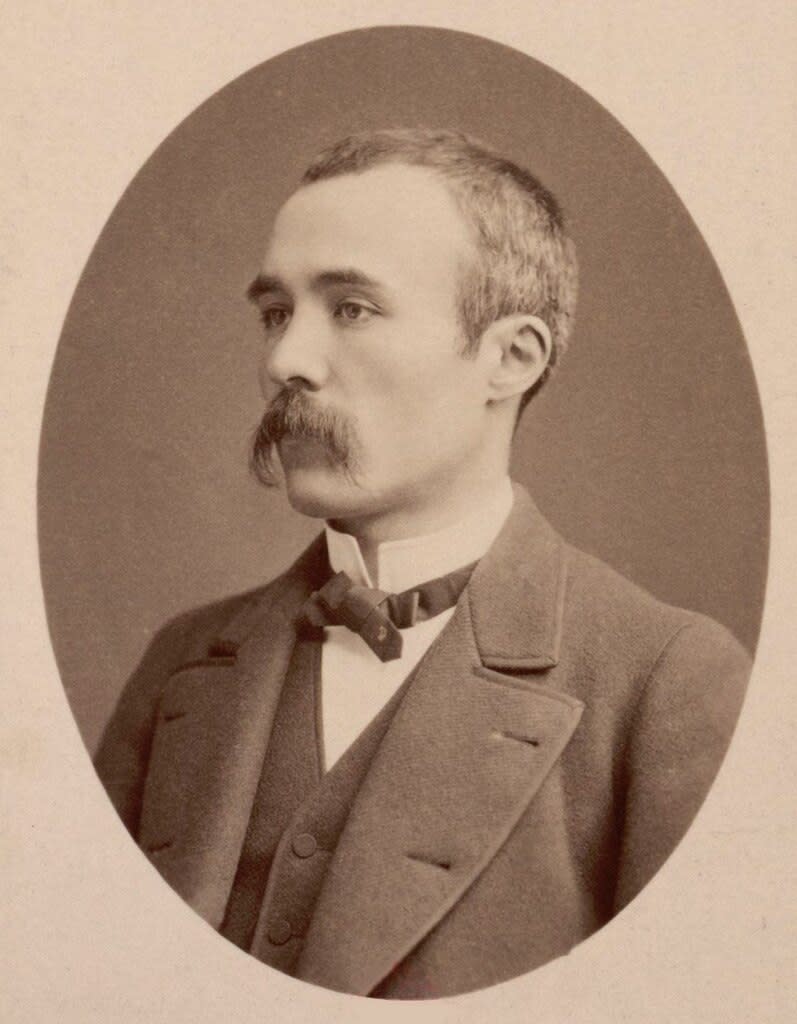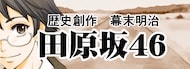メリークリスマスです。
キリストの誕生日は実は12/25でなくご都合だった、なども聴きますけど
日本ではなぜか、
いや最近では外国でも?
「キリストの誕生日」のありがたさよりは
商業的な意味の方が強くなっている気がします。
などという自分は、特にキリスト教信者ではない
無いはずなんですが…
え、だって家は浄土真宗、それでなくても仏教国
もしくは神道、祖父母は天皇=神!
そんな感じでしたもんね
ただ、私中学の時にちょびっと母に熊本YMCAなるものに行かされまして
その影響なのか心の超地味〜な所に
キリスト教のプラグインがインストールされていますのよ…マジで。
これはねえ…本当に、日本にいると時々、バグを起こします。
けども同時に、私が精神的にギリまで追い詰められた時には
救ってくれていたような気もして
だとすると、「どっかで微妙にプロテスタント的要素を含」
なのかも?しれません。
キリスト様の生誕がなぜ尊いか
これ日本人には「案外、2次創作で説明できるかもしれん」
と最近思ってしまいました。
こうです…
ある所に、ナマモノアイドルでない架空2次元アイドルの推しが尊すぎる女性がいました。
名前はマリア。
愛しすぎる尊すぎる、辛い時も救ってくれて
推しは絶対に自分を裏切ったりしません。
みんなは「そんなやつは架空であって実在しないのに」と笑いますが
マリアには、推しは信じているので存在します。信じるからいるんです。
でも触ることもできないし、まあせめてグッズで祭壇作るくらいですよ。
ところがある日、マリアの前に公式天使が現れ
「あなたは産めるはずもない2次元の推しの子を妊娠しました」
と告げられる。
そんなもん奇跡以外の何でもないです
が、マリアの推しは2.5次元などでなく、本物の3次元としてお生まれになります。
そらもう究極のアイドル。
「金輪際現れない一番星の生まれ変わり」です。
養父に選ばれたのはこれまたオタでして
同、推しに人生捧げたので女に興味ない、ファンクラブ会長みたいなやつです。
ヨセフといいます。
マリアにとって、ヨセフにとっても
推しは自分の心の支えであり、辛い時も見離さず守って下さる
本物の愛を持っている存在。絶望の淵からでも救ってくれるので
「これ全世界に布教した日にゃ全員ハッピーになれんじゃね?」
て感じです。
そのお生まれになった愛の対象が磔刑になるまでは聖書という原作参照、
になるんですが。
そう考えると
最初にあって然るべき「信仰」はやっぱり「目覚め」みたいなのは
どうしても必要になってくるのでは…
ただしこれは、日本人は日本文化に囲まれて生活しているがゆえに
仏教エリアから出れないので
何らか西洋文化か海外渡航歴あるとか、そういう文化に触れるか
教会方面から直にインストールされるか
何かは必要なんじゃないかなあ…でないと
やっぱりあの崇高ってやつには、ちょっと懐疑的にはなります。
「ならそれって…別にアンジェリークの守護聖でもよかないか」
て思っちゃう自分もいるわけですよ。
ガチの宗教家さん、新興宗教の方
対応をお断りさせていただきます。
結局、無宗教です。ごめんやで〜